いらない土地を国に返す!相続土地国庫帰属制度やほかの処分方法などを解説!
「いらない土地を処分したい」と考えている方も多いのではないでしょうか。近年では、「先代から所有している地方の土地の相続先が決まらない」「相続した田舎の山林を手放す手段を探している」など、さまざまな悩みを抱えている方が増えています。土地を所有していると固定資産税や管理費用などが発生するため、放置することもできません。
このような土地の扱いに悩む方々を対象に、新たな法律の成立が始まっています。その法律を「相続土地国庫帰属制度」と言います。この記事では、相続土地国庫帰属制度の概要や具体的な利用方法、注意点などを詳しく解説します。
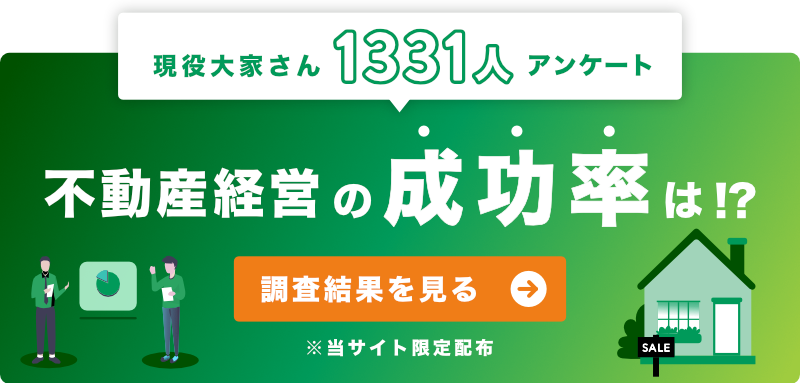
-
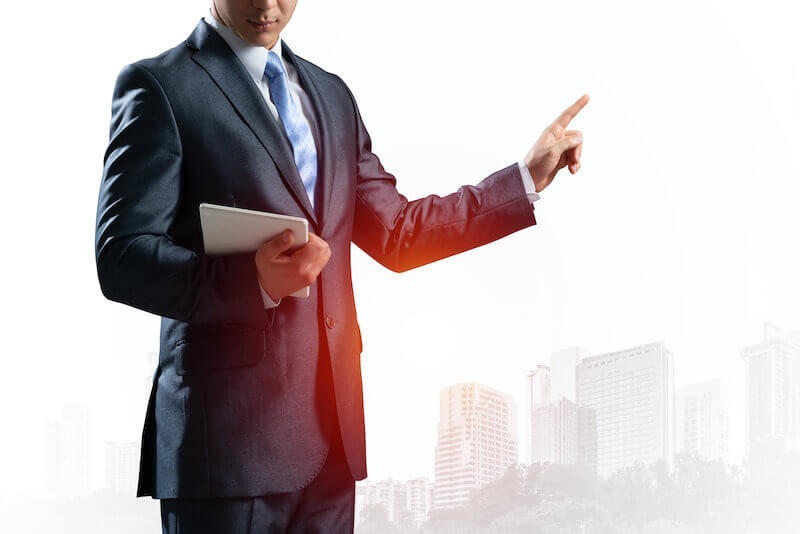
相続土地国庫帰属制度とは、相続した不要な土地の所有権を国に返せる制度です。令和3年4月21日に「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」の成立によって制度の内容が盛り込まれ、令和5年4月27日より施行されます。
この制度によって、相続などによって土地の所有権を取得した相続人は、法務大臣の承認によって土地を手放して国庫に帰属できます。
なお、令和3年4月21日同日には「民法等の一部を改正する法律」も成立しています。民事基本法制のさまざまな見直しが同時に行われているため、不動産登記制度と民法の変更されるポイントについても確認しましょう。相続土地国庫帰属制度が新設された背景
国庫帰属制度が新設された背景として、「所有者不明土地」の増加が挙げられます。所有者不明土地とは、以下のような条件の土地のことを指します。
・不動産登記簿で所有者がすぐに判明しない土地
・所有者が判明しても所在が不明で連絡できない土地
人口減少の進展によって土地需要は年々低下しており、それに比例して土地所有に対する負担感が増加しています。相続しても負担が大きくなるばかりのため、土地相続後に「所有者不明土地」となってしまう土地が増えているのです。
用地買収などを行う際に土地の所有者が不明だと、円滑で適正な土地利用に支障が生じるため、所有者不明土地の増加は国や自治体の公的事業にとって深刻な問題となっています。そこで、所有者不明土地をこれ以上発生させないために、相続土地国庫帰属制度が新設されたのです。-

相続土地国庫帰属制度は、相続や遺贈によって土地の所有権を持つ相続人であれば誰でも申請できます。制度の開始前に土地を相続した方でも問題ありません。ただし、売買などで任意に土地を保有した方や法人は対象外なので注意しましょう。また、土地が共有地の場合は共有者全員で申請しなければなりません。
ここでは、申請方法について見ていきましょう。どんな土地なら国に返せる?
国庫へ返還できる土地は、「抵当権などの設定や争いがなく建物もない更地」と決められています。管理や処分の実施に大きな費用や労力が必要な土地は、対象から除外されるため気をつけましょう。
以下では、代表的な除外対象の例をまとめています。
・建物や工作物、車両などがある土地
・担保権などの権利が設定されている土地
・通路など他人による使用が予定される土地
・土壌汚染や埋設物がある土地
・境界が明らかではない土地
・危険な崖がある土地
・隣接する土地の所有者などと争訟が必要な土地
・管理や処分で過分の費用や労力がかかる土地
このように、どんな土地でも国に返せるわけではありません。土地の状態は厳しくチェックが実施されます。そのため、自身の土地のステータスをしっかりと確認してから、相続土地国庫帰属制度の活用を検討しましょう。申請手順
申請の流れとしては、以下の4つのステップで相続土地国庫帰属制度を利用できます。
1. 承認申請
相続などによって土地を取得した相続人が申請します。共有地の場合は共有者全員で申請を行いましょう。
申請書や添付書類を提出して、審査手数料を納付します。
2. 法務大臣による要件の審査と承認
書面審査や実地調査などの要件審査が実施され、要件を満たしていると法務大臣から承認を得られます。無事に承認された場合には負担金の額が通知されます。
3. 申請者が負担金を納付
申請者は、通知に記載された負担金額を納付します。納付は、負担金の額の通知を受け取ってから30日以内に行いしょう。
4. いらない土地が国庫に帰属
ここまでのステップをクリアできれば、いらない土地を国に返せます。-

では、そもそもいらない土地を放置してしまうと、どういったデメリットが発生するのでしょうか。一般的に土地の整理が重要と言える代表的な理由を確認しましょう。
固定資産税が発生する
いらない土地は持っているだけで、固定資産税が発生します。土地を持っている限り固定資産税の支払いは必要となるため、使い道のない土地ではさらに手間となります。
田舎の土地などで評価が低ければ固定資産税も安くなりますが、土地が広ければ負担額は軽視できません。ただし、建物が建っていたり、農地で利用していたりすると税負担軽減を受けられます。土地だけの場合はその特例の適用も受けられないため、いらない土地は放置できないのです。管理には手間がかかる
土地は定期的に状態維持などを管理しなければ、草が生えるなどして荒れてしまいます。放置する期間が続けば、周辺の土地を所有する方からクレームを受けてしまうかもしれません。そのため、いらない土地だからと何もしなくていいわけではなく、最低限の手入れが必要です。
専門の業者にメンテナンスの依頼もできますが、それなりの費用がかかってしまうでしょう。なお、市町村によっては条例で土地の雑草の除去が義務とされているケースもあります。損害賠償のリスクがある
いらない土地の場所によっては、損害賠償が発生してしまうリスクもあります。いらない土地が崖地などで、崖崩れなどによって損害が発生した場合には、損害賠償責任を負わなければなりません。また、空き家が倒壊して通行人を怪我させてしまうケースも同様です。
いらない土地であったとしても所有者は責任が求められるため、事故が発生する前に適切な処理を行いましょう。-

いらない土地は放置したままではいけません。しかし、相続土地国庫帰属制度を利用以外にもほかの処分方法はあるのでしょうか。ここでチェックしてみましょう。
売却
いらない土地を売りたいものの、売れなくて困っている方も珍しくありません。いらない土地もうまく工夫すれば十分に売却可能なケースがありますので、土地の売り方などを見直してみましょう。
例えば、売り出した時期に問題がある、相場よりも価格設定が高いなど、さまざまな改善点が見つかるはずです。再度、いらない土地を売るための条件を見直して、売却にチャレンジすると道が開ける場合があります。まずは、土地の相場を改めて勉強して、土地売却の実績が豊富な不動産屋を見つけてみましょう。法人へ寄付する
法人へ寄付するという選択肢もあります。もし、保有している土地がある程度広いなら、ビルや保養所を建てるなど法人ならではの利用法も考えられます。また、個人に譲渡を行う場合は税金が発生しますが、法人であれば経費で処理できることもポイントです。
ただし、自身のいらない土地の価値やニーズを考えると、法人が簡単に寄付を承諾してくれるとは限りません。収益性の高い土地であれば寄付せずに売却できてしまうためです。そのため、法人への寄付を検討する際は一般企業よりも、学校・NPO法人・社団法人などの方に相談してみると良いでしょう。個人に譲渡する
いらない土地を引き受けてくれる方を探すのは簡単ではありませんが、個人譲渡するという方法もあります。さまざまな可能性がありますが、いらない土地のお隣にお住まいの方などに声をかけて話が進んだという例もあるようです。お隣の方であれば自分の敷地が増えるため、メリットを感じやすいためです。
ただし、譲渡には相手方に譲渡税がかかる点には注意しておきましょう。譲渡税とは土地や建物の譲渡所得に対する税金で、ほかの所得と区分して計算しなければなりません。事前にどの程度の税金が発生するかを調べてから、いらない土地の譲渡の話を進めた方が良いでしょう。自治体へ寄付をする
自治体に寄付する方法も考えられます。ただし、自治体が喜んで対応してくれるとは限りません。土地を引き取るということは、本来であればその土地から得られるはずの固定資産税が得られなくなるということです。固定資産税という収入源を差し引いて考えても、納得のできるメリットがある土地でない限り自治体へ寄付は難しいでしょう。
加えて、土地の寄付を引き受ける基準は各自治体によって異なるため、それぞれで確認が必要です。寄付したい土地に関する情報が記載された書類や写真を持参して、自治体の担当者の方にまずは相談をしてみましょう。-
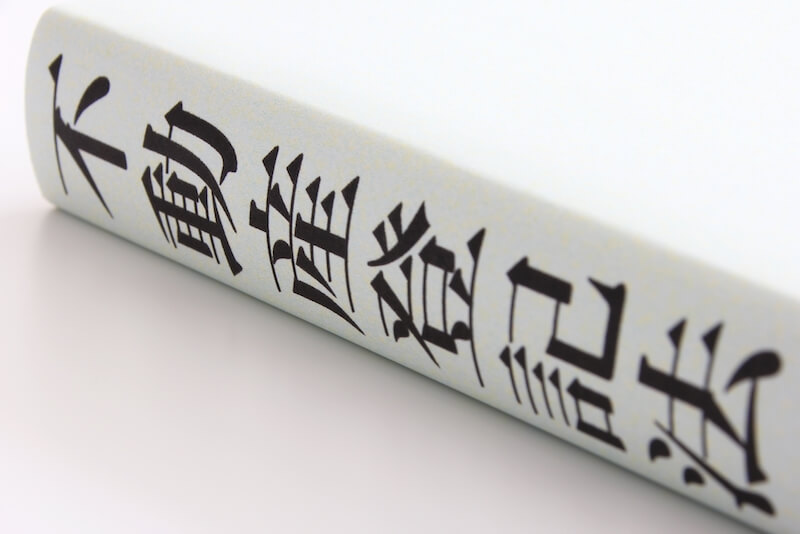
ここまで相続土地国庫帰属制度についてご紹介してきましたが、冒頭でお伝えしたように令和3年4月21日に成立した法律によって、その他の不動産のルールが大きく変わります。ここで不動産登記制度の変更点についても確認しておきましょう。
相続登記の申請が義務化される
所有者不明土地の発生を予防するため、相続登記の申請を義務化が決定しました。義務化の具体的なルールを見ていきましょう。
基本的なルール
相続によって不動産を取得した相続人は、所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。被相続人の死亡を知った日からではなく、不動産の取得を知らなければ3年の期間はスタートしないことがポイントです。
遺産分割のルール
遺産分割の方向性が整理できた場合、相続人は遺産分割の成立日から3年以内に登記を申請しなければなりません。
罰則
それぞれの義務化のルールに正当な理由なしに違反した場合、10万円以下の罰金の対象になる恐れがあります。相続人申告登記が設けられる
より簡単に相続登記の申請義務を実施できる仕組みとして、相続人申告登記が新たに設けられます。登記簿に記載されている所有者について相続が始まったことと、自分が相続人であることを登記官に申し出ると、相続登記の申請義務を履行可能です。
申出をした相続人の氏名や住所などは登記されますが、持分の割合までは登記されないため、すべての相続人を把握できるような資料は必要ありません。自分が相続人であると分かる戸籍謄本などの提出を行いましょう。住所などの情報の変更登記を行う申請が義務化される
登記簿に記載されている所有者は、住所などを変更した日から2年以内に変更登記の申請が義務となります。正当な理由がなく義務に違反した場合、5万円以下の罰金の対象となるため注意しましょう。
従来では、登記に記載されている所有者の氏名や住所に変更があった際に、登記されないケースも多く見られました。その理由として、住所などの変更登記の申請は任意とされており、申請を行わなくても所有者自身が不利益をほとんど被らなかったことが挙げられます。また、転居などの際に所有不動産の住所変更登記を行うのは負担がかかるからと、最新情報が反映されないケースも目立ちました。
このような背景から、変更登記が義務化されたのです。
なお、変更登記では利用者の立場に立って、いくつかの改善されたポイントがあります。それぞれ詳細を見ていきましょう。
公的機関との情報連携で便利になる
ほかの公的機関との情報連携により、職権で登記がされるように改善されました。従来の課題であった住所などの変更登記の手続きの手間をなくすため、より分かりやすくシンプルになったのです。
登記官がほかの公的機関と連携して入手した情報より、職権によって住所などの変更登記を実施できるようになります。具体的には、個人の場合には住基ネット、法人の場合には商業・法人登記のシステムなどとの連携です。
ただし、変更登記が実施されるのは本人の了承が得られる場合に限定されます。
DV被害者などへの対応が強化される
「DV被害などが原因で不動産登記簿上に住所を公開されたくない」という問題にも対処がされています。DVといった被害を受けた方々が載っている登記事項証明書などを登記官が発行する際には、現住所に代わる事項を記載する制度が設けられました。対象はDV防止法・ストーカー規制法・児童虐待防止法上の被害者の方などです。-

不動産登記制度だけでなく、民法にも変更がありました。新たなルールも導入されるので、何がどのように変わるのかポイントをチェックしましょう。
土地や建物の財産管理制度が創設される
土地や建物の管理を専門とする財産管理制度が誕生します。所有者が分からなかったり、所有者の管理に問題が生じていたりする土地や建物が対象です。では、新設される2つの制度を見ていきましょう。
所有者不明土地・建物の管理制度
近年、調査しても所有者や所在が分からない土地や建物の増加が目立っています。そこで所有者不明土地を減らすために、地方裁判所への申し立てによって、該当の土地や建物の管理人を選んでもらえる制度が誕生しました。
管理不全状態にある土地・建物の管理制度
不適当な管理で権利や法的利益が侵害されている、もしくは恐れがある土地や建物も増加しています。該当する場合は地方裁判所への申し立てによって、土地や建物の管理人を選んでもらえます。共有制度が見直される
共有物の利用や共有関係の解消をより簡単にするために、共有制度全般についてさまざまなポイントが改善されます。
共有物の利便性が向上する
共有物の軽微な変更の要件が緩和され、持分の過半数で決定できるようになります。所在が分からない共有者がいる場合には、地方裁判所に申し立て、共有者の持分の過半数があれば管理行為、共有者全員の同意が得られれば変更行為を行えます。
共有関係の解消が簡単になる
所在が分からない共有者がいる場合、ほかの共有者は地方裁判所に対して申し立てを行えるようになります。居場所などがはっきりしない共有者の持分を取得したり、その持分を含めて不動産全体を第三者に譲渡したりできるので、共有関係の解消が簡単です。遺産分割の新たなルールが導入される
遺産分割がされずに長い間放置されるケースを削減するために、新たなルールが設けられます。具体的には、被相続人の死亡から10年を経過した後の遺産分割は、原則として具体的相続分を考慮せず法定相続分、または指定相続分で均一に行うとされました。
これは、改正法の施行日前に開始した相続についても適用されるので、早めの遺産分割が重要です。相隣関係が見直される
隣地を正しくスムーズに使用できるようにするため、相隣関係に関する取り決めも大きく変わります。見直されるポイントを以下にまとめました。
隣地使用権のルールの見直し
境界調査や越境している木の枝の除去などのために、隣地を一時的に使用できると明言されました。さらに、隣地の所有者やその所在を調べても分からない場合にも、隣地を使用できるように改善されます。
ライフラインの設備の設置、使用権のルールの整備
ライフラインを自己の土地に引き込むための考え方が改善されました。導管などの設備を他人の土地に設置する権利や、他人が所有する設備を使用する権利が明確になっています。
越境した竹木の枝を切取る際のルールの見直し
越境された土地の所有者が自らその枝を切り取れる仕組みが整備されます。例えば、なかなか越境した枝が除去されない場合、竹木の所有者や居場所を調べても分からない場合などが対象です。-

近年、いらない土地を国に返すための法制度が整ってきています。相続土地国庫帰属制度などのルールや考え方を正しく理解すれば、いらない土地の解決方法も見つかるかもしれません。
また、所有者不明土地などの問題を解決するため、行政もさまざまな法整備に前向きです。そのため、昔は諦めていた土地の悩みも改めて課題を整理してみると一歩前に進めるかもしれません。
ただし、土地に関する問題は専門知識も多く必要で、発生するお金も高額になるケースがあります。不明瞭な点があるままで土地に関する話を進めてしまうと、思わぬトラブルが発生してしまう場合も少なくありありません。いらない土地で悩みを抱えている場合は、まずは土地の近くの専門家に話を聞いてもらいましょう。関連記事
-
 不動産投資における平均利回り相場とは?利回りの注意点も併せて解説詳しく見る
不動産投資における平均利回り相場とは?利回りの注意点も併せて解説詳しく見るアパートを経営するにあたり、安定した利益を得るには、利益を得られる物件を選ぶことが大切です。アパートの収益率を把握するには、「経費率」に着目すると良いでしょう。経費率とは、出費に対して経費がどれくらいあるかを表す指標です。 しかし、所有している土地でアパート経営を始めるには、いくつかのリスクがあることも覚えておきましょう。それぞれのリスク回避のために適切な対策を行って、効率的な土地活用を行いましょう。 この記事では、土地有りでアパート経営を行うメリット・デメリットについて、そして経営を進める時の流れや必要な資金などについて解説します。
-
 アパート経営時に車(車両費)は経費に計上できる?車選びや節税のコツも解説詳しく見る
アパート経営時に車(車両費)は経費に計上できる?車選びや節税のコツも解説詳しく見るアパート経営は、物件までの行き来や不動産管理会社との打ち合わせなどに車が必要な場合もあります。そのため、アパート経営時に車の購入費用が経費に計上できるのか、疑問に思うオーナーもいるのではないでしょうか。この記事では、アパート経営における車両費は経費に計上できるのかを中心に、経費の仕組みやメリット・デメリット、計上の仕方などを紹介します。 しかし、所有している土地でアパート経営を始めるには、いくつかのリスクがあることも覚えておきましょう。それぞれのリスク回避のために適切な対策を行って、効率的な土地活用を行いましょう。 この記事では、土地有りでアパート経営を行うメリット・デメリットについて、そして経営を進める時の流れや必要な資金などについて解説します。
-
 賃貸の自主管理におけるトラブルと対策、委託管理についても紹介!詳しく見る
賃貸の自主管理におけるトラブルと対策、委託管理についても紹介!詳しく見るアパートやマンションを賃貸物件として貸し出しているオーナー様の中には、管理業務を管理会社に任せるのではなく、自ら行っている方もいるでしょう。その中で、さまざまなトラブルに見舞われるケースは少なくありません。 本記事では、自主管理においてよくあるトラブルとその対処法、および委託管理という選択肢について紹介します。
タウングループ不動産仲介・周辺事業- 賃貸不動産仲介(東京・神奈川・埼玉・千葉) タウンハウジング
- 賃貸不動産仲介(東海) タウンハウジング東海
- 賃貸不動産仲介(九州) タウンハウジング福岡
- 土地・建物の不動産販売及び仲介 タウン住宅販売
- 首都圏を中心に引越サービスを展開 タウン引越サービス
- 賃貸不動産仲介(東北) タウンハウジング東北
- 賃貸不動産仲介(北関東) タウンハウジング北関東
建築事業- 賃貸住宅の企画・設計・施工 アヴェントハウス
多角化事業- 都内を中心に飲食店を運営 タウンダイニング
- インドアテニススクール タウンインドアテニスアカデミー


 一覧へ戻る
一覧へ戻る