土地活用の相談はどこでする?おすすめの相談先や選ぶ際のポイントを解説
所有する土地を使って利益を生み出す土地活用にはさまざまなメリットがありますが、相談先選びに悩んでいる方もいるのではないでしょうか。土地活用を成功させるためには、希望の活用方法に合わせて適切な相談先を選ぶことが重要です。
本記事では、土地活用の相談先や主な相談先、相談先を選ぶ際のポイントや成功させるためのポイントを解説します。
-

ここでは、土地活用の相談の流れと相談先を解説します。土地活用を検討する際は専門業者に相談し、必要に応じて専門家に相談や調査を依頼することで、調査結果に基づいたプランが提案されます。
土地活用を考え始めた時の流れ
土地活用を検討する際の流れは、以下の通りです。
1.専門業者への相談
賃貸マンションやアパートの経営などの土地活用に精通している専門業者に相談します。所有している土地の規制を確認することも重要です。
なお、相談する際は土地活用の目的や希望などを明確にしておくと話がまとまりやすいですが、土地の状況を伝えて相談しながら活用方法を決めるケースもあります。
2.専門家への相談や調査の依頼
必要に応じて専門家に相談や調査を依頼します。例えば、資金計画や税金に関して不明点がある場合は税理士やファイナンシャルプランナーへの相談が必要です。
なお、こうした専門家は専門業者に所属しているケースも多いため、ステップ1の段階で提携している専門家を紹介してもらえる可能性があります。
3.土地や市場の調査
専門業者が土地の状況を調査して、最適な活用方法を見つけます。調査項目は土地の広さや形状、地盤や法規制や周辺の環境などです。
また、収益物件を建築・運用する場合は周辺の需要も調査します。調査項目は周辺の賃料や店舗・事務所の需要などです。
4.プランの提案
オーナーの希望と調査結果を基に、具体的なプランを提案します。需要が見込まれる場合は建物を建てて活用する方法が有力な選択肢になり得ますが、土地をそのまま活用したり売却したりするケースも少なくありません。
また、この段階になればおおよその費用も算出できるため、資金計画も立てられる見込みです。事業計画や資金計画が固まったら、契約へと進みます。土地活用にはさまざまな相談先がある
土地活用に関する相談先は多岐にわたり、それぞれによって得意分野や専門領域が異なります。土地活用では不動産の知識だけでなく、法律や資金・税金に関する知識も必要です。そのため、自身の目的や解決したい悩みに合わせて適切な相談先を選ぶ必要があります。どんな選択肢があるのかを把握し、それぞれの特徴を理解することが重要です。
-

ここでは、土地活用に関する相談先を紹介します。主な相談先として、不動産会社やハウスメーカーや工務店などが挙げられます。
不動産会社
不動産会社は、土地・建物の売買・賃貸・仲介・管理などを行う会社です。その地域の情報に詳しく、需要に基づいた活用方法を提案してもらえます。賃貸経営のサポートもしてくれるため、借地として土地を活用したい場合におすすめです。
また、売却の相談も可能ですが、土地を売却するとその後の収益にはつながりません。税金や管理コストがなくなるのはメリットですが、どんな土地も収益性を見つけ出せる可能性はあるため、さまざまな視点から検討することが重要です。
なお、借地や売却の際は、不動産契約の知識や手続きが必要になるため、不動産会社の仲介を受けることになります。ハウスメーカー
ハウスメーカーは、住宅の設計・建築・販売などを行う会社で、全国規模で展開している会社を指すのが一般的です。基本的に商品が規格化されているため、独自性には欠けますが、失敗しにくい確実なプランを見つけられます。
また、規格化された建材を工場で加工し、マニュアル化された工程で進めるため、品質にばらつきが出にくく建築期間も短い傾向です。さらに、グループ内に管理会社や不動産会社を持っている会社も多いため、竣工後の管理までまとめて対応できるでしょう。特に、アパート経営や賃貸併用住宅の建築などを検討している人におすすめです。工務店
工務店は、主に地域に密着して住宅の新築・増改築などの工事を請け負う会社です。ハウスメーカーとは異なり設計の自由度が高く、注文住宅の施工を得意としています。そのため、変わった形をした土地や面積が小さい土地を活用する際に向いているでしょう。また、地域密着型の会社が多く、その地域の需要や特徴に敏感です。
ただし、現場施工が基本のため、施工期間は長くなる傾向があります。また、階数や戸数が多い建物といった大規模な工事には向いていません。デベロッパー・建設会社
デベロッパー・建設会社は、土地や街の企画・開発や大規模な建設工事を行う会社です。資金力やブランド力が高く、大規模な事業を幅広く手掛けています。そのため、立地の良い場所や商業地、または広い土地を持っている場合におすすめです。
ただし、規模が大きいため、施工期間が相対的に長期化する傾向が見られます。また、取引先の多くは会社・法人のため、個人の相談には応じないケースも少なくありません。さらに、下請け業者に工事を依頼するため、建築費が通常より高くなりやすいといわれます。設計事務所
設計事務所は、建築物の設計や工事監理を専門に行う事務所です。土地の形状・面積や法規制などの考慮しながら設計してくれるため、条件の悪い土地でも活用できる可能性が広がります。
ただし、設計事務所の業務に施工は含まれないため、別途ハウスメーカーや工務店などに建築を依頼しなければなりません。また、管理会社の手配も自分で行う必要があります。特定の土地活用に特化した専門業者
初期投資を抑えたい人や条件の悪い土地を持っている人は、各種専門業者に依頼するのも一つの手です。駐車場経営やトランクルーム経営など特定の土地活用に特化した専門業者に依頼することで、手軽に土地活用ができます。
役所の相談窓口
土地活用に困っている場合は、役所の相談窓口を利用する選択肢もあります。例えば、資産価値がなく所有していても維持費や税金ばかりかかる、いわゆる「負動産」は売却が困難です。その場合、役所に相談することで、空き家バンクに登録してもらえたり公有地として買い取ってくれたりする可能性があります。
また、どんな建物が建てられるか確認する際にも有効です。役所の建築課に相談すると、建ぺい率・容積率・高さ制限など土地利用の制限を教えてくれます。どのような活用方法が良いかまでは提案してくれませんが、法規制を把握することで土地活用の選択肢を整理できるでしょう。
さらに、自治体によっては補助金制度が設けられている場合もあります。一般的に利用するためには申請が必要なため、お住まいの自治体の制度を確認することが重要です。
なお、相続や遺贈によって取得した土地は一定の条件を満たすことで国に引き渡せます。この制度を相続土地国庫帰属制度といい、2023年4月に施行されました。審査や手続きにはお金がかかりますが、選択肢の一つとして知っておくとよいでしょう。-

ここでは、土地活用の資金や税金に関する相談先を解説します。主な相談先として、税理士や金融機関やファイナンシャルプランナーが挙げられます。
税理士
税理士は、国が認める税の専門家です。土地には固定資産税や都市計画税や相続税などの税金が発生するほか、一定以上の不動産所得を得た場合は確定申告をしなければなりません。税理士に相談することで、税金対策や税務申告に関する正しい知識を得られます。特に、土地の規模が大きい場合は専門的なアドバイスが必要です。
金融機関
金融機関の中には、土地活用や相続に関する相談ができるコンサルティング部署が設けられている場合もあります。土地活用に関する業者を紹介してもらえる場合もあるため、スムーズに話が進むでしょう。
そもそも土地活用の資金が不足している場合、金融機関から融資を受けなければなりません。金融機関とのつながりを持っておけば、スムーズに融資を進められる可能性があります。また、融資を相談すれば、自身の事業計画を客観的に再検討する機会にもなるでしょう。
なお、土地を出資して専門業者に土地を有効活用してもらい、その収益から配当金を受け取れるサービスを提供している信託銀行もあります。こうしたサービスは土地活用や経営の知識がない初心者、自己資金を抑えたい人や安定した収益を得たい人に最適です。ファイナンシャルプランナー(FP)
ファイナンシャルプランナーは、個人の夢や目標を達成するためにお金に関する計画を立て、経済的な側面から実現をサポートする専門家です。土地活用の関連会社は売上に関わってくるため、自己利益を優先した発言がされるケースも少なくありません。一方、ファイナンシャルプランナーは土地活用の収支計画を第三者の立場で判断できます。
なお、不動産会社やハウスメーカーにはファイナンシャルプランナーが所属しているケースも少なくありません。しかし、この場合は中立的な意見かどうか相談者が見極める必要があります。-
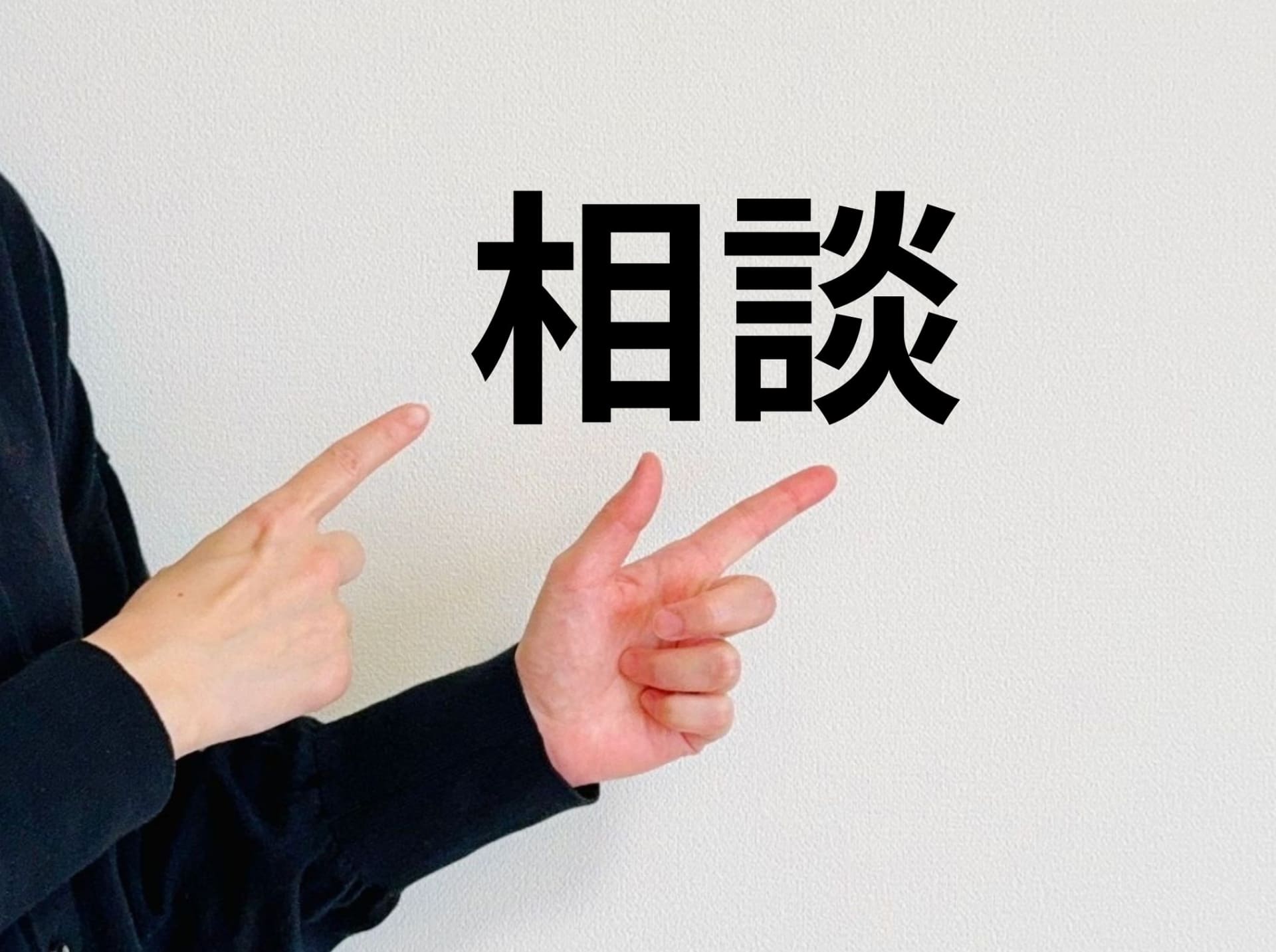
ここでは、土地活用の法律面に関する相談先を解説します。主な相談先は弁護士や司法書士です。
弁護士
弁護士は、高度な法律知識を備えた専門家です。土地活用に関する法律的な問題を解決したり契約書を作成・確認したりする際に相談します。相談できる主な法律的な問題は、相続土地の権利や土地の境界・日照権の問題などです。作成・確認してもらえる契約書として、土地の売買契約書や賃貸借契約書などが挙げられます。
ただし、弁護士は法律の専門家であり不動産の専門家ではありません。不動産に精通した弁護士に相談することが重要です。司法書士
司法書士は、登記や供託などを独占業務とする法律系の専門家です。主に、不動産登記に関する手続きや相続に関する法的な問題をサポートします。例えば、相続した土地の名義が被相続人のままの場合は名義を相続人に変更する相続登記が必要です。こうした手続きを司法書士に依頼すると滞りなく進めてくれます。
-

ここでは、主な土地活用の方法と、それぞれの方法に適した相談先を紹介します。土地は貸したり売却したりするだけでなく、賃貸経営や駐車場経営やトランクルーム経営などの活用方法もあります。
マンション・アパートなどの賃貸経営
マンション・アパートなどの賃貸経営は、安定した収入源を確保できる魅力的な選択肢です。法律上の建設可能地域も多く、比較的土地を選びません。
また、税制面で優遇措置を受けられるため、相続税や固定資産税を抑えられる可能性があります。さらに、物価上昇によるインフレリスクに強い点もメリットです。
しかし、マンションやアパートの建設には多額の費用がかかります。また、賃貸経営では融資を受けて家賃収入で返済していくのが一般的ですが、空室が発生すると想定通りの家賃収入を得られません。さらに、入居者対応や家賃回収や物件の維持・管理などの業務も発生するため、負担がかかります。
小・中規模のアパートの場合は工務店やハウスメーカー、大規模なマンションの場合はデベロッパー・建設会社が主な相談先です。また、不動産会社に相談すると事業計画の提案から管理業務まで任せられる可能性があります。トランクルーム経営
トランクルーム経営は、所有する土地にコンテナや建物を設置し、荷物保管スペースとして貸し出して収益を得る事業です。駅から遠い土地や変わった形をした土地や面積の小さい土地など賃貸経営に適さない土地でも、トランクルーム経営であれば活用できます。
また、賃貸物件に比べて利用者が入れ替わりにくいため、一度契約を獲得すれば長期間にわたって収益を得られるでしょう。維持・管理の負担が低いのもメリットです。
しかし、他の土地活用方法に比べて収益性は低いといわれます。また、立地によっては競合が多く、集客が難しいかもしれません。
主な相談先はトランクルーム経営の専門業者です。駐車場経営
駐車場経営も初期費用が比較的少なく土地の形状も選ばないため、一定の人気があります。取り壊す設備が少ないことから更地に戻しやすく、別の業態に転用しやすいのもメリットでしょう。
駐車場経営には、月極駐車場とコインパーキングの2種類があります。月極駐車場経営の場合、不動産会社に相談するのが一般的です。コインパーキング経営の場合は専門的な設備が必要になるため、専門業者に相談する必要があります。太陽光発電として活用
郊外に日当たりの良い広い土地を持っている場合は、太陽光発電として活用するのもおすすめです。維持・管理は定期的な清掃や点検のみであり、一部の作業は専門業者に委託するため、ほとんど手間はかかりません。
また、再生可能エネルギーで発電した電気は10kW以上あれば20年間固定価格で買い取ってもらえます。これを固定価格買取制度といい、この制度により長期にわたって安定した収入が見込めるでしょう。
ただし、賃貸経営ほどの高収益は期待できません。風水害や盗難のリスクもあるほか、設置コストの回収には最低でも10年かかるといわれます。
主な相談先は、太陽光発電専門会社や太陽光発電事業を手がける不動産会社です。業者によって価格や取り扱えるメーカーなどが異なるため、複数の業者を比較検討することをおすすめします。高齢者施設の建設
高齢化が進む現代社会では、安定した収益と社会貢献を両立させられる選択肢として高齢者施設の建設が注目されています。基本的に施設を運営する事業者に建物を一棟丸ごと貸し出すため、空室リスクはありません。賃料も毎月固定で契約期間も長期となるため、安定した収益を得られます。
また、清掃や照明器具の交換など小規模な修繕は施設を運営する事業者が行うため、管理する手間がかかりません。
ただし、高齢者施設の建設には大きな土地が必要になります。例えば、土地活用の対象となる主な高齢者施設は、老人ホーム・サービス付き高齢者住宅(サ高住)・グループホーム・デイサービスです。このうち、老人ホームやサ高住は最低でも300~400坪、グループホームやデイサービスは150坪以上の敷地面積を要するといわれます。必然的に建設規模も大きくなるため、ローン額も大きくなるでしょう。
なお、高齢者施設は福祉施設のため、バリアフリー設計や安全対策や一定の設備などが必要です。そのため、高齢者施設の建設の実績がある工務店・ハウスメーカー・建設会社に相談することをおすすめします。土地を貸す
所有している土地をそのまま法人や個人に貸し出し、地代を得るという方法もあります。不動産会社が主な相談先です。
一般的な土地活用では、建物の建設に伴い多くの初期費用がかかります。一方、土地を貸す場合は初期費用がかからないため、借り入れも不要でしょう。また、借地で賃貸経営を行っても管理するのは借主のため、管理の手間もほとんどありません。さらに、固定資産税や相続税の節税につながる可能性もあります。
ただし、土地を貸す際は借地権の種類に注意が必要です。借地契約には普通借地権と定期借地権がありますが、普通借地権は借主が契約延長を希望した場合、正当な事由がない限りオーナーは更新を拒否できません。土地の返還時に建てられている建物の買取が必要になる恐れもあるため、契約内容はしっかり確認する必要があります。土地を売却する
土地を売却して現金化するという選択肢もあります。不動産会社が主な相談先です。土地を管理する必要や固定資産税を納税する義務がなくなるほか、相続する際も分割しやすいというメリットがあります。
ただし、他の方法とは異なって定期的な収益は得られません。また、土地の売却により譲渡益が出た場合は譲渡所得税が発生します。他の方法で収益を得られる見込みがない場合は、売却を検討してもよいでしょう。-

ここでは、土地活用の相談先を選ぶ際のポイントを解説します。主なポイントとして実績や担当者の対応や提案内容などが挙げられるほか、複数の業者に相談して比較検討することも重要です。
検討している土地活用に関して十分な実績があるか
活用方法がある程度決まっている場合は、その分野で十分な実績を持っている会社を選ぶことをおすすめします。実績が豊富であれば、過去の事例に基づいて現実的かつ具体的な提案をしてくれるでしょう。
一般的にホームページから施工事例を確認できますが、確認できない場合は直接問い合わせるのも一つの手です。特に、高齢者施設は専門的な知識が求められるため、実績の有無が重要になります。相談先の口コミや評価が良いか
相談先を利用したユーザーの口コミや評判を確認することも重要です。対応の丁寧さや提案内容やトラブル発生時の対応など、実際にサービスを利用した人の声を聞かないとわからない部分もあります。
確認する際はホームページに掲載されているユーザーの声だけでなく、比較サイトやGoogleマップの口コミなど第三者の評価も確認することが重要です。ただし、評価や価値観はユーザーによって異なるため、参考程度にとどめるとよいでしょう。長期的な収益が見込める具体的なプランを提案してくれるか
相談先からプランを提案された際は長期的な収益を見込めるかどうか、具体的かつ実現可能かどうか確認することが重要です。例えば、賃貸住宅は新築であれば人気が高く入居者を獲得しやすいですが、年月が経過すると空室率が上がりやすくなります。こうした変化やリスクを想定していないシミュレーションを鵜呑みにすると、想定通りの収益を得られないでしょう。
そのため、どのような根拠で収益を予測しているのか、提案内容で考えられるリスクとその対策を確認することをおすすめします。自身で判断できない場合は、ファイナンシャルプランナーや税理士に確認してもらうのも有効です。担当者の対応が丁寧で相談しやすいか
土地活用は数十年単位で進むケースが多く、担当者とは長く付き合うことになるため、担当者の対応が丁寧で相談しやすいかどうかも重要になります。人柄が合わない、または対応が不誠実な担当者の場合、計画の進行に支障が出るかもしれません。
質問や連絡に迅速かつ丁寧に対応してくれるか、専門用語を避けてわかりやすく説明してくれるかなどを確認し、信頼できる担当者を見つけましょう。逆に無理に契約を迫るような強引な営業をする担当者や、利益を優先するために顧客に隠し事をする担当者は要注意です。複数の業者に相談することも検討する
一社だけに相談すると最適な活用方法を見落とすだけでなく、適正な価格やプランも見極めにくくなるため、高額な費用を支払ってしまう恐れがあります。そのため、複数の業者に相談して比較検討することが重要です。
最低でも2~3社以上と相談するのが理想で、設計や収支計画など提案内容に魅力を感じた会社があれば追加の希望を伝えてプランをブラッシュアップします。プランの検証にかかる期間は約1か月~半年が目安です。-

ここでは、土地活用をスムーズに相談するためのコツを紹介します。必要資料を準備し、活用目的や要望を整理したり自分の土地を説明できるようにしたりすることがポイントです。
自分の土地について説明できるようにする
相談先から的確なアドバイスをもらうためには、自分の土地について説明できるようにすることが必要です。土地の広さや立地や地形はもちろん、自身の年収や自己資金額も伝えると最適なプランを提案してくれる可能性が高まります。長所だけでなく土地の形状が悪い、日当たりが悪いなどの短所も隠さずに伝えると現実的なアドバイスをもらえるでしょう。
必要な資料を準備する
口頭での説明だけでなく、客観的な資料もあると正確な情報を伝えられます。必要になる資料は登記簿謄本や固定資産税納付書、地積測量図や権利書などです。
登記簿謄本と地積測量図は法務局から取得でき、固定資産税納付書は毎年4~6月頃に市区町村から送付されます。権利書は土地を新たに取得した際に法務局から発行されますが、再発行はできないため、大切に保管しましょう。活用目的や要望を整理して伝える
目的によって最適な活用方法は異なるため、活用目的の整理が重要です。例えば、収益を最大化したい場合は賃貸経営、初期費用を抑えたい場合は駐車場・トランクルーム経営や借地が適しています。
また、デザインや費用感など複数の要望がある場合は優先順位も含めて伝えておきましょう。目的や要望を明確に伝えることで、自分と相談先とのイメージのズレを防ぎ、納得のいく土地活用を実現できます。相談費用を確保する
初回相談を無料としている場合もありますが、一般的にファイナンシャルプランナーや税理士や弁護士などへの相談は有料です。また、一般的に不動産会社やハウスメーカーへの相談は無料ですが、市場調査や分析は料金が発生する場合もあります。
そのため、相談する際は事前に料金の有無・金額を確認し、費用を確保しましょう。一般的に、ファイナンシャルプランナー・税理士・弁護士などの相談費用は30分あたり5000~1万円が相場です。希望する連絡手段を決める
一般的に相談先にプランを請求すると、数日以内に電話やメールで連絡が来ます。プランを提案するために必要な情報がある場合は、追加のヒアリングも必要です。
複数の企業にプランを提案してもらい比較検討する場合は何件も電話が来るため、負担に感じる人は事前にメールでの連絡を希望しましょう。希望する連絡手段を決めておくことで、スムーズかつ効率的にやり取りできます。-

ここでは、土地活用のメリットを解説します。安定した収入が見込める点や土地を所有し続けられる点、税金対策になる点が主なメリットです。
安定した収入が見込める
賃貸経営や駐車場・トランクルーム経営などの方法で土地を活用することで、入居者や利用者から家賃や利用料を定期的に得られます。自身が働かなくても継続的に得られる、安定した不労所得です。土地活用のためにローンを借り入れている場合はその返済に充てる必要がありますが、余った分は貯蓄や老後資金などに活用できます。
また、こうした収入は景気変動や市場環境など外的要因の影響を受けにくいのも特徴です。特に、生活に欠かせない賃貸物件は景気が悪化しても需要が大きく落ち込まないため、長期にわたって収入が見込めます。売却しなければ土地を所有し続けられる
土地は商品としての側面だけでなく、そこでの生活体験や家族の歴史など思い入れの側面も持っています。特に、古くから受け継がれてきた土地や自分の生まれ故郷である土地は、簡単には手放せません。
しかし、土地を所有するだけでも固定資産税や管理費用などはかかるため、経済的な問題で売却を考える人もいます。土地活用で収益を得られれば売却せざるを得ない状況を回避でき、思い入れのある土地を所有し続けられるのです。相続税対策になる
相続税は亡くなった人が残した財産の評価額に対して課税されますが、土地活用はこの評価額を下げるうえで有効な手段です。土地活用として賃貸物件を建築することで、その土地は貸家建付地となり、更地よりも評価額が下がります。そして建築したその物件を第三者に貸し出すと貸家として扱われるため、さらに評価額が下がるのです。
また、亡くなった人や同一生計の親族がその土地で事業を行っていた・土地を貸していた、貸付事業用の土地になっていた場合は小規模宅地等の特例が適用されます。これにより、一定の面積にかかる評価額を5~8割まで軽減可能です。
さらに、土地活用の際はローンを借り入れるケースが一般的ですが、借入金は相続財産から控除できるため、課税遺産額を減額できる可能性があります。ただし、借り入れると利息が発生するため、収益が低いと相続税を加味しても財産が減少するでしょう。所得税対策になる
土地活用で経営を始めた場合、個人事業主となるため経営で発生した費用を必要経費として計上できるようになります。課税所得は収入から経費や各種控除を差し引いて求められるため、さまざまな費用を経費として計上することで所得の圧縮が可能です。
例えば、賃貸経営の場合は物件の取得にかかった費用を減価償却費として経費にできます。事業の関係者と食事した場合は接待交際費、情報収集のために本を購入した場合は書籍代としていずれも必要と認められれば経費として計上可能です。
また、土地活用で得た利益は基本的に不動産所得として扱われますが、不動産所得は確定申告の際に給与所得や事業所得などと合算して申告します。これを損益通算といい、不動産所得が赤字の場合は他の所得からその分を差し引けるため、課税所得を減らせるのです。固定資産税対策になる
不動産を所有している場合は固定資産税や都市計画税が毎年かかりますが、土地活用を始めるとこれらの税金を減らせる可能性があります。土地が更地の場合は評価額が課税標準額(税金の計算の基礎となる金額)となりますが、住宅用の建物を建築すると固定資産税評価額が1/6まで軽減されることがあります。
また、都市計画税がかかる地域の場合、評価額は1/3まで軽減されます。ただし、駐車場やトランクルームなどは住宅として扱われないため、更地と同じ評価になり、固定資産税評価額は下がりません。-

土地活用にはさまざまなメリットがある一方、いくつかのリスクもあります。ここでは、土地活用のリスクを解説します。
初期費用・ランニングコストがかかる
活用方法によって異なりますが、基本的に土地活用で収益を得るためには物件・施設の建築・建設や設備の設置が必要になるため、初期費用がかかります。既設の建物や設備がある場合は解体費や立ち退き費用も発生するため、さらに初期費用がかさむでしょう。
また、物件・施設は建てた後も維持・管理する必要があるため、ランニングコストも発生します。固定資産税や都市計画税などの税金もかかるため、初期費用やランニングコストは正確に見積もることが重要です。空室が発生すると支出が増える恐れがある
賃貸経営の場合、空室が発生すると収益が得られなくなり、支出が増える恐れがあります。特に、ローンを借り入れている場合は自己資金から捻出する必要があるため、返済が困難になるかもしれません。賃料を下げれば空室が埋まる可能性はありますが、その場合は収益性が下がります。
空室が発生する主な原因は不適正な賃料や立地の悪さ、需要のミスマッチなどです。土地活用ではこれらのリスクを考慮し、その土地に合った活用方法を選ぶ必要があります。希望するタイミングで売却できないケースがある
不動産は購入希望者が現れるまでに時間がかかり、一般的に売買の完了には数か月要するため、希望のタイミングで売却できないケースがあります。特に、立地や形状が悪い土地や道路への接地面が狭い土地や傾斜地などは売却しづらい傾向です。
また、借地の場合は定期借地権で契約期間を決めて土地を貸し出すと契約が満了するまで解約・売却できません。損失を最小限に抑え、希望のタイミングで現金化できるようにするためにも出口戦略を意識しておくことが望ましいといえます。金利が上昇して返済額の負担が大きくなる恐れがある
土地活用ではローンを借り入れるケースも多いですが、変動金利でローンを借り入れた場合、金利が上昇すると月々の返済額が増加してしまいます。不動産の収益だけでは返済が困難になり、手持ちの資金から返済しなければならなくなるかもしれません。
金利上昇リスクを回避したい場合は、頭金を多く入れて月々の返済額を減らす、もしくは固定金利型での借り入れを検討しましょう。賃貸経営では入居者トラブルに注意が必要
賃貸経営の場合、入居者がトラブルを起こすリスクもあります。具体的には、家賃滞納や騒音トラブル、設備の破損や無断でのペット飼育などです。こうしたトラブルが発生すると物件の評判が下がり、空室率が上昇したり収益性が悪化したりする恐れがあります。
入居者トラブルを避けるためには、入居者募集時に信用できる入居者を選んだり入居者へのルール説明を徹底したりすることが重要です。-

ここでは、土地活用を成功させるためのポイントを解説します。リスクを理解し、市場調査をしたうえで、立地に適した方法を選んだり具体的な収支計画を立てたりすることが重要です。
リスクを理解しておく
前述した通り、土地活用には空室リスクや金利上昇リスクなどさまざまなリスクがあります。土地活用を成功させるには、これらのリスクを理解し、対策を立てることが重要です。例えば、空室リスクは周辺の競合物件にはない特徴を持たせることで、金利上昇リスクは自己資金を3割程度準備することで対策できます。
立地に適した方法を選ぶ
どのような土地でも土地活用の対象になるとは限らないため、日当たりや広さや周辺環境を確認して特性を生かした方法を選ぶことが重要です。賃貸経営に不向きな土地でも、駐車場経営であれば成功する可能性があります。
なお、活用方法を選ぶ際は用途地域の確認も必要です。用途地域とは、都市計画法に基づき用途に応じて分けられたエリアで、計画的に街づくりをするために定められています。用途地域によっては、希望の土地活用方法が選べない可能性があるため留意が必要です。周辺の地域を調査してニーズがあるのか見極める
賃貸経営を行う場合は、周辺の地域を調査してニーズがあるのか見極めましょう。ニーズがない土地活用方法では収益が見込めず、損失につながりかねません。
ターゲットとする顧客層が求めている物件のタイプや規模、必要な設備や家賃相場などを調査し、その土地に合った活用方法を選ぶことが重要です。専門の不動産会社やハウスメーカーに相談して土地活用のプランを請求すれば、プロに市場調査を依頼できます。具体的な収支計画を立てる
事業を成功させるうえで、具体的な収支計画の立案は不可欠です。これにより、資金不足のリスクを抑え、事業が成功する可能性を検証できます。
例えば、賃貸経営では初期費用やランニングコストやローンの返済額などを算出し、家賃収入と比較することで収益性や安全性を把握可能です。収支計画は一般的に不動産会社やハウスメーカーなどに作成してもらえるほか、金融機関やファイナンシャルプランナーに計画の妥当性を確認してもらえます。過度な借り入れに注意する
土地活用では高額な初期費用がかかるケースも多いですが、過度な借り入れは返済不能リスクを高めるおそれがあるため、回避を検討するのが無難と考えられます。金融機関によっては融資に積極的な場合もありますが、借入可能額と適切な借入額は異なります。シミュレーション通りに収益が上がらなくても無理なく返済できるように、余裕のある資金計画を立てましょう。
節税だけを目的にした土地活用をしない
土地活用には固定資産税や相続税を節税できるメリットがありますが、節税だけを目的にすると収益が低くても問題ないと判断してしまう恐れがあります。そもそも土地活用は納税の先延ばしであり、うまく活用しなければ節税効果は得られません。総合的な視点で土地活用を考え、土地の特性に合わせた活用方法を選ぶことが重要です。
-

土地活用の相談先は不動産会社やハウスメーカー、金融機関や弁護士などさまざまあります。土地を貸す・売却する場合は不動産会社に、賃貸経営の場合はハウスメーカーや工務店に相談するのが一般的です。駐車場経営やトランクルーム経営などは、特定の土地活用に特化した専門業者に相談します。
相談先を選ぶ際は実績や担当者の対応や提案内容がポイントとなり、複数の業者に相談して比較検討することも重要です。必要資料を準備したり活用目的や要望を整理したりしておくと、スムーズに相談が進みます。周辺の市場調査を行い具体的な収支計画を立てて、土地活用を成功させましょう。関連記事
-
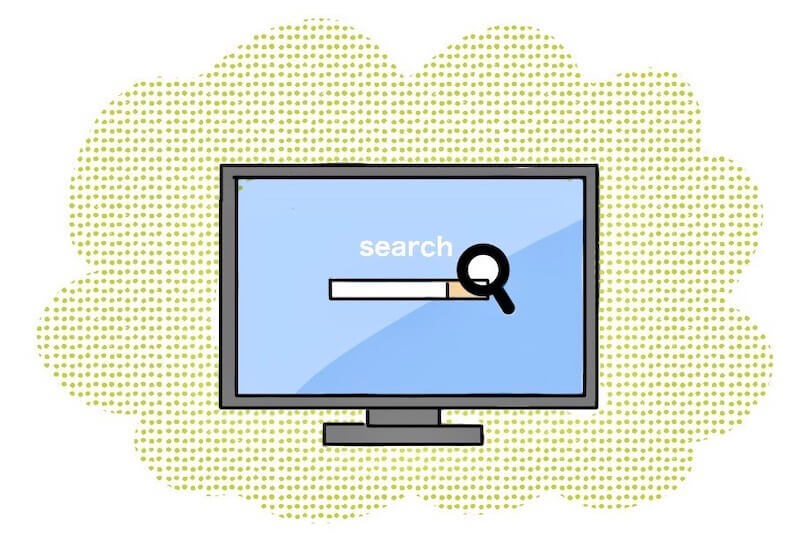 いらない土地を国に返す!相続土地国庫帰属制度やほかの処分方法などを解説!詳しく見る
いらない土地を国に返す!相続土地国庫帰属制度やほかの処分方法などを解説!詳しく見る「いらない土地を処分したい」と考えている方も多いのではないでしょうか。近年では、「先代から所有している地方の土地の相続先が決まらない」「相続した田舎の山林を手放す手段を探している」など、さまざまな悩みを抱えている方が増えています。土地を所有していると固定資産税や管理費用などが発生するため、放置することもできません。 このような土地の扱いに悩む方々を対象に、新たな法律の成立が始まっています。その法律を「相続土地国庫帰属制度」と言います。この記事では、相続土地国庫帰属制度の概要や具体的な利用方法、注意点などを詳しく解説します。
-
 アパート経営でインターネットを導入するには?費用やポイントを解説詳しく見る
アパート経営でインターネットを導入するには?費用やポイントを解説詳しく見るインターネットを無料で利用できるアパートは多くの需要がありますが、実際に導入しているアパートはあまり多くありません。そのため、アパート経営をするにあたりインターネットの導入を検討しているオーナーの方は多いでしょう。インターネット環境の有無で入居を決めるケースは増加傾向のため、入居率アップを狙うなら早めに導入するのがおすすめです。 この記事では、アパート経営で成功を収めたい方向けに、インターネット導入の費用相場や導入で失敗しないためのポイントなど、インターネット導入方法を解説します。 しかし、所有している土地でアパート経営を始めるには、いくつかのリスクがあることも覚えておきましょう。それぞれのリスク回避のために適切な対策を行って、効率的な土地活用を行いましょう。 この記事では、土地有りでアパート経営を行うメリット・デメリットについて、そして経営を進める時の流れや必要な資金などについて解説します。
-
 不動産の利回りとは?20パーセントを超える物件は多いのか詳しく見る
不動産の利回りとは?20パーセントを超える物件は多いのか詳しく見る不動産投資といった資産運用には、毎年の収支を予測するのに有効な指標である利回りが存在します。不動産投資用の物件を長期経営するには、利回りは重要な数値です。 投資を実施する際は投資用物件の利回りを確認し、高利回りの物件を探しますが、利回りの相場はどのくらいなのでしょうか。 この記事では一つの基準として、利回りが20パーセント以上ある物件の特徴や種類、基本的な利回りの相場、利回り改善の方法などを解説します。
タウングループ不動産仲介・周辺事業- 賃貸不動産仲介(東京・神奈川・埼玉・千葉) タウンハウジング
- 賃貸不動産仲介(東海) タウンハウジング東海
- 賃貸不動産仲介(九州) タウンハウジング福岡
- 土地・建物の不動産販売及び仲介 タウン住宅販売
- 首都圏を中心に引越サービスを展開 タウン引越サービス
- 賃貸不動産仲介(東北) タウンハウジング東北
- 賃貸不動産仲介(北関東) タウンハウジング北関東
建築事業- 賃貸住宅の企画・設計・施工 アヴェントハウス
多角化事業- 都内を中心に飲食店を運営 タウンダイニング
- インドアテニススクール タウンインドアテニスアカデミー


 一覧へ戻る
一覧へ戻る