自宅の売却で税金がかからないケースとは?受けられる特例はある?
自宅などの不動産を売却して売却益が出た場合、その利益に応じて税金が発生します。不動産の売却に関係する税金はさまざまありますが、売却時に必ずしも税金が課されるわけではありません。
この記事では、自宅の売却で税金がかからない条件や、税負担を軽減できる特例制度の概要などを解説します。
-

転勤やライフスタイルの変更など、自宅を売却する理由はさまざまです。不動産を売却する場合、「登録免許税」や「譲渡所得税」といった税金が発生しますが、どの税金がどのタイミングで課税されるのかは、状況によって異なります。そのため、自宅を売却する際はどういった税金がいくら発生するのか、支払いのタイミングなどを把握しておくことが大切です。
ここでは、不動産売却に関連する4種類の税金について解説します。登録免許税
登記費用とも呼ばれる登録免許税は、所有権移転登記や抵当権抹消登記といった、登記手続きの際に課される国税です。固定資産税評価額に、各種利率をかけて税額を算出します。
例えば、自宅を売却する場合は、抵当権が残っていると売却のために抵当権抹消登記を行う必要があり、このときに登録免許税がかかります。抵当権抹消登記にかかる登録免許税は、不動産1件につき「1,000円」課税されますが、建物と土地はそれぞれ別で抵当権が設定されているケースも見られるため、合わせて「2,000円」かかると把握しておくとよいでしょう。売却する自宅に抵当権が付いていないのであれば、抵当権抹消登記が不要のため、登録免許税は発生しません。
なお、不動産取引で所有権移転登記を行う際は、基本的に買主が負担します。印紙税
印紙税とは印紙税法に基づき、契約書や借用書といった課税文書に課される税金です。自宅を売却する際は売買契約を締結しますが、その際に作成する不動産売買契約書は課税文書に該当するため、収入印紙を対象の契約書に添付して納付することになります。
印紙税は、契約金額や文書の種類によって税額が変わります。以下に、自宅の売却において発生する印紙税について、契約金額別の税額をまとめました。
不動産の譲渡に関わる契約書においては、平成26年4月1日から令和9年3月31日までの期間に作成される文書に、軽減措置が適用される期間が設けられています。契約金額 印紙税額(本則税率) 印紙税額(軽減税率) 10万円以下 200円 200円 10万円以上50万円以下 400円 200円 50万円以上100万円以下 1,000円 500円 100万円以上500万円以下 2,000円 1,000円 500万円以上1,000万円以下 10,000円 5,000円 1,000万円以上5,000万円以下 20,000円 10,000円 5,000万円以上1億円以下 60,000円 30,000円 1億円以上5億円以下 100,000円 60,000円 5億円以上10億円以下 200,000円 160,000円 10億円以上50億円以下 400,000円 320,000円 50億円以上 600,000円 480,000円
自宅の売却に関しては、上記の表の1,000万円〜1億円の範囲に収まるケースが多いと考えられます。この範囲内であれば、印紙税の相場は1万円から3万円程度です。
電子契約で売買契約を結ぶと、契約書が電磁的記録として扱われます。電磁的記録には印紙税が課されません。また、不動産売買契約書の原本を買主に渡し、原本のコピーを売主が持つ場合、売主に印紙税は課税されません。譲渡所得税
譲渡所得にかかる税金として、所得税・住民税・復興特別所得税が課されます。不動産を売却した日から翌年に確定申告を行って納付します。
譲渡所得税は、不動産の所有期間に応じて税率が異なります。税の種類や税率の違いは以下の通りです。
短期譲渡所得は、売却した年の1月1日時点で不動産の所有期間が「5年以内」、長期譲渡所得は「5年以上」が条件です。復興特別所得税は、2037年12月31日までと定められています。所得税 住民税 復興特別所得税 合計 短期譲渡所得 30% 9% 0.63% 39.63% 長期譲渡所得 15% 5% 0.315% 20.315%
上記の表から、短期譲渡所得に該当する場合は「39.63%」、長期譲渡所得では「20.315%」の税率が「譲渡所得」に適用される仕組みです。2つの区分を比較すると、所有期間が短いほど税率が高い傾向があります。
譲渡所得は、「譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除」の計算式で算出します。消費税
自宅を売却すると、場合によっては消費税が発生します。以下では、消費税がかかる条件とそうでないケースを確認しましょう。
<消費税がかかる場合>
1.課税事業者が事業用の不動産を売却する
事業用の不動産を課税事業者(消費税の納付義務がある法人や個人事業主)が売却するときは、消費税の課税対象になります。例えば、家賃収入を得るための賃貸マンションを売却するケースなどです。
2.司法書士への報酬
所有権移転登記など売却時に行う手続きは、司法書士に依頼するケースがほとんどです。司法書士に対して支払う報酬は、消費税の課税対象になります。
3.不動産会社に支払う仲介手数料
不動産会社に依頼して自宅を売却する際は、仲介手数料が必要です。仲介手数料は、売却金額によって上限が決められています。
4.ローンの手数料
住宅ローンの繰上げ返済を行うと、金融機関によっては手数料がかかります。その手数料が消費税の課税対象です。
<消費税がかからない場合>
1.免税事業者が不動産を売却する
個人事業主・法人に関係なく、売主が免税事業者であれば消費税はかかりません。
2.自宅の売却
自宅や別荘といった非業務用の不動産を売却した際は、消費税が非課税とされています。
3.土地
不動産の中で、土地には消費税が発生しません。例えば建物が2,000万円、土地が1,000万円で売却できたとき、消費税の課税対象になるのは建物部分の2,000万円のみです。-

上述したように、自宅を売却するとさまざまな税金が課税されます。しかし、「売却益が出ない」「3,000万円控除の特例を受ける」といったケースでは、税金がかからない可能性があります。
売却しても利益が出ない
売却益が出ないということは、譲渡所得が得られていない状況です。つまり、売却益に対して譲渡所得税が発生しません。自宅を売却して譲渡所得がマイナスになり、損をした状態を「譲渡損失が発生」といいます。
例えば、3,000万円で購入した自宅を3,500万円で売却すると、500万円の売却益が発生し、その500万円に譲渡所得税が課税されます。一方で、3,000万円で購入した自宅を2,800万円で売却した場合は、200万円の譲渡損失が発生したことになり、譲渡所得税は課税されません。「居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の特例」を利用する
自宅の売却時に一定の要件に該当する場合は、所有期間の長さに関係なく「居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の特例」が受けられます。この特例を受けると、自宅の売却によって得た譲渡所得(売却益)が3,000万円以下であれば、税金はかかりません。
適用するための要件は決まっているものの、自宅を売却するのであれば基本的にこの特例を活用できるケースが多いと考えられます。なお、売却益を3,000万円以上得たときでも、この特例は利用可能です。
「3,000万円控除の特例」に関する詳細は、次の項目で解説します。-

自宅などの不動産を売却すると、原則として譲渡所得税が課税されます。売却金額が高いほど譲渡所得税も高くなるため、負担が大きくなるでしょう。
「3,000万円控除の特例」を利用できれば、譲渡所得税を大幅に抑えることが可能です。場合によっては、税金が課税されることなく自宅を売却できる可能性もあります。ここでは、「3,000万円控除の特例」について、仕組みや要件を解説します。「3,000万円控除の特例」を受けるための要件
特例を受けるには、以下で挙げる要件のいずれかを満たさなければなりません。
・住んでいる自宅を売却すること、または住まなくなってから3年目までに売却すること
・親や夫婦といった特別な関係の人以外に売却すること
・別荘など娯楽や保養のための住宅でないこと
・自宅を売却した年の前年と前々年に、この特例を受けていないこと
・自宅を売却した年と前年、前々年に、「マイホーム買換えの特例」など他の特例を受けていないこと
・自宅を売却した年の前年と前々年に、損益通算や繰越控除を受けていないこと
・自宅を解体して売却する場合は、解体から売買契約を締結するまでに敷地を貸し駐車場といった別の用途に使用していないこと
・自宅が災害によって滅失した場合は、住まなくなってから3年目までに売却すること
ただし、上記の要件は一部を抜粋したものです。特例の適用を検討する場合は、国税庁のホームページで要件に該当しているかどうか確認しましょう。「3,000万円控除の特例」と併用できない制度
「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」との同時利用はできません。「3,000万円控除の特例」を受ける年の前年から3年前の間に、売却した自宅以外の不動産に住宅ローン控除を適用していた場合も同様です。
住宅ローン控除とは、住宅ローンを組んで自宅を購入したケースで、ローン残高に応じて税金が還付される制度です。売却した自宅に「3,000万円控除の特例」を適用して、新しく購入する自宅に住宅ローン控除を利用することはできません。そのため、自宅の買い換えを検討している場合は、どちらの控除を利用するのかシミュレーションを行ったうえで考える必要があります。
また、「特定の居住用財産の買換えの特例」も併用できません。この特例については、別の項目で詳細を解説しています。特例の対象にならないケース
特例を適用できれば、節税対策として有効です。しかし、適用要件を満たしていても特例の対象にならないケースがあります。
特例の対象外となるケース例
・自宅を建築するまでの一時的な住まいとして入居していた
・所有以外の目的で一時的に入居していた
・「3,000万円控除の特例」の利用が目的で購入した
この特例は、あくまでも居住目的で所有していた不動産が対象です。マイホームであれば基本的に適用されますが、それ以外は適用対象になりません。手続きの流れと必要な書類
「3,000万円控除の特例」を受けるには、税務署で確定申告をする必要があります。確定申告を行う時期は、売却した翌年の2月16日から3月15日の間です。手続きが難しいときは、税理士に確定申告を依頼することも可能です。
特例を受けるために必要な書類を以下にまとめました。
確定申告書
国税庁のホームページや税務署で入手できます。
譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)
土地・建物用を用意します。確定申告書と同様に、国税庁のホームページや税務署で入手可能です。
戸籍の附票(コピー可)
売買契約を締結する前日において、売主の住民票に記載されている住所と実際の住所が異なる場合に必要です。戸籍の附票は役所で発行してもらえます。
売買契約書(コピー可)
売買契約書には、収入印紙の添付と消印が必要です。
譲渡した建物・土地の全部事項証明書
法務局で発行してもらえます。
本人確認書類
マイナンバーカードや住民票の写しが該当します。
確定申告では、さまざまな書類を用意しなければなりません。状況によって用意する書類が変わるため、期限までに余裕を持って税務署などに確認しましょう。「3,000万円控除の特例」を受ける際の注意点
特例を受ける際に注意しておきたいポイントは以下の3つです。
自動的に3,000万円が非課税になるわけではない
「3,000万円控除の特例」が適用できるといった通知が税務署から届くわけではないため、手続きは自身で進めなければなりません。適用を受ける場合は、売却の翌年に確定申告を行います。また、特例を受けて納税額が0円になっても確定申告は必要です。
共有名義では1人につき適用される
自宅の名義が複数人での共有の場合、名義人1人につき特例が適用できます。例えば、夫婦共有名義の自宅を売却する際は、夫と妻でそれぞれ特例を受けられるため、2人とも確定申告が必要となる場合があります。
本人がマイホームに住んでいなくても適用を受けられる可能性がある
売却する本人が、単身赴任や入院といった事情で自宅から離れて暮らしていた場合、離れて生活という事情が解消したときに自宅で生活することが認められれば、特例を適用できます。-

「3,000万円控除の特例」の他にも、税金を節税できる制度があります。ただし、制度を利用するにはそれぞれ定められている要件を満たさなければなりません。
以下では、自宅の売却時に適用できる可能性がある特例を4つ紹介します。「特定の居住用財産の買換えの特例」
「買換えの特例」は、住んでいた自宅を売却して新しい住宅を購入したときに、売却時の譲渡所得にかかる税金の支払いを繰り延べられる特例です。特例を適用できれば、購入した新しい住宅を将来売却するときまで、売却益を繰り延べられます。
特例を受けるための要件の一部を以下で紹介します。
・住んでいる自宅を売却すること、または住まなくなってから3年目までに売却すること
・親や夫婦といった特別な関係の人以外に売却すること
・令和7年12月31日までに売却すること
・売却金額が1億円以下であること
・売却した自宅と買い換えた住宅が日本国内にあること
・自宅を売却した年の前年から翌年までの3年間に、住宅を買い換えること
・自宅を売却した年と前年、前々年に、「3,000万円控除の特例」や「マイホームを売ったときの軽減税率の特例」「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」を受けていないこと
売却時と購入時の金額をよく確認してから特例を受けるかどうか検討しましょう。「マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」
自宅を売却して譲渡損失が発生した際に、新しい住宅をローンを組んで購入すると適用できる特例です。適用要件を満たすと給与所得や事業所得などと損益通算ができ、所得税や住民税を抑えられます。
適用要件の一部は以下の通りです。
・売却した自宅が居住用であること
・親や夫婦といった特別な関係の人以外に売却すること
・売却損失が発生している状態にあること
・売却した年の1月1日時点で所有期間が5年以上であること
・新居はローンで購入し、償還期間は10年以上であること
・新居は売却した年の前年から翌年までに購入し、床面積が50㎡以上あること
・売却した年の翌年までに新居に住むこと
・合計所得金額が3,000万円以内であること
損益通算をしても控除しきれなかった譲渡損失は、売却した年の翌年から最大3年繰り越して控除できます。「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」
住宅ローンの残っている自宅を、住宅ローンの残高を下回る金額で売却して譲渡損失が発生した場合に適用できる特例になります。新しく住宅を購入しなくても適用できる点がメリットです。
特例を受けるための要件の一部は以下の通りです。
・住んでいる自宅を売却すること、または住まなくなってから3年目までに売却すること
・親や夫婦といった特別な関係の人以外に売却すること
・売却損失が発生している状態にあること
・売却した年の1月1日時点で所有期間が5年以上であること
・譲渡した自宅の売買契約を行った日の前日において、償還期間が10年以上の住宅ローンの残高があること
・自宅の売却金額よりもローン残高のほうが多い状態であること
・合計所得金額が3,000万円以内であること
損益通算の限度額は、自宅の売買契約を行った日の前日における住宅ローンの残高から、売却金額を差し引いた金額となります。損益通算しきれなかった場合は、売却した年の翌年から最大3年の繰り越しが可能です。住宅の買い換えを行わないのであれば、この特例を検討してもよいでしょう。「マイホームを売ったときの軽減税率の特例」
10年以上所有していた自宅を売却した場合に、譲渡所得税の税率を下げることが可能な特例です。軽減税率を適用すると、課税譲渡所得が6,000万円以下までは「14.21%」、6,000万円を超えると「20.315%」となります。
この特例が適用される要件の一部を以下にまとめました。
・住んでいる自宅を売却すること、または住まなくなってから3年目までに売却すること
・親や夫婦といった特別な関係の人以外に売却すること
・売却した年の1月1日時点で、建物と敷地の所有期間が10年以上であること
・自宅を売却した年の前年と前々年に、この特例を受けていないこと
・売却した自宅に関して「マイホーム買換えの特例」などの特例を受けていないこと
・自宅を解体して売却する場合は、解体から売買契約を締結するまでに敷地を貸し駐車場といった別の用途に使用していないこと
・自宅が災害によって滅失した場合は、住まなくなってから3年目までに売却すること
所有期間が10年以上といった要件が定められていますが、この特例は「3,000万円控除の特例」との併用できるとされています。-

自宅を売却する際は、基本的に確定申告が必要です。ここでは、譲渡所得税の計算例を含め、確定申告の流れと必要書類について解説します。
自宅を売却する際にかかる税金の計算方法
課税譲渡所得金額を算出するときは、まず取得費・譲渡費用・減価償却費の3つを計算します。計算の流れを順番に見ていきましょう。
1.取得費を確認する
取得費は、建物と土地の購入金額になります。取得費になる主な項目は以下の通りです。
・不動産の購入金額
・建物の建築費
・登録免許税や不動産取得税、印紙税などの費用
・リフォーム費用
建物の取得費を計算する際は、建物の購入金額から減価償却費を控除します。減価償却費の計算式は、「減価償却費=建物購入価額×0.9×償却率×経過年数」です。
2.譲渡費用を確認する
売却に要した費用が譲渡費用です。譲渡費用に加えられる項目は以下になります。
・売主が負担した印紙税
・仲介手数料
・測量費
・建物の取り壊し費用
3.課税譲渡所得金額を計算する
譲渡所得は、自宅を売却した年の1月1日時点での所有期間により、税率が「長期譲渡所得」か「短期譲渡所得」に分かれます。適用税率については、前述の「譲渡所得税」の項目で解説しているのでご覧ください。
以下では、例を挙げて実際の税額を計算します。
売却時の状況
建物の売却金額:5,000万円
建物の購入金額:4,000万円
取得費:200万円
譲渡費用:200万円
建物の種類:鉄筋コンクリート(償却率0.015)
居住期間:8年(長期譲渡所得)
4,000万円×0.9×0.015×8=432万円(減価償却費)
4,000万円-432万円=3,568万円(建物取得費)
5,000万円-(3,568万円+200万円+200万円)=1,032万円(譲渡所得)
1,032万円×20.315%≒209万6500円(課税譲渡所得)
「3,000万円控除の特例」を適用できる場合、譲渡所得から「3,000万円」を控除できるため、この例では譲渡所得税は発生しません。税金を申告する流れ
確定申告の場所は、納税地の税務署です。譲渡所得の金額と納税額を「申告分離課税用の確定申告」と「譲渡所得の内訳書」に記入します。給与所得や事業所得などは「確定申告書」に記入しましょう。総合課税の確定申告書も同時に作成します。
確定申告に必要な書類
自宅を売却する際の確定申告に必要な書類は以下の通りです。
・譲渡所得の内訳書(不動産の売却金額や所在地などを記入する書類)
・確定申告書第一表及び第二表
・確定申告書第三表(分離課税用)・不動産売却や特例制度に関する書類
譲渡所得の内訳書や確定申告書に関しては、税務署や国税庁のホームページで入手できます。その他の書類は、不動産会社や法務局から入手が可能です。-

特例や控除を利用することは、自宅を売却する際の節税につながります。売却益をできるだけ多く得るためにも、可能な範囲で節税することが大切です。ここでは、節税のポイントを5つ紹介します。
譲渡費用は漏れなく計上する
不動産を売却したときの利益は、売却金額から取得費や譲渡費用を差し引いて算出します。そのため、取得時と譲渡時に発生した費用は、細かいものを含めて漏れなく計上することが重要です。取得費であれば自宅の購入金額や登録免許税、譲渡費用であれば仲介手数料や司法書士への報酬などを全て計上します。
なお、取得費に関しては記録が残っていないケースもあるでしょう。取得費が不明なときは、売却金額の「5%」を概算として計上できます。利用できる特例・控除は全て利用する
本記事ですでに解説した特例や控除の中で、利用できるものは最大限に活用しましょう。特例や控除を適用できれば、税負担の軽減につながります。併用して適用できる制度もあるため、適用要件や節税効果を考慮して検討する必要があります。
ただし、こういった特例や控除は自身で申告しなければならないため、申告漏れに注意です。売却のタイミングを見極める
売却する自宅の所有年数により、譲渡所得税が変わります。所有期間が5年未満と5年以上で税率が異なるため、売却のタイミングを見極めることが大切です。基本的に、長期所有のほうが税率の軽減が大きいため、自宅の売却時は所有期間が5年を超えているかどうかを確認しましょう。
「ふるさと納税」を活用する
ふるさと納税は、自治体に寄附をすることで返礼品を受け取れる制度で、寄附の一部が税金から控除されるという特徴があります。
自宅を売却したときに得た利益は譲渡所得として扱われるため、課税所得が上がり、個人住民税所得割額や所得税率が高くなります。そうすると、ふるさと納税の控除限度額も上がり、より多くの金額を自己負担なく寄附に回せる点がメリットです。不動産会社や税理士に相談する
不動産に関係する特例や控除は、自動的に適用されるものではなく、自身で申告するのが基本です。不動産会社や税理士に相談すれば、状況に合った最適な節税対策を提案してもらえる可能性があります。自宅の売却時にかかる税金について不安な場合は、専門家に相談するとよいでしょう。
-

自宅を売却すると各種税金がかかりますが、その他にも売却に際してはさまざまな費用が必要になります。ここでは、税金以外の費用について確認しておきましょう。
登記・抵当権抹消費用
自宅を売却する際は、所有権を売主から買主に変更する「所有権移転登記」が必要です。このときに登録免許税がかかり、費用は買主が負担します。
住宅ローンが残っている自宅を売却する場合、ローンの残債を精算した後に「抵当権抹消」の手続きを行うため、費用が発生します。ローンを完済していても、抵当権抹消手続きを行っていなければ、抹消手続きが必要になります。抵当権抹消のための登録免許税の費用は、不動産1件ごとに「1,000円」です。住宅ローンの返済手数料
自宅を売却する際の住宅ローン一括返済のため、金融機関に支払う事務手数料といった費用を指します。一括返済では、自宅の売却金額が充当されるのが基本です。手数料は、金融機関によって異なります。
各種書類の発行費用
自宅を売却する際は、住民票や固定資産税評価証明書といった書類を自治体や法務局などで発行してもらう必要があります。書類によって発行手数料は異なりますが、用意すべき書類にも費用がかかることに注意しましょう。
仲介手数料
売却の仲介を依頼した不動産会社に支払う手数料です。成功報酬として、自宅の売却が成立したときに支払います。
仲介手数料は、売買契約の締結時に半額を支払い、残りは買主に不動産を引き渡す際に支払うのが基本です。仲介手数料には上限があり、宅地建物取引業法によって取引金額ごとに上限額が決められています。引っ越し代
新しい自宅への引っ越し代も用意しなければなりません。引っ越し先の自宅が完成していない場合は、仮住まいへの引っ越しが必要です。住んでいた家から仮住まい、仮住まいから新居というように、2回分の引っ越し費用がかかることになります。
不用品の処分費用
新居に持っていかない家具や家電には処分の費用がかかります。不用品回収業者に頼んだり、粗大ごみに出したりといった方法がありますが、どれもある程度の処分費用が必要です。
測量費用
自宅と敷地部分の土地を同時に売却する場合は、土地の面積や境界線を明確にするために、測量を行わなくてはなりません。測量は専門の業者が行うため、依頼の費用が発生します。測量費用の目安は、35万円〜45万円程度です。
解体費用
自宅(建物)部分を解体し、土地のみを売却するケースも少なくありません。そういった状況では、建物の解体を業者に依頼しなければならないため、解体費用が発生します。
司法書士への報酬
登記手続きの数によって支払う報酬額は変わります。相場としては、10,000円〜15,000円ほどかかると見てよいでしょう。司法書士へ支払う報酬は、登記手続きのタイミングで、登録免許税とまとめて支払うケースがほとんどです。
-

税負担を抑えるために特例や控除を受けるように、かかる費用を抑えるにはコツがあります。ここでは、4つのコツを紹介します。
複数社に査定を依頼する
複数の不動産会社に査定を依頼することで、より安価な費用で対応してくれる会社を探せます。相場がどのくらいなのかも確認できるため、悪質な不動産会社を回避できるのもメリットです。複数社に査定依頼するのであれば、一括査定サービスの利用がおすすめです。
良質な不動産会社に依頼する
適切な売却活動を行ってくれる不動産会社に依頼するためには、良質な会社を選ばなくてはなりません。不動産会社を選ぶ基準としては、以下4つの特徴が挙げられます。
・査定価格が相場にあっている
・不動産売買の経験が豊富で業歴が長い
・不動産売買において得意分野がある
・販売戦略がしっかりしている資金は余裕を持って準備する
自宅の売却では、税金や手数料といった費用が発生します。自宅を売ったことで得られる売却益より、先に支払わなければならない費用もあるため、売却のための資金はある程度の余裕を持たせておくことが大切です。
かかる費用は売却金額の5%までを目安にする
自宅の売却で発生する費用や手数料の総額は、目安として売却金額の5%以下に収めるとよいでしょう。不動産売却時の費用の相場は、売却金額の5%〜10%になるケースが多く見られます。売却益の1割以上が費用になってしまうと、その後の引っ越しや生活に余裕を持ちにくくなる恐れがあります。
-

自宅など、不動産を売却すると登録免許税や印紙税、譲渡所得税といった税金が発生します。しかし、自宅を売却しても売却益が出なかったり、「3,000万円控除の特例」を受けたりした場合、税金がかからない可能性があるため確認が必要です。
自宅の売却時に適用できる特例や控除には、さまざまなものがあり、同じように節税可能なケースがあります。売却する自宅が要件を満たしているか確認し、適用するかどうか検討しましょう。関連記事
-
 安定してワンルームマンションを経営するために空室対策を押さえよう詳しく見る
安定してワンルームマンションを経営するために空室対策を押さえよう詳しく見る単身者向けの賃貸ワンルームマンションを経営しているオーナー様は少なくないでしょう。マンション・アパートに関係なく、賃貸物件を経営するうえでは、空室を発生させず安定した家賃収入を得ることが重要です。ワンルームマンションで空室を抑えるには、入居者様のニーズに合わせた空室対策を行わなければなりません。 この記事では、ワンルームマンションでおすすめの空室対策や、対策を実施する際のポイントなどを解説します。その他、空室が発生しやすい物件の特徴、入居率が上がりやすい物件についても紹介するため押さえておきましょう。
-
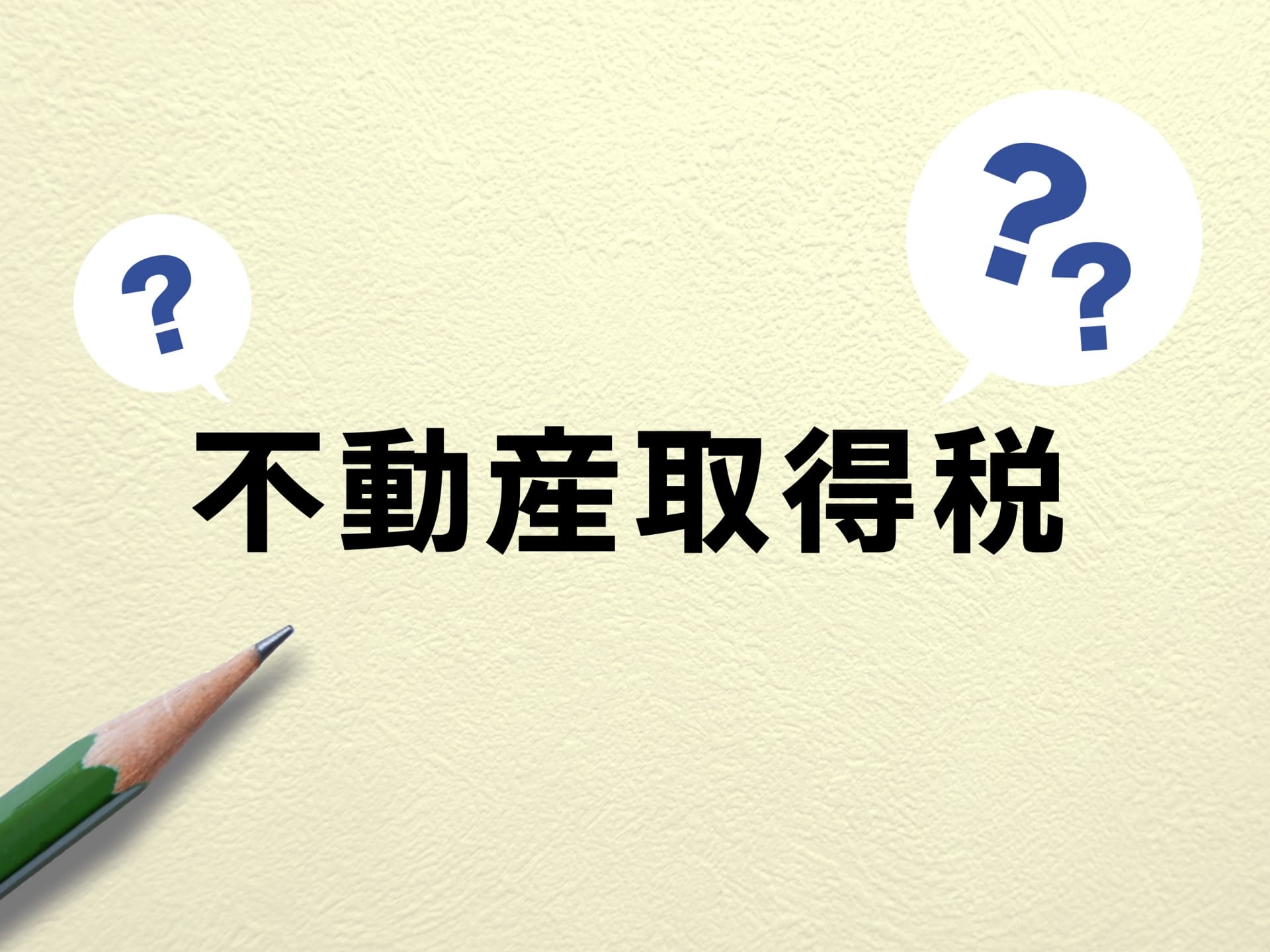 不動産取得税とは?軽減措置の概要や適用要件をわかりやすく解説詳しく見る
不動産取得税とは?軽減措置の概要や適用要件をわかりやすく解説詳しく見る不動産には、あらゆる税金が発生します。土地や住宅などの不動産を所有すれば固定資産税、不動産の登記には登録免許税など、ケースによって発生する税金はさまざまです。 土地を購入したり、新築住宅を建設したりする際には、「不動産取得税」を支払う義務があります。初めて不動産を取得する方にとっては、不動産取得税の仕組みや納税額がいくらかかるのか分からず、不安を感じることもあるでしょう。 そこで、この記事では不動産取得税の概要や納税額の計算方法、納付方法を紹介します。また、不動産取得税には軽減措置が適用されるため、軽減措置の適用要件や申請の流れなどに関しても分かりやすく解説します。
-
 居住用財産の3000万円控除は3年以内?住宅ローン控除の併用は?詳しく見る
居住用財産の3000万円控除は3年以内?住宅ローン控除の併用は?詳しく見る相続した実家を売却してマンション購入の資金に充てたい、使用する予定のない土地を売却して余計な固定資産税を抑えたいなど、不動産を売却する理由は人それぞれです。不動産によっては、高額での売却が可能なケースもあるでしょう。 しかし、不動産の売却時は譲渡所得税などが発生するため、安定した売却益を得るには節税対策も考えなければなりません。居住用財産の場合「3000万円控除」といった優遇制度が設けられているため、売却が有利になるでしょう売却が有利になる可能性があります。 この記事では、居住用財産の概要やその優遇制度、住宅ローン控除などを解説します。
タウングループ不動産仲介・周辺事業- 賃貸不動産仲介(東京・神奈川・埼玉・千葉) タウンハウジング
- 賃貸不動産仲介(東海) タウンハウジング東海
- 賃貸不動産仲介(九州) タウンハウジング福岡
- 土地・建物の不動産販売及び仲介 タウン住宅販売
- 首都圏を中心に引越サービスを展開 タウン引越サービス
- 賃貸不動産仲介(東北) タウンハウジング東北
- 賃貸不動産仲介(北関東) タウンハウジング北関東
建築事業- 賃貸住宅の企画・設計・施工 アヴェントハウス
多角化事業- 都内を中心に飲食店を運営 タウンダイニング
- インドアテニススクール タウンインドアテニスアカデミー


 一覧へ戻る
一覧へ戻る