アパート経営で必要な修繕費の目安は?修繕費を抑えるためのポイントを徹底解説
これからアパート経営を検討している方のなかには、多額の修繕費用が発生するのが不安な方も多いのではないでしょうか。アパート経営で利益を最大化するためにも、修繕費用は可能な限り抑えたいところでしょう。
修繕費はアパート経営を続けるうえで避けられない経費ですが、費用を抑えることはできます。まずは、どの箇所に修繕が発生するのかを把握しておきましょう。修繕箇所を把握したうえで、対策を講じることが重要です。
この記事では、アパート経営における修繕費の必要性や資本的支出との違い、必要となる修繕、修繕のタイミング、修繕箇所、修繕におけるポイント、修繕費を抑える方法についてご紹介します。
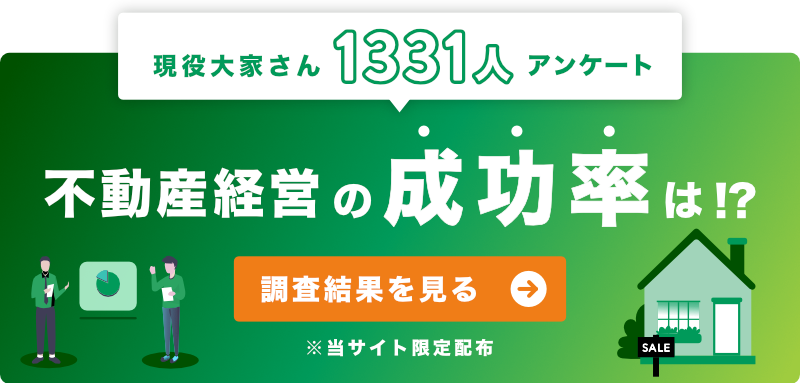
-

アパート経営では、「空室リスクを避けるため」「入居者様や近隣の住民、通行人の安全を守るため」などの理由で設備や建物の修繕が必要となります。
入居者様は暮らしやすさや利便性、快適さなどの住環境を希望する人が多いので、設備の修繕や投資をしないことで、現在の入居者様が出て行ってしまったり、新しい入居者様が見つからなかったりなどのリスクが発生します。入居者様の退去が繰り返されれば、原状回復費用の負担も増加するでしょう。さらに、空室が長期化すれば家賃収入の減少は避けられません。
また、設備や建物の修繕をすることは、入居者様はもちろん、近隣の住民や通行人の安全を守ることにもつながります。修繕を怠たりベランダや階段が崩壊して怪我人が出た場合、損害賠償責任を負うことになります。その際、本来負担すべき修繕費を遥かに上回る金額になる可能性が高いでしょう。
これらの観点から、空室リスクを避け、入居者様や近隣の住民、通行人の安全を守るためにも、アパートの修繕は必要なのです。-

建物や設備の自然による劣化・損傷(経年変化)や入居者様の通常の使用による損耗(通常損耗)は、原則として、アパートオーナー様の負担となります。入居者様の故意や過失、管理不足、通常の使用を超えた損耗に対しては、負担を負う義務はありません。
ここでは、アパート経営で必要な修繕の種類を小規模修繕、大規模修繕、予防修繕に分けてご紹介します。原状回復
原状回復とは、入居者様が退去した後、部屋の状態を元通りにすることを指します。一般的には、入居の際に、入居者様が支払う「敷金」から差し引かれますが、その損傷が入居者様の過失によるものでない場合、オーナー様が費用を負担します。
具体的に、入居者様とオーナー様それぞれが負担する例としては、以下のようなものが挙げられます。
■入居者様が負担するもの
・タバコなどによる焼け焦げ
・引越作業で生じた傷やへこみ
・結露を放置したために生じたシミやカビ
■オーナー様が負担するもの
・壁に貼ったポスターや絵画の痕跡
・家具の設置などによるカーペットのへこみ
・日照等のよる畳やクロスの変色
長らく入居者様の負担で元通りにするものという考えが一般的でしたが、近年の法改正などにより、たとえ入居者様の行為によるものでも、普通に生活していれば発生してしまうであろう傷や痛みなどは、基本的にはオーナー様の負担で元通りにするものと考えておいた方が良いでしょう。補修
補修は、設備の不具合や突発的な事故・災害による破損個所の修繕のことを言います。水回りの設備や機械類の故障であれば数万円~数十万円程度で済むことが多いものの、雨漏りや突発的な事故・災害の場合は、必要な期間や費用が増加する恐れがあります。
雨漏りなどの中規模な修繕は、完璧な支出計画を立てるのが難しくなりますが、万が一に備えて視野に入れておくと良いでしょう。特に、水回りの設備や機械類の故障などの修理や原状回復は、月日が経てば必ず発生するため、こちらの費用に関しては支出計画をしっかり立てておくことが大切です。大規模修繕
大規模修繕は、屋根やベランダ、外壁など建物の修繕のことです。その他、築年数の古い物件の場合は、耐震補強工事を行う必要があるかもしれません。
これらの修繕をせず放っておくと、外観が劣化するだけでなく、雨漏りや安全性の面でリスクが生じます。築年数の古い物件であっても、外装の配色を変えたり、再度塗装したりするだけで明るい印象になり、空室リスクの低減ができるでしょう。
大規模修繕の費用は、工事する場所によっても異なります。特に、建物の外回りの工事は足場が必要となることが多く、多額の費用がかかり工事期間も長くなる傾向にあります。規模や箇所にもよりますが、数百万~数千万円かかることも少なくありません。
また、小規模修繕よりも補修や改修する周期は長いため、大きな費用が必要となります。アパート経営を始める前に周期を把握しておき、早期から積立を行うなどして修繕費用を用意しておくことが重要です。
大規模修繕の費用を準備できなかった場合、金融機関で借り入れをするという方法もあります。とはいえ、建築時のローン返済が完了していなければ、追加で返済しなければなりません。この場合、建築と修繕のローンを返済できる余力があるか自身の経済状況や今後の資金計画を見直す必要があります。予防修繕
予防修繕とは、大きな修繕が必要になる前に行う修繕のことです。前述した大規模修繕も、完全に補修が必要になる前に対策を講じる修繕であることから、予防修繕の一環と言えます。
予防修繕は、床下のシロアリ防除や屋根・外壁・配管などの劣化調査など、不具合が発生する前に故障や破損が予測される箇所の対処を行います。予算に余裕があれば、屋根・外壁・廊下・階段・排水溝などの高圧洗浄も行うと良いでしょう。
また、空室リスク防止のための、設備・機器の入れ替えや和室をフローリングにするリフォームなども予防修繕に含まれます。これらは、入居者様が退去した際に行ったり、入居者様がなかなか決まらず、空室率を改善するために行ったりすることが一般的です。周期は数年に1回や退去時など、アパートの経営状態やアパートオーナー様の判断によって異なります。また、予防修繕に必要な費用も数万円~数十万円程度と物件によって幅があります。-

国土交通省の「民間賃貸住宅の計画修繕ガイドブック」によると、木造10戸1LDK~2DK 、1Kそれぞれの修繕時期・費用のイメージは以下のように記載されています。木造アパートの間取りを検討する際の参考にしてみましょう。
なお、30年以降も修繕は必要となります。また、税制上の木造の耐用年数は22年とされていることを念頭に置いておきましょう。
木造10戸(1LDK~2DK)の修繕時期・費用のイメージ
木造10戸(1K)修繕時期・費用のイメージ5~10年目 ベランダ・階段・廊下(塗装)
室内設備(修理)
排水管(高圧洗浄等)戸あたり
約9万円
(棟あたり 約90万円)11~15年目 屋根・外壁(塗装)
ベランダ・階段・廊下(塗装・防水)
給湯器等(修理・交換)
排水管(高圧洗浄等)戸あたり
約64万円
(棟あたり 約640万円)16~20年目 ベランダ・階段・廊下(塗装)
室内設備(修理)
給排水管(高圧洗浄等・交換)
外構等(修繕)戸あたり
約23万円
(棟あたり 約230万円)21~25年目 屋根・外壁(塗装・葺替)
ベランダ・階段・廊下(塗装・防水)
浴室設備等(修理・交換)
排水管(高圧洗浄)戸あたり
約90万円
(棟あたり 約900万円)26~30年目 ベランダ・階段・廊下(塗装)
室内設備(修理)
給排水管(高圧洗浄等・交換)
外構等(修繕)戸あたり
約23万円
(棟あたり 約230万円)合計 戸あたり 約216万円 (棟あたり 約2,160万円) 5~10年目 ベランダ・階段・廊下(塗装)
室内設備(修理)
排水管(高圧洗浄等)戸あたり
約7万円
(棟あたり 約70万円)11~15年目 屋根・外壁(塗装)
ベランダ・階段・廊下(塗装・防水)
給湯器等(修理・交換)
排水管(高圧洗浄等)戸あたり
約52万円
(棟あたり 約520万円)16~20年目 ベランダ・階段・廊下(塗装)
室内設備(修理)
給排水管(高圧洗浄等・交換)
外構等(修繕)戸あたり
約18万円
(棟あたり 約180万円)21~25年目 屋根・外壁(塗装・葺替)
ベランダ・階段・廊下(塗装・防水)
浴室設備等(修理・交換)
排水管(高圧洗浄)戸あたり
約80万円
(棟あたり 約800万円)26~30年目 ベランダ・階段・廊下(塗装)
室内設備(修理)
給排水管(高圧洗浄等・交換)
外構等(修繕)戸あたり
約18万円
(棟あたり 約180万円)合計 戸あたり 約174万円 (棟あたり 約1,740万円) -

アパートとひと口に言っても、屋根や外壁、住宅設備など、物件によって使用している素材や機器は異なります。できる範囲で目視をし、専門家にも定期的に点検を依頼することが大切です。ここでは、アパートにおける修繕箇所や確認すべきポイントなどをご紹介します。
建物全体
建物全体の修繕箇所として、屋根や外壁、雨樋、ベランダ、階段・廊下が挙げられます。
■屋根
割れ・ズレ・色褪せなどを確認しましょう。屋根の状態を自分で確認する場合は、アパートより高い位置にある道路や橋を利用する、距離をとって遠くから見るなどの方法があります。日頃から自分でも可能な限り確認しておき、定期的に専門家に点検を依頼しましょう。
なお、鉄筋コンクリートなどでアパートを建設した場合、「陸屋根」と呼ばれる屋根を使用する場合があります。陸屋根とは、傾斜のない平坦な屋根を指し、この屋根を使用した場合は定期的に屋上防水工事を行わなければなりません。
■外壁
ひび・シーリング部の劣化・汚れ・色褪せを確認します。インターネットなどでアパートの広告写真を掲載している場合は、外壁塗装工事を行ったあと写真を差し替えることも忘れずに行いましょう。外壁塗装を行うと、アパートの見た目がきれいになり、入居者様募集効果もアップします。
なお、外壁は屋根よりも自分で確認しやすい箇所ですが、こちらも専門家に定期点検を依頼しましょう。
■雨樋(あまどい)
割れ・ジョイント部分の接合・雨漏りなどを確認する必要があります。雨樋は意外と見落としがちですが、定期的な修理を怠ると、雨漏りの発生や雨樋自体の破損、雨水によるコンクリートの破損などのリスクにつながるため、注意しましょう。
■ベランダ
鉄部のさび・割れ・色褪せ・排水状況などがチェックポイントです。ベランダは、雨水があたる箇所のため、防水メンテナンスも必要になります。
また、鉄製の手すりがある場合は、さびなどの確認も必要です。近年では防水効果が高い素材も多く出ていますが、手すりは雨風にさらされやすいため、見た目以上に内部の腐食が進んでいる場合があります。放っておくと入居者様の安全に関わるため、メンテナンスは定期的に行いましょう。
■階段・廊下
ベランダと同様、鉄部のさび・割れ・色褪せ・排水状況などを確認しましょう。塗装や防水を行う目安のタイミングもベランダと変わらないため、ベランダとあわせて修繕を行うことをおすすめします。特に鉄骨階段は一度さびが発生すると内部に広がって鉄骨の強度が弱くなるリスクがあるため、専門家による定期的なメンテナンスが必須です。給排水管
排水管・枡(ます)と給排水管も、修繕の必要があります。枡とは、排水詰まりを予防したり、排水詰まりが起きてしまったりした際に対処するための設備です。住宅内の水回りから出る排水や汚水を敷地外の排水本管へ流す際にごみを溜める役割を果たします。
■排水管・枡
5~10年目、11~15年目、21~25年目、26~30年目ごとに高圧洗浄を行う必要があります。金額の目安は5,500円程度のため、そこまで負担にはならないでしょう。枡のメンテナンスを怠ると、排水管に穴が開いたり、周囲の土壌が陥没したりする場合がため、大規模な工事になりかねません。定期的に点検や高圧洗浄を行いましょう。
■給排水管
継ぎ手・エルボー部分を26~30年目を目安に交換します。これはあくまでも目安のため、劣化している場合は早めの交換が必要です。その他建具など
建物や給排水管のほか、外部建具や外構の修繕やメンテナンスも必要となります。
■外部建具
玄関の戸・雨戸・サッシを11~15年目を目安に調整を行いましょう。調整を行う際に室内に立ち入る場合は入居者様に通知をし、入居者様の立ち合いのもと行うことになります。
■外構
通路・フェンス・駐車場・駐輪場を26~30年目を目安に修理します。車や自転車を入居者様にどかせてもらう場合は、一時的に置ける場所を確保しておく必要もあるでしょう。室内設備
室内設備は、賃借人が入居中に故障してしまった際や、退去者が出た際に修理や交換を行います。こちらは他の個所や設備と比較してメンテナンスを要する頻度が高くなります。交換の場合は費用が高額になるため、日頃から積立をして備えておきましょう。
■給湯器
故障が頻繁に起こるようになった際は一斉交換が望ましいとされています。5~10年目に修理、11~15年目に交換がおおよその目安です。
■浴室設備
お湯が出ない、湯船の破損など故障が発生次第対応し、築年数が古くなった時点で部分交換を行います。11~15年目に部分交換、21~25年目に部分交換、26~30年目に修理を目安にしましょう。
■洗面台
こちらも浴室設備と同様に故障が発生次第、修繕対応します。5~10年目に修理、11~15年目に修理、21~25年目に部分交換、26~30年目に修理がおおよその目安ですが、劣化が早ければ修理や部分交換の頻度が高くなります。
■トイレ
故障が発生次第の対応となるため、基本的には5年~10年程度を目途に修理を行うと想定しておきましょう。劣化が著しい場合や空室リスク防止のために一斉交換を行わなければならないこともあります。
■キッチン
こちらも故障発生時の対応のみが一般的ですが、築年数が古くなれば部分交換が必要です。5~10年目に修理、11~15年目に部分交換、21~25年目に部分交換、26~30年目に修理と想定しておきましょう。
■エアコン
給湯器と同様に故障が頻繁に発生するようになり次第、一斉交換することを推奨されています。目安としては、5~10年目に修理、11~15年目に交換となっています。-

住宅性能の維持は、入居率の高さや家賃水準の確保に繋がります。その結果、次の修繕に向けた資金を確保でき、住宅性能が維持されることになります。アパート経営を安定させ、入居者様が安心かつ快適に暮らせる住まいを将来にわたって提供するために修繕やメンテナンスはしっかり行いましょう。
ここでは、アパート修繕のポイントを2点ご紹介します。修繕計画を立てる
修繕は一度実施して完了するわけではありません。修繕の都度、図面や現場写真などの資料を整備・保管し、記録しておくことが重要です。流れとしては以下のようになります。
■長期修繕計画作成
まずは、前述したような建物の修繕費用やタイミングなどを確認して、計画を立てましょう。専門知識も必要なため、施工会社に相談するのもおすすめです。また、室内の設備は、メーカーに直接問い合わせる方法もあります。
■定期的な点検の実施
修繕計画を立てただけでは、修繕のタイミングが最適かわかりません。適したタイミングで修繕計画を立てるには、こまめな点検が必要です。不具合が早めに見つかれば、部分修繕が可能になり、修繕コストを抑えられます。
また、災害や台風などのあとは、必ず点検しておき、予測不能な修繕が発生しないように気を付けましょう。
■専門的な検査の実施(問題を発見した場合)
不具合が見つかったり、計画によって修繕時期が近付いたりしたら、専門的な検査を行いましょう。専門業者にすぐに連絡して、しかるべき対応を取りましょう。
■修繕・更新もしくは部分的修繕の実施(問題個所の状態に応じる)
検査などの結果をもとに、修繕を実施します。
■記録作成
修繕は一度行ったら終わりではありません。ここまでご紹介したように、定期的な修繕が発生することがほとんどです。そのため、次の修繕に備えるためにも、今回の実施状況などを記録しておきましょう。
一度この流れを終えたら、定期的な点検、必要な対応、記録作成、定期的な点検のサイクルで繰り返していきます。期間の目安は「修繕のタイミングと費用の目安」の表をご確認ください。修繕費の積立をしておく
修繕を実施しないアパートオーナー様の多くは、「資金的余裕がない」ことを理由としています。長期修繕計画を立てておけば、高額な修繕費が必要となるタイミングも把握できるため、将来に備えて積立てておくことをおすすめします。定期的な点検によって、修繕のタイミングや費用が見込めたら、積立額を調整していくのもポイントです。
修繕資金の確保方法として、積立と融資が挙げられます。積立は定期預金などの預貯金や、金銭信託で資金を積み立てていきます。積立額が不足し、金融機関からの融資が必要な場合は、融資が可能かどうか早めに相談する必要があります。いざというときに資金不足で対応できないということを避けるために、長期修繕計画と自己資金を定期的に照らし合わせておくようにしましょう。
いずれにせよ、ご自身で長期的に修繕費の積立をしておくことが大切です。-
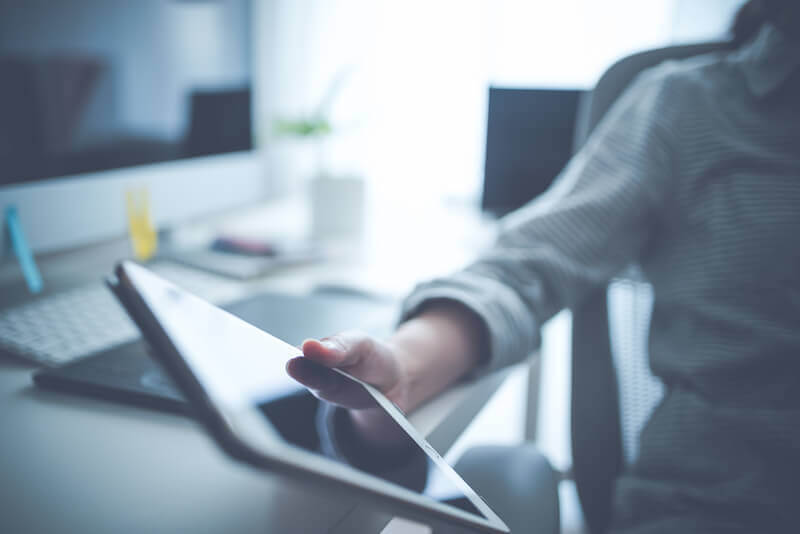
積立をするとしても、修繕費は可能な限り抑えたいところです。修繕費を抑え、アパート経営による利益を最大限にするためには、対策を継続的に講じることが重要です。可能であれば自らも足を運んでアパートの状態を確認すると良いでしょう。
ここでは、アパート修繕費を抑えるためのポイントを3点ご紹介します。定期的な点検・修繕の実施
繰り返しご紹介してきたように、日常的な清掃とあわせて点検を行い、1年に1回は専門家による点検を実施しましょう。不具合のある箇所を早期発見できれば部分修繕のみで済むため、将来的にコストを抑えられます。台風や地震などの後に破損箇所がないか臨時点検することもポイントです。
また、入居者様の安全を確保するために各種法令で義務付けられている法定点検も遵守しましょう。予防修繕を兼ねて定期的な点検・修繕の実施を推奨します。修繕費用を含めた建築計画の検討
アパートを建築する際は、修繕費用を含めて建築計画を立てることがポイントです。アパートをこれから建築するとなると、つい目の前の建築費のみに焦点を当てがちですが、修繕費を含めてどのようなアパートにするか検討するようにしましょう。そのためには、複数のハウスメーカーに建築プランを出してもらい、各社の提案をしっかり比較検討することが大切です。
また、修繕を減らすために劣化に強い素材を使用した外壁を選ぶという方法もあります。ご自身でも、前述した「修繕時期・費用のイメージ」の表を参考に、ある程度の目安を把握しておきましょう。大規模な修繕が必要なときに資金が足りないという事態を防ぐために、修繕費用を含めた建築計画を作成することが重要となります。-

修繕費はアパートオーナー様を悩ませる課題のひとつですが、対策次第で費用を最小限に抑えることが可能です。アパートを建築する際は修繕費用を含めた建築計画を検討し、入居者様の審査を徹底しましょう。無理のない建築計画であれば資金不足によって修繕できないという事態を防げ、入居者様審査を徹底すれば入居者様の管理不足による修繕リスクの予防ができます。
また、定期的な点検・修繕をしっかり行えば、大規模修繕になる前に部分修繕で補えることもあります。いずれ大規模修繕が必要になるとはいえ、日頃からメンテナンスしておくことで費用を抑えられます。入居者様に安心・快適な住まいを提供しながら修繕費を抑え、アパートの利益を最大化しましょう。関連記事
-
 アパート経営を相続したくない!相続放棄の方法と注意点詳しく見る
アパート経営を相続したくない!相続放棄の方法と注意点詳しく見るアパート経営は、相続税の節税対策の一つとして利用されることもあります。しかし、建物の老朽化が激しいものや、資産運用が困難な賃貸アパートを任され、手放したいと考える人もいるでしょう。 築年数が経っているアパートは、様々な問題を抱えており、アパート経営に活用できないどころか、売却もできないこともあります。しかし、アパート経営の相続を放棄することは可能なのでしょうか。 そこで、この記事では、アパート経営の相続放棄の方法や注意点、放棄の判断基準などについてご紹介します。 しかし、所有している土地でアパート経営を始めるには、いくつかのリスクがあることも覚えておきましょう。それぞれのリスク回避のために適切な対策を行って、効率的な土地活用を行いましょう。 この記事では、土地有りでアパート経営を行うメリット・デメリットについて、そして経営を進める時の流れや必要な資金などについて解説します。
-
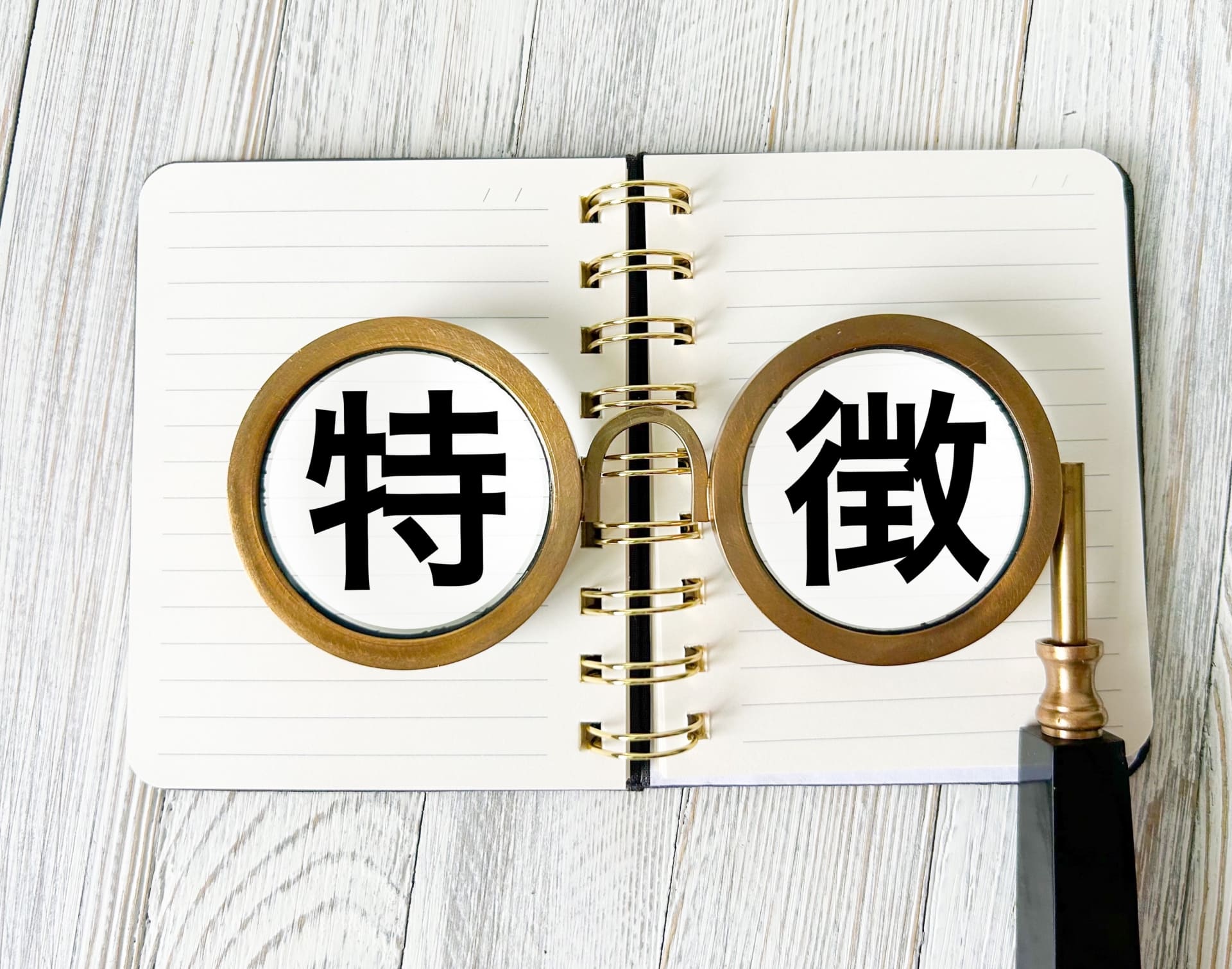 フルリノベーションの賃貸物件の特徴は?メリットや相場などを解説詳しく見る
フルリノベーションの賃貸物件の特徴は?メリットや相場などを解説詳しく見る新しく部屋を探している方の中には、間取りや内装や設備に物足りなさを感じる方も多いでしょう。 そのような方にはフルリノベーションの賃貸物件がおすすめです。 そうした場合には、フルリノベーションされた賃貸物件の検討も一案です。 本記事では、フルリノベーションの賃貸物件の特徴やメリット・デメリットや相場などを解説します。
-
 相続した不動産の名義変更のやり方は?費用や必要書類についても解説詳しく見る
相続した不動産の名義変更のやり方は?費用や必要書類についても解説詳しく見る土地や建物といった不動産を相続した場合、被相続人から名義を変更しなければなりません。名義変更は自分で行えますが、司法書士に依頼することも可能です。しかし、自分で進めるとなるとどういった手続きを行えばいいのか、どの書類を用意すればいいのか分からない方は多いでしょう。この記事では、不動産を相続した際に自分で名義変更を行う手続きや、発生する費用、準備が必要な書類について解説します。
タウングループ不動産仲介・周辺事業- 賃貸不動産仲介(東京・神奈川・埼玉・千葉) タウンハウジング
- 賃貸不動産仲介(東海) タウンハウジング東海
- 賃貸不動産仲介(九州) タウンハウジング福岡
- 土地・建物の不動産販売及び仲介 タウン住宅販売
- 首都圏を中心に引越サービスを展開 タウン引越サービス
- 賃貸不動産仲介(東北) タウンハウジング東北
- 賃貸不動産仲介(北関東) タウンハウジング北関東
建築事業- 賃貸住宅の企画・設計・施工 アヴェントハウス
多角化事業- 都内を中心に飲食店を運営 タウンダイニング
- インドアテニススクール タウンインドアテニスアカデミー


 一覧へ戻る
一覧へ戻る