賃貸の自主管理におけるトラブルと対策、委託管理についても紹介!
アパートやマンションを賃貸物件として貸し出しているオーナー様の中には、管理業務を管理会社に任せるのではなく、自ら行っている方もいるでしょう。その中で、さまざまなトラブルに見舞われるケースは少なくありません。
本記事では、自主管理においてよくあるトラブルとその対処法、および委託管理という選択肢について紹介します。
-

まずは、賃貸物件の自主管理について、基本的なおさらいをしておきましょう。併せて、自主管理に向いているオーナー様と向いていないオーナー様、それぞれの特徴についても解説します。
自主管理の定義と業務内容について
賃貸物件の自主管理とは、オーナー様が所有している物件の管理業務を自らの手で行うことを指します。自主管理を行うオーナー様の主な業務内容は、以下の通りです。
入居者募集と契約・契約更新
チラシやHPを作成し、入居者の募集を行います。希望者が現れたら内見対応を行い、入居を希望する場合は希望者の入居審査も実施します。問題がなければ契約書を作成し、入居希望者と契約を結ぶまでが一連の流れです。また、契約更新時期になったら更新の可否を入居者に確認し、改めて契約手続きを実施します。
トラブル・クレームの対応
自主管理を行うオーナー様は、トラブルの報告、クレームに自ら対処する必要があります。この際、対応をないがしろにしたり、迅速に対応できなかったりすると入居者の不満につながるため、できる限り真摯に対応することが重要です。
家賃の集金と管理
各入居者から毎月、家賃の集金を行うのも自主管理オーナー様の仕事です。オーナー様によって、手渡しや口座振り込みなどやり方はさまざまですが、いずれも集金した家賃の管理まで徹底的に行わなければなりません。
所有物件の維持管理および保全
共用部の清掃や老朽化している箇所がないかなどの点検、必要があれば修繕を業者に依頼するなど、物件そのものの維持と保全も重要な業務です。災害のような万が一の事態に備えて、耐震補強工事や防水工事を行わなければいけないケースもあるでしょう。そうすることで、入居者の安心感・満足感につながるだけでなく、所有物件という財産を守ることにもつながります。
入居者の退去立ち会いと原状回復・敷金精算
入居者が退去する際には、オーナー様ご自身で立ち会う必要があります。入居者と一緒に部屋の状態を確認し、原状回復にかかる費用を計算し、負担する割合を確認しましょう。この際、敷金の精算も行いますが、入居者からのクレームにつながりやすい傾向があるため、敷金精算に関するガイドラインを確実に把握しておく必要があります。
※参考:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン (再改訂版)|国土交通省
消防点検
「消防法第17条の3の3」に基づき、「6カ月に1回、消防機器の点検」を行う必要があります。
また、同法に基づき「1年に1回、消防用設備等全部もしくは一部を作動させる総合点検」の実施も必須です。点検の結果は、消防長か消防署長に報告する義務があります。
※参考:消防用設備等点検報告制度とは|総務省消防庁賃貸物件の自主管理に向いている人、向いていない人の特徴
自主管理を行うオーナー様が担う役割は多岐にわたります。そのため、自主管理に向いていない方も存在します。具体的には「本業が別にある」「複数の部権を所有している」ため、物件管理に手が回らない「遠方に物件がある」ため物理的に管理が難しい場合です。また、精神的にトラブル解決が難しい場合も、自主管理には向いていないでしょう。
一方で、専業のオーナー様・物件を近所に所有している・入居者とのコミュニケーションをスムーズに行えるオーナー様であれば、自主管理に向いているといえるでしょう。-

ここからは、賃貸の自主管理においてよく挙げられるトラブルについて紹介します。これから賃貸経営を行いたいと検討している方は、ここで挙げられているトラブルについて、あらかじめ把握しておくとよいでしょう。
家賃滞納・夜逃げ
賃貸トラブルの中でも、家賃の滞納は特に多くの入居者に見られる問題です。また、オーナー様が知らない間に入居者が夜逃げしてしまうケースもあります。いずれの場合でも、オーナー様にとっては金銭的に大きな損害となるうえに、対応にかかる労力は相当のものです。
ペットの飼育
ペット不可物件にもかかわらず、ペットを飼育する入居者も存在します。ペットによって部屋や共用部分に汚れ・臭いが付着することがあります。また、鳴き声を聞いた他の入居者からクレームが入ることもあるでしょう。加えてアレルギー問題や、ペットの逃亡に伴う事故に発展するおそれもあるため、迅速に対応しなければなりません。
入居者間トラブル
入居者間でトラブルに発展する原因は少なくありません。原因となる入居者や、クレームを入れた入居者が特定されないよう、注意喚起が必要な場合は、入居者全員に行う等の配慮が必要になります。また、トラブルを主張する入居者が2人以上の場合は、中立の立場で解決に導く姿勢が重要となります。
水漏れ
水漏れが発生しているという報告があった場合、オーナー様は迅速に修理業者の手配を行いましょう。水漏れによって部屋の壁紙に損傷が発生している場合は、リフォーム業者の手配も必要です。
騒音トラブル
入居者間のトラブルとしてよく挙げられるのが騒音トラブルです。騒音を発生させている入居者に非がある場合もあれば、音に過敏な入居者によってクレームが入るケースもあります。騒音トラブルは、最悪の場合大きな事件に発展するおそれもあるため、オーナー様は慎重かつ中立的な立場で問題解決に挑まなければなりません。
鍵の紛失
入居者が部屋の鍵を紛失した場合、夜中や早朝など、時間帯にかかわらずオーナー様に連絡が入ります。防犯上の観点から非常にリスクが高い問題であるため、迅速な対応が必須です。一般的に、鍵紛失時の交換費用は、入居者負担となります。クレーム防止のためにも、契約書に明記しておくとよいでしょう。
退去時の敷金精算
入居者の中には、退去時に敷金の全部が返還されると誤認しているケースがあります。実際には、原状回復のために敷金の一部(場合によっては全部)が使われるため、それを知らない入居者とトラブルになるかもしれません。そのため、契約時に入居者に対してはっきりと告知しておくこと、および契約書にも明記しておくことが重要です。
ゴミ出しトラブル
各種ゴミの日にルールを守らずゴミを出したり、粗大ごみを勝手にゴミ置き場に放置したりする入居者も存在します。他の入居者からのクレームにつながるだけでなく、地域の治安悪化にもつながるおそれがあるため、ゴミ出しルールは徹底して周知しましょう。監視カメラを設置するのも効果的です。
異臭
入居者が部屋にゴミを溜めることで、異臭騒ぎに発展するおそれがあります。また、溜まったゴミが火災の原因にもなり得るため、当該入居者への注意勧告と連帯保証人への連絡を行い、早期に撤去してもらうように働きかけることが必要です。なお、ゴミといえど入居者の所有物であるため、オーナー様が勝手に撤去することはできないため注意しましょう。
無断駐車
賃貸物件の駐車場は私有地となるため、無断駐車が発生しても警察は介入できません。オーナー様が警告文を当該の車両にはさんで注意喚起を行ったり、内容証明によってより強力な勧告を行ったりする必要があります。あらかじめ駐車場に「無断駐車を行った際に罰金を徴収する」という内容の掲示を行っておくのも1つの手です。
孤独死問題
必ずしも高齢者に限りませんが、単身で入居している人が孤独死してしまった場合、当該入居者の連帯保証人や親族に連絡をし、一緒に死亡確認をしなければなりません。また、入居者の相続人にあたる人物が賃借人の地位を相続したうえで初めて、賃貸借契約の解除が行えます。さらに、死亡期間によっては特殊清掃業者を入れる必要もあります。
共用部の使用に関するトラブル
共用部に関するトラブルも入居者間トラブルの1つとしてよく挙げられる問題です。ベランダでタバコを吸っていたり、廊下や階段に廃棄物が放置されていたりなどが挙げられます。オーナー様は、全入居者への注意喚起、当該入居者への交渉、法的措置という段階を経て解決に導きましょう。
設備故障
民法第606条によれば、オーナー様は賃貸物件の修繕義務を負うとされています。物件に備わっている設備が老朽化や災害によって故障した場合、オーナー様による迅速な修繕対応が必要です。
※参考:民法 | e-Gov 法令検索客付けの弱さ
自主管理オーナー様にとって入居者の募集は重要な業務です。しかし、自力で募集するのは労力がかかるうえに、求めているような結果が得られるとは限りません。そのため、客付けのみを不動産業者に依頼するというやり方もできますが、不動産業者にとって、自社が所有していない物件に関する客付けは優先度が低いものです。自力で広告を打ち出しても、不動産業者に客付けを依頼しても必ずしも効果が期待できないという点は、自主管理の弱点といえるでしょう。
-

続いて、自主管理物件におけるトラブルの一般的な対処法を紹介します。
家賃保証会社を利用する
家賃滞納リスクを防止するためにも、あらかじめ家賃保証会社と契約を結んでおくのがおすすめです。仮に家賃滞納が発生しても、滞納分は家賃保証会社から支払われ、回収作業も家賃保証会社が代理で行ってくれます。
入居者と関係を築く
自主管理オーナー様は入居者との距離感が近く、ゆえに日頃のコミュニケーションを密にしておくことが重要です。そうしておくことで入居者からの信頼度が増し、何らかのトラブルが発生した場合でもスムーズに問題解決を行える可能性が高まります。
設備故障に対応できる業者を選定しておく
日頃から設備の点検を行っていても、急に設備故障が発生することはあり得ます。故障が発覚してから慌てて業者を探すと時間も手間もかかるため、あらかじめ、設備故障に対応できる業者を選定しておくとよいでしょう。
管理委託も視野に入れる
委託費用がかかりますが、管理業務の一切を管理会社に委託することで、自主管理に伴うさまざまなトラブルや問題を一任できます。自主管理に限界を感じている、または自主管理に自信がないという方は、管理委託への切り替えを検討してみるのもよいでしょう。
専門家と連携する
自主管理を維持したい場合でも、トラブル解決のために外部の専門家を頼ることは有効的です。トラブル解決のために弁護士を頼ったり、税理士や会計士に税務・会計処理の面で相談したりと、各種専門家と連携することでスムーズに自主管理を行えるでしょう。
ITサービスを導入する
入居者情報管理ソフトやオンライン家賃決済システム、相談受付システムの導入は、自主管理の煩雑な業務を効率化できます。オーナー様だけではなく、入居者にとっても便利なため、入居者の定着率上昇・満足度の向上にもつながるでしょう。
-

自主管理に限界を感じている場合は、委託管理に切り替えるのも1つの手です。委託管理について、そのメリットとデメリット、および委託する管理会社の選び方を紹介します。
委託管理とは
その名の通り、賃貸物件の管理業務を管理会社に委託することを指します。管理業務の一部を任せることも、全てを任せることもできるため、オーナー様の方針に応じて選ぶことが可能です。
委託管理のメリットとデメリット
委託管理を依頼することで、自主管理に際して避けることのできなかった時間や手間を省略することが可能です。また、管理会社で培われたノウハウに基づき、入居者面でも建物・設備面でもよりスムーズな運営が期待できます。加えて、遠方の物件を所有することも可能となるため、収入源を増やせる可能性が高まるというメリットもあるのです。
一方、委託費用がかかる点や、経営ノウハウが身に付かなくなるなどのデメリットがあります。また、管理会社や担当者の質によっては不満が発生するおそれもあるため、管理会社選びは慎重に行いましょう。管理会社を選ぶポイント
質の高い管理会社を選ぶためには、次の点に着目するとよいでしょう。
・HPや口コミなどで高い実績を誇っている
・管理業務の範囲について明確に記載されているか、契約時に伝えてくれる
・管理戸数が多い
・入居率が高い
・担当者の対応が良く、信頼できる
・オーナー様の目線で相談に乗ったり、アドバイスをしてくれたりする
このような特徴を持った管理会社の場合、安心して管理業務を委託できるでしょう。-

賃貸物件を自主管理しているオーナー様にとって、本記事で挙げたような各種トラブルは常に悩みの種といっても過言ではないでしょう。それらを解決するためには自力で何とかしようとするだけではなく、専門家を頼ったり、不動産業者と協力したりすることが重要です。自主管理が難しいと判断される場合は、質の高い管理会社に業務を委託するのも賢明な判断といえます。
無理をせず、ご自身に合った方法で賃貸経営を成功に導いていきましょう。関連記事
-
 不動産管理会社の管理料の「上限」を節税につなげるコツを解説!詳しく見る
不動産管理会社の管理料の「上限」を節税につなげるコツを解説!詳しく見るアパートやマンションなどの賃貸経営には、物件の管理を依頼する不動産管理会社の管理料に注目した節税方法があります。所有する物件と相性の良い管理方法は、大家自身のライフスタイルや建物の管理に重視する項目次第で異なります。大家の同族経営をする不動産管理会社に管理を依頼したり、管理料の「上限」や税金申告時の「否認」の制度を理解したりすることで、物件の収益性を高めることが可能です。この記事では、管理料の仕組みや上限、管理方法の種類ごとの特徴、管理会社や入居者と良好な関係性を構築するコツやヒントを紹介します。この記事では、アパート経営の概要や、アパート経営の経費率の目安、ポイントなどを紹介します。そこで、この記事では、経営しているアパートに自分が住む条件から、メリット・デメリット、注意点について解説します。 しかし、所有している土地でアパート経営を始めるには、いくつかのリスクがあることも覚えておきましょう。それぞれのリスク回避のために適切な対策を行って、効率的な土地活用を行いましょう。 この記事では、土地有りでアパート経営を行うメリット・デメリットについて、そして経営を進める時の流れや必要な資金などについて解説します。
-
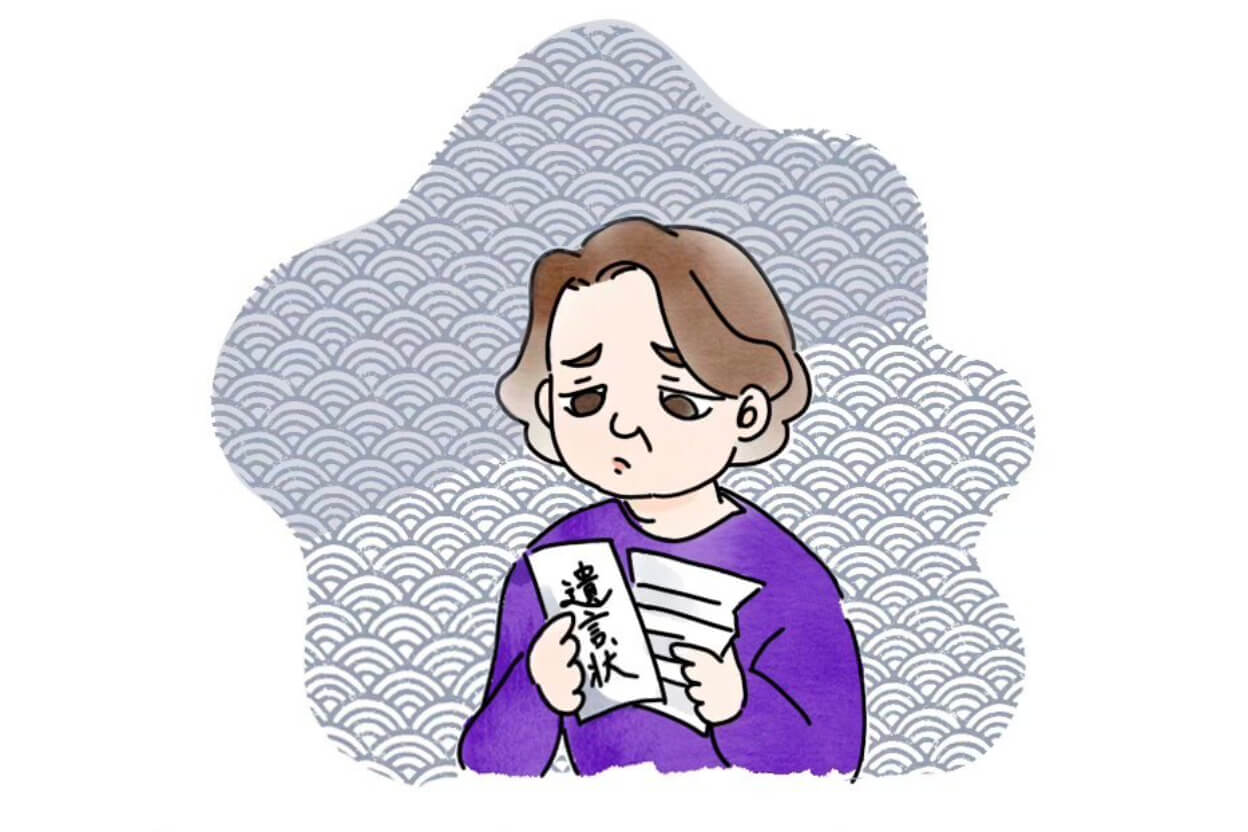 田舎の土地の相続は地獄!?実家を「負動産」にしないポイント詳しく見る
田舎の土地の相続は地獄!?実家を「負動産」にしないポイント詳しく見る「田舎の土地の活用方法が見出せない」「実家が空き家になっていて何とかしたい」と考える方も多いのではないでしょうか。突然の相続などで思いがけず取得してしまった空き家は、放置しておくとコストばかりかかり、資産が減ってゆく原因になります。 空き家は所有者にとって税負担が重く、特に毎年課税される固定資産税は厄介とされています。しかし、放置すると周辺の住環境に悪影響を及ぼしトラブルの火種にもなりかねません。 そこで、この記事では、田舎の土地の相続にまつわる問題や、相続を回避する方法などをご紹介します。
-
 【アパート経営がうまくいかない方へ】よくある13の失敗ポイント詳しく見る
【アパート経営がうまくいかない方へ】よくある13の失敗ポイント詳しく見る自己資産を運用して増やしたいと思っている方のなかには、アパート経営を検討しているケースがあるかもしれません。アパート経営は、株式取引などとは異なり現物がイメージしやすいため、比較的安全で簡単な投資先に思えます。しかし、魅力的な反面、うまくいかなかったときのリスクについて注意する必要があるのも事実です。この記事では、よくある13個の失敗ポイントと、その対策についてご紹介します。
タウングループ不動産管理事業- 賃貸債務保証業務代行 株式会社イズミ
- 賃貸契約に関する家財保険 イズミ少額短期保険会社
- 建物・お部屋のリフォーム 株式会社イズミリフォーム
不動産仲介・周辺事業- 賃貸不動産仲介(首都圏) タウンハウジング
- 賃貸不動産仲介(東海) タウンハウジング東海
- 賃貸不動産仲介(九州) タウンハウジング福岡
- 土地・建物の不動産販売及び仲介 タウン住宅販売
- 首都圏を中心に引越サービスを展開 タウン引越サービス
建築事業- 賃貸住宅の企画・設計・施工 アヴェントハウス
多角化事業- 都内を中心に飲食店を運営 タウンダイニング
- インドアテニススクール タウンインドアテニスアカデミー


 一覧へ戻る
一覧へ戻る