不動産取得税とは?軽減措置の概要や適用要件をわかりやすく解説
不動産には、あらゆる税金が発生します。土地や住宅などの不動産を所有すれば固定資産税、不動産の登記には登録免許税など、ケースによって発生する税金はさまざまです。
土地を購入したり、新築住宅を建設したりする際には、「不動産取得税」を支払う義務があります。初めて不動産を取得する方にとっては、不動産取得税の仕組みや納税額がいくらかかるのか分からず、不安を感じることもあるでしょう。
そこで、この記事では不動産取得税の概要や納税額の計算方法、納付方法を紹介します。また、不動産取得税には軽減措置が適用されるため、軽減措置の適用要件や申請の流れなどに関しても分かりやすく解説します。
-
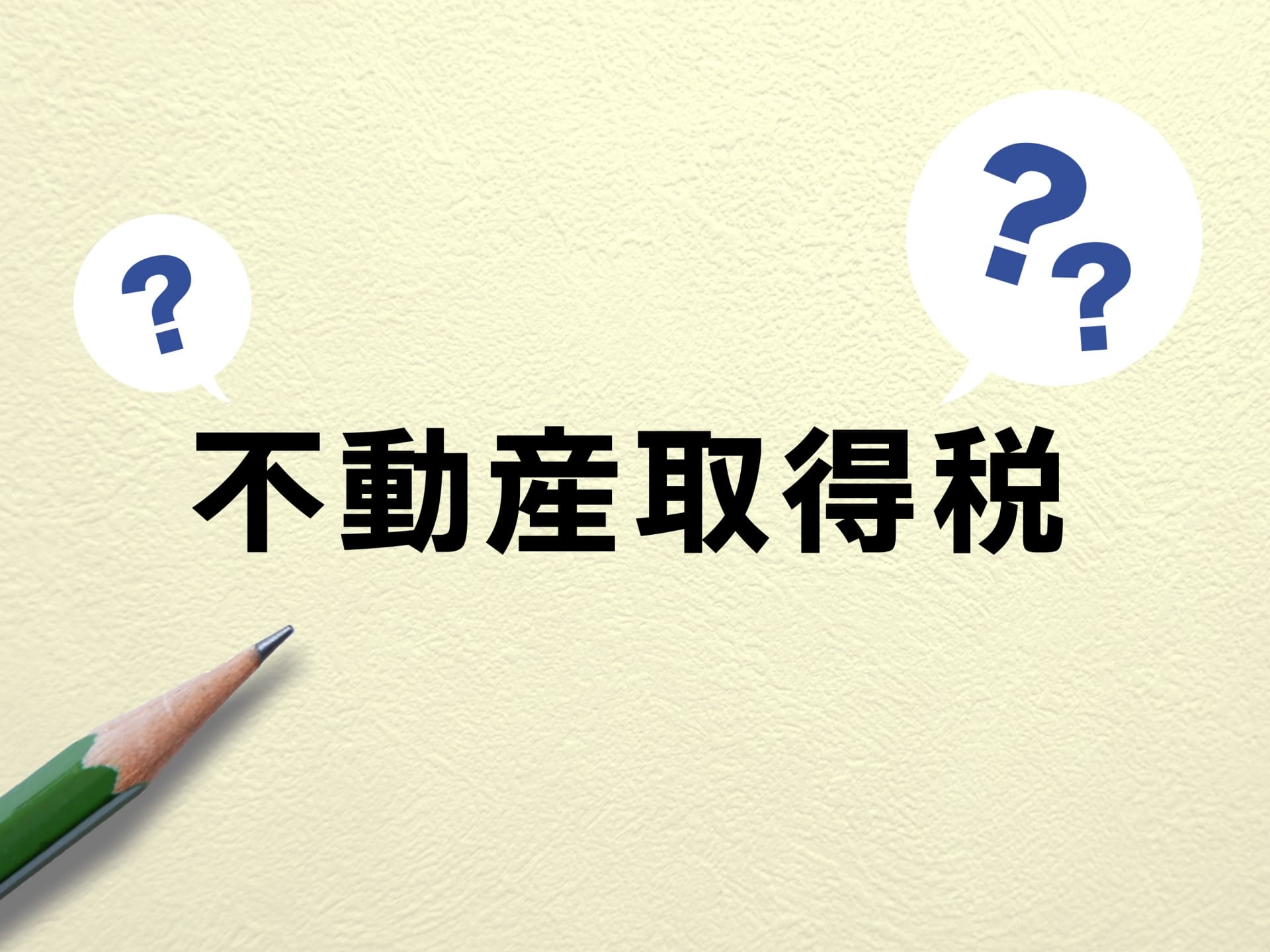
ここでは、不動産取得税の仕組みや納付方法、納税額の計算方法を解説します。不動産取得税に関して不安がある方は、まず基本の概要を押さえると良いでしょう。
また、不動産取得税は固定資産税とは異なる税金です。両者を混同しないように、どういった特徴があるのか、それぞれの特徴と違いも確認しておきましょう。不動産取得税の概要
不動産取得税とは、家屋・土地の購入または建築、贈与などで不動産を取得した際に、その取得者に課税される税金です。不動産の取得の意味は、不動産を得るのに有償・無償問わず、不動産の所有権を取得した事実を指します。ただし、相続によって取得した不動産には、この税金は適用されません。
また、不動産取得税は不動産の取得時に課される税金のため、納付は一度で済むのが特徴です。
不動産取得税の歴史は古く、大正時代に府県税が設立されたことから始まります。
明治時代以前の年貢を中心にした税から、税収の安定を図るために不動産取得税や所得税、法人税などが導入されました。不動産取得税は、1954年のシャウプ勧告の際に一旦は廃止されましたが、その後1954年(昭和29年)の税制改正で再び納税が義務付けられるようになっています。なお、令和4年度(2022年)には、不動産取得税の税収が4億円を超えました。不動産を取得した人が納める
不動産取得税は、不動産を取得した方が納付する税金です。不動産を複数人で共有している場合は、共有者全員で納付します。不動産取得税の納税先は、取得した不動産が所在する都道府県です。住んでいる地域とは別の都道府県にある不動産を取得した場合でも、納付先は不動産が所在している都道府県になります。
不動産取得税において、不動産とは土地・家屋の総称です。土地であれば畑や田んぼ、住宅地、山林や原野、牧場などになります。家屋には、住宅や店舗の他に、工場や倉庫が含まれます。これらの不動産を取得した際に、土地と家屋それぞれに不動産取得税が課税されるのです。例えば、一戸建て住宅を土地付きで購入した場合、土地と住宅の2つに課税されるため、両方の分を納付します。不動産取得税の納付方法
不動産取得税は、都道府県から送られてくる納税通知書を確認し、記載されている期限までに納付します。納付方法は現金の他に、クレジットカード払いやコンビニ払いなど、自治体によってさまざまです。
主な納付方法は以下になります。
都道府県の窓口
金融機関
郵便局
クレジットカード
コンビニ
口座振替
ペイジー(Pay-easy)
スマートフォンの決済アプリ(PayPayなど)
e-TAX
近年では、決済アプリの利用で納付ができる都道府県も増えており、納付の手間が省きやすくなっています。どの納付方法が選択できるかは、都道府県の各税事務所のホームページなどを確認しましょう。不動産取得税の計算方法
不動産取得税の税率は4%に設定されています。この税率と固定資産税課税台帳に記載された不動産の評価額を基に、不動産取得税の額を算出します。
不動産取得税 = 固定資産税評価額 × 税率(4%)
基本的に不動産取得税の税率は4%ですが、現在は税負担を軽減するための措置が設けられており、これが適用されると税率は3%に引き下げられます。
不動産取得税の軽減措置に関しては、この後で詳しく解説します。固定資産税との違い
不動産に関係する税金というと、固定資産税を考える方も多いでしょう。不動産を所有すれば固定資産税が発生するのは事実ですが、不動産取得税とはいくつかの点で異なります。
固定資産税は、土地や建物に加え、企業の備品や工場の機械などの償却資産(固定資産)にも課せられる税金です。不動産取得税と同様に、不動産に対して課税されます。しかし、不動産取得税の課税は取得時に1回限りであることに対し、固定資産税は不動産を所有している限り継続的に課税されます。また、不動産取得税は都道府県に納付しますが、固定資産税の納付先は市区町村です。税率も異なり、不動産取得税は4%、固定資産税は1.4%となっています。
不動産を取得し所有する際は、不動産取得税と固定資産税の特徴を把握し、両者の違いを押さえておきましょう。-

住宅の購入など、不動産の取得には多額の費用がかかる場合がほとんどです。その上、取得時の税金も高額になってしまうと、さらに金銭的な負担がかかってしまうでしょう。
先にも述べたように、不動産取得税には税負担の軽減措置が設けられており、要件を満たせば軽減措置が適用されます。ここでは、軽減措置の概要や適用対象になる不動産など、基本的な仕組みを解説します。不動産取得税の軽減措置とは
基本的に不動産取得税の税率は4%ですが、軽減措置が適用されると、住宅用の土地・家屋では税率が3%に下がります。軽減措置を受けるか受けないかで、不動産取得税には大きな差が生じるでしょう。
ただし、住宅用以外の家屋に関しては、税率はそのままの4%で変わりません。
なお、令和6年(2024年)3月31日までに取得した、宅地や宅地評価された土地については、課税標準額は価格の2分の1になります。つまり、計算式に当てはめると、「不動産取得税 = 固定資産税評価額 × 1/2 × 税率(3%)」で発生する税額を算出できます。軽減措置が適用される対象
不動産取得税の軽減措置が適用される対象は、「新築住宅」「中古住宅」「新築住宅用土地」「中古住宅用土地」の4つです。これらの不動産を取得した際に、軽減措置が適用される可能性があります。
土地と住宅、新築や中古と、状況によって軽減措置を受けられる要件が変わるため注意しましょう。また、新築の時期や長期優良住宅としての認定などで、控除額も変わります。
それぞれの条件に関して、詳しい概要は以下で解説します。-

新築住宅を購入したり、すでに所有している土地に家屋を新しく建てたりと、新築住宅を所有した際の不動産取得税には、軽減措置が適用されます。新築住宅を購入した時に、不動産取得税が課税されるケースは多く見られるため、該当する方は参考として押さえておくと良いでしょう。
適用要件
新築住宅を購入するなどで、不動産を取得した時の軽減措置について、満たさなければならない適用要件は以下の通りです。
1.個人の居住を目的とした住宅、もしくは、セカンドハウス用の住宅であること
2.物置や車庫、共用部分を含め、延べ床面積が50㎡以上240㎡以下であること
3.戸建て以外の新築住宅は、1戸あたりの延べ床面積が40㎡以上240㎡以下であること
延べ床面積は、狭すぎても広すぎても上記の要件を満たせませんので注意しましょう。新築住宅における軽減措置の内容
新築住宅においては、適用要件を満たすことで2つの軽減措置を受けられます。
固定資産税評価額から1,200万円が控除される
不動産取得税の軽減措置について、新築住宅の場合は要件を満たすことで固定資産税評価額から1,200万円が控除されます。例えば、新築住宅の固定資産税評価額が4,500万円だと、1,200万円が控除されるため課税対象になる額は3,300万円です。1,200万円が控除されるというのは、つまり固定資産税評価額が1,200万円を超えていないならば、税金はかからないと判断できます。
加えて、「長期優良住宅」と認定された新築住宅は、控除額が100万円増加します。
長期優良住宅とは、長期間良好な状態で使用できる措置が講じられている住宅のことです。平成21年(2009年)6月4日から令和8年(2026年)3月31日までの間に、長期優良住宅を取得した場合は、1,200万に100万が上乗せされるため、合わせて1,300万円の控除が受けられます。
3%の軽減税率が適用される
新築住宅を取得した際の、基本的な不動産取得税の税率は4%ですが、軽減措置によって3%になる軽減税率が適用されます。
固定資産税評価額が1,800万円になる新築住宅のケースで、軽減措置を受ける際の不動産取得税額の例を確認してみると、計算式は以下のようになります。
1,800万円(固定資産税評価額)- 1,200万円(控除額)× 3%(軽減税率)= 18万円-

既存の中古住宅を購入する方も少なくありません。新築住宅だけでなく、中古住宅を取得した際も、不動産取得税では軽減措置が適用されます。ここでは、中古住宅での不動産取得税について、適用要件と軽減措置の内容を確認しておきましょう。
適用要件
中古住宅を購入するなどで、不動産を取得した際の不動産取得税の軽減措置は、以下の要件を満たすことで受けられます。
1.個人の居住を目的とした住宅、もしくは、セカンドハウス用の住宅であること
2.物置や車庫、共用部分を含め、延べ床面積が50㎡以上240㎡以下であること
3.戸建て以外の中古住宅は、1戸あたりの延べ床面積が40㎡以上240㎡以下であること
4.昭和57年(1982年)1月1日以降に建築されている住宅であること
5.昭和56年(1981年)12月31日以前に建築されている場合は、建築士などが実施する耐震診断によって、新耐震基準を満たしていることが証明できる住宅であること
新築住宅と同様の適用要件もありますが、新耐震基準を満たしている証明が必要なことと、長期優良住宅の控除がないことが、両者の相違点として挙げられます。中古住宅における軽減措置の内容
中古住宅では適用要件を満たすことにより、2つの軽減措置を受けられます。
築年次ごとの控除額を固定資産税評価額から差し引ける
中古住宅の軽減措置も控除を受けられます。中古住宅の場合は、築年次ごとに決まった建物の控除額を、固定資産税評価額から差し引く仕組みです。
例えば、昭和60年(1985年)7月1日から昭和64年(1989年)3月31日までに新築された住宅であれば450万円の控除、昭和64年(1989年)4月1日から平成9年(1997年)3月31日までに新築された住宅では1,000万円の控除になります。
このような中古住宅の築年次ごとによる控除額は、都道府県のホームページなどで確認が可能です。
3%の軽減税率が適用される
中古住宅を取得した際の不動産取得税の税率は、新築住宅と同様に軽減措置によって3%に設定されています。
中古住宅の不動産取得税は、該当する築年次の控除額を用いて計算します。
例として、新築した年が平成11年で、固定資産税評価額が1,400万円としましょう。平成9年(1997年)4月1日以降の控除額が、1,200万円に設定されていることを踏まえると、計算式は以下のようになります。
1,400万円(固定資産税評価額)- 1,200万円(控除額)× 3%(軽減税率)= 6万円
中古住宅における軽減措置では、住宅の築年数ごとに控除額が変動するため、算出の際は注意が必要です。-

住宅そのものだけでなく、その住宅を建てるための土地を取得した場合でも、要件を満たす限りは不動産取得税の軽減措置を受けることができます。
ここからは、新築住宅用の土地について、軽減措置を受けるための適用要件やその内容を解説します。適用要件
新築住宅用の土地で軽減措置を受けるには、住宅そのものとは別に、土地に関する要件を満たさなければなりません。以下に挙げる2つの項目が、新築住宅用の土地における適用要件です。土地と住宅どちらを先に取得したのか確認しましょう。
1.土地を先に取得した場合
土地を取得した後、3年以内に該当の土地に住宅が新築されていることが要件です。ただしこれは、土地を取得した方が住宅の新築まで土地をそのまま所有していること、土地を取得した方から譲渡された方が住宅を新築したこと、この2つが条件になります。
2.新築住宅を先に取得した場合
土地よりも新築住宅を先に取得しているケースでは、新築後の1年以内にその土地を取得すること、新築未使用の住宅とその土地を、新築して1年以内に同じ方が取得することの2つが適用要件になります。新築住宅用土地における軽減措置の内容
新築住宅用の土地においては、上記の適用要件を満たすことにより、以下の軽減措置を受けられます。なお、土地の不動産取得税の税率は、軽減税率として現在は3%が適用されています。
新築住宅用の土地では、次の条件に当てはまる場合、算出された金額のうち、高い方が軽減額として適用されます。
A:4万5,000円
B:土地1㎡あたりの固定資産税評価額 × 1/2 ×(住宅の床面積(200㎡まで)×2)× 3%(税率)
土地の面積が200㎡、 住宅の床面積が140㎡、土地部分の固定資産税評価額が1,400万円のケースを例として軽減額を計算します。
まず、土地1㎡あたりの価格を以下の式で算出します。
1,400万円(固定資産税評価額)× 1/2 ÷ 200㎡(土地の面積)= 3万5000円
次に、計算した土地1㎡あたりの価格3万5000円を元にして、控除額を計算していきます。
使用する計算式は、上記の条件Bと同じです。計算結果の金額が4万5,000円よりも高ければその金額、4万5,000円以下であれば、そのまま4万5,000円が軽減額として適用されます。
3万5000円(土地1㎡当たりの価格)× 200㎡(住宅の床面積200㎡ × 2 = 400㎡になりますが、式の通り200㎡として計算します)× 3% = 19万8000円
計算結果が、条件Aの4万5,000円よりも高い金額であるため、軽減額はそのまま19万8000円となります。-

住宅用の土地を取得した際は、住宅が新築か中古かによって適用要件が変わります。ここでは、中古住宅用の土地における軽減措置の要件を確認しておきましょう。
適用要件
中古住宅用の土地を取得した際に利用できる、軽減措置の適用要件は以下の通りです。
1.土地を先に取得した場合
土地を取得した後1年以内に、該当の土地に中古住宅を取得していることが要件です。土地と中古住宅の両方を、同時に取得したケースも含みます。
2.中古住宅を先に取得した場合
土地よりも中古住宅の方を先に取得しているのであれば、中古住宅を取得した方が、取得後1年以内にその土地を取得するのが要件になります。
中古住宅用の土地で不動産取得税の軽減措置を受ける際は、1年以内に中古住宅かその土地を取得しなければならないことに注意しましょう。中古住宅用土地における軽減措置の内容
新築住宅用の土地と同様に、軽減措置としての控除額は次の条件の中で、算出された金額のうち、より高い方が適用されます。
A:4万5,000円
B:土地1㎡あたりの固定資産税評価額 × 1/2 ×(住宅の床面積(200㎡まで)×2)× 3%(税率)
不動産取得税の軽減措置による控除額を算出する際、住宅の場合は新築か中古によって計算方法が変わります。一方、土地の場合は建っている住宅が新築・中古に関係なく、両方とも同じ方法で控除額を計算します。
軽減措置を受けられれば、税金の負担を減らすことが可能です。取得した不動産がどの適用要件に該当するのか確認し、要件を満たしているのであれば、積極的に軽減の適用を利用しましょう。-

マンションにおける不動産取得税の軽減措置は、どのような要件・内容になるのでしょうか。
軽減措置はマンションであっても、これまで解説した通りの新築住宅・中古住宅・土地といった分類で、適用要件や軽減される内容が定められます。新築マンションの場合は、新築住宅と新築住宅用土地、中古マンションであれば中古住宅と中古住宅用土地の項目が、軽減措置適用の対象です。
ただし、賃貸マンションを借りて住んでいるケースでは、不動産取得税の課税対象にはなりません。理由は、不動産取得税があくまでも、不動産を取得した時に課せられる税金であるためです。マンションの所有権を取得したのであれば課税対象になりますが、賃貸マンションに住んだだけでは、不動産取得税はかかりません。-
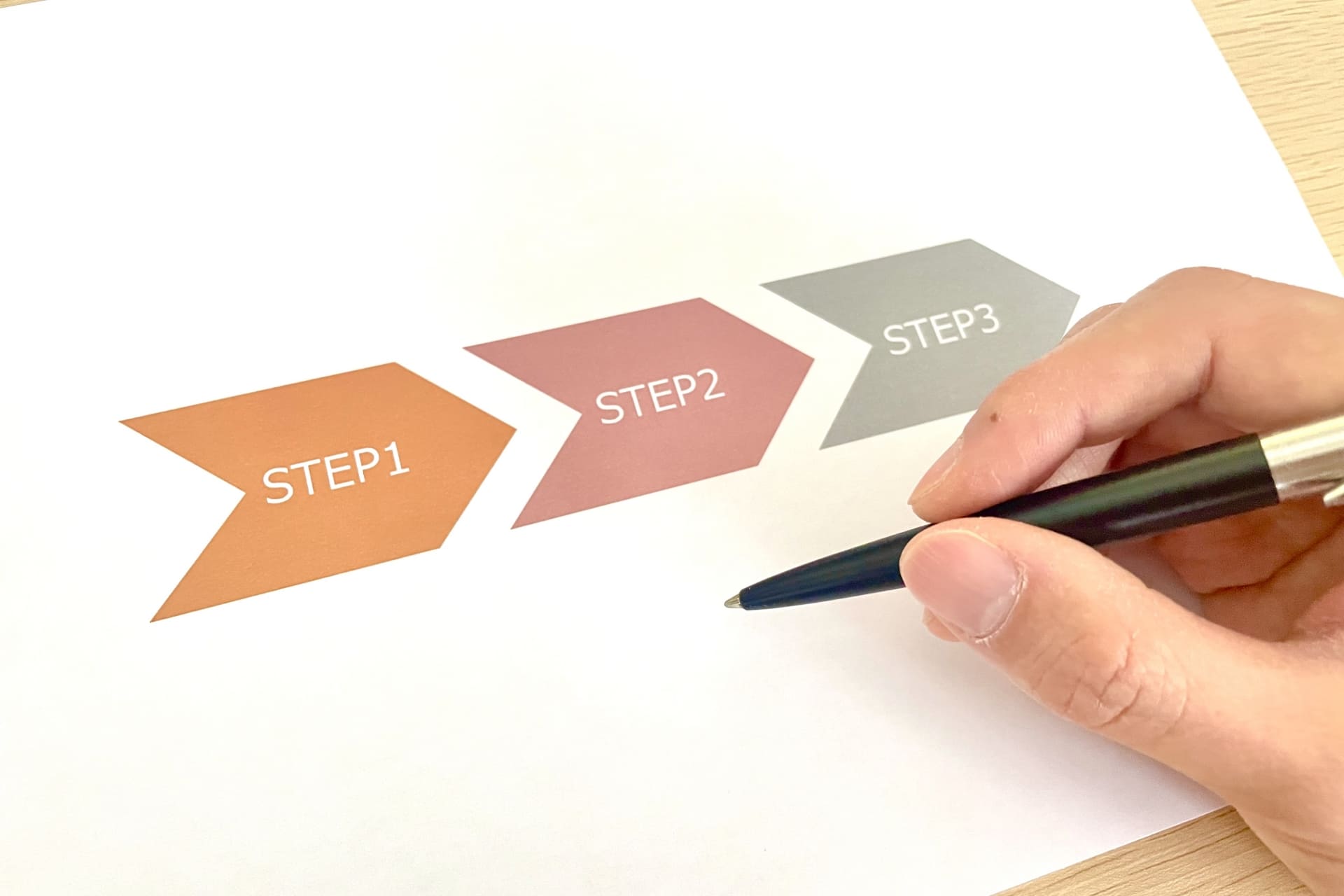
不動産を取得した際に納付する不動産取得税には、軽減措置が設けられており、適用要件を満たすことで支払いの負担を大きく軽減できます。
では、その軽減措置を受けるには、どういった手順を踏めば良いのでしょうか。以下では、申請の手順を解説します。1.管轄の都道府県税事務所に申請する
不動産取得税は、都道府県に納める地方税です。そのため、軽減措置を受ける際は税務署ではなく、取得した不動産の所在地にある管轄の都道府県税事務所に、自身で申請する必要があります。
都道府県税事務所は、住民税や自動車税など都道府県の税金を管理している役所で、国の税金を管理する税務署とは取り扱う税金の種類が異なります。
申請場所は、都道府県税事務所の不動産取得税担当課です。「不動産取得税申告書」の必要事項を記入して、窓口に申請しましょう。この際、軽減措置を受ける旨も申請します。都道府県によって申請書の提出期限が異なるため、不安を感じるのであれば都道府県税事務所に直接問い合わせると良いでしょう。2.不動産取得税を納める
不動産取得税の軽減措置を申請した後に、都道府県税事務所から納税通知書が送付されます。軽減措置の申請を行っていない場合、納税通知書には軽減される前の税額が記載されているため、軽減措置を受けられません。また、軽減措置によって納税額が0円になると、納税通知書は送付されないため注意しましょう。
納税通知書が送付される時期は、不動産を取得した日からおよそ半年から1年後になります。納税通知書を受け取ったら、記載されている期日までに、自治体が指定する支払い方法で税金を納付しましょう。
期日までに納付できないと、延滞金が発生する恐れがあります。万が一、間に合わない場合は、管轄の都道府県税事務所に相談しましょう。-

不動産取得税の軽減措置を受ける時の流れに関しては、上述した通りです。では、申請にはどういった書類を用意しなければならないのでしょうか。
ここでは、軽減措置を受ける際に必要な書類を解説します。なお、都道府県や軽減措置の対象になる不動産によって、用意する書類が異なるため、詳細は管轄の都道府県税事務所に問い合わせるようにしましょう。不動産取得税申告書・不動産取得税減額申告書
まずは、「不動産取得税申告書」や「不動産の取得申告書」「不動産取得税減額申告書」を用意して必要事項を記入し、管轄の都道府県税事務所に提出しましょう。申告書の書類は、各都道府県で名称が異なるケースがあります。
また、不動産取得税に関する申告書は、都道府県ごとに書式が定められていることにも注意しましょう。申告書を用意するには、都道府県税事務所または都道府県のホームページからダウンロードする、税事務所の窓口で直接受け取るといった方法があります。どちらの方法でも、必ず取得した不動産が所在している管轄の都道府県を選びましょう。不動産取得税の納税通知書
先にも述べたように、不動産を取得すると「不動産取得税の納税通知書」が管轄の都道府県税事務所から送付されます。場合によっては、この不動産取得税の納税通知書か、「不動産取得税の納税通知書の領収証書」が申請時に必要です。
ただし、納税通知書が送付される時期は、都道府県によって異なるため注意しましょう。住宅の登記事項証明書
「登記事項証明書」とは、不動産を所有する方の氏名や住所、所在などが記載された証明書で、電子データとして管理されているのが特徴です。
登記事項証明書はどこの法務局でも、不動産の場所に関係なく取得できます。なお、取得する際に用意しなければならない書類は特にありません。
登記事項証明書の取得時には、1通で600円の手数料がかかるため、窓口から収入印紙で納めます。現在は、インターネットからオンラインでの取得申請も可能です。平面図
「平面図」とは、水平方向に輪切りにした建物を上から見た図面で、間取り図とも言います。平面図は、法務局の窓口や郵送、またはオンライン申請で取得可能です。
取得の際に、印鑑や身分証明書などは不要ですが、1通につき450円の手数料がかかるため、収入印紙で納めなければなりません。建築工事請負契約書
注文者が請負人に建物の工事を発注し、請負人が受注する内容が記載された書類が「建築工事請負契約書」です。この契約書には、工事内容や完成の時期、請負金額などが記載されています。
通常、契約自体は口頭でも成立するものですが、建築工事請負契約書に関しては建設業法19条で、工事の請負契約の当事者による契約書の作成・交付が義務付けられています。耐震基準適合証明書・住宅性能評価書の写し
不動産を取得した日から前2年以内で、新耐震基準に適合している証明された住宅を取得した場合は、「耐震基準適合証明書」や「住宅性能評価書」の写しが必要になるケースもあります。
耐震基準適合証明書は、建物が新耐震基準に適合していることを証明する書類で、住宅性能評価書は、国土交通省に登録されている第三者機関が住宅性能を評価した書類です。耐震基準適合証明書や住宅性能評価書は、国土交通省が指定した評価機関や、建築士事務所の登録を行っている事務所に所属する建築士などに申請すると取得できます。
また、長期優良住宅の認定を受けている場合に限り、「長期優良住宅認定書」の写しを用意しなければならないケースがあります。-

不動産取得税の軽減措置を申請する際の流れや必要書類を確認したら、申請時に注意したいポイントも押さえておきましょう。主な注意点は以下の2つです。
軽減措置の申請を忘れないようにする
都道府県によっては、指定の期限内に不動産の登記が行われていれば、軽減措置の申請が不要となるケースもあります。しかし、不動産取得税の軽減措置を受けるには、基本的に申請が必要です。
軽減措置の適用を受ける際は、不動産を取得した日からおよそ60日以内に申請するのが目安とされています。ただし、申請期間も都道府県ごとに異なるため、管轄の都道府県税事務所のホームページなどで確認するようにしましょう。東京都の場合、軽減措置を申請する期限は、取得日から30日以内と定められています。軽減措置の適用の有無で不動産取得税は変動する
当記事の前半で述べたように、不動産取得税は軽減措置を受けるか受けないかで、課税額が大きく変動します。軽減措置を申請することで、税金の負担を軽減できるため、忘れず期限までに管轄の都道府県税事務所へ申請するようにしましょう。
-

不動産取得税の軽減措置を受けようとして申請を忘れてしまった場合は、軽減前の不動産取得税を納付しなければなりません。しかし、後から申請することで、軽減措置が適用されるケースもあります。申請の内容に問題がなければ、納めすぎた不動産取得税は還付されるでしょう。
不動産取得税の還付請求は、必要書類を用意し、管轄の都道府県税事務所に申請します。還付請求が可能な期限は5年と決まっているため、5年以内に申請しましょう。-

不動産取得税の還付を受ける際は、どのような流れで還付の手続きを進めれば良いのでしょうか。ここでは、還付の流れを順番に解説します。
1.不動産取得税申告書を提出する
不動産取得税の軽減措置を申請するのと同様に、まずは管轄の都道府県税事務所へ不動産取得税申告書を提出しましょう。申告書は、都道府県税事務所や都道府県のホームページからダウンロードするか、税事務所の窓口で直接受け取るかして用意します。
2.不動産取得税を納める
次に、都道府県税事務所から送付された納税通知書を確認して、指定された期限内で不動産取得税を納付しましょう。いったん、不動産取得税を納付してから、還付を受ける流れになります。
3.不動産取得税減額申請書を提出して還付を受ける
納税通知書で不動産取得税を納付し、軽減措置が受けられることになった場合、「不動産取得税減額申請書」を都道府県税事務所に提出しましょう。申請書の内容に問題がなければ、不動産取得税の還付を受けられます。
還付金は、申請書を提出してからおよそ2か月で、指定した口座に振り込まれます。-
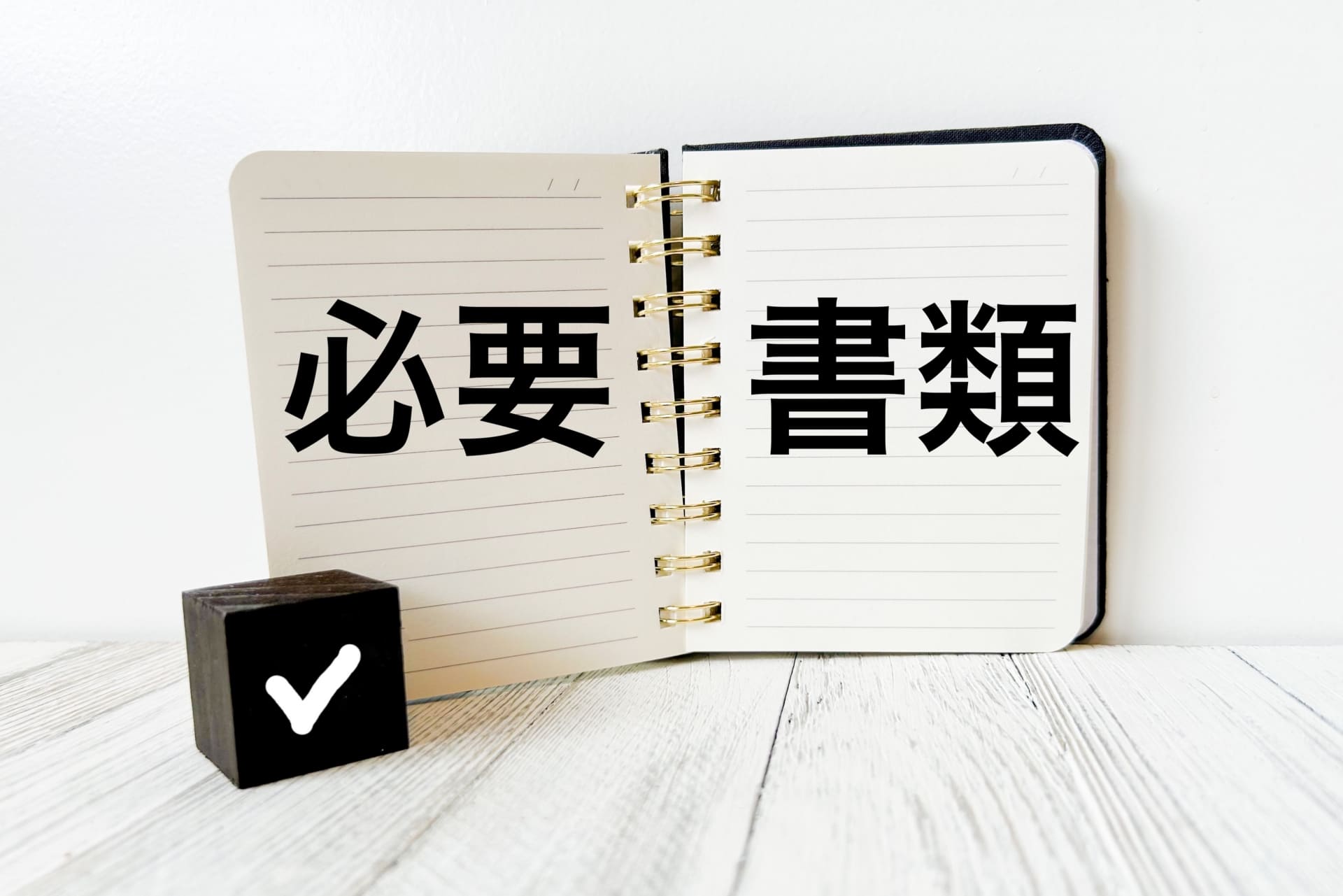
不動産取得税の還付には、申請書などの書類が必要になります。用意しなければならない書類はケースによって異なるため、管轄の都道府県税事務所に問い合わせて確認しましょう。
不動産取得税減額申請書
不動産取得税の還付にまず必要なのは、「不動産取得税減額申請書」です。申請書は、都道府県のホームページからダウンロードできます。不動産取得税減額申請書を用意する際は、取得した不動産が所在する都道府県のホームページからダウンロードしましょう。
住宅の登記事項証明書
不動産取得税の軽減措置を受ける際にも必要になる登記事項証明書は、還付を申請する時にも必要になる書類です。
法務局であれば、取得した不動産の所在地に関係なく証明書を発行してもらえます。法務局に直接出向くのが難しい方は、オンラインで取得の申し込みをすると良いでしょう。なお、登記事項証明書の取得には、1通で600円の手数料がかかります。不動産取得税の納税通知書・領収証書
軽減措置の申請と同様に、不動産を取得した際に都道府県税事務所から送付される、不動産取得税の納税通知書や、その領収証書が還付に必要になるケースがあります。
平面図
不動産取得税の還付の申請時に、建物の平面図を用意しなければならないケースもあります。平面図を取得するには、直接法務局の窓口に出向くか、郵送で申請するか、もしくはオンラインでの申し込みが可能です。取得時に身分証明書などは必要ありませんが、手数料が1通につき450円かかります。
本人の口座番号がわかるもの
不動産取得税の還付の申請が承認されると、還付金が指定した口座に振り込まれます。そのため、還付を申請する際は必要書類だけでなく、通帳など振り込みを希望する口座の番号がわかるものも用意しましょう。なお、不動産取得税減額申請書を提出した後は、およそ2か月で還付金が振り込まれます。
ここまで、不動産取得税の還付を申請する時に必要なものや、用意しなければならない可能性がある書類を紹介しました。他にも、中古住宅の場合は耐震基準適合証明書や、耐震改修を行ったことを証明する書類が必要になることもあります。
また、状況によっては、軽減措置の適用要件を満たしていることを証明できる書類を用意しなければなりません。軽減措置の適用要件に関する書類が必要であれば、各都道府県の税務署に問い合わせると良いでしょう。-

不動産を取得すると、不動産取得税がかかるケースがほとんどです。しかし、中には制度によって、不動産取得税が非課税になる場合もあります。
不動産取得税が非課税になる際は、都道府県のホームページからダウンロードできる、「不動産取得税非課税申告書」を提出します。ここでは、不動産取得税が課税されない5つのケースを確認しましょう。取得した不動産の価格が低い
取得した土地や家屋の価格が一定額よりも低いと、不動産取得税が課税されない可能性があります。以下のケースに該当する場合は、不動産取得税は非課税です。
1.土地を取得した金額が10万円未満
2.新築や増築を行った場合に、1戸につき23万円に満たない
3.売買や贈与など建築以外で建物を取得した場合に1戸につき12万円に満たない
上記の条件として定められている金額を超えると、不動産取得税の課税対象になります。非課税対象の土地と隣接している土地を1年以内に取得、または取得した建物と一構造になっている建物を1年以内に取得した場合は、1つの土地・家屋として判断されます。相続によって不動産を取得した
当記事の前半でも述べたように、不動産取得税は相続で引き継いだ不動産に関しては、基本的に非課税です。ただし、以下のように贈与や特定遺贈を受けて取得した場合は、不動産取得税が課税されます。
不動産を生前贈与された
贈与者が生きているうちに所有する財産を譲る生前贈与は、節税効果が期待できるといったメリットがあります。しかし、生前贈与は相続には該当しないため、不動産取得税を納付しなくてはなりません。
不動産を死因贈与された
被相続人が死亡することで効力が発生する贈与が死因贈与です。生前贈与と同じく、相続ではなく贈与契約であるため、不動産取得税が課税されます。
相続人以外が特定遺贈を受けた
被相続人の配偶者や子ども、孫などの法定相続人が不動産の所有権を相続した際は、不動産取得税は課税されません。遺言書で財産内容と受遺者を指定する「特定遺贈」の場合、法定相続人以外の第三者が特定遺贈によって不動産を取得すると、不動産取得税を納付しなければなりません。 また、財産内容を指定しない「包括遺贈」に関しては、法定相続人でもそれ以外の第三者でも、不動産取得税は課税されません。土地区画整理の換地や一般に開放されている私道
土地の区画整理で「換地」を取得した際は、不動産取得税は課税されません。換地とは、土地の区画整理が行われる時に、区画整理前の土地の代わりとして交付される宅地です。
また、一般に開放されている私道も周辺住民に広く利用されている状況から、公共の用に供する道路と判断されるため、取得時に発生する不動産取得税が非課税となります。特定の法人が事業用の不動産を取得する場合
学校法人や宗教法人など、特定の法人が事業用に不動産を取得した場合は、不動産取得税は非課税です。本来の事業とは異なる用途を目的に取得した不動産については、不動産取得税を納付しなければなりません。
学校法人
教育や保育のために使用する建物や土地
宗教法人
境内がある建物や土地
社会福祉法人
介護施設や養護施設など社会福祉事業を行うための建物や土地法人の合併・分割によって不動産を取得した場合
法人が組織の再編などによって合併・分割したケースで、不動産を取得した場合、不動産取得税は課税されません。これは、不動産の所有権が移動しただけで、新規で取得したわけではないからです。
なお、法人の分割による非課税には、「金銭不交付要件」を満たすことが条件になるケースがあります。金銭不交付要件とは、組織再編の対価として株主に承継法人株式以外の金銭を交付しないことを求める要件です。-

家屋や土地などの不動産を、購入したり贈与されたりして取得すると、その家屋や土地に対して不動産取得税が課税されます。しかし、不動産取得税には税負担を抑えられるように、軽減措置が設けられているのも特徴です。
不動産取得税の軽減措置は、定められている要件を満たすことで適用されます。申請時の必要書類は、管轄の都道府県税事務所のホームページなどを見て確認しましょう。取得した不動産が新築か中古かなど、状況によって軽減措置の要件は変わるため注意が必要です。-
不動産取得税とはなんですか。
不動産取得税とは、家屋・土地の購入または建築、贈与などで不動産を取得した際に、その取得者に課税される税金です。
-
不動産取得税の計算方法について教えてください。
不動産取得税の税率は4%に設定されています。この税率と固定資産税課税台帳に記載された不動産の評価額を基に、不動産取得税の額を算出します。
不動産取得税 = 固定資産税評価額 × 税率(4%)
基本的に不動産取得税の税率は4%ですが、現在は税負担を軽減するための措置が設けられており、これが適用されると税率は3%に引き下げられます。
関連記事
-
 アパート経営で大切な火災保険とは?役立つ基礎知識をまとめました詳しく見る
アパート経営で大切な火災保険とは?役立つ基礎知識をまとめました詳しく見るアパート経営において、リスクを最小化するためにも、火災保険への加入は必須と言えます。 火災保険の補償範囲は火災だけに留まらず、落雷や雪災などのさまざまな自然災害も含まれます。補償範囲は加入する火災保険の種類や特約によって異なるため、加入前に検討することが大切です。 しかし、火災保険はさまざまな保険会社が提供しているため、「どの保険に加入すれば良いかわからない」という方もいるのではないでしょうか。 そこで、この記事では、火災保険の必要性や種類、補償範囲などを詳細にご紹介します。 しかし、所有している土地でアパート経営を始めるには、いくつかのリスクがあることも覚えておきましょう。それぞれのリスク回避のために適切な対策を行って、効率的な土地活用を行いましょう。 この記事では、土地有りでアパート経営を行うメリット・デメリットについて、そして経営を進める時の流れや必要な資金などについて解説します。
-
 サブリースはワンルーム物件に必要?メリット・デメリットを紹介詳しく見る
サブリースはワンルーム物件に必要?メリット・デメリットを紹介詳しく見る不動産投資には多くの資金が必要になるケースが多くありますが、ワンルームマンションは少額からの投資が可能な点で近年人気が高まっています。このような賃貸物件の経営に、サブリースを利用している方も少なくありません。 サブリースとは、サブリース業者が賃貸物件を借り上げて運営する契約のことです。ワンルーム物件を運営する際、サブリースにはどういったメリットやデメリットがあるのでしょうか。この記事では、ワンルーム物件やサブリースのメリットとデメリット、サブリースを利用したワンルーム投資のポイントなどを解説します。
-
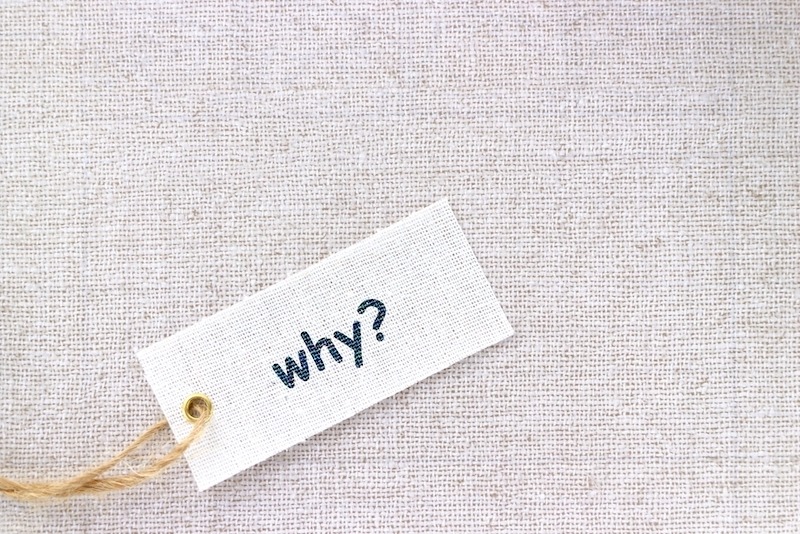 土地相続だけを放棄できない?相続放棄の方法や注意点をまとめて解説!詳しく見る
土地相続だけを放棄できない?相続放棄の方法や注意点をまとめて解説!詳しく見る両親や祖父母が所有する土地が田舎にある場合や遠方の場合、土地の相続が不要に思うこともあるでしょう。しかし、相続財産の中で土地だけの放棄はできません。また相続をきっかけに相続人間の関係が悪化するケースも少ないため、想定される相続に関してはあらかじめ選択肢など方向性を検討しておくことも必要です。今回は相続の仕組みや土地だけの相続放棄ができない理由、相続放棄手続き、相続放棄以外の土地の処分方法を中心に解説します。まだ先のように思っていても、人が亡くなった時点で相続は突然始まります。土地や空き地など不動産の相続が見込まれる方に役立つ内容となっているのでぜひ、参考にしてください。
タウングループ不動産仲介・周辺事業- 賃貸不動産仲介(東京・神奈川・埼玉・千葉) タウンハウジング
- 賃貸不動産仲介(東海) タウンハウジング東海
- 賃貸不動産仲介(九州) タウンハウジング福岡
- 土地・建物の不動産販売及び仲介 タウン住宅販売
- 首都圏を中心に引越サービスを展開 タウン引越サービス
- 賃貸不動産仲介(東北) タウンハウジング東北
- 賃貸不動産仲介(北関東) タウンハウジング北関東
建築事業- 賃貸住宅の企画・設計・施工 アヴェントハウス
多角化事業- 都内を中心に飲食店を運営 タウンダイニング
- インドアテニススクール タウンインドアテニスアカデミー


 一覧へ戻る
一覧へ戻る