家賃収入も確定申告は必要?家賃収入にかかる税金や確定申告の方法などを分かりやすく解説
アパートやマンション、貸事務所などの賃貸物件を所有し、年間で一定以上の家賃収入がある場合に避けて通れないのが、確定申告と納税です。家賃収入が年間20万円を超える場合は、確定申告を行うことが義務付けられています。しかし、確定申告に関連する税金や必要経費の種類、必要な書類や手続き方法について、詳しくは理解していないという人も多いでしょう。本記事では、収入額に応じて異なる確定申告の必要性と、家賃収入にかかる税金について解説します。加えて、家賃収入がある場合に経費扱いできるものとできないもの、確定申告の方法についても詳しく紹介します。
-

所得区分上、家賃収入は「不動産所得」に分類されます。この不動産所得が年間で20万円以上ある場合は、確定申告が必要です。確定申告とは、1年間(1月1日~12月31日)の所得に対して納税額を計算・申告・納税する手続きを指します。主に個人事業主や自営業者、フリーランスなど一定額以上の事業所得のある人が対象です。ただし、会社員でも確定申告の対象となるケースもあります。なお、家賃収入の場合は、毎月の家賃だけでなく入居時の礼金や契約更新時にかかる更新料も家賃収入となります。ここでは、以下の通り家賃収入が20万円以下でも確定申告したほうがいいケースと確定申告が必要なケースについて解説します。
家賃収入が20万円以下でも確定申告したほうが良いケース
家賃収入を含む各種収入から、必要経費を差し引いた金額が年間で20万円以下のケースでは、一般的に確定申告の必要はありません。しかし、副業が赤字経営の場合には、確定申告をおすすめします。これは、不動産所得が本業の給与所得と損益通算できるためです。損益通算とは、本業などの所得と合算した額で所得税の金額を算出する制度です。この損益通算によって課税所得が減少し、必要以上に収めていた税金が還付される可能性があります。この損益通算制度をうまく利用することで、節税も可能となります。
家賃収入が20万円以下でも確定申告が必要なケース
副業の家賃収入が年間20万円以下でも、本業の給与収入が2,000万円を超える場合、企業側が行う年末調整の対象外となるため、確定申告が必要です。
年末調整とは、納めるべき所得税額を算出し金額の過不足を調整して一致させる清算手続きを指します。基本的には、企業の従業員すべてが年末調整の対象ですが、給与収入が2,000万円を超える従業員は対象外となるのです。年末調整を行わないと、生命保険控除などが適用されず、過払い分の所得税が還付されません。また、住民税の場合は前年度の課税所得を基に算出されるため、本来であれば納める必要がない分まで納めることになるのです。なお、確定申告が必要となる給与の基準となる2,000万円とは、あくまで額面であって給与所得控除や社会保険料控除後の所得ではないため注意しましょう。-

適切に納税するには、家賃収入にかかる税金を理解する必要があります。ここでは、以下の通り家賃収入にかかるさまざまな税金について解説します。
所得税
所得税とは、個人の所得に対してかかる税金を指します。1年間のすべての所得から所得控除を差し引いた課税所得に税率をかけて税額を計算します。なお、所得税の税率は、以下の表の通り5%から45%の7段階に区分されます(分離課税に対するものなどは除く)。
出典:国税庁|No.2260 所得税の税率課税される所得金額 税率 控除額 1,000円~1,949,000円 5% 0円 1,950,000円~3,299,000円 10% 97,500円 3,300,000円~6,949,000円 20% 427,500円 6,950,000円~8,999,000円 23% 636,000円 9,000,000円~17,999,000円 33% 1,536,000円 18,000,000円~39,999,000円 40% 2,796,000円 40,000,000円以上 45% 4,796,000円
課税所得金額と所得税の計算式は以下の通りです。
●課税所得金額の計算式:課税所得金額 = 給与所得 +(家賃所得 – 経費)- 各種控除
●所得税の計算式:所得税 = 課税所得金額 × 所得税率住民税
住民税は、1月1日時点で住民登録していた都道府県や市区町村に納める地方税です。都道府県民税と市区町村民税に分かれており、納税する際は一括して各市区町村に納め、都道府県民税は各市区町村を通じて支払われます。住民税には、所得に応じて納める「所得割」と所得にかかわらず定額を納める「均等割」があります。所得割の税率は、都道府県民税が4%で市区町村民税が6%の計10%(政令指定都市については道府県民税が2%で市民税が8%)です。均等割は4,000円(都道府県民税1,000円、市区町村民税3,000円)ですが、2024年度からは均等割と併せて森林環境税(国税)が1,000円徴収されています。所得割の場合は、家賃収入が増えるとその分課税所得も増えるため、翌年の住民税が高くなるのです。
消費税
消費税は、商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して課税される税で、事業者が納付する仕組みです。ただし、家賃収入で所得があっても、運用している賃貸物件が住宅用の場合は、非課税となります。一方、家賃収入を得ている賃貸物件が、店舗やオフィスなどの事業用の場合は、収入が1,000万円以上になると消費税が課せられます。なお、運用している賃貸物件が住宅用だと判断してもらうためには、以下のふたつの要件を満たさなければなりません。
●契約書に明示されていること
住宅用かどうかは、契約で住宅用と明示されているかで判断します。
●賃貸期間が1か月以上
住宅用として運用している物件でも、賃貸期間が1か月未満の場合は、住宅用と判断されず課税の対象となります。ただし、課税所得が1,000万円以下の場合は、非課税となります。固定資産税
固定資産税は、土地や家屋、償却資産といった固定資産にかかる税金です。固定資産の所有者が、資産価値に応じて算定した税額を市町村に納めます。
償却資産とは、土地や家屋以外の事業の用に供することができる資産です。税額は、土地や家屋などの固定資産税評価額(適正時価)に基づく課税標準額で定められています。また、償却資産の評価は、取得年月や取得価格および耐用年数に基づき、申告のあった資産について一品ごとに賦課期日(1月1日)現在の評価額を算出することで行います。固定資産税は、固定資産を所有している間は毎年徴収される点がポイントです。不動産取得税
不動産取得税は、土地や家屋の購入・贈与、家屋の建築などで不動産を取得したときに、取得者に対して課される税金です。取得者は、取引された不動産が所在する都道府県に納税します。前述した固定資産税とは異なり、不動産を取得したときだけに発生する一時的な税金です。不動産取得税の税額は、以下の通り不動産の評価額(固定資産税の税額算定に使用される課税標準額)に税率を掛けて算定します。税率は4%ですが、現在は軽減税率として土地と住宅については3%が適用されています。
●不動産取得税の税額 = 不動産の評価額(固定資産税の税額算定用の課税標準額)× 税率
なお、不動産取得税は、以下の通り税負担を軽減する特例措置が適用されるケースもあります。
「新築住宅・住宅用地特例」
●新築住宅を取得するケース
新築住宅を取得するケースでは、評価額から1,200万円控除されます。ただし、住宅の床面積が50㎡(一戸建て以外の住宅で貸家の用に供する場合は40㎡)以上で240㎡以下である必要があります。
●住宅用地を取得するケース
住宅用の土地を取得したケースでは、以下の①②のいずれか高い方の額を土地の税額から軽減する。
①150万円×税率
②土地1㎡当たりの価格 × 住宅の床面積の2倍(1戸当たり200㎡を上限)× 税率
ただし、土地の取得日から一定期間内に、取得した土地に住宅が新築されているなど、一定の要件を満たす必要があります。登録免許税
登録免許税は、不動産・船舶・航空機・会社・人の資格などについての登記や登録・特許・免許・許可・認可・認定・指定および技能証明にかかる税金です。主なものとしては不動産の登記で、土地と建物の両方に課税されます。不動産の取引では、売買で所有権が移転した際や住宅ローンを借りて抵当権を設定した際などの登記申請時に納付します。税額は、固定資産税評価額に税率をかけて算出しますが、新築で固定資産税評価額がつけられていない場合は、法務局で認定した課税標準価格に税率をかけて算出します。税率は登記の種類によって異なり、中古建物や土地などの所有権移転登記の場合は2.0%、建物を新築した際の所有権保存登記の場合は0.4%です。なお、条件によっては、軽減措置が適用され、税率が引き下げられることもあります。
都市計画税
都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業の費用に充てるために課される市町村税(東京23区は都税)です。原則として市街化区域内に所在する土地や建物を1月1日時点で所有している人に対して課される地方税になります。固定資産を所有している間は、基本的に毎年発生するのが特徴です。この都市計画税の課税については、都市計画事業などに応じた市町村の自主的な判断に委ねられています。詳しい内容については、住んでいる自治体に問い合わせてみるとよいでしょう。
印紙税
印紙税とは「不動産売買契約書」や「金銭消費貸借契約書」などを含むさまざまな課税文書に対して発生する税金を指します。「収入印紙」を書類に貼り、課税文書の作成者が消印をすることで納税が完了する形式です。税額は、契約書に記載されている金額によって異なります。なお、収入印紙とは、税金や手数料を支払う目的で書類に貼り付ける証票を指します。
-

不動産所得を正しく計算するためには、家賃収入を得るのにかかった必要経費を把握・計上する必要があります。ここでは、家賃収入がある場合に経費として計上できるものを、以下で解説します。
租税公課
租税公課とは、国や地方自治体に納める税金と公共団体に納める会費や罰金など(公課)を合わせたものです。租税公課で経費扱いできる代表的なものは、以下の通りとなります。
●固定資産税
●不動産取得税
●登録免許税
●都市計画税
●個人事業税保険料
火災保険や地震保険、施設賠償保険など、自身で負担した保険料は必要経費として計上できます。ただし、数年分の保険料を一括で支払った場合に必要経費として計上できるのは、申告する年にかかる分だけなので注意しましょう。
建物の維持に必要な費用
建物の維持に必要な、管理費・共益費・修繕費は必要経費として計上できます。ここでは、それぞれについて以下の通りに解説します。
●管理費:
物件のオーナーが管理業務を委託する賃貸管理会社に支払う報酬を指します。
●共益費:
家賃と一緒に入居者から受け取る費用を指します。用途としてはエレベーターや階段など、共用部のメンテナンス費用・清掃費用・電気代などです。入居者全員が共同で使用する設備の維持費用に充てられます。前述した管理費は、実質的に入居者から受け取る共益費でまかなうことになります。
●修繕費:
建物などの資産維持や管理のために支出したものを指します。ただし、増改築や耐震補強など、建物の価値を高めたり耐用年数を延ばしたりする工事は、すぐに費用とはなりません。「資本的支出」とされ、取得価額として扱って減価償却によって計算する必要があります。減価償却費
土地以外の建物・車・備品・駐車場の舗装など、月日の経過によって価値が減少する固定資産を「減価償却資産」といいます。減価償却資産の取得費用は、取得した年に全額経費となるわけではなく、減価償却資産の耐用年数で分割して減価償却費として経費を計上するのです。資産によって耐用年数と償却率が定められており、例えば、建物の場合は鉄筋コンクリートや木造など、構造に応じて変動します。
未収の家賃
回収できなくなった家賃は、経費として計上できることがあります。債権の回収が不可能であると確定することを「貸し倒れ」といい、条件によっては損失としての処理が可能です。経費計上は、貸し倒れが確定した年の分として行います。ただし、経費に計上できるのは、不動産の貸し付けを事業で行っている場合のみです。事業的規模かどうかは、社会通念上、事業といえる規模で行われているか否かによって判断されます。アパートやマンションなどは、貸与できる独立した室数がおおむね10室以上、独立した家屋の貸し付けの場合はおおむね5棟以上で、事業的規模と判断されます。
水道光熱費
賃貸物件の水道光熱費をオーナー自身が負担する場合は、必要経費です。また、自宅を事務所にしているケースでも、水道光熱費の一部が必要経費となります。自宅を居住部分と事務所部分に分け、事務所部分が経費に該当します。
消耗品費
賃貸物件経営のために使用した消耗品費は、経費として計上可能です。文房具代だけでなく、耐用年数1年未満もしくは取得価格が10万円未満の備品などの代金も消耗品費に該当します。例えば、物件を管理するために使っているプリンターのインク代や用紙代は、消耗品費にあたります。
交通費
賃貸物件経営に関わる物件の視察・管理・契約などで発生する交通費は、経費として計上可能です。例えば、遠方にある物件の状態をチェックするために、車や電車などで出向いたときのガソリン代や電車賃などは、経費として認められます。
通信費
賃貸物件経営に関わる電話代や郵便代などの通信費も経費として計上可能です。例えば、不動産会社や管理会社とのやり取りにかかった電話代などが該当します。また、インターネットを活用して物件を管理している場合も、プロバイダ代などを経費として計上できます。
ローン返済金のうち利息分
ローンを組んで賃貸物件を購入した場合、ローン返済金の利息分は経費として計上できます。ただし、元本返済部分は経費として計上できないため、注意が必要です。
税理士・司法書士への報酬
賃貸物件経営では、さまざまな業務を専門家に依頼するケースがあります。例えば、税理士に確定申告の手続きを依頼したり、司法書士に不動産登記の手続きを依頼したりするなどです。仕業への依頼報酬は高額になるケースもありますが、その場合の報酬も経費として計上できます。
青色事業専従者給与
納税者と生計を一にしている配偶者やその他の親族が、納税者が経営する事業に従事している場合、支払われる給与は原則として必要経費とはなりません。しかし、青色申告者の場合、一定の要件を満たしていれば、支払った給与を必要経費とする「青色事業専従者給与」の特例が設けられています(認められる場合があります)。
地震などの原因により発生した損失
地震などの自然災害や火災などが原因で被害を受けた場合、その損失分は経費として計上可能です。
-

プライベートでの支出や個人に課される税金など、経費扱いできない費用があります。経費として不適切な費用を計上すると、税務調査の際に修正を求められてしまうため注意が必要です。ここでは以下の通り、経費扱いできない費用を解説します。
借入金のうち「元本分」
前述した通り、ローン返済金の利息分は経費として計上できますが、元本分は経費として計上できないため、注意が必要です。
所得税と住民税
所得税と住民税は、賃貸経営とは関係なく発生する税金のため、家賃収入の経費として計上できません。基本的に経費として計上できるのは、賃貸経営と関連するものだけになります。
プライベートと判別が難しいもの
賃貸経営に関係のない支出は、経費として計上できません。例えば、カバンやスーツなどプライベートとの判別が難しいものは、不動産会社や管理会社などとの打ち合わせで使用するとしても経費とは認められないため、注意が必要です。
賃貸経営とは無関係な私生活で発生した交通費・通信費・自宅の修繕費など
賃貸経営とは無関係の私生活で発生した交通費・通信費・自宅の修繕費などは、経費として計上できません。
-
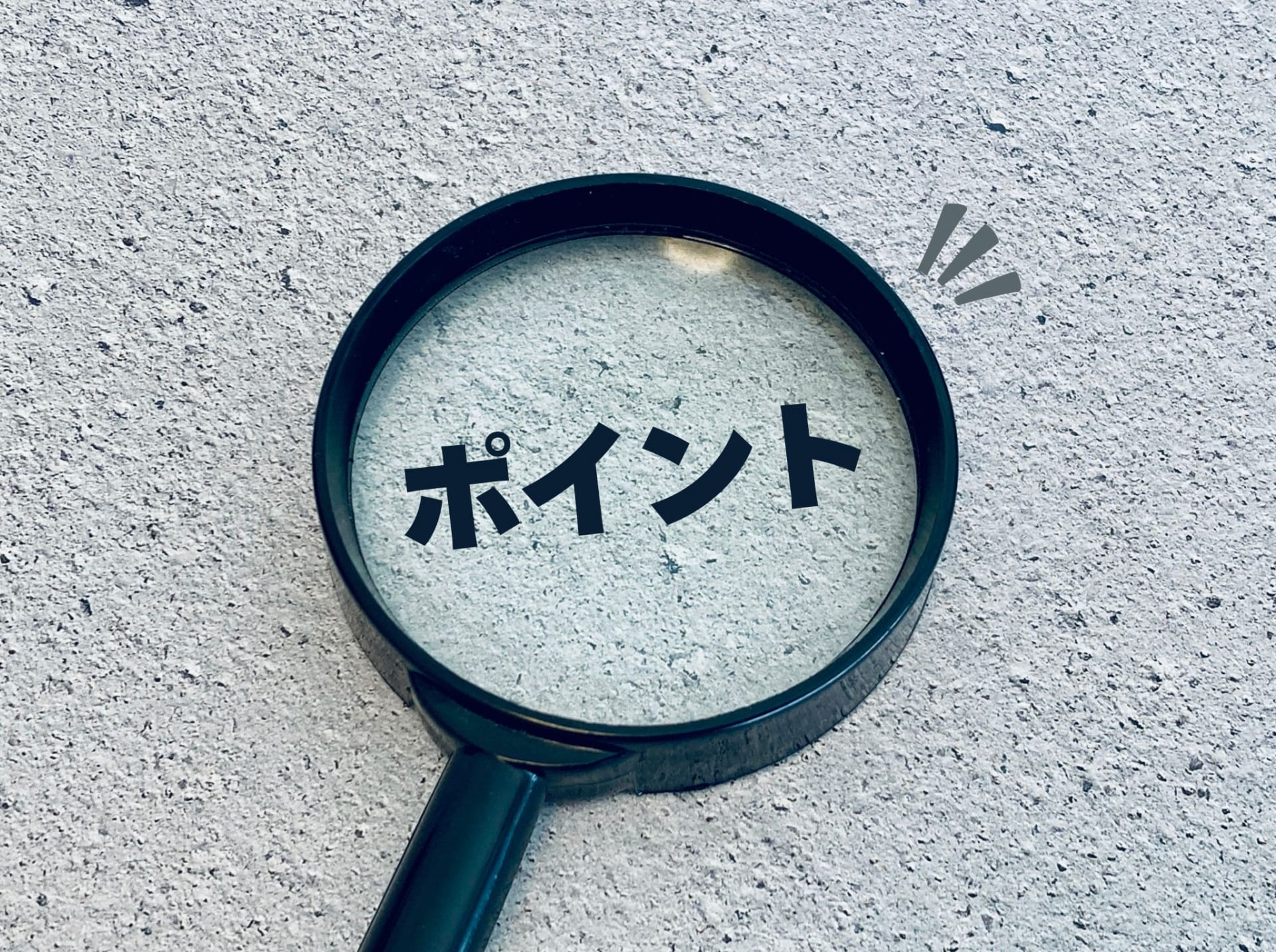
家賃収入の経費については、以下のポイントを押さえておきましょう。
領収書がもらえない場合やなくしてしまった場合
経費と証明するためには、領収書やレシートが必要です。しかし、領収書をもらい忘れたり、なくしてしまったりした場合は、支払いの事実を証明する他の書類を保存しておくことで代用できます。具体的には、クレジットカードの利用明細や電車の乗車履歴などが該当します。明細や履歴もない場合は、文具店で出金伝票を購入して、以下の通り取引内容4項目を記載しましょう。
●書類作成者の名称
●取引年月日
●取引内容
●取引金額過剰な経費計上のデメリット
節税になるからと経費を計上しすぎると、事務負担の増加や会計上の利益減少といったデメリットがあります。短期的にみた場合には節税効果はありますが、長期的にみると金融機関からの評価が下がり、融資が受けづらくなる恐れがあるのです。引き続き融資を受けて投資の拡大を目指すのであれば、金融機関におけるローン審査の観点から収入金額を考える必要があります。
-
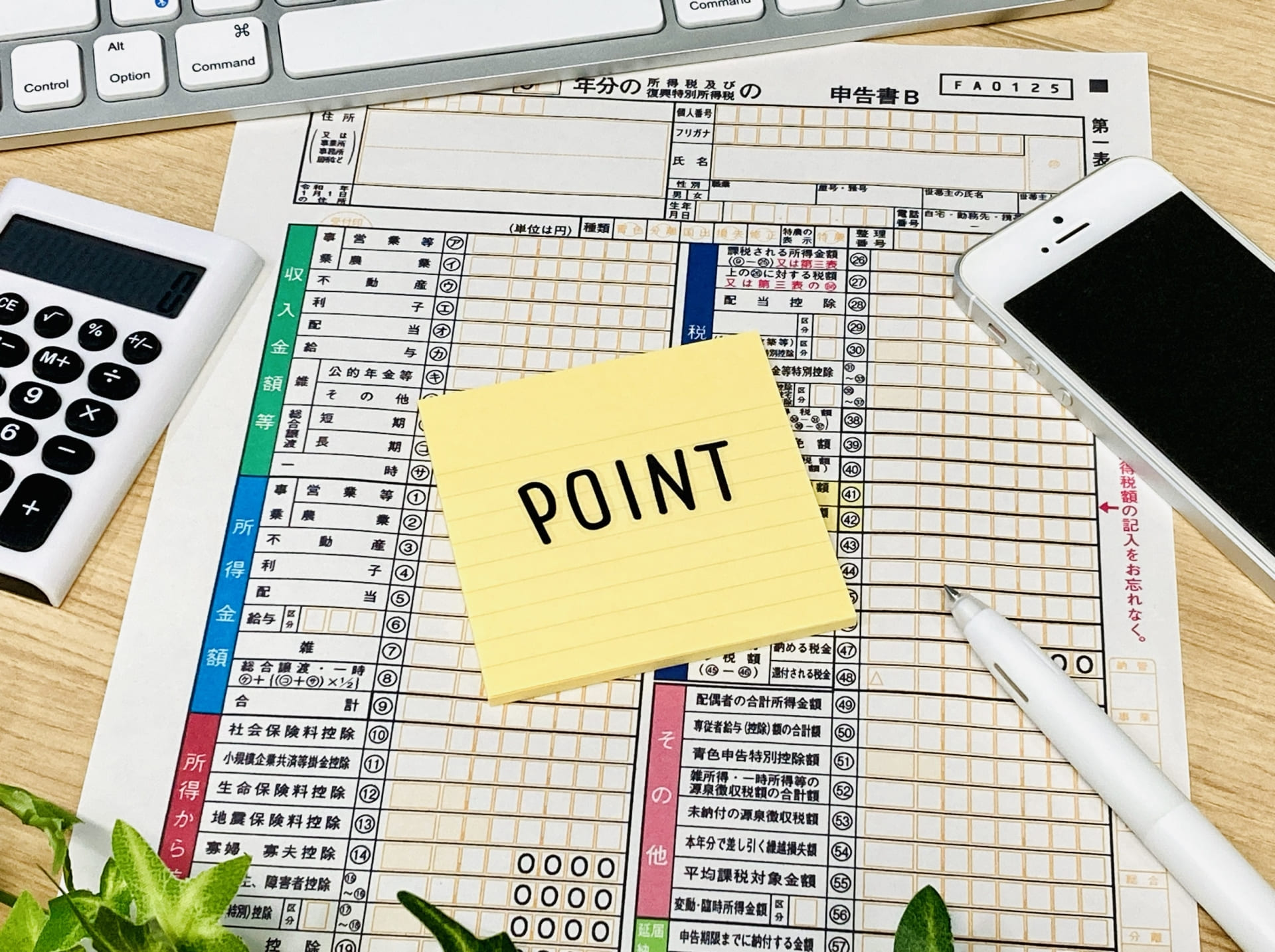
確定申告をスムーズに行なうには、必要な準備や進め方について、ある程度事前に理解しておく必要があります。ここでは、以下の通り家賃収入の確定申告方法を解説します。
手続きの準備
確定申告は、青色申告と白色申告の2種類に分類されます。確定申告にあたっては、まずどちらで行うか選択する必要があるのです。青色申告を選択した場合は、最大65万円の特別控除が受けられるだけでなく、赤字を3年間繰り越すことも可能です。ただし、所轄の税務署に「開業届」と「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。一方、白色申告は、手続きや準備する書類がシンプルです。また、記帳も青色申告の複式簿記とは違って単式簿記で良いため、初めて確定申告する場合でも比較的スムーズに作業できるのがメリットです。しかし、青色申告のような特別控除は受けられませんし、赤字を繰り越せないといったデメリットもあります。
必要な書類を準備する
確定申告書の作成で必要となる以下の書類を、事前に準備しましょう。
入手先・送付元 準備する書類 勤務先 ・源泉徴収票 不動産会社 ・不動産売買契約書
・売渡精算書(不動産を売買したときの費用明細がわかるもの)
・譲渡対価証明書(マンションを土地と建物に按分した際の割合を示すもの)
・家賃送金明細書
・賃貸契約書融資元 ・借入金の返済予定表 修繕を請け負った会社
(修繕した場合)・修繕の見積書
・修繕の請求書
・修繕の領収書地方自治体 ・固定資産通知書
・火災保険や地震保険などの証券
・管理費や修繕積立金がわかる通帳など確定申告書を作成する
必要な書類が準備できたら、確定申告書を作成します。確定申告書は、役所や税務署に行って直接窓口で受け取れるほか、国税庁の公式HPからもダウンロードできます。確定申告書の作成には、国税庁のWebサイトで公開されている「確定申告書等作成コーナー」を参考にするのがおすすめです。しかし、確定申告書作成に関して不明な点がある場合は、税務署の窓口や確定申告会場での相談ができます。
確定申告書を提出する
確定申告書を提出する方法には以下の3種類があり、それぞれメリットとデメリットが存在します。
①所轄税務署の窓口に提出するメリット・デメリット
内容 メリット ・税務署の窓口担当者が、必要書類を確認してくれる(内容は確認しない) デメリット ・所轄税務署まで出向く必要がある
・確定申告の時期は、混みあっている
・書類による青色申告の場合、特別控除が最大55万円➁所轄税務署に郵送するメリット・デメリット
内容 メリット ・所轄の税務署まで出向かなくてもよい
・確定申告期間内の消印が押されていれば有効デメリット ・窓口担当者に書類を確認してもらえない
・書類による青色申告の場合、特別控除が最大55万円③e-Taxで申告するメリット・デメリット
内容 メリット ・所轄税務署まで出向く必要がなく、自宅でできる
・e-Taxでの青色申告の場合、特別控除は最大65万円デメリット ・窓口担当者に書類を確認してもらえない -

確定申告書の提出期限は、毎年2月16日から3月15日の間です。提出方法によって締切時間が微妙に異なります。税務署の窓口に直接提出する場合は3月15日の17時までで、e-Taxで申告する場合は3月15日の23時59分までです。申告期限が土日祝日の場合は、その翌日または翌々日が期限となります。なお、税務署へ郵送する場合は、3月15日の消印があれば有効となります。3月15日が土日祝日の場合は、翌日または翌々日の平日の消印があれば問題ありません。
-

確定申告が遅れた場合は、以下のようなペナルティが課されますが、ケースによっても違います。
●無申告加算税
申告期限が過ぎた場合に課税されるのが「無申告加算税」です。税率は、5~20%の範囲で定められており、以下の通りケースによって異なります。
①期限を過ぎてから、自主的に申告したケース:納税額の5%
➁税務調査などを通じて、納税すべき金額が発覚したケース(50万円まで):納税額の15%
③税務調査などを通じて、納税すべき金額が発覚したケース(50万円を超える部分):納税額の20%
●延滞税
申告期限を過ぎてから実際に納付が完了するまでの期間に対する利息として、「延滞税」が課されます。税額は、申告期限から2か月を過ぎる日までは年利7.3%、2か月以降だと年利14.6%の割合で日数ごとに増えていきます。-

家賃収入が年間20万円以上であれば、確定申告が必要となります。ただし、年間20万円以下でも確定申告したほうが節税になるケースや、確定申告しなければならないケースがあるため注意が必要です。家賃収入にかかる税金は、毎年かかるものから単発的にかかるものまでさまざまで、すべてを把握するのは容易ではありません。そのため、専門家のサポートを受けるなどして適正に申告・納税する必要があります。また、家賃収入から必要経費を引いた額が課税所得ですが、節税のためといって過剰に経費を計上すると、融資の際に不利になる恐れがあるため注意しましょう。確定申告は青色申告と白色申告の2種類あり、それぞれにメリット・デメリットがあります。それらを理解したうえで自身にあった申告方法を選び、提出期限を考慮しながら準備を進めていくのが望ましいでしょう。
関連記事
-
 アパート経営時に車(車両費)は経費に計上できる?車選びや節税のコツも解説詳しく見る
アパート経営時に車(車両費)は経費に計上できる?車選びや節税のコツも解説詳しく見るアパート経営は、物件までの行き来や不動産管理会社との打ち合わせなどに車が必要な場合もあります。そのため、アパート経営時に車の購入費用が経費に計上できるのか、疑問に思うオーナーもいるのではないでしょうか。この記事では、アパート経営における車両費は経費に計上できるのかを中心に、経費の仕組みやメリット・デメリット、計上の仕方などを紹介します。 しかし、所有している土地でアパート経営を始めるには、いくつかのリスクがあることも覚えておきましょう。それぞれのリスク回避のために適切な対策を行って、効率的な土地活用を行いましょう。 この記事では、土地有りでアパート経営を行うメリット・デメリットについて、そして経営を進める時の流れや必要な資金などについて解説します。
-
 賃貸物件の管理費とは?主な用途や相場、管理費無料物件についても解説詳しく見る
賃貸物件の管理費とは?主な用途や相場、管理費無料物件についても解説詳しく見る賃貸物件とは、物件のオーナーが部屋の貸し出しを行い、賃料を得ることを目的とした物件をいいます。賃貸物件の入居時は家賃を支払いますが、他にも物件の「管理費」を払う必要があります。管理費とは、入居者が快適に住めるよう物件を管理・維持する際に使われる費用です。 この記事では、賃貸物件に興味がある方や、これから入居しようと考えている方、管理費の仕組みを詳しく知りたい方向けに、賃貸物件の種類や管理費の主な用途を解説します。また、管理費無料・管理費込み物件の仕組みや、本当にお得なのかどうかも紹介します。 しかし、所有している土地でアパート経営を始めるには、いくつかのリスクがあることも覚えておきましょう。それぞれのリスク回避のために適切な対策を行って、効率的な土地活用を行いましょう。 この記事では、土地有りでアパート経営を行うメリット・デメリットについて、そして経営を進める時の流れや必要な資金などについて解説します。
-
 【アパート経営の年収・手取り収入は?】プロがわかりやすく解説詳しく見る
【アパート経営の年収・手取り収入は?】プロがわかりやすく解説詳しく見るアパート経営は安定した運用を行うことで長期的な収益源となりやすいというメリットがあります。そのため、土地の活用方法、もしくは不動産投資の一つとして、アパート経営を検討している方もいるでしょう。 そのアパート経営を始めるにあたり、気になるのが「どの程度の収入が得られるのか」ということではないでしょうか。アパート経営では、経費や税金などの支出も考慮して、運営を行わなければなりません。そのため、経営を始める前に、「何に費用がかかるのか」を知っておくと良いでしょう。 そこで、この記事ではアパート経営の年収、各種経費や税金の内訳を解説します。
タウングループ不動産仲介・周辺事業- 賃貸不動産仲介(東京・神奈川・埼玉・千葉) タウンハウジング
- 賃貸不動産仲介(東海) タウンハウジング東海
- 賃貸不動産仲介(九州) タウンハウジング福岡
- 土地・建物の不動産販売及び仲介 タウン住宅販売
- 首都圏を中心に引越サービスを展開 タウン引越サービス
- 賃貸不動産仲介(東北) タウンハウジング東北
- 賃貸不動産仲介(北関東) タウンハウジング北関東
建築事業- 賃貸住宅の企画・設計・施工 アヴェントハウス
多角化事業- 都内を中心に飲食店を運営 タウンダイニング
- インドアテニススクール タウンインドアテニスアカデミー


 一覧へ戻る
一覧へ戻る