空き家の3,000万円特別控除とは?チェックシートの内容も詳しく解説
相続や遺贈で空き家を取得した際に、譲渡所得を最大3,000万円まで控除できる特例があることをご存じでしょうか。空き家の3,000万円特別控除は、税金の負担額を軽減し、空き家を減らすという目的で設けられた減税制度です。「空き家を相続したけれど、売却時に多額の税金がかかってしまう」と悩んでいる方も多いでしょう。
本記事では、空き家の3,000万円特別控除(空き家特例)とは何か、控除を受ける際の適用要件などを詳しく解説します。また、手続きに便利なチェックシートについても見ていきましょう。
-
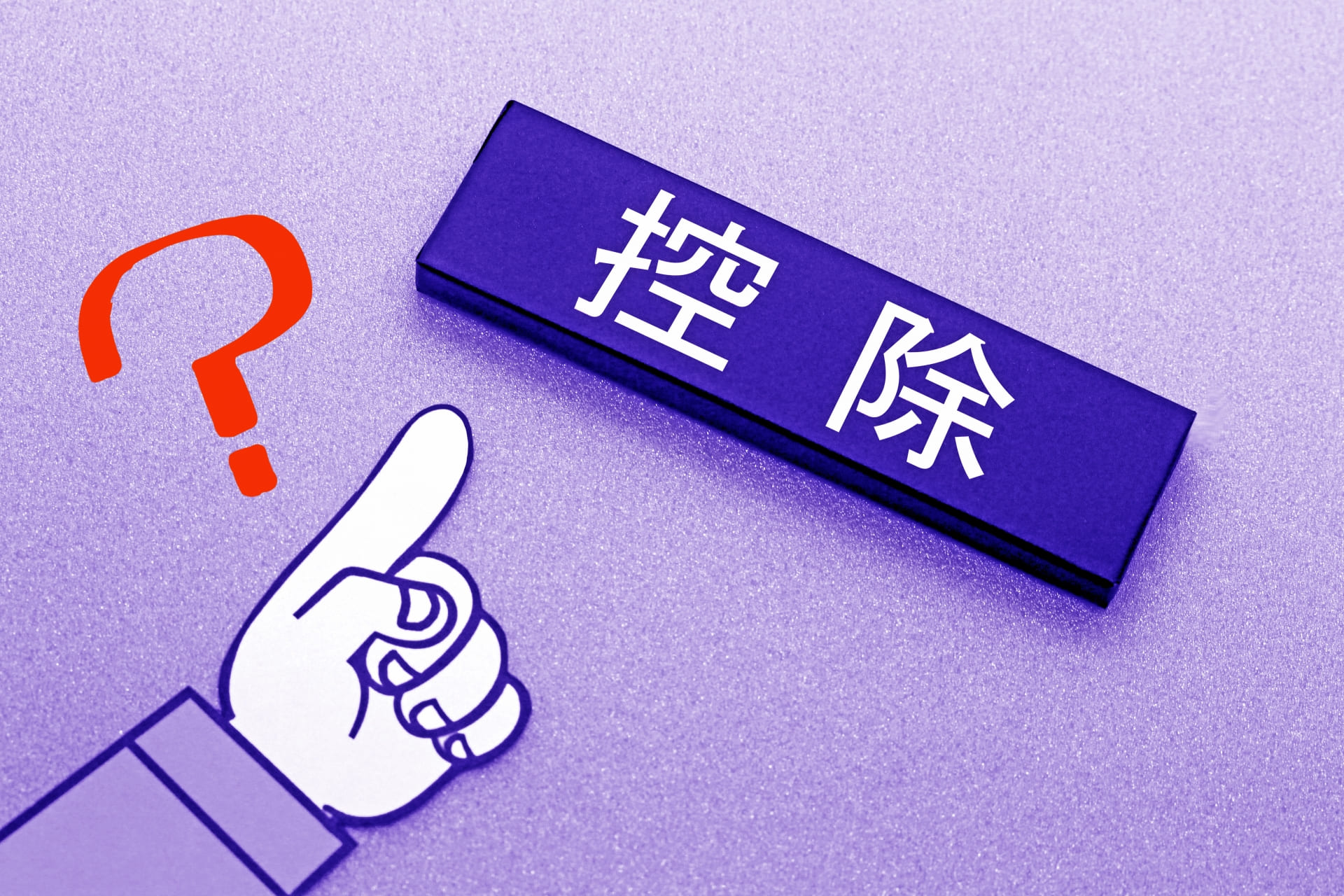
空き家の3,000万円特別控除(空き家特例)とは、相続で取得した空き家を譲渡し、所得が発生した際に譲渡所得(売却益)から最大3,000万円を控除できる制度です。
空き家を売却する際に譲渡所得が発生すると、所得税や住民税が課税されますが、特別控除で税金の負担額を減らすことで、空き家を減らすという目的があります。
譲渡所得の計算式は、以下の通りです。
譲渡所得 = 売却価格 -(取得費 + 譲渡費用)
空き家特例の適用期間は、平成28年4月1日~令和5年12月31日まででしたが、令和5年度税制改正により期間が延長され、令和9年12月31日までとなりました。
現在も空き家問題が解決されていないことから、引き続き問題の解消に取り組む必要があるため、改正が行われたと考えられます。-

空き家の3,000万円特別控除を利用する際には、確認すべき要件が多くあります。不備なく手続きを進めるためには、国税庁が提供するチェックシートを利用することがおすすめです。チェックシートでは、質問に「はい」か「いいえ」で回答し、空き家特例の対象であるかを確認できます。そのため、空き家の売却を検討する際は、まずチェックシートの確認からはじめるとよいでしょう。
-
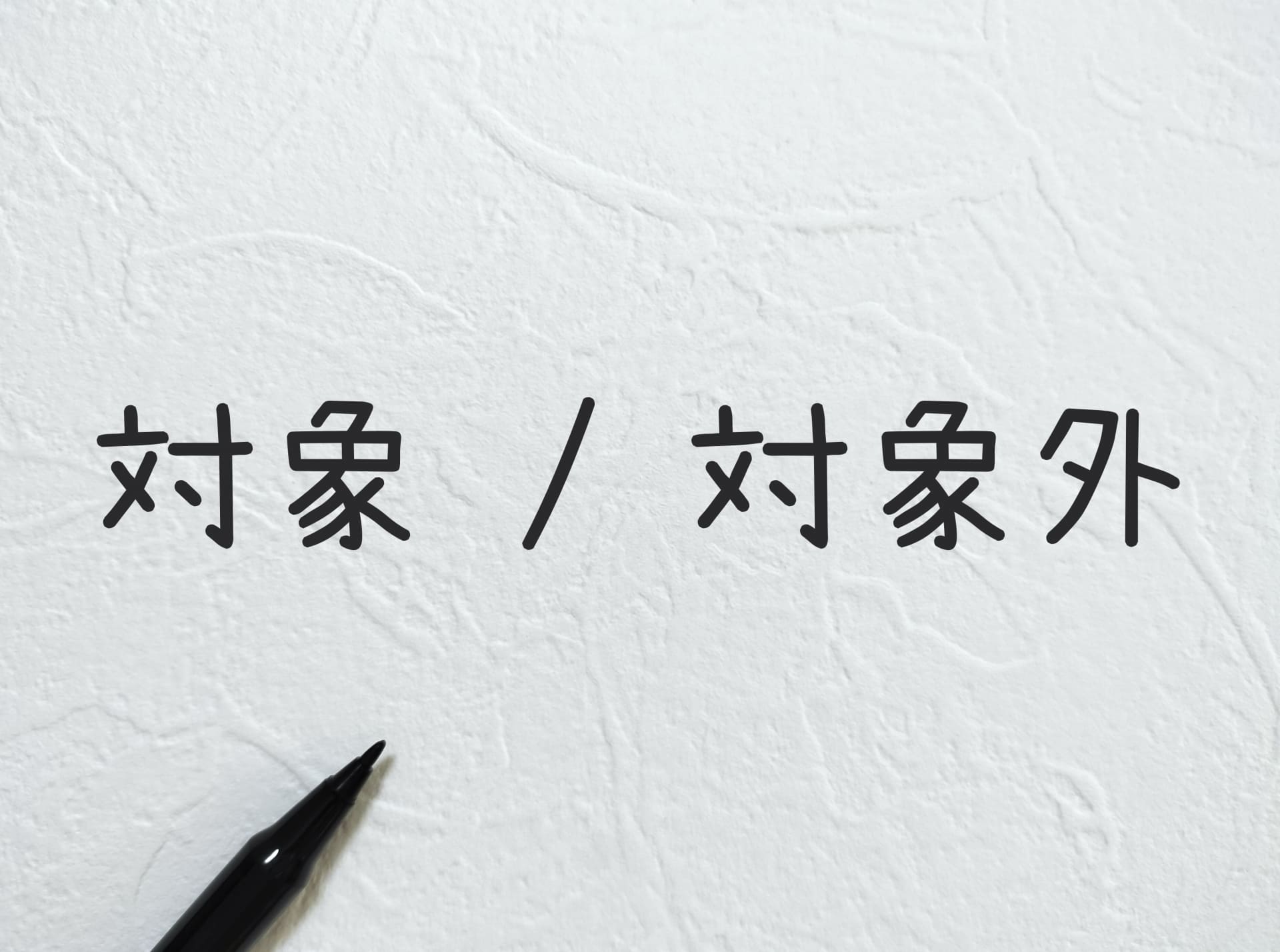
続いて、空き家の3,000万円特別控除の適用条件を見てみましょう。控除を受けるには、適用条件を全て満たす必要があります。
建物・土地を相続または遺贈により取得したか
譲渡する建物や土地は、相続または遺贈により取得している必要があります。相続は、被相続人(亡くなった方)が保有していた財産を、配偶者や子どもなど一定の身分関係にある法定相続人が受け継ぐことです。一方、遺贈とは被相続人の遺言により、法定相続人以外に遺産をゆずることを指します。
建物は区分所有権物に該当しないか
空き家の3,000万円特別控除を受けるには、建物が「区分所有権物」に該当しないことが条件です。区分所有建物とは、一棟の建物が壁により複数の部屋に区切られ、各部屋が別々の所有権の対象となる建物です。主にビルやマンションが該当し、構造上や利用上の独立性があり、住居や事務所などのさまざまな用途で利用可能な複数の部屋で構成されています。
なお、一戸建てであっても区分所有建物に該当する場合や、区分所有建物ではないマンションも存在します。そのため、一戸建てやマンションなど建物の種類で判断せず、空き家の登記簿謄本(全部事項証明書)を確認して、区分所有建物に該当するかを判断しましょう。
空き家が区分所有建物であれば、登記簿謄本に区分所有権を有する旨の情報が記載されています。建物は1981年(昭和56年)5月31日より前に建築されたか
控除を適用するには、空き家が1981年(昭和56年)5月31日より前に建築されていなければなりません。1981年5月以前に建てられた家であれば、どれほど築年数が古くても控除の対象となります。この日付は、建築基準法が改正されたタイミングであり、建物の耐震基準に関する条件が大幅に変更されました。法律が改正される前に建築された建物を対象とすることで、耐震基準を満たしていない空き家の増加を防ぐ意図があると考えられます。
なお、空き家の築年数は、登記簿謄本に記載されています。被相続人(亡くなった方)以外に居住していた方はいないか
控除適用の条件として、被相続人(亡くなった方)が空き家を譲渡する直前まで一人で暮らしていたことが挙げられます。したがって、他に居住していた人がいる場合は、控除の対象となりません。被相続人が一人で暮らしていたことを証明するには、建物が所在する市区町村で「被相続人住居用家屋等確認書」を交付してもらう必要があります。
また、2019年(平成31年度)の税制改正により、空き家を譲渡する直前に老人ホームを利用していた場合も、控除の適用が認められるようになりました。空き家の3,000万円特別控除を受けるのは初めてか
空き家の3,000万円特別控除は、被相続人一人につき、適用を受けられるのは1回までです。例えば、父親と母親から空き家を1軒ずつ相続する場合は、それぞれの空き家に対して控除を受けることが可能です。しかし、母親から空き家を2軒相続しても、控除は1回しか適用されません。
売却先(買主)は第三者であるか
控除を適用するには、空き家を売却する相手が第三者でなければなりません。
親子や配偶者といった親族や、親族が経営する会社などの特別関係者に売却する場合は、控除の適用外となります。売却金額は1億円以下か
空き家の3,000万円特別控除を受けるには、譲渡された空き家を1億円以下で売却しなければなりません。1億円を超えてしまうと控除の適用とならないため、注意しましょう。
また、複数の相続人で共有する空き家を売却する際は、全ての売却価格を合わせて計算されます。相続時から譲渡時まで空き家の状態であったか
相続時から譲渡時までの期間、空き家の状態である必要があります。
例えば、譲渡するまで空き家を貸して誰かが住んでいたり、事業に利用していたりした場合は、控除の対象となりません。第三者に貸した期間が少しでもあると控除を利用できないため、注意が必要です。空き家をどのような状態で譲渡するか
空き家のまま譲渡する場合も、空き家を解体して土地を譲渡する場合も、空き家の3,000万円特別控除が適用されます。ただし、それぞれ要件が異なるため、以下で詳しく説明します。
空き家のまま譲渡する
空き家のまま譲渡する場合は、売却時に空き家の耐震性を証明することが必要です。
耐震性が証明できなければ、改築やリフォームなどで耐震性を高めてから、耐震基準適合証明書を取得する必要があります。
なお、耐震基準適合証明書を取得する際、耐震診断に約10万円、証明書の取得に約3〜5万円が必要です。また、耐震診断の依頼から調査の実施まで約1週間、診断結果の提出まで約1か月かかる場合があります。加えて、診断結果によりリフォームが必要となると、工事する期間も考慮しなければなりません。
証明書の取得費用や取得に要する期間など、余裕を持って準備するのが望ましいでしょう。
空き家を解体し土地を譲渡する
空き家を解体し土地を譲渡する場合は、売却を完了するまで更地の状態であることが条件となります。空き家の相続時から解体、売却までの期間に、敷地内に家を建築すると、控除の適用とならないため注意が必要です。建物と土地を合わせて相続したか
空き家の3,000万円特別控除を利用する際は、建物と土地を合わせて相続する必要があります。例えば、空き家と土地を別々の人が相続していると、控除の適用となりません。
控除を受けるためには、空き家と土地をセットで相続しましょう。相続開始から3年後の12月31日までに譲渡するか
控除を受けるには、適用期間内に、相続開始から3年後の12月31日までに譲渡する必要があるとされています。期間内に空き家を譲渡できるように、速やかに手続きを進めましょう。
-

ここでは、空き家3,000万円特別控除の手続き方法を紹介します。
申請に必要な書類を把握し、スムーズに手続きを行いましょう。手続きの流れ
空き家3,000万円特別控除の手続きは、確定申告と合わせて行います。
手続きの流れは以下の通りです。
1.水道の給水装置廃止証明書や、ガス・電気の開栓証明書を準備する
2.空き家が所在する市区町村の自治体に「被相続人住居用家屋等確認書」を交付申請する
3.被相続人住居用家屋等確認書を受け取る
4.手続きに必要な書類を添付し、確定申告する手続きに必要な書類
空き家3,000万円特別控除の手続きに必要な書類は、以下の通りです。
・被相続人住居用家屋等確認書
・空き家の登記簿謄本(全部事項証明書)
・譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算証明書)
・不動産売買契約書の写し
・建設住宅性能評価書または耐震基準適合証明書の写し
また、被相続人住居用家屋等確認書の発行には、以下の書類が必要です。
・被相続人の住民票除票の写し
・相続人全員分の住民票の写し
・閉鎖事項証明書の写し
・不動産売買契約書の写し
・空き家の解体時から売却時まで、土地の使用状況が把握できる写真
・相続時から売却時まで、空き家の状態を確認できる書類-

空き家3,000万円特別控除を適用するために、気を付けるポイントがいくつかあります。
ここでは、空き家3,000万円特別控除を受ける際の注意点を見ていきましょう。倉庫や店舗は控除適用対象外
控除の対象となる空き家は、相続を開始する直前に、被相続人の居住用として使用されている必要があります。したがって、倉庫や店舗の用途に使用していた場合は、控除の適用となりません。
建物を事前取得している場合は適用対象外
空き家3,000万円特別控除の対象は、相続または遺贈により取得された空き家です。
ただし、相続を開始する直前に、空き家の所有者が居住者以外である場合は、控除の対象とはなりません。そのため、被相続人の生前に贈与で所有者を変更した空き家は、控除を受けられなくなる可能性があるため、留意が必要です。税額にかかわらず確定申告が必要
控除の適用を受けるには、必要書類を添付して確定申告をする必要があります。
そのため、控除により所得が減り、税額が0円になる場合でも、確定申告を行わなければなりません。確定申告をしなければ控除の適用とならないため、注意しましょう。-

ここでは、空き家3,000万円特別控除と併用できる制度を紹介します。
併用可能な制度を利用することで、節税につながる可能性があります。居住用財産の3,000万円控除
居住用財産の3,000万円控除とは、自分が住んでいたマイホーム(居住用財産)を売却する際に利用できる制度です。この特例の正式名称は「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」です。例えば、家を4,000万円で売却し、譲渡益が3,000万円であるとすると、特例により3,000万円が控除されます。これにより、不動産売却時に発生する税負担を大きく軽減できるのです。
なお、この控除を受けるには、「譲渡先が親族や特別関係者ではないこと」「重複適用できない特例を利用していないこと」など、いくつかの適用要件を満たす必要があります。
さらに、以下の要件に当てはまる場合は、控除の適用除外となります。
・居住用財産の3,000万円控除を目的として入居した家屋
・新築や改築の期間中のみ仮住まいとして居住した家屋、一時的な目的で居住した家屋
・別荘のように趣味や娯楽のために保有する家屋小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例とは、被相続人が所有していた宅地(土地)の評価額を最大80%減額し、土地の相続税の負担を軽減できる制度です。
土地や建物など、通常の評価額を相続税の計算に当てはめると、高額な税金が発生することがあります。その結果、相続税が支払えなくなったり、支払いのために自宅を売却せざるを得なかったりする恐れがあるでしょう。
そのため、要件を満たす土地の評価額を下げることで相続税の負担を軽減し、残された家族が安心して住み続けられるように特例が創設されました。
ただし、宅地の利用区分によって、特例を適用できる面積や減額割合が異なります。
特例の対象となる宅地は、以下の4種類です。
・特定居住用宅地等(被相続人が住んでいた宅地)
・貸付事業用宅地等(被相続人が貸付用としていた宅地)
・特定事業用宅地等(被相続人が個人事業に利用していた宅地)
・特定同族会社事業用宅地等(被相続人が会社として利用していた宅地)
また、宅地の利用区分に対する限度面積と減額割合を、以下の表に示します。宅地の利用区分 要件 限度面積 減額割合 居住用 特定居住用宅地等 330㎡ 80% 事業用(貸付事業用) 貸付事業用宅地等 200㎡ 50% 事業用(特定事業用宅地等) 特定事業用宅地等 400㎡ 80% 事業用(特定事業用宅地等) 特定同族会社事業用宅地等 400㎡ 80% -

空き家の3,000万円特別控除とは、相続や遺贈で取得した空き家を売却する際に、譲渡所得を最大3,000万円控除できる制度です。特別控除を受けるには「空き家の売却先が第三者である」「空き家と土地を合わせて相続する」などのさまざまな適用要件が存在し、それらを全て満たす必要があります。その適用要件を確認する際は、国税庁が公開しているチェックシートを利用することでスムーズに確認を進められます。しかし、適用要件や手続き方法が複雑であるため、自身で進めるのが難しい場合はお近くの不動産会社や税理士に相談するとよいでしょう。
なお、弊社でも相談に乗っておりますので、空き家の売却を検討されている方はお気軽にお問合せください。-
空き家の3,000万円特別控除(空き家特例)について教えてください。
空き家の3,000万円特別控除(空き家特例)とは、相続で取得した空き家を譲渡し、所得が発生した際に譲渡所得(売却益)から最大3,000万円を控除できる制度です。
空き家を売却する際に譲渡所得が発生すると、所得税や住民税が課税されますが、特別控除で税金の負担額を減らすことで、空き家を減らすという目的があります。 -
空き家3,000万円特別控除と併用できる制度はありますか。
居住用財産の3,000万円控除や小規模宅地等の特例などが、空き家3,000万円特別控除と併用できる制度として挙げられます。
詳細はこちらを参考にしてください。
関連記事
-
 【不動産管理業務とは】内容や業務フローをプロがわかりやすく解説!詳しく見る
【不動産管理業務とは】内容や業務フローをプロがわかりやすく解説!詳しく見る不動産投資は、物件を購入するだけで利益が出るというものではありません。適切な不動産業務を行うことによって初めて利益が発生し、収入につながります。 しかし、所有している土地でアパート経営を始めるには、いくつかのリスクがあることも覚えておきましょう。それぞれのリスク回避のために適切な対策を行って、効率的な土地活用を行いましょう。 この記事では、土地有りでアパート経営を行うメリット・デメリットについて、そして経営を進める時の流れや必要な資金などについて解説します。
-

-
 不動産管理会社設立のメリットは?設立する方法や注意点なども解説!詳しく見る
不動産管理会社設立のメリットは?設立する方法や注意点なども解説!詳しく見るアパートやマンションの運営をしている方のなかには、「税金対策」に頭を悩ませている方もいるのではないでしょうか。不動産から発生する税金を節税する方法として、不動産管理会社を設立するという方法があります。なぜ、不動産管理会社を設立すると節税になるのでしょうか。 そこで、この記事では、管理会社を設立する方法やメリットデメリット、節税を行う上での注意点などを詳しく解説します。 しかし、所有している土地でアパート経営を始めるには、いくつかのリスクがあることも覚えておきましょう。それぞれのリスク回避のために適切な対策を行って、効率的な土地活用を行いましょう。 この記事では、土地有りでアパート経営を行うメリット・デメリットについて、そして経営を進める時の流れや必要な資金などについて解説します。
タウングループ不動産仲介・周辺事業- 賃貸不動産仲介(東京・神奈川・埼玉・千葉) タウンハウジング
- 賃貸不動産仲介(東海) タウンハウジング東海
- 賃貸不動産仲介(九州) タウンハウジング福岡
- 土地・建物の不動産販売及び仲介 タウン住宅販売
- 首都圏を中心に引越サービスを展開 タウン引越サービス
- 賃貸不動産仲介(東北) タウンハウジング東北
- 賃貸不動産仲介(北関東) タウンハウジング北関東
建築事業- 賃貸住宅の企画・設計・施工 アヴェントハウス
多角化事業- 都内を中心に飲食店を運営 タウンダイニング
- インドアテニススクール タウンインドアテニスアカデミー


 一覧へ戻る
一覧へ戻る