居住用財産の3000万円控除は3年以内?住宅ローン控除の併用は?
相続した実家を売却してマンション購入の資金に充てたい、使用する予定のない土地を売却して余計な固定資産税を抑えたいなど、不動産を売却する理由は人それぞれです。不動産によっては、高額での売却が可能なケースもあるでしょう。
しかし、不動産の売却時は譲渡所得税などが発生するため、安定した売却益を得るには節税対策も考えなければなりません。居住用財産の場合「3000万円控除」といった優遇制度が設けられているため、売却が有利になる可能性があります。
この記事では、居住用財産の概要やその優遇制度、住宅ローン控除などを解説します。
-

居住用財産の考え方は、不動産の売却において優遇措置が受けられるため重要です。居住用財産として認められる基準は、厳密に定義されています。そのため、売却を検討している不動産が居住用財産に該当するかどうか、しっかりと把握しておきましょう。
ここでは、まず居住用財産の内容や特徴、基準の要件を解説します。居住用財産の概要
居住用財産とは、一般的にマイホームを指し、生活のために継続して住んでいる家屋とその敷地を意味します。仮住まいのために短期間一時的に居住した住宅や、趣味・保養を目的とした別荘などは、居住用財産には該当しないため優遇措置は受けられません。
住居として実際に使用されている実績があれば、不動産が居住用財産であることを証明できます。なお、証明するための手続きは特に必要ありません。前述の通り、仮住まい用の住宅や別荘は居住用財産には該当しません。しかし、家族の生活実態や住宅の設備などを考慮した結果、住民票が別の住所で登録されていても居住用財産として認められるケースもあります。居住用財産とされる基準
不動産が居住用財産として認められるかどうかは、以下の基準によって判断されます。
1.個人が主として居住用に使用している家屋とその敷地であり、かつ国内にあるもの。また、特例ごとに定められている所有期間を満たしていること。
2.居住用の家屋とその敷地として使用しなくなった日から、3年後の12月31日までに売却するもの。
3.上記1の家屋を取り壊した場合、取り壊した年の1月1日から現在まで、特例ごとに定められている所有期間を満たしていること。加えて、取り壊しから1年以内に売買契約を行い、居住用として使用しなくなった日から、3年後の12月31日までに売却するもの。
4.居住用の家屋が災害によって滅失した場合、滅失した年の1月1日時点で当該家屋の敷地が特例ごとに定められている所有期間を満たしていること。また、災害があった日から3年後の12月31日までに売却するもの。ただし、個人が当該家屋を引き続き所有しているケースに限られる。単身赴任で家を離れる場合
生活のために継続して住んでいない場合は、居住用財産として認められません。しかし、生活スタイルは日々変化します。仕事の都合で不動産を購入した本人が単身赴任のため家を離れるケースもあるでしょう。その場合は、居住用財産として認められるのでしょうか。
不動産を購入した本人が単身赴任等で家に居住していない場合でも、配偶者が継続してその住宅に住んでいれば問題ありません。単身赴任の期間が終了した後、本人が戻ってくることが明確であれば、その不動産は居住用財産として認められます。単身赴任のケースだけでなく、病気療養のため一時的に自宅を離れ、その後にまた戻ってくる場合も居住用財産であると判断されます。親族へ売却する場合
夫婦や親子など、一定の親族へ居住用と認められる不動産を売却した場合、生計を共にしている(共通の資金で生活を営んでいる)ため、居住用の特例は受けられません。親族以外にも、内縁関係にある人や親族が役員をしている法人も、居住用の特例は対象外となります。
-

不動産を売却すると、通常であれば売却益に対して多額の税金がかかります。しかし、居住用財産には「3000万円控除」の優遇制度が設けられています。そのため、居住用財産を売却する際はこの税負担を大きく抑えることが可能です。
なお「3000万円控除」の優遇措置が受けられるのは、居住用財産を売却した時と、相続した空き家を売却した時です。この記事では、主に居住用財産を売却した場合について詳しく解説します。マイホームを売却する際にかかる税金
マイホームを売却すると、譲渡所得税や仲介手数料の消費税がかかります。それぞれの税金について詳しくみていきましょう。
譲渡所得税
家屋や土地などの不動産を売却し、利益が発生した時にかかる税金です。
例えば、3000万円で購入した不動産が3500万円で売却できた場合、差額の500万円に譲渡所得税が発生します。しかし、実際は差額から売却にかかった費用を差し引いた金額が課税対象です。税率は一般的に不動産の所有期間によって異なるとされています。5年を境にして「短期譲渡所得」と「長期譲渡所得」に分類されていますが、長期譲渡の方が税率は低くなります。なお、譲渡所得税は「3000万円控除」を受けることで、実際の税額が変わってくるため注意しましょう。
仲介手数料の消費税
不動産会社を通してマイホームを売却する場合は仲介手数料を支払いますが、この仲介手数料には消費税がかかります。仲介手数料の上限額は「売却価格 × 3% + 6万円」となっており、その金額に10%の消費税がかかる仕組みです。
その他、売却時の手続きにも登録免許料や印紙税などの費用が発生するため、税金と合わせるとさらに負担も大きくなるでしょう。居住用財産であれば「3000万円控除」を受けて、少しでも負担を抑えることが望ましいでしょう。居住用財産の「3000万円控除」の概要
居住用財産を売却した時、所有期間の長さに関係なく譲渡所得を最高3000万円まで控除できる制度が「3000万円控除」です。譲渡所得には所得税と住民税がかかりますが、控除が適用された場合、売却益のうち3000万円までの所得税と住民税が非課税となる可能性があります。
居住用財産の「3000万円控除」は、「居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の特例」とも言い、譲渡所得の特例制度の中では比較的適用しやすいのが特徴です。ただし、控除を受けるには適用要件を満たさなければなりません。「3000万円控除」の計算例
大きな節税効果を期待できる居住用財産の「3000万円控除」ですが、計算する際は譲渡所得の数字を出します。譲渡所得の計算式は以下の通りです。
譲渡所得 = 売却金額 -(取得費 + 諸経費)- 特別控除額(3000万円)
取得費とは、売却する不動産の購入金額で、諸経費は収入印紙代や仲介手数料といった売却時の費用です。住宅の取得費に関しては、経過年数に応じて減価償却費を差し引くため、購入金額がそのまま取得費になるわけではありません。
以下では、控除が適用される場合と適用されない場合に分けて、計算例を解説します。一例として挙げる売却内容は次の通りです。
売却金額:4500万円
取得費:3500万円
諸経費:400万円
所有期間の年数:4年
譲渡所得 = 4500万円 -(3500万円 + 400万円)- 3000万円 = 0円
上記の場合、控除額が算出した譲渡所得を上回っているため、課税額は0円になります。
控除を受けないケースでは、所有期間が5年以下の短期譲渡所得の税率が適用され、課税額は下記の計算式によって求められます。
課税額 = 4500万円 -(3500万円 + 400万円) × 39.63% = 約238万円-

「3000万円控除」を受けるには、定められている適用要件を全て満たす必要があります。
1つでも要件を満たさないと、控除を受けられないため注意が必要です。
ここでは、5つの適用要件とその内容を解説します。売却する不動産が居住用財産であること
「3000万円控除」は、居住用財産を売却した際に適用できる優遇制度です。現在住んでいる家屋・敷地であることが居住用財産の条件のため、仮住まいや別荘、賃貸物件に対しては適用されません。また、節税対策を目的に入居した家屋でないことも条件に入ります。
退去した日から3年後の12月31日までに売却していること
家屋に住まなくなった日から、3年後の12月31日までに売却していることが条件です。
家屋を取り壊した場合は、取り壊した日から1年以内に売却契約を結んだ上で、3年後の12月31日までに売却を完了させる必要があります。取り壊した日から売却契約を締結する日までに、家屋を賃貸として使ったり、敷地を駐車場にしたりといった使い方をしてはいけないのも条件の1つです。売却先が親族や特別な関係のある人でないこと
居住用財産の売却先が第三者であれば問題ありませんが、親族や特別な関係にある人に売却する場合、「3000万円控除」は適用されません。
親族・特別な関係にある人の具体例は以下の通りです。
両親・子・孫などの親族
配偶者
生計を一にする親族
家屋の売却後も同じ家屋で同居する親族
内縁関係にある人
同族法人など特別な関係にある法人所有期間や居住期間の要件はなし
「3000万円控除」は、売却する居住用財産の所有期間や居住期間に関係なく受けることが可能です。住んでいた期間が短くても、自宅として生活のために継続して住んでいたのであれば、控除を受けられます。
ただし、居住用財産の「3000万円控除」は3年に1回しか利用できません。また、売却した年の前年と前々年に「3000万円控除」や「譲渡損失の損益通算及び繰越控除」を受けていないことも条件になります。「譲渡損失の損益通算及び繰越控除」は、マイホームを買い替える際に、売却した住宅の譲渡損失について、損益通算及び繰越控除が受けられる特例です。他の居住用財産の特例と併用するのは原則認められていない
売却した年の前年と前々年に、居住用財産の「買換えの特例」や、前述した「譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」を適用している場合は、原則「3000万円控除」は適用できません。つまり、居住用財産の優遇措置には、併用して適用できない特例もあるということです。
居住用財産を売却した際に、どの特例措置を受けられるか判断できるチェックリストが国税庁からWeb上に公表されているため、迷った時は参考にしてみるのも良いでしょう。-

居住用財産の「3000万円控除」は、生活のために住んでいた住宅を売却した際に受けられる優遇措置です。住んでいたままの住宅ではなく、家屋を解体して土地を売却する場合でも、要件を満たせば控除を適用できることがあります。
適用要件
1.家屋を取り壊した後、1年以内に譲渡(売却)契約を結ぶこと
2.居住用として使用しなくなった日から、3年後の12月31日までに土地を売却すること
3.土地の売却契約が完了するまでの間に、その敷地を貸していないこと
土地を売却する時、家屋を取り壊さずに敷地の一部を売却した場合や、居住用部分の敷地より庭・駐車場が広い場合は、控除が受けられないおそれがあります。-
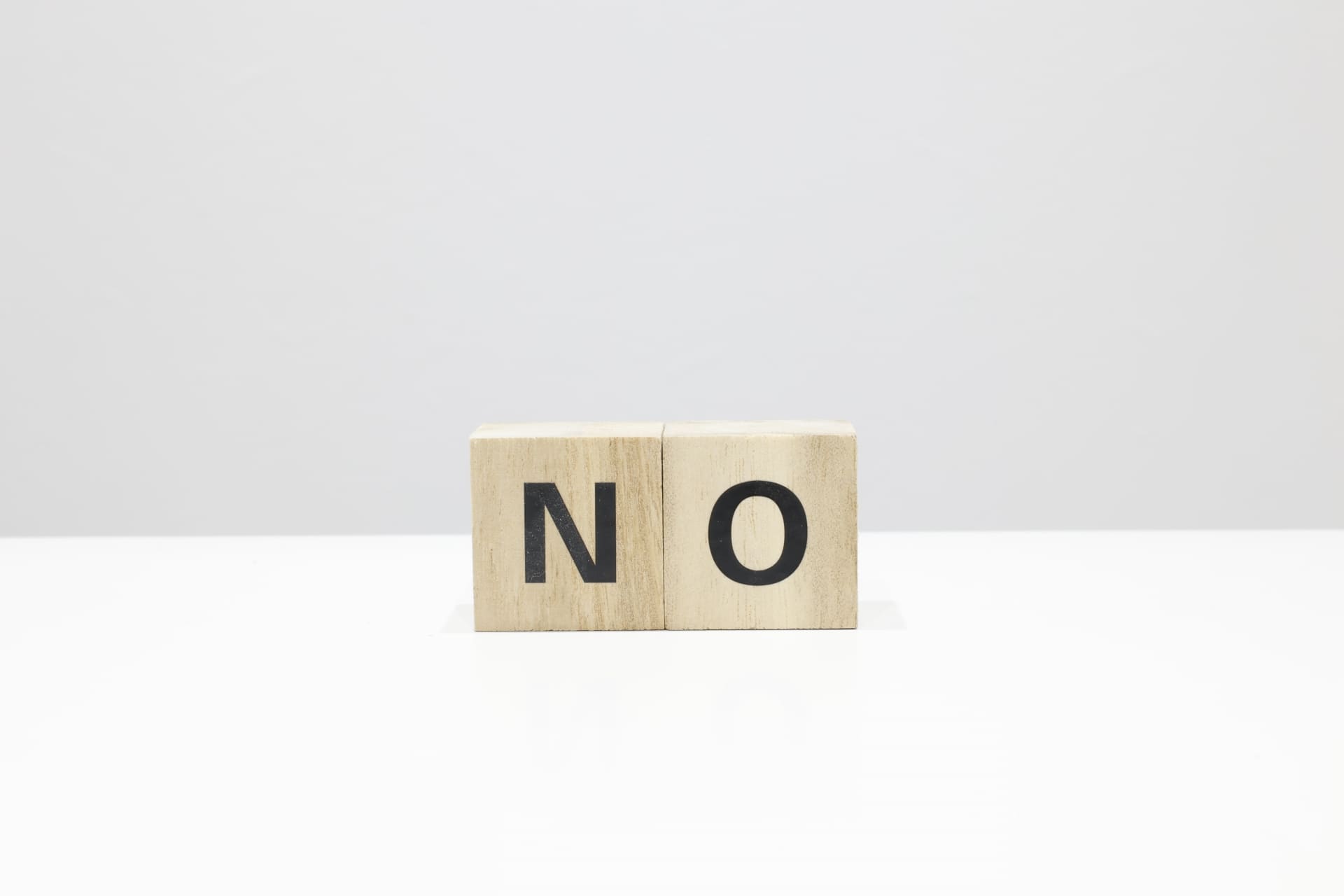
新しく住宅を購入した時、要件を満たしていれば住宅ローン控除の優遇措置を受けられます。しかし、居住用財産の「3000万円控除」と住宅ローン控除は、同じ年の確定申告において原則併用できません。
ここでは「3000万円控除」と住宅ローン控除の併用について確認しましょう。住宅ローン控除とは
住宅ローン控除とは、住宅ローンを借り入れて新しく住宅を購入した際に特定の条件を満たすことで所得税及び住民税から住宅ローン残高の0.7%を控除できる制度です。住宅ローン減税、または住宅借入金等特別控除とも呼ばれます。
なお、住宅の種類や入居時期によって、住宅ローン控除の対象となる借入限度額は異なります。また、2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅を購入する場合は、省エネ基準を満たしていないと住宅ローン控除は受けられません。「3000万円控除」を受けた前後2年間は「住宅ローン控除」を利用できない
基本的には、居住用財産の「3000万円控除」と住宅ローン控除は併用できません。
一度「3000万円控除」を受けると、その前後2年間は住宅ローン控除を受けることができないため、注意が必要です。例えば、自宅の売却後すぐに新しい住宅を購入する場合、売却した自宅に「3000万円控除」を受け、同時に新しい住宅に住宅ローン控除を利用することはできません。
特例措置を一度受けてしまうと、後からキャンセルができないため、マイホームを買い替える時は譲渡所得や新居の購入費用の確認が重要です。「10年超所有軽減税率の特例」とは併用できる
居住用財産を売却する時、所有期間が10年を超えていた場合、譲渡所得税に軽減税率を適用できる優遇措置が10年超所有軽減税率の特例です。所有期間が5年を超える長期譲渡所得の税率は約20%ですが、10年超所有軽減税率の特例を利用すると、約14%まで節税効果を期待できます。 10年超所有軽減税率の特例は、居住用財産の「3000万円控除」と併用できるのが大きなメリットです。しかし、住宅ローン控除とは併用できません。売却時の状況に応じて、損をしない適切な特例を選択することが重要です。
-
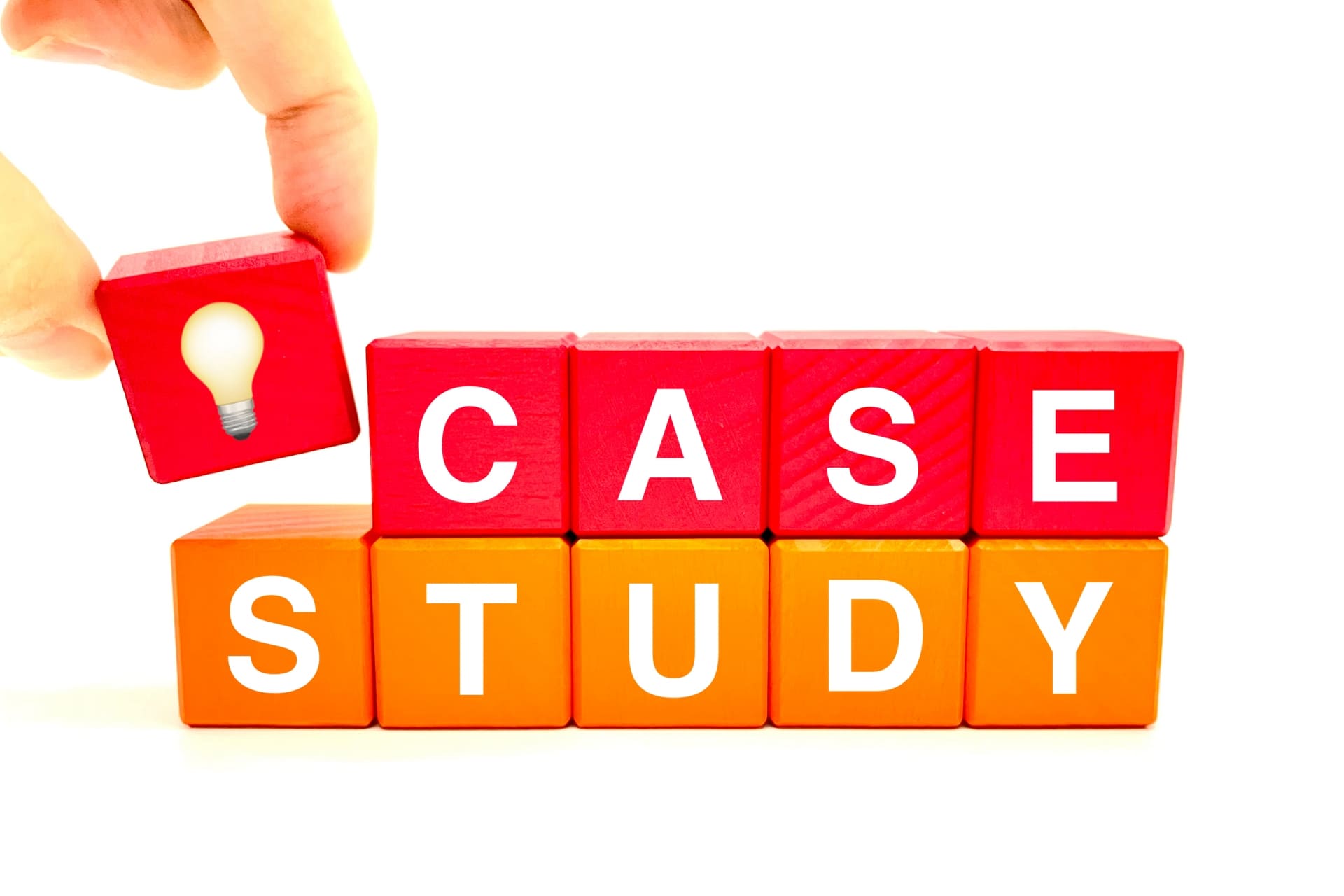
ここでは、特定の状況における居住用財産の「3000万円控除」について、特例措置が適用されるかを確認しましょう。
居住用財産を生前贈与した場合
居住用財産の「3000万円控除」は、譲渡所得から3000万円を控除して所得税と住民税の負担を軽減できる優遇制度です。そのため、不動産を譲渡しても譲渡所得が発生しない生前贈与には、「3000万円控除」は適用されません。生前贈与を行うのであれば、譲渡所得税ではなく贈与税がかかります。
例外として、生前贈与を受けた人がその不動産を第三者へ売却する場合は、その譲渡益に「3000万円控除」が適用される可能性もあります。ただし、生前贈与された不動産が、譲渡時点で贈与を受けた人の居住用として使用されていることが条件です。共有名義の住宅を売却した場合
不動産の名義を複数人で共有しているケースもあるでしょう。共有名義の不動産を売却する場合、居住用財産の「3000万円控除」は名義の共有者全員にまとめて適用されるわけではありません。共有者1人につき、持分に応じて控除が適用されます。
共有者の持分によって計算が異なるため、それぞれ正確に確認しなければなりません。
また、不動産を売却する際の確定申告は各共有者が行う必要があります。
家屋と敷地の所有者が異なる場合、以下の条件を全て満たした時に控除が受けられます。ただし、家屋と敷地の所有者を合わせて3000万円までの控除です。
1.家屋と敷地は同時に売却すること
2.家屋と敷地の所有者同士が親族であり、生計を一にしていること
3.家屋と敷地の所有者がその住宅に住んでいること財産分与で居住用財産を譲渡した場合
離婚によって財産分与が行われ、居住用財産を譲渡した場合「3000万円控除」は受けられません。理由は、財産分与が法律では財産の分配と判断され、売却に該当しないためです。
財産分与後に、元配偶者へ譲渡した不動産が第三者に売却される際は、その譲渡益に控除が適用される可能性もあります。店舗兼住宅の場合
住宅の一部を店舗として扱っているケースでも、居住用財産の「3000万円控除」が適用されます。ただし、控除が受けられるのは居住用に使用していた部分に限定されます。
確定申告の際に床面積などを考慮して計算し、家屋の90%以上が居住用として判断された時に、家屋全体が居住部分と見なされ控除を受けられます。-

控除を受けるには、必要書類を記入・用意して確定申告を行う必要があります。
ここでは、申請方法や確定申告の必要書類を解説します。マイホームを売却した翌年に確定申告を行う
控除を受ける時は、居住用財産を売却した翌年の2月16日〜3月15日の間に税務署にて確定申告を行います。なお、確定申告の期限は土日祝日の関係で変動する可能性があるため、注意が必要です。
「3000万円控除」が適用され、課税額が0円になる場合でも確定申告は必要です。確定申告の手続きは、税理士に依頼することもできます。確定申告に必要な書類
居住用財産の「3000万円控除」を受けるための確定申告には、下記の必要書類に内容を記入して用意する必要があります。
確定申告の際に必要な申告書・書類
確定申告書(B様式)
家屋・敷地用の確定申告書付表兼計算明細書(譲渡所得の内訳書)
不動産取得費の証明書(購入時の契約書など)
譲渡費用の証明書(売却時の各種費用の領収書など)
売買契約書の写し
分離課税用の申告書(第三表)
運転免許証といった本人確認書類
戸籍の附票の写し(居住用財産を売却した人の住民票の住所と、その居住用財産の所在地が異なる場合)書類の書き方
確定申告書(B様式)を用意したら、「収入金額等」に譲渡(売却)した金額、「所得金額等」には譲渡所得の金額を記入します。確定申告書付表兼計算明細書には、それぞれ売却した不動産の取得費や所在地などを記入しましょう。また、分離課税用の申告書(第三表)の特例摘要欄では「3000万円特別控除」を選び、控除の金額を記入します。
e-Taxを利用して申請する場合、特例の種類の選択は、居住用財産に該当するものを選びましょう。特例摘要欄から「3000万円特別控除」を選び、必要事項を入力していきます。-

不動産の状況によっては、居住用財産として認められないため「3000万円控除」が適用されません。申請する前に、控除を受ける際の注意点を確認しておきましょう。
居住用財産と認められない場合は「3000万円控除」が受けられない
居住用として使用されていない不動産は、居住用財産として認められません。
具体的には、仮住まいの住宅や保養・趣味のための別荘、投資用物件などです。
これらの用途で使用していた不動産をマイホームとして偽った場合、追徴課税のペナルティを課されるおそれがあるため注意しましょう。税額が0円の場合でも確定申告は必要になる
居住用財産の「3000万円控除」は自動で適用されるわけではないため、確定申告での申請が必要です。申請により、控除が適用されて課税額が0円になっても、確定申告を行わなければなりません。
異なる不動産の「3000万円控除」は3年以上の経過で2回目以降も受けられる
同じ不動産では、控除を複数回受けることはできません。しかし、異なる不動産を売却する際は、一度「3000万円控除」を受けてから3年以上経過している場合など、適用要件を満たせば2回目以降も控除を受けられます。
相続財産であれば「相続空き家の3000万円控除」が利用できる
「3000万円控除」の特例措置は、居住用財産以外に空き家を対象としたものもあります。この措置は「被相続人の居住用財産(空き家)に関する譲渡所得の特別控除の特例」と呼ばれ、空き家の増加を防ぐために設けられました。相続空き家の特例措置は、控除額の限度を3000万円とした上で、居住用財産の控除との併用も可能です。
-

居住用財産の控除に関して把握した上で、マイホームの売却で損失が出た時の特例措置を確認しておきましょう。ここでは、2つの特例措置を紹介します。
「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除」
マイホームを売却して新居を購入した際に譲渡損失が出た場合、住宅ローン残高があれば所得金額を以降3年間に渡って繰越控除できる制度です。適用可能な期限は、令和7年12月31日までとなります。
制度を利用できる主な条件は以下の通りです。
1.売却する不動産が居住用財産であること
2.売却する不動産の所有期間が5年以上あること
3.売却した年の前年から翌年までに新居を購入し、その翌年末までに住むこと
4.購入した新居の住宅ローンの返済期間が10年以上あること「特定の居住用財産の譲渡損失の繰越控除」
マイホームを売却して新居を購入した時、譲渡資産にかかる住宅ローン残高があって譲渡損失が出た場合に受けられる制度です。住宅ローン残高から譲渡額を控除した金額を限度に、新居の種類を問わず、所得金額を以降3年間に渡って繰越控除できます。なお、適用期限は令和7年12月31日までです。
制度を利用するための主な条件は以下のようになります。
1.売却する不動産が居住用財産であること
2.売却する不動産の所有期間が5年以上あること
3.売却した不動産の住宅ローンの返済期間が10年以上あること-

マイホームである居住用財産を売却する時は、一定の条件を満たすことで「3000万円控除」の優遇措置を受けられます。控除が適用されれば、所得税と住民税が3000万円まで非課税となり、節税対策として効果的です。
住宅ローンを借り入れて新居を購入した場合には、マイホーム売却時の「3000万円控除」と併用して、住宅ローン控除を利用できます。ただし、住宅ローン控除との併用はマイホームを売却してから4年後になる点に注意しましょう。-
居住用財産とはなんですか。
居住用財産とは、一般的にマイホームを指し、生活のために継続して住んでいる家屋とその敷地を意味します。居住用財産の考え方は、不動産の売却において優遇措置が受けられるため重要です。仮住まいのために短期間一時的に居住した住宅や、趣味・保養を目的とした別荘などは、居住用財産には該当しないため優遇措置は受けられません。
-
居住用財産の「3000万円控除」の概要を教えてください。
居住用財産を売却した時、所有期間の長さに関係なく譲渡所得を最高3000万円まで控除できる制度が「3000万円控除」です。譲渡所得には所得税と住民税がかかりますが、控除が適用された場合、売却益のうち3000万円までの所得税と住民税が非課税となる可能性があります。
居住用財産の「3000万円控除」は、「居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の特例」とも言い、譲渡所得の特例制度の中では比較的適用しやすいのが特徴です。ただし、控除を受けるには適用要件を満たさなければなりません。
関連記事
-
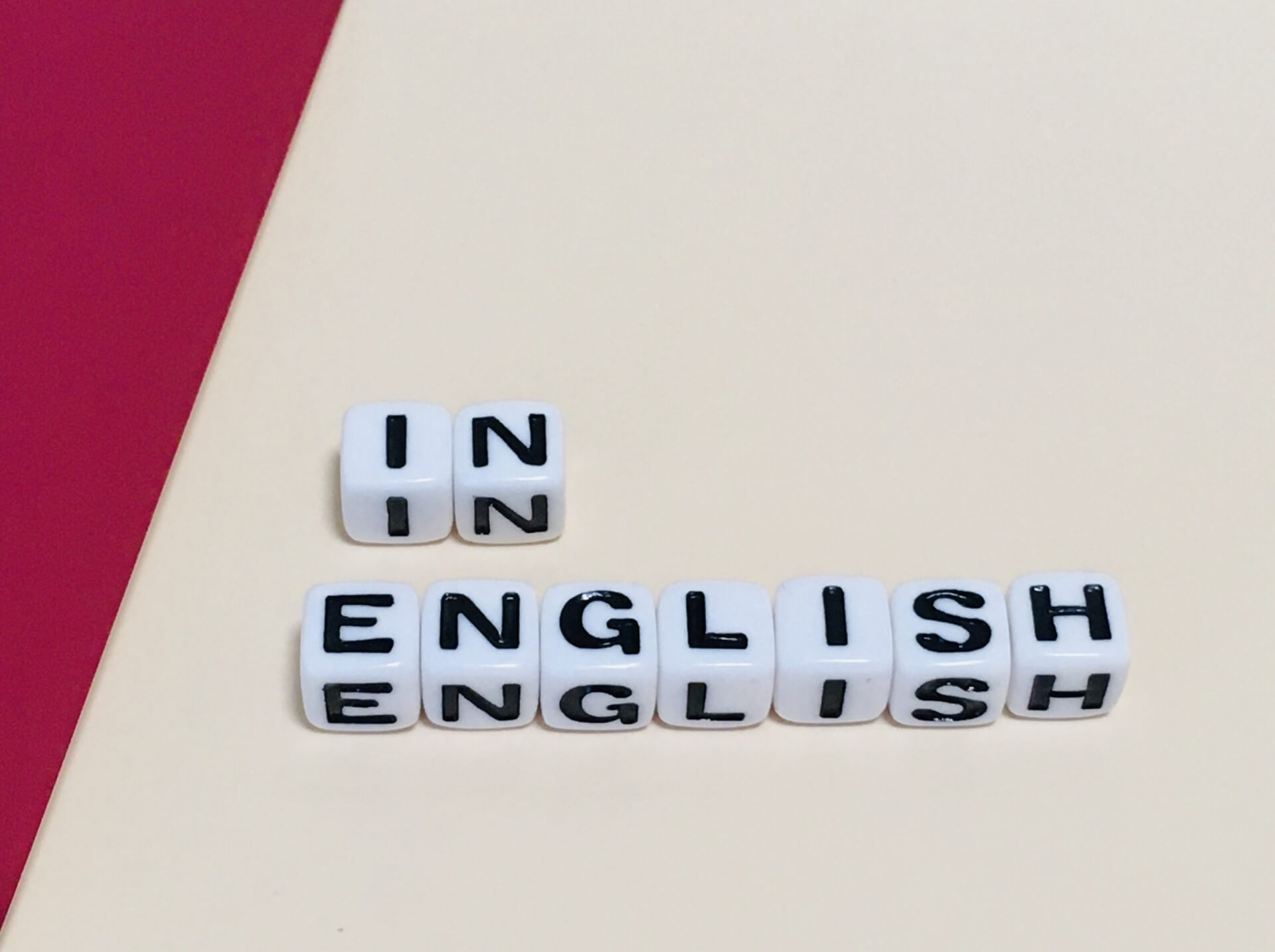 管理会社は英語で何と言う?管理会社の概要や業務についても解説!詳しく見る
管理会社は英語で何と言う?管理会社の概要や業務についても解説!詳しく見る「不動産管理会社」は英語で何というのでしょうか。英語にすると難しく感じる方もいるかもしれませんが、単語で分けて見ると容易です。 この記事では、不動産管理会社の英語での言い方や、それぞれの単語の意味を解説します。また、不動産会社の概要や業務内容について紹介します。 しかし、所有している土地でアパート経営を始めるには、いくつかのリスクがあることも覚えておきましょう。それぞれのリスク回避のために適切な対策を行って、効率的な土地活用を行いましょう。 この記事では、土地有りでアパート経営を行うメリット・デメリットについて、そして経営を進める時の流れや必要な資金などについて解説します。
-
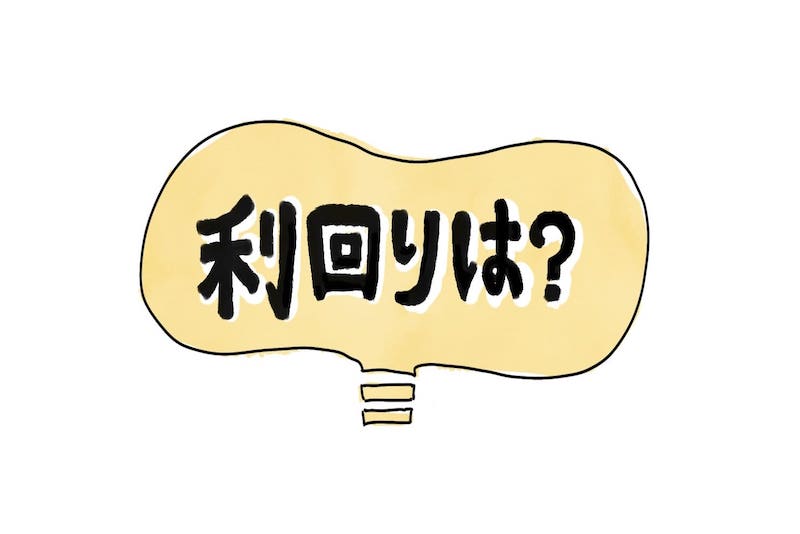 アパート経営の回収期間は?パターン別に目安を調査詳しく見る
アパート経営の回収期間は?パターン別に目安を調査詳しく見る不動産投資の一つとしてアパート経営を検討されている方のなかには、「投資資金の回収期間をあらかじめ知っておきたい」という方もいるのではないでしょうか。不動産投資は、家賃収入を継続的に得るだけではなく、投資資金以上の金額を回収できることも大切になります。不動産商品は高額のため、投資する前に資金回収のシミュレーションを行いましょう。 しかし、所有している土地でアパート経営を始めるには、いくつかのリスクがあることも覚えておきましょう。それぞれのリスク回避のために適切な対策を行って、効率的な土地活用を行いましょう。 この記事では、土地有りでアパート経営を行うメリット・デメリットについて、そして経営を進める時の流れや必要な資金などについて解説します。
-
 アパートローンの相続には対策が必要!選択肢やトラブルの事例を紹介詳しく見る
アパートローンの相続には対策が必要!選択肢やトラブルの事例を紹介詳しく見るアパートローン(アパート経営)の相続が想定される場合、必要な対策や選択肢を理解しておくのは重要です。相続発生時はアパート経営の有無によらず、相続や相続人間で遺産分割が難航するケースは少なくありません。被相続人(故人)の存命中に相続の方針をまとめておくと、相続発生時の負担を減らせます。今回は、アパートなどの収益物件を相続する見通しがある方に向け、アパートローンの相続に必要な対策、選択肢を解説します。
タウングループ不動産仲介・周辺事業- 賃貸不動産仲介(東京・神奈川・埼玉・千葉) タウンハウジング
- 賃貸不動産仲介(東海) タウンハウジング東海
- 賃貸不動産仲介(九州) タウンハウジング福岡
- 土地・建物の不動産販売及び仲介 タウン住宅販売
- 首都圏を中心に引越サービスを展開 タウン引越サービス
- 賃貸不動産仲介(東北) タウンハウジング東北
- 賃貸不動産仲介(北関東) タウンハウジング北関東
建築事業- 賃貸住宅の企画・設計・施工 アヴェントハウス
多角化事業- 都内を中心に飲食店を運営 タウンダイニング
- インドアテニススクール タウンインドアテニスアカデミー


 一覧へ戻る
一覧へ戻る