40歳で貯金が1000万円は少ない?不動産投資などの資産形成で貯金を増やそう
40歳を迎えるころから、老後を意識しはじめる方も多いのではないでしょうか。どれぐらいの貯金があれば安心できるのか、また貯蓄を増やすためにはどうすればよいのか不安に思う人も多いかもしれません。
本記事では、40代の平均貯金額や資産形成の方法、効果的な貯金方法などを解説します。
-
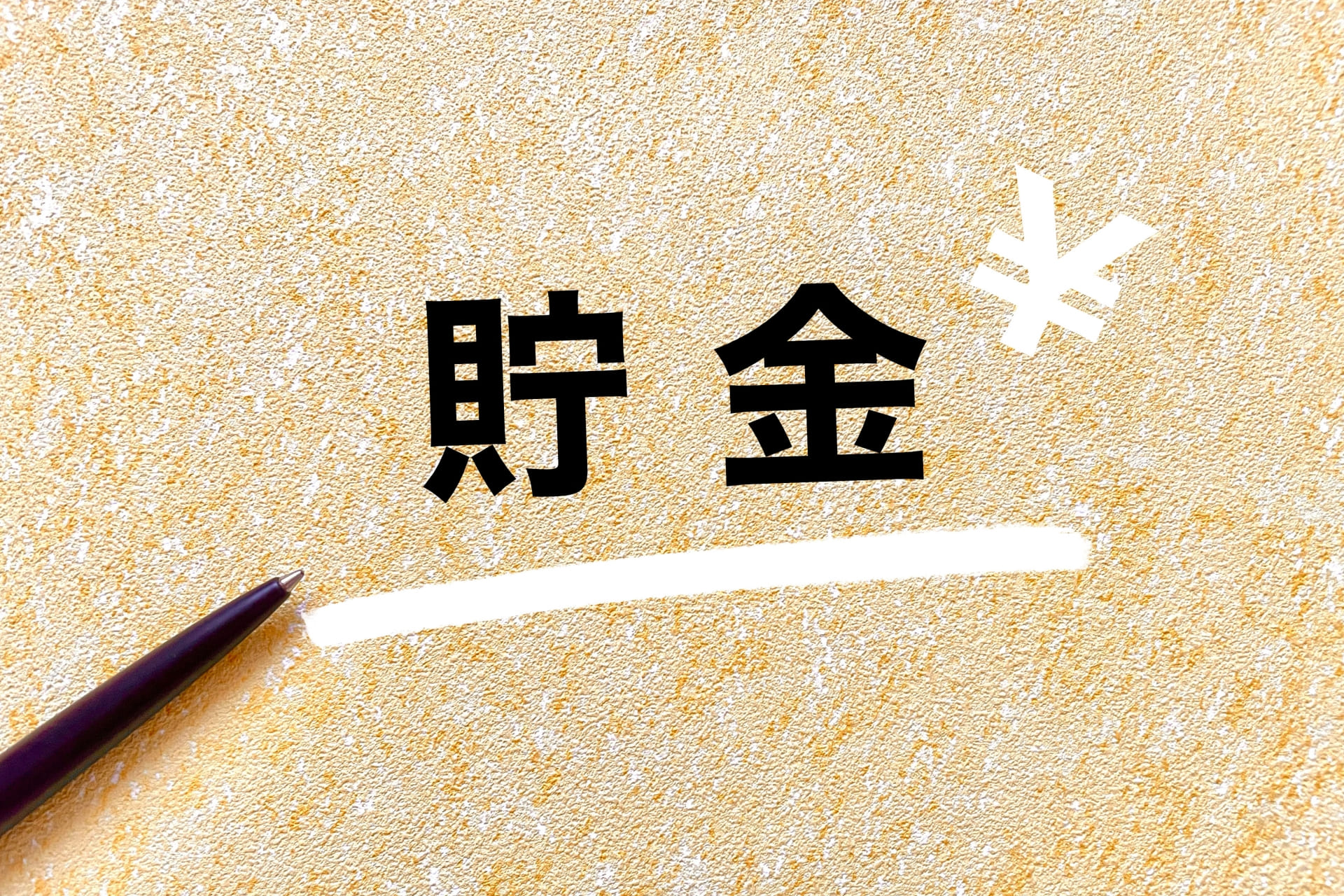
ここでは、中央値と平均値の意味と40代の平均貯金額を解説します。2人以上世帯は単身世帯よりも貯金額の平均値や中央値が高い傾向です。
「中央値」と「平均値」
平均値とは、全てのデータの数値を合計し、それをデータの個数で割った値を指します。一方、中央値はデータの数値を大きさ順に並べた際に、中央に位置する値です。
平均値はデータが正規分布している場合に適していますが、外れ値(極端に高い・低い数値)に影響されるため、実態から大きく外れる場合もあります。中央値は外れ値に左右されにくいため、自分の貯金額と比較する際は中央値を基準にしましょう。40代の平均貯金額
40代全体の平均貯金額は929万円、中央値は200万円です。単身世帯・夫婦世帯などを合わせた数値であるため、中央値の方が実態に近いでしょう。
40代の単身世帯に絞った場合、平均貯金額は883万円、中央値は85万円です。近年は共働き世帯が増えていることから、単身世帯はそのほかの世帯に比べて貯金額が低くなっています。単身であるために余暇時間が多く、出費が増えてしまうことも理由の一つでしょう。
40代の2人以上世帯に絞った場合、平均貯金額は944万円、中央値は250万円です。収入が2人以上になる世帯もあるため、そのほかの世帯に比べて貯金額が高くなっています。子供がいる世帯の場合は、家計を管理して支出を抑えているケースも少なくありません。
出典:家計の金融行動に関する世論調査 2024年-

実際のデータと比較すると、40歳で貯金1000万円は少ないとはいえませんが、多いともいえません。理想の貯金額は人によって異なるため、シミュレーションを行って自身がどの程度の貯蓄を必要とするのか把握しておくことが重要です。
老後に必要な資金を計算しておく
老後2,000万円問題が提起されたことから、老後資金に不安を覚える人も少なくありません。現代では、平均寿命が伸びており、人生100年時代と呼ばれています。仮に65歳で定年退職する場合、老後期間は約20年です。
退職金や年金だけでは生活費が足りなくなる場合は、貯金を取り崩す必要があるため、現役世代のうちに老後資金は、できるだけ現役世代のうちから準備しておくと安心です。ゆとりのある老後生活を送るためには、趣味やレジャーなどに費やすお金のほかに、病気やケガに備えるためのお金なども確保する必要があるでしょう。一般的に、老後資金として退職金と合わせて約2,000万円が必要とされるという説もあります。ただし、個人の生活スタイルや支出内容によって必要になる老後資金は異なるため、一度自分で試算することをおすすめします。老後資金の試算は、現在の生活水準の維持を基準とするのが一般的です。趣味などの自己投資や緊急時に対応できる貯蓄も必要
生活費だけでなく、自己投資や緊急時に対応できる貯蓄も必要です。趣味やスキルアップにお金を使うことで、自身の成長につながり、精神的な豊かさを得られます。自己投資を通して得た知識が仕事でも役に立てば、収入が安定して貯蓄が増える好循環が生まれるでしょう。
また、病気・ケガによって入院・手術となった場合、公的制度の適用を受けても自己負担は数万円に及ぶケースもあります。そのような事態に陥っても、貯蓄があれば家計の安定が保たれます。休業・退職によって一時的に収入が減少した場合も同様です。ライフイベントに応じて目標金額を設定する
ライフイベントに備えるのも貯蓄の目的の一つです。住宅ローンや子どもの教育費などのライフイベントでかかる費用を分析することで、より現実的な貯蓄目標額の設定につながる可能性があります。ライフイベントごとにかかる費用は後述します。
-

ここでは、ライフイベントごとに貯金しておきたい金額を解説します。特に、結婚や住宅の購入には数百万円必要になるほか、子どもの教育費は合計で1,000万円を超える場合もあります。
結婚
結納・婚約から新婚旅行までにかかる費用の総額は、平均492万1,000円です。結婚に関する主な費用の平均(首都圏)は以下の通りです。
また、二次会を開催する場合は会場費や飲食費などの費用も生じます。新生活に向けて、家具・家電の購入や賃貸物件に住むための敷金礼金なども必要になることもあるでしょう。項目 平均額 結納式 84万8,000円 両家の顔合わせ 10万2,000円 婚約指輪 43万2,000円 結婚指輪(二人分) 31万6,000円 挙式、披露宴・ウエディングパーティー 374万8,000円 新婚旅行 64万6,000円 新婚旅行土産 6万9,000円
一方、結婚の際は参列者からのご祝儀や親・親族からの援助金を受け取れる場合もあります。ご祝儀の総額は平均212万9,000円、親・親族からの援助総額は平均191万5,000円です。あくまでこの金額は目安ですが、約100万~200万円の資金の確保が必要になります。
出典:ゼクシィ結婚トレンド調査 2024出産
室料差額等を除いた全施設の出産費用(正常分娩)は平均48万2,000円です。施設ごとの出産費用(正常分娩)の平均額は以下の通りです。
平均額だけで見れば、出産育児一時金の50万円で費用のほとんどをまかなえる可能性があります。しかし、出産費用が上昇傾向にあるともいわれており、資金をあらかじめ用意しておくと安心です。施設 出産費用(室料差額等を除く) 全施設 48万2,000円 公的病院 46万3,000円 私的病院 50万6,000円 診療所(助産所含む) 47万9,000円
出典:出産費用の見える化等について子どもの教育費
1年における子どもの学習費総額の平均は以下の通りです。幼稚園3歳から高校3年まで全て公立の場合は596万円、全て私立の場合は1,976万円かかる計算となっています。
また、大学費用は進学先や専攻学部によりますが、大学(昼間部)に4年通った場合の費用総額の目安は以下の通りです。種類 学習費総額(子ども1人あたり) 公立幼稚園 18万4,646円 私立幼稚園 34万7,338円 公立小学校 33万6,265円 私立小学校 182万8,112円 公立中学校 54万2,475円 私立中学校 156万359円 公立高等学校(全日制) 59万7,752円 私立高等学校(全日制) 103万283円
これらを合計すると、最低でも子どもの教育費は800万円以上かかる計算となります。通学費や教材費や受験費用なども加えた場合、教育費はさらに高くなるでしょう。種類 授業料(1年あたり) 入学料(1年あたり) 4年通った場合の費用 国立 53万5,800円 28万2,000円 242万5,200円 公立 53万6,363円 39万1,305円 253万6,757円 私立 93万943円 24万5,951円 396万9,723円
出典:令和5年度子供の学習費調査の結果を公表します
出典:(参考2) 国公私立大学の授業料等の推移車の購入
車を購入する際には、本体価格に加えて多くの費用がかかります。本体価格は車種やグレードによって異なりますが、軽自動車の場合は新車で約100万~200万円、中古で約30万~150万円が相場です。
また、法定費用として自動車税・自動車重量税・自賠責保険料・消費税などもかかります。検査登録費用や車庫証明費用やナンバープレート代も必要になるでしょう。さらに、販売店やディーラーに購入手続きを代行させる場合は、代行費用も必要になります。住宅の購入
住宅購入費用はグレードや居住地によって異なります。各エリアの住宅購入資金の平均は以下の通りです。
これらの住宅購入資金のうち、手持金は約1~2割です。約200万~1000万円の頭金を用意しておくと、無理のない返済計画を立てやすくなるでしょう。全国 首都圏 近畿圏 東海圏 その他 注文住宅 3,863万4,000円 4,194万6,000円 4,142万2,000円 3,896万7,000円 3,625万2,000円 土地付注文住宅 4,903万4,000円 5,679万6,000円 5,265万3,000円 4,810万5,000円 4,299万4,000円 建売住宅 3,603万2,000円 4,199万3,000円 3,720万9,000円 3,055万2,000円 2,873万円 マンション 5,245万3,000円 5,801万2,000円 5,343万円 4,732万3,000円 4,352万1,000円 中古戸建 2,535万6,000円 3,172万円 2,484万9,000円 2,268万円 2,025万4,000円 中古マンション 3,037万1,000円 3,378万6,000円 2,809万3,000円 2,308万9,000円 2,415万4,000円
出典:2023年度フラット35利用者調査親の介護
月々の介護費用は平均8万3,000円、介護期間は平均5年1か月といわれています。この場合、506万3,000円の介護費用が必要になる計算です。親本人の資産や年金で介護費用をまかなえない場合は、親が元気なうちから貯金したり民間保険に加入させたりすることをおすすめします。
参考:介護にはどれくらいの費用・期間がかかる?|リスクに備えるための生活設計-

40歳から1,000万円貯金するためには、資産形成が重要です。ここでは、おすすめの資産形成の方法を解説します。
NISA
NISA(少額非課税投資制度)とは、年間非課税枠内の投資に限り、得られた利益が非課税になる制度です。2024年から従来の積立NISAと一般NISAが統一された新NISAが始まりました。つみたて投資枠と成長投資枠の2つの枠があり、年間で360万円、生涯で1,800万円まで非課税で投資することが可能です。
参考:NISAを知る:NISA特設ウェブサイトiDeCo
iDeCo(個人型確定拠出年金)とは、公的年金とは別に給付を受けられる私的年金制度です。原則60歳まで資産を引き出せませんが、掛け金が全額所得控除の対象となるため、所得税や住民税の負担を抑えられます。運用益が非課税になる点もメリットです。
投資信託
投資信託とは、投資家から集めた資金を運用の専門家が株式や債券などに投資・運用し、その成果を投資家に分配する金融商品です。少額から分散投資できるため、手軽に始められる点が特徴です。
また、専門家が運用を行ってくれるため、自分で売買のタイミングを判断する必要もありません。さらに、複数の資産に分散して投資するため、リスク分散も可能です。
ただし、投資信託には手数料や税金がかかるほか、元本保証がないため、市場相場によっては購入価格を下回る恐れがあります。積立保険
積立保険とは、保障と貯蓄の両方の機能を兼ね備えている保険です。保険料を支払う必要はありますが、満期時や解約時にお金を受け取れるため、保障を得ながら貯蓄ができます。一方、掛け捨て型に比べて保険料が高い点や解約返戻金が支払った保険料を下回るかもしれない点がデメリットです。
以下の保険が積立保険に該当します。
終身保険
亡くなった場合に保険金が支払われる保障が一生涯続く保険です。解約時に解約返戻金を受け取れます。
養老保険
亡くなった場合に保険金が支払われる保障が満期まで続く保険です。満期を迎えた場合にも満期保険金を受け取れます。
個人年金保険
一定期間まで保険料を支払い、契約した時期から年金を受け取れる保険です。iDeCoとは異なり、年金を受け取る際に課税されます。
学資保険
子どもの教育資金を準備するための保険です。子どもの入学や進学時に教育資金・満期保険金を受け取れます。財形貯蓄制度
財形貯蓄制度とは、給与やボーナスから一定額を天引きし、事業主が労働者に代わって金融機関に送金して積み立てる制度です。自動的に積み立てられるため、無理なく貯蓄できます。
また、貯蓄の目的によって「一般財形貯蓄」「財形住宅貯蓄」「財形年金貯蓄」の3種類に分けられ、非課税になる可能性や住宅ローンを利用できる可能性があります。ただし、財形貯蓄制度を導入していない企業では利用できません。債券
債券は、国や企業が資金を調達するために発行する有価証券で、購入は資金を貸し出すことを意味します。満期まで保有すると利息を受け取り、元本が返還されるため、安定した収入が得られます。しかし、金利上昇や途中売却で損失が生じる可能性があり、発行体の信用度が低いと価格が下落し、元本や利息の回収が難しくなることもあります。
株式投資
株式投資とは、企業が事業活動に必要な資金を調達するために出資者を募る目的で発行される株式の売買やその配当金によって利益を得る投資方法です。近年では、通常の単元株(一般的には100株)よりも少ない単位で購入できるミニ株も登場し、少ない資金でも投資が可能になりました。しかし、元本保証がないため、資金を失うリスクがあります。少額投資では、利益が手数料を下回るケースも少なくありません。
-

40歳からの資産形成には、不動産投資も効果的です。ここでは、不動産投資の概要を解説します。
不動産投資とは
不動産投資とは、アパートやマンションなどを所有し、賃貸や売却によって利益を得る投資方法です。一般的に、自己資金だけでなく融資を受けて不動産購入資金を調達するため、短期での資産形成には向いていません。一方、入居者がいる限り安定して賃料収入を得られることから、長期での資産形成に向いています。
投資信託の「J-REIT」とは
J-REITは不動産投資信託で、投資家から集めた資金で不動産を取得し、賃料収入や売却益を分配する金融商品です。自分で物件を運用する必要がなく、専門家が管理するため、手間が省けます。
ただし、専門知識も不要で、複数の不動産に投資できますが、不動産の所有権は保有できません。災害リスクや元本割れリスク、J-REITを運用する会社が倒産・上場廃止になるリスクもあります。また、一口あたり数万~数10万円で取引されることが一般的なため、少額投資には向いていないでしょう。-

ここでは、不動産投資のメリットを解説します。安定した収入を得られる点や自己資金が少なくても高額投資できる点がメリットです。
安定した収入を得られて年金対策にもなる
入居者がいる限り、毎月一定額の賃料収入が期待できます。賃料収入が毎月の返済額よりも多い必要がありますが、長く住み続ける入居者を見つけられれば、安定した収益を期待できる可能性があります。そのうえ不労所得のため、老後の年金対策にもつながります。
自己資金が少なくても高額投資ができる
自己資金が少なくても、金融機関からの融資を受けることで高額投資ができます。これは不動産が担保として利用できるためです。そのため、少額の資金で大きな利益を上げられる可能性があります。
長期的な資産形成を目指せる
安定的に収入を得られるうえに経済情勢に左右されにくいため、長期的な資産形成に最適です。融資を受けていても、計画的に借入残高を減らしていくことが可能になります。不動産の市況が良ければ購入時よりも高値で売却できる場合もあり、大きな利益を上げられる可能性もあります。
また、不動産は現物資産であるため、資産価値の保全にも有効です。インフレ時には金融資産の価値が下がりますが、不動産は賃料が上昇するため、資産価値の減少リスクを軽減できます。節税効果を期待できる
建物価格が1億円の物件を購入し、その減価償却期間が10年の場合、毎年1,000万円の減価償却費が発生します。この費用は会計上計上されますが、購入年度を除いて現金支出はありません。これにより、黒字を維持しつつ会計上の赤字を生じさせることが可能です。不動産所得の赤字は他の黒字所得と相殺でき、本業の所得から減価償却費を控除することで税務上の所得を圧縮し、住民税や所得税などの節税が可能です。また、相続税を計算する際は相続税評価額を算出する必要があります。相続税評価額は現金であれば額面のままです。一方、不動産であれば土地は道路に面している土地の1㎡あたりの価格、建物は固定資産税評価額によって決められます。
一般的に、固定資産税評価額は地価公示価格の約7~8割となるため、不動産で相続を受けた方が結果として節税効果が得られる場合もあります。-

不動産投資にはさまざまなメリットがある一方で、いくつかの注意点もあります。ここでは、不動産投資をする際の注意点を解説します。
初期費用が必要になる
不動産投資では、一般的に物件価格の7~10%の自己資金が必要になるといわれます。具体的には、頭金や融資手数料、仲介手数料や不動産取得税などです。自己資金ゼロでの不動産投資も可能ですが、融資審査のハードルが高くなるほか、毎月の返済額も増えるため、おすすめしません。
空室や家賃滞納などさまざまなリスクがある
不動産投資には、さまざまなリスクがあります。具体的なリスクは以下の通りです。
空室リスク
物件が空室になり、賃料収入が得られなくなるリスクです。不動産投資における最大のリスクであり、賃料が下がったり返済が難しくなったりする恐れがあります。 老朽化リスク
築年数の経過に伴い、物件の劣化が進むリスクです。修繕費が増えるほか、不動産価値が下がり、賃料収入や入居率や売却時の価格に悪影響を与える恐れがあります。 家賃滞納リスク
入居者から家賃を滞納されるリスクです。賃料収入が不安定になり、返済に悪影響を与える恐れがあります。 事件事故リスク
所有する物件で事件・事故が発生するリスクです。不動産価値の下落や入居者の退去につながるほか、売却が難しくなる恐れもあります。 災害リスク
地震・火災・水害・土砂災害などにより、建物の損壊や不動産価値の下落を招くリスクです。保険へ
の加入や投資エリアの分散を行って、災害リスクを抑える必要があります。
金利上昇リスク
金利の上昇によって返済額が増加し、収支が悪化するリスクです。特に、返済額が大きい場合や返済期間が長い場合は金利上昇リスクが上がります。流動性が低いため売却が難しいケースがある
不動産は価格が高く、不特定多数の人が自由に売買できるわけではないため、流動性が低い傾向です。そのため、売却したくても売却できないケースも少なくありません。
不動産は保有しているだけでも維持管理費や固定資産税などを支払う必要があるため、現金化できずに出費がかさんでしまう恐れがあります。-

資産形成・運用の際は、目的の明確化が重要です。目的を明確にすることで、目標金額や運用期間を設定しやすくなり、適した金融商品を選べます。
また、長期運用・分散投資・積立投資を意識した運用も大切です。運用益を元本に含めて得られる利益を増やす複利効果は、運用期間が長いほど効果が高まります。分散投資や積立投資はリスクを抑えつつ、安定して資産形成を目指すうえで欠かせません。さらに、貯金と資産形成・運用のバランスを考えるのもポイントです。資金が必要な場合に金融商品の価格が下落するリスクも考えて、貯金を確保しておくことをおすすめします。-

ここでは、効果的な貯金方法を解説します。固定費の見直しや家計簿アプリの活用や先取り貯蓄などを行って、無理なく貯金しましょう。
固定費を見直す
固定費を見直すことで無駄な出費を減らし、効率よく貯金できるようになります。電気・ガス代はプランや供給会社を見直すことで、使用料金の削減が可能です。また、携帯電話の料金もデータ使用量に合ったプランに変更したり、不要なオプションを解約したりすることで削減できます。無駄なサブスクサービスを利用していないかどうかも見直しのポイントです。
家計簿アプリを使って支出を管理する
家計簿アプリを使うことで支出管理ができ、貯蓄計画が立てられます。レシート撮影で自動記録する機能があり、初心者でも簡単に始められるでしょう。また、銀行口座やクレジットカードと連携できるアプリもあります。
先取り貯蓄を行う
先取り貯蓄とは、給与が入る前にあらかじめ決めた金額を貯蓄に回す方法です。これにより、お金の使い過ぎを防げます。企業の財形貯蓄制度や銀行の自動積立を利用して、貯金を習慣化しましょう。
心身の健康に注意する
心身の健康に注意するのも、支出の削減につながります。健康状態を維持することで、通院費や治療費を抑えられるほか、長く働けるようになるため、収入も安定します。バランスを意識した食事や規則正しい生活、適度な運動などを心がけましょう。
-

40代全体の平均貯金額は929万円、中央値は200万円となっており、40歳で貯金1,000万円は決して少なくありません。ただし、今後のライフイベントや老後を考えると安心できない貯金額でもあります。40歳から1,000万円の貯金を目指す際はNISAやiDeCo、投資信託や不動産投資などの資産形成がおすすめです。資産形成の際は、目的の明確化や長期運用・分散投資・積立投資を意識した運用がポイントになります。
また、固定費の見直しや家計簿アプリの活用などを行って、出費を抑えるのも効率的に貯金するうえで重要です。-
「中央値」と「平均値」の違いについて教えてください。
平均値とは、全てのデータの数値を合計し、それをデータの個数で割った値を指します。一方、中央値はデータの数値を大きさ順に並べた際に、中央に位置する値です。
-
40歳から貯金を始めるにはどうすればいいですか。
固定費の見直しや家計簿アプリの活用や先取り貯蓄などを行って、無理なく貯金しましょう。効果的な貯金方法を解説しています。
詳細はこちらを参考にしてください。
関連記事
-
 100万円以下でマンションは購入できる?その方法や必要な費用、デメリットや注意点も解説詳しく見る
100万円以下でマンションは購入できる?その方法や必要な費用、デメリットや注意点も解説詳しく見るマンション投資に興味がある方の中には、投資資金が少なくて始められないと考えている方も多いでしょう。マンション投資には、まとまった初期費用が必要になりますが、少額からでもマンション投資を始めることは十分に可能です。 本記事では、マンション投資を100万円以下で始める方法や必要な費用、デメリットや注意点などを解説します。
-
 不動産管理会社に支払う管理費(手数料)はいくら?業務内容も紹介!詳しく見る
不動産管理会社に支払う管理費(手数料)はいくら?業務内容も紹介!詳しく見る所有するアパートやマンションを賃貸物件として経営する際は、入居手続きや設備メンテナンスなどの管理業務を行わなければなりません。管理業務は個人で行うことも可能ですが、幅広い業務を一人で行うのは負担が大きく難しいとされています。そのため、多くの不動産オーナーは、管理業務を不動産管理会社に委託しています。 ただし、管理業務を委託する際は、手数料などの管理費がかかります。実際に管理を委託する場合、どの程度の費用がかかるのでしょうか。 そこで、この記事では、不動産管理会社に支払う管理費の相場や、管理業務を委託するメリット・デメリットなどについて紹介します。 しかし、所有している土地でアパート経営を始めるには、いくつかのリスクがあることも覚えておきましょう。それぞれのリスク回避のために適切な対策を行って、効率的な土地活用を行いましょう。 この記事では、土地有りでアパート経営を行うメリット・デメリットについて、そして経営を進める時の流れや必要な資金などについて解説します。
-
 マンション経営のメリットやデメリットは?失敗やリスク回避の方法を解説詳しく見る
マンション経営のメリットやデメリットは?失敗やリスク回避の方法を解説詳しく見る土地活用を考える際、マンション経営は一つの方法です。土地があれば新しくマンションを建てたり、中古の物件を購入して経営したりできます。マンションの維持管理は多岐にわたり負担が大きいものの、管理会社に任せれば少ない手間で安定した収入を得られます。 しかし、マンションの経営にはメリットだけでなく、デメリットが存在するのも事実です。不動産運用やマンション経営についての知識を身に付けた上で、メリットやデメリットを把握しておかなければ、経営を順調に行うことは難しいでしょう。 マンション経営を検討する際、「マンション経営で安定した収入が得られるかどうか不安」「経営の利点やリスクについて分からない」と思う方は少なくありません。この記事では、マンション経営のメリット・デメリット、経営におけるリスクの回避方法などを解説します。
タウングループ不動産仲介・周辺事業- 賃貸不動産仲介(東京・神奈川・埼玉・千葉) タウンハウジング
- 賃貸不動産仲介(東海) タウンハウジング東海
- 賃貸不動産仲介(九州) タウンハウジング福岡
- 土地・建物の不動産販売及び仲介 タウン住宅販売
- 首都圏を中心に引越サービスを展開 タウン引越サービス
建築事業- 賃貸住宅の企画・設計・施工 アヴェントハウス
多角化事業- 都内を中心に飲食店を運営 タウンダイニング
- インドアテニススクール タウンインドアテニスアカデミー


 一覧へ戻る
一覧へ戻る