居住用財産の3,000万円控除とは?要件はチェックリストで確認しよう
居住用財産の売却において一定の要件を満たすと、譲渡所得から最高3,000万円の控除が受けられるのをご存じでしょうか。マイホームを買い換える際に活用すれば、大きな節税につながる可能性がある特例といえます。
本記事では、居住用財産の3,000万円控除を受けるための要件や要件を確認できるチェックリストについて解説しましょう。また、控除を受けるためのケース別の要件や控除のシミュレーションもあわせて紹介します。
-
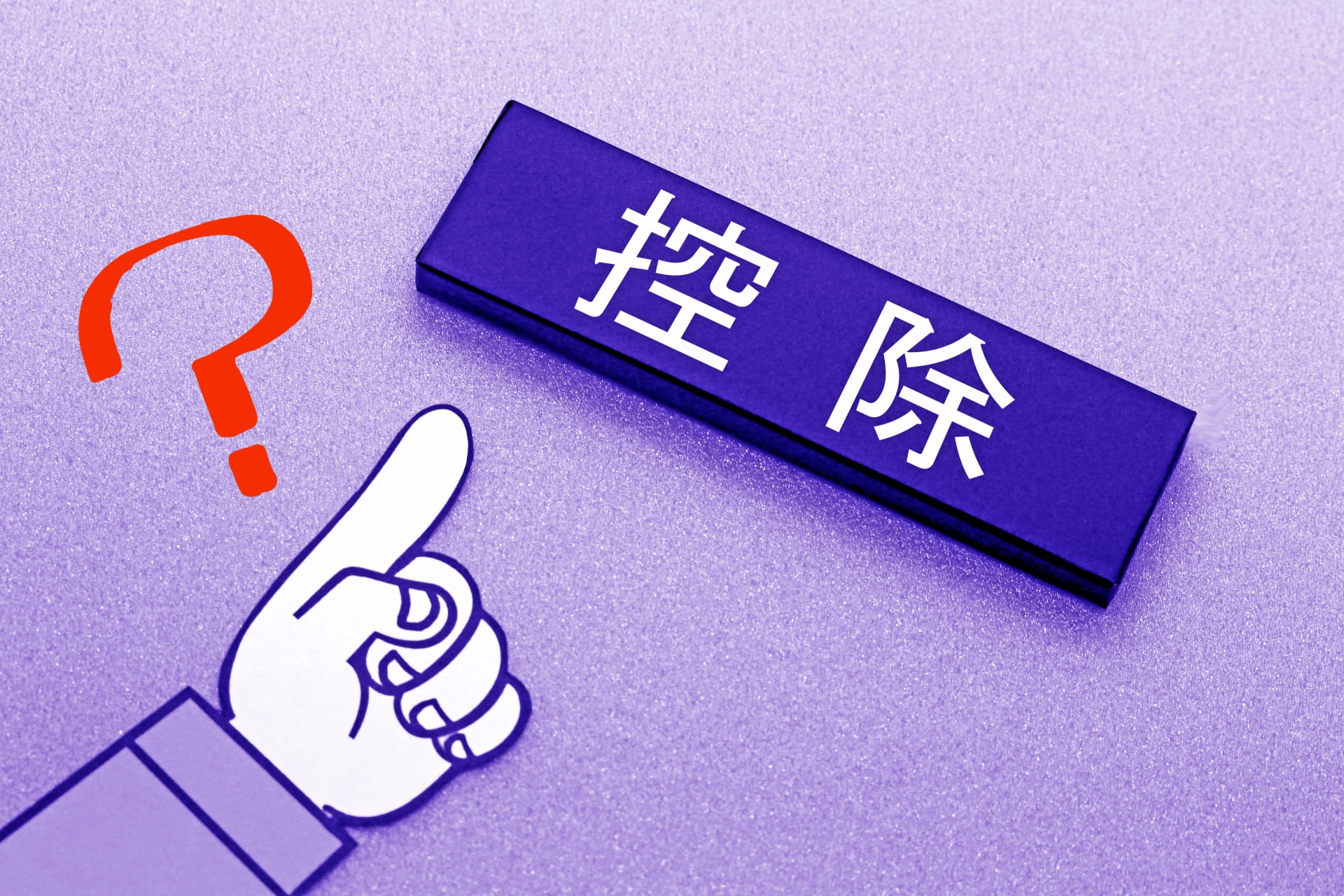
居住用財産の3,000万円控除とは、居住用財産を売却した際に譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができるとされる特例です。ここでは、この特例の概要を解説します。
正式名称は「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」
一般的に居住用財産の3,000万円控除と呼ばれる特例の正式名称は「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」です。以下のいずれかに該当する資産を売却した際の譲渡所得から、最高3,000万円まで控除できます。
1. 自分が住んでいる家屋
2. 以前に住んでいた家屋
● 住まなくなってから3年目の12月31日までに売却する場合に限る
● 住まなくなった日以後はどのような用途に使用してもよい
3. 上記1または2の家屋とともに売った敷地や借地権
4. 上記1または2の家屋を取り壊した場合の敷地で、次の2つの要件すべてに当てはまるもの
● 敷地の譲渡契約が家屋を取り壊した日から1年以内に締結し、かつ住まなくなった日から3年目の12月31日までに売却する
● 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用途で使っていない
5. 家屋が災害で滅失した場合の敷地で、以下の区分に応じた期限までに売却する
● 上記1の敷地の場合は、災害が発生した日から3年目の12月31日まで
● 上記2の敷地の場合は、住まなくなった日から3年目の12月31日まで適用を受けるために必要な書類と申請方法
控除の適用を受けるには、以下の書類が必要です。
書類をそろえても居住用財産を売却した翌年の2月16日から3月15日に確定申告を行わなければ、特別控除は適用されません。申告時期には注意しましょう。必要書類 取得場所 譲渡所得の内訳書 税務署またはインターネット 確定申告書 第一表・第二表 税務署またはインターネット 確定申告書 第三表(分離課税を申告する場合) 税務署またはインターネット 本人確認書類(マイナンバーなど) 自分で用意 売却時の契約書や各種領収書のコピー 自分で用意 購入時の契約書や各種領収書のコピー 自分で用意 譲渡した不動産の全部事項証明書 法務局 戸籍の附票
(売買を行う契約日の前日時点で、住民票の住所と売却物件の所在地が異なる場合)本籍地の市区町村役場 「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例適用チェック表」
国税庁では、居住用財産の3,000万円控除の適用要件について確認できるチェックリストを公表しています。居住用財産を譲渡した場合の適用要件をチェックするものです。チェック表の質問に「はい/いいえ」で答えることで、特例の要件に合っているかを自分で確認できます。
参考:国税庁|居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例適用チェック表
特例の適用を受ける場合、確定申告書と譲渡所得の内訳書等とともにチェック表の提出も求められます。「10年超所有軽減税率の特例」と併用できる
10年超所有軽減税率の特例とは、不動産の所有期間が10年を超えた場合に譲渡所得が6,000万円以下の部分の税率を軽減できる制度です。居住用財産の3,000万円控除は、10年超所有軽減税率の特例と併用できます。
例えば、不動産を売却して1億円の売却益が出たケースを考えましょう。まず居住用財産の3,000万円控除の適用を受けると、売却益は7,000万円になります。そして、10年超所有軽減税率の特例を併用しない場合とした場合の計算式は以下の通りです。6,000万円以下 6,000万円を超える部分 所得税 10% 15% 住民税 4% 5% 復興特別所得税 0.21% 0.315% 合計 14.21% 20.315%
● 特例を適用しない通常の長期譲渡の場合:7,000万円×20.315%=1,422万500円
● 10年超所有軽減税率の特例を併用した場合:6,000万円×14.21%+1,000万円×20.315%=1,055万7,500円
居住用財産の3,000万円控除と10年超所有軽減税率の特例の併用により、約366万3,000円の節税につながる可能性があります。「住宅ローン控除」とは併用できない
住宅ローンを借り入れて住宅の新築・取得または増改築等をした場合に利用できる、住宅ローン控除とは併用できない点に注意しましょう。居住用財産の 3,000万円控除を受けると、その前後2年間は住宅ローン控除を受けることができません。そのため、どちらを適用すれば有利なのか比較検討する必要があります。
-

控除を受けるためには、どのような必須条件を満たす必要があるのでしょうか。ここでは、売却する物件や売却先など具体的な要件を解説します。
売却する不動産が居住用財産(マイホーム)である
控除は、居住用財産(マイホーム)を売却する際に適用される特例です。そのため、別荘やセカンドハウスや賃貸物件などには適用されません。
所有期間や居住期間はない
売却する物件の所有期間や居住期間に関する要件はありません。居住期間が短くても、自宅として使用していれば特例は適用されます。
売却先が親子や配偶者といった特別関係者でない
控除は、第三者に対して売却する際に適用されます。親子や夫婦、生計をともにする親族の特別関係者への売却には適用されません。また、自宅を売却した後に、その売却した自宅で同居する親族も特別関係者に該当します。
親族に売却する際は相手が特別関係者の規定に抵触しないか確認が必要です。一部他の特例の適用を受けていない
居住用財産を売却する年の2年前までさかのぼり、他の居住用財産の特例を適用していないか確認が必要です。他の特例適用を受けていた場合は、原則として控除は適用されません。ただし、2年前までに適用していた特例が空き家特例であれば控除は適用されます。空き家特例とは、空き家の発生を制御するために国が行っている特例措置です。 被相続人(故人)の住居を相続した人が、その家屋または敷地の譲渡にあたり一定の要件を満たした場合、 その譲渡所得の金額から3,000万円控除されます。相続人が3人以上の場合は、2,000万円まで控除対象です。
控除が適用されないケース
居住用財産の3,000万円控除は、以下のような家屋には適用されません。
1. 特例の適用を受けるためだけに入居したと認められる家屋
2. 居住用の家屋を新築する期間だけに仮住まいとして使用した家屋、その他一時的な目的で入居したと認められる家屋
3. 別荘のように主に趣味や娯楽、保養のために所有する家屋-

ここでは、居住用財産の売却をケース別にみていきましょう。控除を受けるために必須となるそれぞれの要件もあわせて解説します。
相続した場合
相続した場合は、売却する物件に相続人が居住しているかどうかが判断基準です。
1. 同居していた父親が亡くなり、父親が所有していた実家を、子どもが相続するケース
2. 同居していた夫が亡くなり、夫が所有していた自宅を妻が相続するケース
3. 父親が亡くなり、父親が所有していた実家からは別居している子どもが相続するケース
上記の1と2のケースであれば、相続人が相続した不動産を居住用として利用しているため、売却した際は控除を受けられます。
一方、3のケースは居住用として相続していないため、控除は適用外です。しかし、以下の3つの要件すべてに該当していれば「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」を利用できる可能性があります。
● 昭和56年5月31日以前に建築された
● 区分所有建物登記がされている建物でない
● 相続開始の直前に被相続人以外に居住していた人がいなかった共有名義の場合
居住用財産が夫婦や兄弟などの共有名義の場合、所有者ごとに最高3,000万円控除が適用される可能性があります。確定申告を個別に行うため、例えば夫婦ともに要件を満たしていれば最大6,000万円まで控除を受けられます。
しかし、この特例は家を基準に考えられているため、夫が家を、妻が土地を保有している場合は3,000万円しか控除を受けられません。店舗併用住宅の場合
店舗併用住宅の場合、控除の対象は居住用部分のみです。一方、居住用部分の割合が全体の90%以上を占める場合、店舗を含めた全体に特例が適用されます。
賃貸併用住宅の場合
賃貸併用住宅の場合、控除の対象は自身の居住用部分のみです。例えば、居住用部分と賃貸部分の割合が半々だったとします。長期譲渡(税率20.315%)で売却した際に1,000万円の利益が出た場合、税額は本来203万1,500円となります。
しかし、居住用部分である半分は控除の対象であり、実際に課税されるのは500万円の利益に対してです。そのため、納税額は半分の101万5,750円となります。-

ここでは、居住用財産の3,000万円控除の特例を適用した節税額をシミュレーションします。前提条件の譲渡内容は以下の通りです。
● 売却金額:1億円
● 取得費:8,660万円(減価の額控除後の金額)
● 譲渡費用:340万円
● 所有期間:10年(長期譲渡所得の対象)控除を適用した場合
居住用財産の3,000万円控除を適用した場合、全額が控除されます。
● 1億円-(8,660万円+340万円)-3,000万円=0円(課税譲渡所得金額)
● 0円×20.315%=0円(譲渡税)控除を適用しなかった場合
居住用財産の3,000万円控除を適用しなかった場合、譲渡税は203万1,500円になります。
● 1億円-(8,660万円+340万円)=1,000万円(課税譲渡所得金額)
● 1,000万円×20.315%=203万1,500円(譲渡税)-

ここでは、居住用財産の3,000万円控除以外で活用できる特例・控除を解説します。主な特例・控除として、「特定居住用財産の買換え特例」や「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」が挙げられます。
「特定居住用財産の買換え特例」
マイホームの買換えをした場合は、「特定居住用財産の買換え特例」を利用可能です。これは譲渡所得のうち、買換えにかかる費用分はなかったものとして課税を繰り延べできる制度です。
例えば、3,000万円で購入した物件を売却し、600万円の利益が出たケースを考えます。その後新たに4,000万円の新居を購入する場合、600万円は繰り延べされるため、売却のタイミングでは課税されません。新たに購入した物件を売却した時点で、繰り延べた600万円を加えた額に譲渡所得税がかかります。なお、この特例は居住用財産の3,000万円控除の特例とは併用できません。「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」
土地と家屋を相続・遺贈で取得した場合、要件を満たせば「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」が適用可能です。一定の要件を満たせば、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できます。
なお、令和6年1月1日以降の譲渡で、土地と家屋を相続・遺贈により取得した相続人が3人以上の場合、控除額は2,000万円までです。「平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除」
平成21~22年に土地を取得した場合、要件を満たせば「平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除」を適用できます。この特例は、平成21年に取得した土地を平成27年以降に、平成22年に取得した土地は平成28年以降に売却すれば、譲渡所得から1,000万円控除できる特例です。特例の適用を受けるには、以下の要件を満たす必要があります。
1. 平成21年1月1日から平成22年12月31日の間に土地等を取得している
2. 平成21年に取得した土地等は平成27年以降に譲渡し、平成22年に取得した土地等は平成28年以降に譲渡する
3. 親子や夫婦など、「特別な間柄」にある者から取得した土地等ではない
4. 相続・遺贈・贈与・交換・代物弁済及び所有権移転外リース取引により取得した土地等ではない
5. 譲渡した土地等について、収用等の場合の特別控除や事業用資産の買換えをした場合の課税の繰延べなど他の譲渡所得の特例の適用を受けない「収用等により土地建物を売ったときの特例」
土地収用法やその他の法律で、収用権が認められている公共事業のために土地建物を売却した場合、課税の特例が適用されます。この課税の特例は、以下の2つです。
● 対価補償金等で他の土地建物の買換えをしたときは譲渡がなかったものとする特例:
この特例により、売却した金額よりも買換えをした金額が多い場合は所得税の課税が将来的に繰り延べされ、売却した年には譲渡所得がなかったものとなります。また、売却した金額よりも買換えをした金額が少ない場合はその差額を収入金額として譲渡所得を計算します。
● 譲渡所得から最高5,000万円までの特別控除を差し引く特例:
以下の要件を満たせば、この特例の適用が受けられます。
1. 売却した土地建物が固定資産である
2. その年に公共事業のために売った資産のすべてについて、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受けていない
3. 最初に買取り等の申し出があった日から6か月以内に土地建物を売却している
4. 公共事業を施行する者から、最初に買取り等の申し出を受けた者が譲渡している-

ここでは、居住用財産の3,000万円控除に関する注意点を解説します。居住用財産の3,000万円控除は自動的に控除されるわけではなく、以下の手続きを進めたり要件を満たしたりする必要があります。
売却の翌年には確定申告を行う
居住用財産の3,000万円控除の特例を受けるには、売却した翌年の2月16日~3月15日に確定申告を行う必要があります。特例を利用して納税額がゼロになる場合でも確定申告は必要になるため、忘れずに余裕をもって準備しましょう。申告手続きが難しい場合は、税理士に依頼するのも一つの方法です。なお、確定申告の期限は土日・祝日の関係で繰り下げられる場合があります。
土地と建物の所有者が異なるときは要件を満たす必要がある
土地と建物の所有者が異なる場合は、以下の要件をすべて満たさなければ控除の対象にはなりません。
● 土地と建物を同時に売却する
● 土地と建物の所有者が親族関係で、生計を一にしている
● 土地と建物の所有者が一緒にその家に住んでいる-

「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」とは、居住用財産を売却した際の譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例です。
一定の要件を満たすだけでなく売却翌年に確定申告を行う必要もあるため、手続きが面倒と感じるかもしれません。しかし、控除の適用を受ければ大きな節税効果が期待できます。マイホームの売却を検討している方は、チェック表で特例の要件に合っているかを確認し、特例の活用を検討してみてはいかがでしょうか。-
居住用財産の3,000万円控除について教えてください。
居住用財産の3,000万円控除とは、居住用財産を売却した際に譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができるとされる特例です。
-
居住用財産の3,000万円控除に関する注意点について教えてください。
居住用財産の3,000万円控除は自動的に控除されるわけではなく、適用を受けるためには、所定の手続きを行い、必要な要件を満たすことが求められます。
詳細はこちらを参考にしてください。
関連記事
-
 アパート経営の一括借り上げって?仕組みや進め方などをまとめました詳しく見る
アパート経営の一括借り上げって?仕組みや進め方などをまとめました詳しく見る一括借り上げはアパート経営に慣れていないオーナーでも、活用しやすい経営システムです。近年、耳にする機会も多くなったこの方法ですが、「仕組みがよくわからない」という方もいるのではないでしょうか。「もし不動産会社とトラブルになったら」という思いから、なかなか実行できない方もいるようです。 しかし、所有している土地でアパート経営を始めるには、いくつかのリスクがあることも覚えておきましょう。それぞれのリスク回避のために適切な対策を行って、効率的な土地活用を行いましょう。 この記事では、土地有りでアパート経営を行うメリット・デメリットについて、そして経営を進める時の流れや必要な資金などについて解説します。
-
 アパート経営にかかる年間経費の仕組みとは?相談先や節約のコツも徹底解説詳しく見る
アパート経営にかかる年間経費の仕組みとは?相談先や節約のコツも徹底解説詳しく見るアパート経営は、家賃や駐車場賃料の収入から管理会社への管理委託料などの経費を支出として差し引いた利益額に対して課税される仕組みです。アパート経営の支出には「経費」として認められるものと認められないものがあり、経費の仕組みを理解していると節税効果も生まれます。この記事ではアパート経営の収支に注目し、経費の仕組みや節税のコツ、アパート経営を行う際の頼りになる相談先について解説します。 しかし、所有している土地でアパート経営を始めるには、いくつかのリスクがあることも覚えておきましょう。それぞれのリスク回避のために適切な対策を行って、効率的な土地活用を行いましょう。 この記事では、土地有りでアパート経営を行うメリット・デメリットについて、そして経営を進める時の流れや必要な資金などについて解説します。
-
 不動産投資信託のデメリットとポイントを把握し、安定収入を得よう詳しく見る
不動産投資信託のデメリットとポイントを把握し、安定収入を得よう詳しく見る現物の不動産投資を行っている方の中には、不動産投資信託に興味がある方もいるでしょう。投資信託とは、運用会社が投資家から集めた資金をまとめ、株式や債券などに分散投資した成果を投資家に分配する金融商品です。不動産投資信託ではさまざまなメリットを得られますが、同時にデメリットも存在します。 この記事では、不動産投資信託のメリットとデメリット、選ぶ際のポイントを解説します。不動産投資信託を活用する際は、損失が発生する可能性を理解し、どういったデメリットがあるか把握しておきましょう。
タウングループ不動産仲介・周辺事業- 賃貸不動産仲介(東京・神奈川・埼玉・千葉) タウンハウジング
- 賃貸不動産仲介(東海) タウンハウジング東海
- 賃貸不動産仲介(九州) タウンハウジング福岡
- 土地・建物の不動産販売及び仲介 タウン住宅販売
- 首都圏を中心に引越サービスを展開 タウン引越サービス
建築事業- 賃貸住宅の企画・設計・施工 アヴェントハウス
多角化事業- 都内を中心に飲食店を運営 タウンダイニング
- インドアテニススクール タウンインドアテニスアカデミー


 一覧へ戻る
一覧へ戻る