遺産相続した不動産の家賃収入は誰のものになるのかを解説!
賃貸物件を所有している方が亡くなられた場合、相続が決まるまで家賃収入は誰のものになるのでしょうか。家賃収入はケースによって取り扱いが異なります。例えば、いつ亡くなられたか、遺言の有無、家賃の入金状況などです。そのため、賃貸物件を相続することになったけど、どうすればよいか悩まれている方も少なくありません。そこでこの記事では、家賃とはどういう財産なのか、家賃収入は誰のものになるのかを解説します。また、相続の際に関係のある遺産分割協議や確定申告についてもまとめています。
-

家賃とは、所有する不動産を借主に使用させる対価として受け取るお金です。つまり、貸主と借主との契約に基づいて生じたものであり、財産の分類としては債権の一種となります。貸主は借主に対して家賃を請求する権利(賃料債権)を持ち、借主は不動産を使用させてもらう対価として、契約上支払う義務(債務)を負うのです。
しかし、同じ家賃でも相続財産になる家賃とならない家賃があるため、ここで詳しく見ていきましょう。相続財産になる家賃①:前月受け家賃が前月末に支払われた
家賃は、当月分を前月末までに支払う「前月受け」が一般的といわれています。例えば、1月分の家賃が12月末に振り込まれたとしましょう。1月10日に被相続人が亡くなられて相続が発生した場合、すでに支払われている1月分の家賃は、亡くなられた方の収入となり現預金として相続財産となるのです。
相続財産になる家賃②:相続発生後に支払われた未収家賃がある
家賃においては、滞納などにより相続発生時点で支払われているはずの家賃が未収のケースもあります。この場合は、相続人が今後受け取る権利を引き継ぐため、相続財産になります。未収家賃は相続財産として計上する必要があり、相続人はその分の相続税の支払い義務が発生するのです。
未収家賃が少額ならば、支払いは軽微なもので済みます。しかし、被相続人がいくつもの不動産を所有し、長年にわたって多額の未収家賃があると、家賃収入がなくてもその分に応じた相続税を支払わなければなりません。このような場合、速やかな対応が重要です。 未収家賃があるときの対処法としては、以下の4つが挙げられます。
1.内容証明で未収家賃を回収するための督促状を送付する
2.簡易裁判所の督促状や、少額訴訟の手続きを実施する
3.敷金を未収家賃の回収に充当する
4.貸倒損失を計上する
ただし、法律的な問題も関わってくるため、できるだけ弁護士などの専門家に依頼するなどして、間違いなく手続きする必要があるでしょう。相続財産にならない家賃
被相続人が亡くなられてから遺産分割協議が成立するまでに発生した家賃収入は、相続財産とはならないため注意が必要です。前述の通り、被相続人が亡くなられた時点で未収の家賃収入は相続財産となりますが、それ以降に発生した家賃は、遺産分割協議で賃貸物件を相続した相続人の所得となります。また、遺産分割協議で相続人が決まるまでの家賃収入は、相続人全員の共有財産です。したがって、相続人全員で法定相続分に応じて分割します。法定相続分とは、遺産を分割するための基準割合で、被相続人が亡くなられた時点の家族構成によって変わります。
なお、以下のような状況での家賃収入も相続財産とはなりません。
●前受家賃
相続開始日前に振り込まれた翌月分の家賃(前受家賃)は、相続開始時点で収益となっていないため、相続財産とはなりません。
●支払い日に到達していない家賃の未収分
例えば、毎月の家賃を当月末日に支払う契約となっている場合、1月の家賃は1月31日に支払われます。被相続人が1月20日に亡くなったのであれば、1月1日から1月20日までに発生した未収家賃は契約による支払い日に到達していない未収家賃という扱いになります。この未収家賃分は、家賃収入に計上する必要がないため、相続財産には含まれません。-

相続手続きを進めるうえで重要なのが、相続財産としてどのようなものがあるか、財産全体を正確に把握することです。現金や自宅、株式といった財産の相続は比較的イメージしやすいですが、賃貸物件の相続は物件だけでなく家賃収入の取り扱いもあるため複雑です。ここでは、家賃収入は誰の財産になるかを解説します。
家賃収入は相続した人の財産である
一般的に遺産相続で複数の相続人がいる場合は、相続した財産の金額を同じくらいにし、相続人の間で不公平を生じさせないことに気を配るのではないでしょうか。不動産の相続では、物件自体の価格に注目が集まる一方で、家賃収入はあまり注目されないことも多いといわれています。しかし、この家賃収入があるのとないのとでは、将来にわたって受け取る金額に大きな差が生じるケースもあるのです。例えば、家賃収入が毎年200万円ある賃貸物件を相続して10年間保有したケースでは、収入金額は累計で2,000万円にものぼります。賃貸物件には管理費用がかかったり損失が発生したりするリスクもありますが、リスクを最小限に抑えられればメリットのほうが大きくなるケースも十分に考えられるのです。賃貸物件を相続した場合、家賃収入は通常、その相続人の財産とみなされます。したがって、遺産相続の際には物件自体の価格だけでなく、家賃収入にも注目することが重要です。
遺言書がある場合は指定された相続人の所得となる
相続人を決めるのに一番わかりやすいのが、遺言書があるケースです。遺言書があれば、基本的にはその通りに遺産を分けます。そして、家賃収入も遺言書に従い、賃貸物件を相続する人が相続開始以降の家賃を受け取ります。なお、相続開始後の家賃収入は、あくまでも相続人の所得であり相続財産ではないため注意が必要です。
遺言書がない場合は遺産分割協議で相続人を決める
被相続人が亡くなると、遺産は相続人が相続します。前述した通り、遺言書があれば、基本的に遺言書通りに遺産を分けますが、遺言書がないのであれば相続人全員の話し合いで遺産の分け方を決めなければなりません。この相続財産をどう分けるかについて決める話し合いを「遺産分割協議」といいます。
遺産分割協議を行わないと手続きを進められなくなるため、相続人が複数いる場合は非常に重要です。遺産分割協議が成立するまでは法定相続分で分ける
遺産相続が発生してから遺産分割協議で分割方法が決定するまでの間の家賃収入は、法定相続人全員の共有財産です。したがって、相続人全員で法定相続分にそって分割します。なお、「法定相続人」とは、亡くなられた時点の家族構成から、財産を相続できる権利がある人のことです。 遺産分割協議が成立するまでの間は、相続人の中から選ばれた代表者1名が家賃を受け取り、その後法定相続分に応じて分配するとよいでしょう。ただし、代表者の口座に家賃が振り込まれた場合、その口座からローンや委託料などの支払いが発生してしまうと、代表者の財産と家賃収入が不明確になってしまいます。代表者は、家賃などの不動産管理用の別口座を作ると、受け取り・分配がスムーズに進みます。
遺産分割協議が成立すると、所有権の帰属はさかのぼる
遺産分割協議の対象である「遺産」とは、被相続人が亡くなられたときに所有していた財産を指します。したがって、前述した通り相続発生後に生じた家賃などの収益は「遺産」とはいえず、法定相続分に応じて分配されると考えられます。ところが民法では、遺産分割協議が成立すると、その効果は被相続人が亡くなられたときにさかのぼるとも定めているのです。だとすれば、相続発生後に生じた家賃収入などの収益もさかのぼってすべて遺産分割協議で決定した相続人に帰属することになります。そのため、仮に遺産分割協議が成立するまでの間に他の相続人に支払った分があるとすれば、それは返還を求められるともいえるのです。ただし、これらの考え方に対して最高裁は、以下の通り相続発生後の家賃収入は法定相続分に応じて分割するという考え方を採用しています。
「遺産は、相続人が複数あるときは、相続開始から遺産分割までの間、共同相続人の共有に属するものであるから、この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産とは個別の財産というべきであって、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得した上記賃料債権の帰属は、後にされた遺産分割の影響を受けないものというべきである。」遺産分割協議で相続人が決まった後の手続き
近年の法改正では、不動産を相続した際にも、名義変更登記をしなければ第三者へ対抗できないとされました。つまり、賃借人に対して新たな物件所有者であることを主張できないのです。反対に、名義変更登記すれば、新たな物件所有者となったことを賃借人に主張できます。そして、今後は相続人の口座へ家賃を振り込むように伝えれば、滞りなく入金されます。加えて、名義が変わったのであれば、「賃貸借契約書」を新たに作り直したほうがよいでしょう。なぜなら、法律上は契約書を書き直さなくても賃貸人の変更自体は有効に行われますが、被相続人名義のままでは契約関係が不明確になるためです。
遺産分割協議によって賃貸物件の相続人が決まったら、早めに所有権の名義変更登記をしましょう。-

遺産相続におけるトラブルとして、遺産分割前に特定の相続人が家賃を独り占めしてしまうケースがあります。ここでは、対処法をいくつか紹介します。
自分の取得分の取戻しを請求する
特定の相続人が家賃収入を独り占めすると、他の相続人の家賃収入を取得する権利が侵害されたことになります。そこで他の相続人は、独り占めした相続人に対して、自分が取得できる分の家賃収入の取り戻しを請求できます。任意に請求して返還に応じてもらえないときは、最終的に訴訟を起こして裁判所による支払い命令を求める必要が出てくるでしょう。なお、訴訟については後述します。
家賃収入を独占されている他の相続人は、家賃収入に関する詳細な情報を把握していないケースもあります。例えば、毎月の賃料額や支払日、支払先の口座などです。これらの情報は、「弁護士法23条照会」を利用すると調べられる可能性があります。家賃の入金先である被相続人名義の口座を調べれば、毎月の賃料額や支払日などを明らかにできるでしょう。ただし、弁護士法23条照会を利用するには、弁護士に依頼しなければなりません。家賃収入の詳細を把握できていないときは、弁護士への相談をおすすめします。振込先の口座を変更する
家賃などの振込先口座を変更するのも方法の一つです。現在振り込まれている口座が被相続人名義なら、口座が凍結され別口座に変更せざるを得ない状態になります。そこで、相続人の代表者名義で口座を作りますが、振込先口座が家賃収入を独占している相続人の名義であるケースもあるでしょう。このとき、賃借人へ通知して相続人代表者口座に変更してもらうことが可能です。ただし、振込先の変更が頻繁だと賃借人が不信感を抱いたり混乱したりする恐れもあります。賃借人には迷惑をかけないような丁寧な対応が必要でしょう。
遺産分割協議で話し合っておく
家賃収入を取り戻すために訴訟は起こせますが、手間がかかります。そのため、遺産分割協議で家賃の独り占め問題について解決する方法がおすすめです。遺産分割協議の際に、相続開始後に発生した家賃収入の総額を計算します。そして、相続人の取得分から独り占めしている家賃収入分を引けば公平に相続できます。なお、この遺産分割協議では相続人全員の合意が必要なため、家賃収入を独占している相続人が反対すると話し合いができず解決しません。別の解決方法を検討しなければならないでしょう。
訴訟を起こす
遺産分割協議で話し合っても家賃収入の返還に応じない場合、最終手段として訴訟を検討するとよいでしょう。そもそも家賃収入は、法定相続人が法定相続分に応じて分配しなければなりません。これを特定の相続人が独占すると「不当利得」となります。よって家賃収入を独占している相続人に対して、法的には「不法行為に基づく損害賠償請求」や「不当利得に基づく返還請求権」を行使し、独占された家賃収入を取り戻します。なお、訴訟提起は訴訟相手から同意を得る必要はありません。遺産分割協議で解決しようとして相手が同意しない、あるいは遺産分割が終了してしまった場合には、地方裁判所や簡易裁判所で不当利得に基づく返還請求訴訟を提起しましょう。
-

遺産分割協議には法律上の期限はなく、相続開始後何年でも協議は可能です。ただし、相続開始後10年で特別受益や寄与の主張はできなくなるため、遺産分割協議は10年以内にする必要があるといわれています。加えて、相続税の申告と納税には、原則として相続が発生したことを知った日から10か月以内という期限が設けられています。もし、申告しなければ無申告加算税や延滞税が課されてしまいます。さらに、相続登記の期限も3年以内と義務化されており、この義務に違反すると10万円以下の過料の対象です。なお、特別受益とは、被相続人から生前に財産を受け取っていた人が、相続する財産を法定相続分より少なくする制度です。一方、寄与分とは、被相続人の財産維持・形成に貢献した相続人が、相続する財産を法定相続分より多くする制度になります。
-

家賃収入を受け取るのは賃貸物件の相続人になりますが、将来の家賃収入は相続税ではなく所得税の対象となります。したがって、確定申告が必要です。また、亡くなられた被相続人が生前得ていた家賃収入も確定申告の対象となるため、誰がどのように申告するか確認しなければなりません。今まで確定申告とは無縁だったという方であっても、賃貸物件を相続することで申告義務が生じるため、忘れないようにしましょう。
確定申告は毎年おこなう
家賃収入のある賃貸物件を相続すると、家賃収入から利益がでます。したがって、相続初年度は「相続発生~その年の12月31日まで」の収入、翌年以降は「1月1日~12月31日まで」の収入について、自分の所得として確定申告しましょう。
青色申告承認申請書を提出する必要がある
青色申告承認申請書とは、青色申告で確定申告する際に使用する書類です。青色申告承認申請書は事前に提出する必要があり、確定申告のタイミングで申請しても間に合いません。提出しないと、青色申告をしていても白色申告に切り替わります。なお、確定申告は「青色申告」と「白色申告」があり、申告者は好きなほうを選択可能です。
青色申告は、白色申告に比べて帳簿作成が難しいというデメリットがあります。しかし、受けられるメリットは大きいでしょう。例えば、青色申告承認申請書を提出すると、不動産所得が発生した際に、5棟10室の基準を満たしていれば最大65万円の特別控除が適用されます。そうでなくとも、10万円の特別控除が適用されるのです。ただし、被相続人が青色申告の適用を受けていても、相続人に自動的に引き継がれるわけではありません。この場合は、提出期限までに青色申告承認申請書を提出すると相続した年から青色申告を適用できます。青色申告承認申請書の提出期限に留意する
青色申告承認申請書の提出期限は以下の通りです。賃貸物件を相続し青色申告の適用を受けたいのであれば、適用条件や提出期限をあらかじめ確認し、できるだけ早めに申請することが望まれます。
ケース 提出期限 亡くなられた方が青色申告者で、相続発生が1月1日~8月31日まで 相続が発生した日から4か月以内
※準確定申告書の提出期限と同じ亡くなられた方が青色申告者で、相続発生が9月1日~10月31日まで 12月31日 亡くなられた方が青色申告者で、相続発生が11月1日~12月31日まで 翌年2月15日 準確定申告を相続人全員で行う
亡くなられた方が生前得ていた家賃収入は、亡くなられてから4か月以内に「準確定申告」を行う必要があります。相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に1月1日から亡くなられた日までの所得を申告し、納税しなければなりません。準確定申告は、相続人全員で行います。相続人が2人以上であれば、各相続人が連署して申告書を提出します。連署ではなく各相続人が個別に申告することも可能ですが、情報が複雑になるため、よほどのことがない限り代表者が作成してまとめて提出するほうがよいでしょう。
準確定申告で還付金を受け取ったら相続財産に加える
準確定申告で、相続人に還付金が支払われるケースがあります。例えば、亡くなられた方に給与や報酬があり、所得税を源泉徴収されていた、あるいは高額の医療費を支払っていた場合などです。還付金は、亡くなられた方に対しての未収金と考えるため、相続財産として扱います。
賃貸物件を相続しなくても確定申告が必要なケースもある
相続発生後の家賃収入は相続人の所得になるため、相続人が給与所得者であるなら、1年間で20万円以上の不動産収入がある場合に確定申告を行う必要があります。一方で、賃貸物件を相続していない方であっても、遺産分割協議が成立するまでの期間に法定相続分で家賃収入を取得していると、確定申告が必要となるケースもあります。
-

賃貸物件を相続した際の家賃の取り扱いにおいては、いつ家賃が入金されて、いつ被相続人が亡くなられたかがポイントです。相続発生前の家賃は被相続人の財産となり、相続遺産に含まれます。遺産は、必ずしも収入になるとは限らず、家賃が未収であっても相続されます。
一方、相続発生後の家賃については、遺言書がなければ誰が相続するか遺産分割協議で決めなければいけません。また、相続にトラブルはつきものであるため、相続人が複数人いるときは特に遺産分割協議が重要です。相続開始から協議が成立するまでは、法定相続人が法定相続分に応じて家賃収入を分けることになるでしょう。
さらに、被相続人が亡くなられた場合、相続人は確定申告を行う必要があります。準確定申告は被相続人が亡くなられてから4か月以内、確定申告も2月16日~3月15日と期限があるため、忘れずに申告しましょう。-
相続が決まるまでの家賃収入は誰のものになりますか。
相続人を決めるのに一番わかりやすいのが、遺言書があるケースです。遺言書があれば、基本的にはその通りに遺産を分けます。そして、家賃収入も遺言書に従い、賃貸物件を相続する人が相続開始以降の家賃を受け取ります。なお、相続開始後の家賃収入は、あくまでも相続人の所得であり相続財産ではないため注意が必要です。一方で、遺言書がない場合は遺産分割協議で相続人を決めます。
詳細はこちらを参考にしてください。 -
賃収入がある賃貸物件を相続したら確定申告は必要ですか。
家賃収入を受け取るのは賃貸物件の相続人になりますが、将来の家賃収入は相続税ではなく所得税の対象となります。したがって、確定申告が必要です。また、亡くなられた被相続人が生前得ていた家賃収入も確定申告の対象となるため、誰がどのように申告するか確認しなければなりません。
詳細はこちらを参考にしてください。
関連記事
-
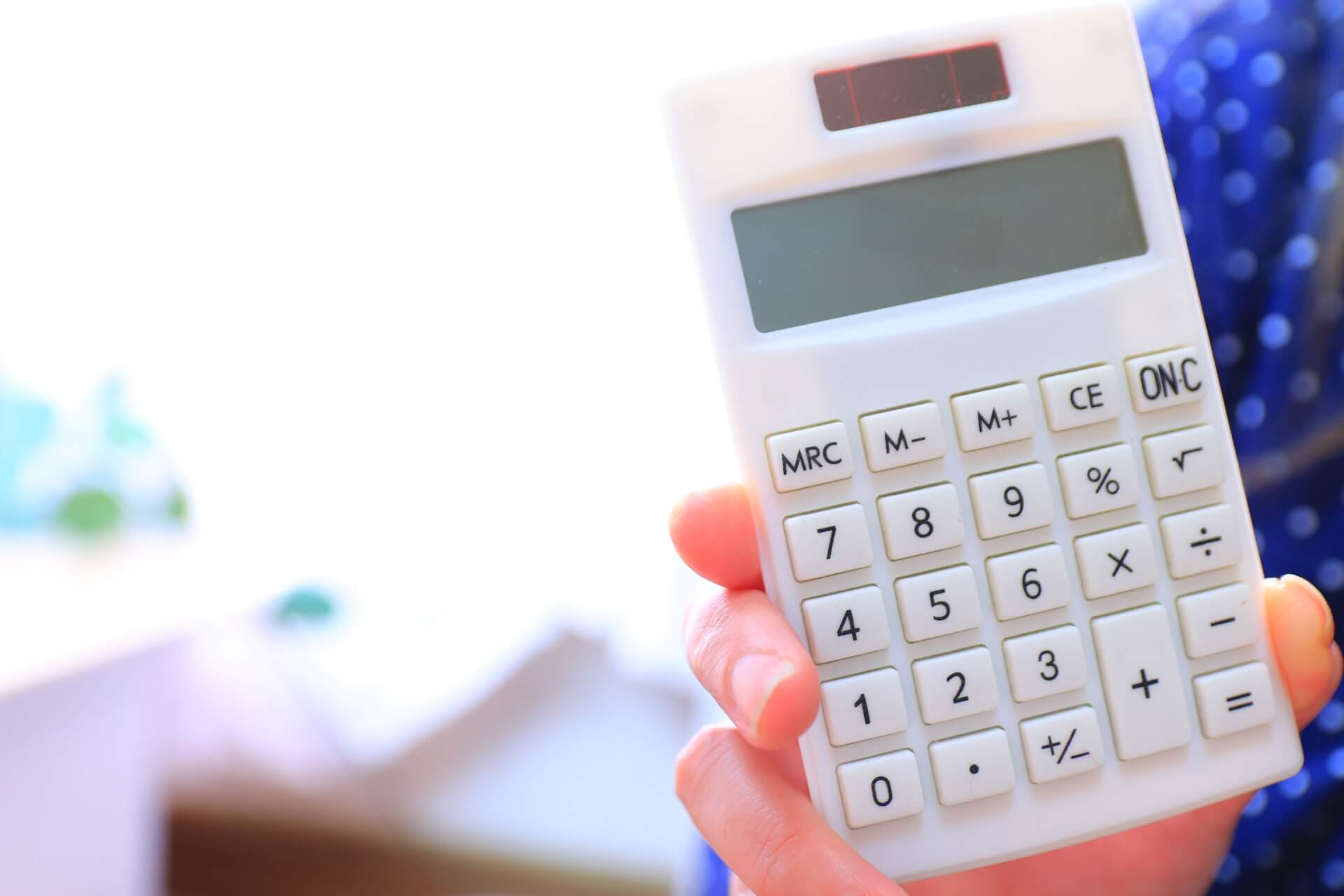 マンション経営の収入はどのくらい?収入を増やすためのポイントとは詳しく見る
マンション経営の収入はどのくらい?収入を増やすためのポイントとは詳しく見る「不動産投資に興味がある」「老後の蓄えとして残したい」「余っている土地を活用したい」など、マンション経営に取り組む理由は人によってさまざまです。マンションやアパートといった不動産を運用する場合、毎月安定した家賃収入が得られるイメージを持つ方は多くいるでしょう。特に、マンション経営は比較的安定した収益を確保できるという特徴があります。 マンション経営で得られる収入は家賃だけではありません。入居者様から受け取る礼金や更新料なども収益に含まれます。一方、収入だけではなく税金や経費といった支出も発生するため、収入・支出の内訳を把握しておくことが重要です。そこでこの記事では、マンション経営における収入と支出について解説します。記事の後半では収入を増やすためのポイントや、マンション経営によるリスクと対策も紹介します。
-
 売りアパートは480万円で購入できる?調べ方や購入費用やメリットなども解説詳しく見る
売りアパートは480万円で購入できる?調べ方や購入費用やメリットなども解説詳しく見る節税したい、老後資金に備えたいなどの理由から売りアパートを購入してアパート経営を始める人が増えています。しかし、売りアパートの購入にはどんな費用がかかるのか、何を基準に売りアパートを選ぶのか分からない方も多いでしょう。 本記事では、売りアパートの調べ方や購入費用、そのメリットや注意点、アパート経営の平均利回りなどを解説します。
-
 サブリース契約は後悔する?やめとけといわれる理由とは?詳しく見る
サブリース契約は後悔する?やめとけといわれる理由とは?詳しく見る不動産を所有するオーナー様の中には、賃貸経営としてサブリース契約を考える方もいるでしょう。しかし、「サブリースでどのように収入が得られるのかわからない」「サブリースはやめた方がいいと言われた」「サブリースの問題点が気になる」など、あまり良い印象を持てない方もいるかもしれません。 不動産の運用は、正しい情報を正確に把握することが大切です。不動産のサブリース契約は本当に後悔するものなのか、サブリースの概要をまとめつつ、「危ない」といわれる理由や事例を解説します。
タウングループ不動産仲介・周辺事業- 賃貸不動産仲介(東京・神奈川・埼玉・千葉) タウンハウジング
- 賃貸不動産仲介(東海) タウンハウジング東海
- 賃貸不動産仲介(九州) タウンハウジング福岡
- 土地・建物の不動産販売及び仲介 タウン住宅販売
- 首都圏を中心に引越サービスを展開 タウン引越サービス
- 賃貸不動産仲介(東北) タウンハウジング東北
- 賃貸不動産仲介(北関東) タウンハウジング北関東
建築事業- 賃貸住宅の企画・設計・施工 アヴェントハウス
多角化事業- 都内を中心に飲食店を運営 タウンダイニング
- インドアテニススクール タウンインドアテニスアカデミー


 一覧へ戻る
一覧へ戻る