不動産の売却時に税金がかからないケースとは?費用を抑える特例・控除を解説
不動産の売却時は仲介手数料や登記費用だけでなく、印紙税や登録免許税などの税金がかかるのが一般的です。しかし、場合によっては特例や控除を受けられる可能性があるため、結果として税負担が生じないケースも考えられます。
不動産を売却した際に税金がかからないケースとは、どのような状況を指すのでしょうか。本記事では、不動産の売却時に発生する税金や費用、節税につながる特例・控除や不動産売却で押さえておきたい節税のポイントなどを解説します。
-

不動産の売却時には、主に印紙税・登録免許税・消費税・譲渡所得税の4つの税金がかかります。手続きにかかるのが印紙税と登録免許税、仲介手数料や司法書士への依頼費用などにかかるのが消費税、売却益が出た時にかかるのが譲渡所得税です。
ここでは、どのような税金が不動産の売却で発生するのか、その内容や金額と併せて解説します。印紙税
印紙税とは、不動産取引で交わされる課税文書を作成した際に課税される税金です。印紙税法によって定められており、税額は契約金額によって変動します。
不動産の売却時に作成する代表的な文書が「不動産売買契約書」です。不動産売買契約書は印紙税の課税文書になるため、売却益の有無に関係なく収入印紙を貼付して納付する取り扱いになります。
なお、収入印紙は法務局や郵便局で全ての種類を購入可能です。使用頻度の高い200円の収入印紙においては、郵便切手類販売所・印紙売りさばき所であるコンビニや酒屋などで購入できます。
国税庁によると、不動産の譲渡に関する契約書の印紙税額は以下の通りです。
※平成26年4月1日~令和9年3月31日に作成された不動産の譲渡に関する契約書で、記載された契約金額が一定以上の場合は税率が軽減されます。契約金額 1通あたりの印紙税額 1万円未満 非課税 1万円以上10万円以下 200円 10万円以上50万円以下 400円 50万円以上100万円以下 1,000円 100万円以上500万円以下 2,000円 500万円以上1千万円以下 1万円 1,000万円以上5,000万円以下 2万円 5,000万円以上1億円以下 6万円 1億円以上5億円以下 10万円 5億円以上10億円以下 20万円 10億円以上50億円以下 40万円 50億円以上 60万円 契約金額の記載がない 200円 登録免許税
登録免許税とは、法務局で登記申請を行う時にかかる国税です。登録免許税を計算する際に用いる計算式は以下になります。
登録免許税=課税標準(固定資産税評価額)×税率2.0%
(令和8年3月31日までの間に登記を受ける場合は税率1.5%)
不動産を売却すると、所有権移転登記や抵当権抹消登記を行う必要があり、その際に登録免許税が課されるのが一般的です。登録免許税では、登記申請時に登録免許税と同額の収入印紙を申請書に添付して申請します。
抵当権抹消登記とは、抵当権を不動産登記簿から抹消する手続きです。抵当権は、お金を借りる際に借主が購入する不動産を担保として金融機関に設定する権利で、抹消しないと不動産の売却や金融機関からの借入が難しくなります。
抵当権抹消登記にかかる登録免許税は、抵当権抹消1件につき1,000円です。建物と土地で合計2件の抵当権を抹消する場合、納付しなければならない登録免許税は2,000円となります。
当事者間の合意によりますが、実務上は買主負担となるケースも見られます。消費税
消費税の課税対象になる条件は以下の4つです。
・国内取引である
・事業者が事業として行う取引である、
・対価を得る取引である
・資産の譲渡や貸付が行われる
個人間での不動産売買は事業に該当しないため、消費税が課されない取り扱いとなるのが一般的です。また、土地の売却は規模や売却金額にかかわらず消費税が非課税です。
ただし、不動産の売却に必要な費用にはそれぞれ消費税がかかるものもあります。具体的には、不動産会社に支払う仲介手数料や住宅ローンの一括返済手数料、登記申請を依頼する司法書士への報酬などです。特に、仲介手数料は負担が大きくなるケースもあるため、相対的に負担が増える可能性があります。譲渡所得税
譲渡所得税は「所得税」「住民税」「復興特別所得税」の総称です。不動産の売却時に発生した所得(利益)に課税されます。
譲渡所得税の計算式は以下の通りです。
譲渡所得税=譲渡所得×税率
譲渡所得=売却金額-取得費用-譲渡費用-特別控除額
譲渡所得は、不動産の売却金額から取得費取得費用や譲渡費用などを差し引いた金額となります。取得費用とは、土地の購入価格や購入時の税金、測量費などです。譲渡費用には、不動産会社に支払う仲介手数料や登録免許税、印紙税が含まれます。
また、譲渡所得は優遇措置や特例を受けられるケースもあり、定められた控除額を売却金額から差し引ける可能性があります。課税対象である譲渡所得は少ないほうが節税対策になるため、特例を適用できればより効果的な節税につながるでしょう。-
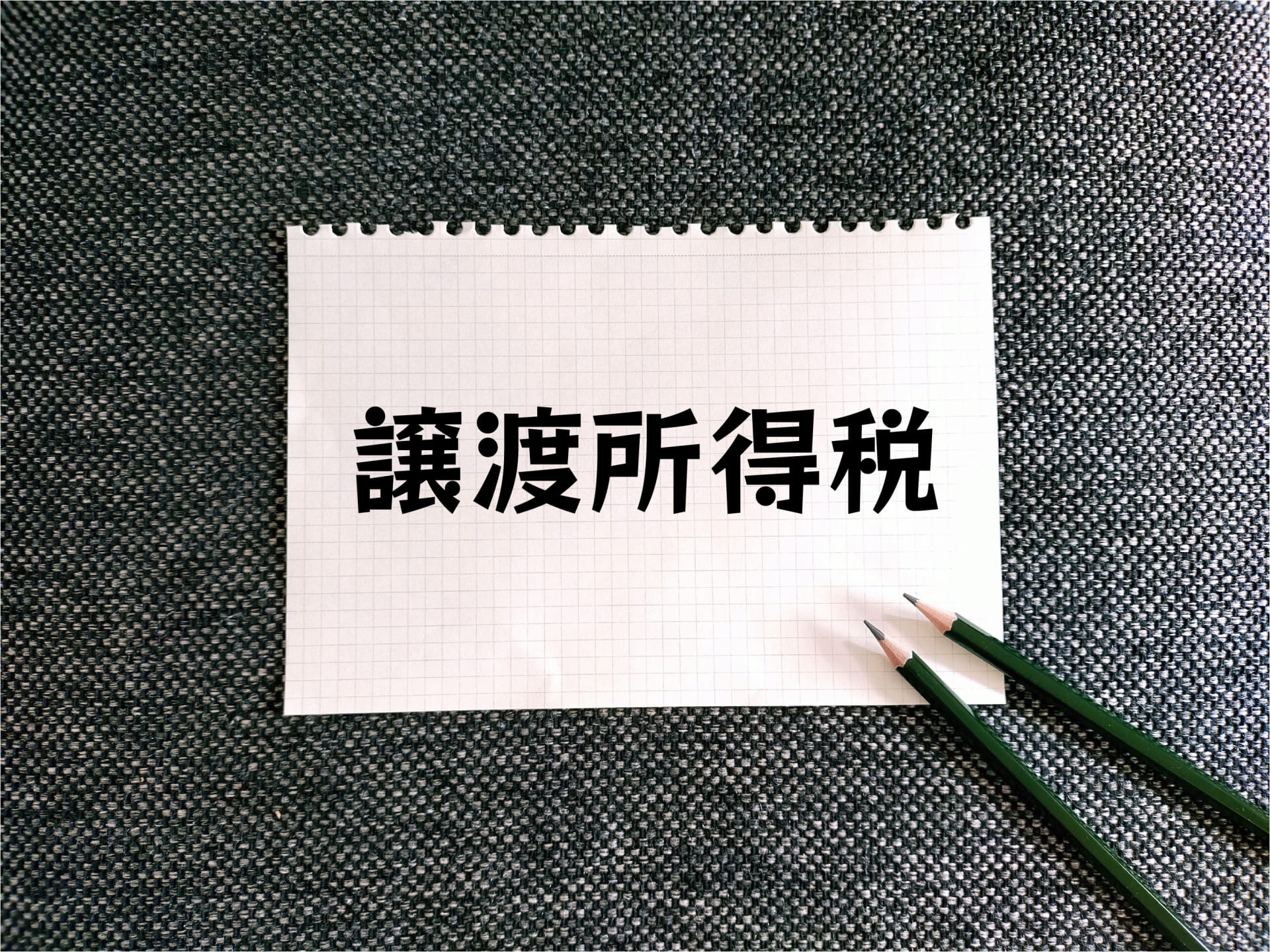
不動産を売却した時の譲渡所得税を求める際は、以下の流れで計算を進めるとよいでしょう。ここでは、譲渡所得税のシミュレーションとその納税方法を解説します。
1.譲渡所得の金額を計算する
まずは、先に述べた計算式に沿って譲渡所得の金額を求めましょう。
例えば、取得費用が3,500万円の不動産を4,000万円で売却し、200万円の譲渡費用がかかった場合の譲渡所得は以下のようになります。
収入金額:4,000万円
取得費用:3,500万円
譲渡費用:200万円
4,000万円-3,500万円-200万円=300万円
上記の計算式により譲渡所得は300万円となり、この金額が課税の対象となる計算です。
一方、譲渡所得がマイナスであれば譲渡所得税が発生しません。例えば、取得費用が3,800万円、売却金額が2,300万円、譲渡費用が100万円のケースでシミュレーションしてみましょう。
収入金額:2,300万円
取得費用:3,800万円
譲渡費用:100万円
2,300万円-3,800万円-100万円=-1,600万円
計算すると譲渡所得はマイナスとなるため、このケースで譲渡所得税は発生しません。2.要件を満たしていれば特例を適用して控除する
優遇措置や特例を受けることで、控除が適用されます。控除によって譲渡所得が0円になれば、譲渡所得税は課税されない取り扱いとなることがあります。ただし、控除を適用するには要件を満たしたうえで、確定申告が必要です。
例えば、取得費用が4,000万円の不動産を4,600万円で売却し、譲渡費用に250万円かかったとすると、譲渡所得は350万円です。しかし、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」を適用できれば、譲渡所得から最高3,000万円を控除できます。
収入金額:4,600万円
取得費用:4,000万円
譲渡費用:250万円
特別控除の特例:3,000万円
4,600万円-4,000万円-250万円-3,000万円=-2,650万円
特例を適用できれば譲渡所得がマイナスとなるため、譲渡所得税が生じない可能性があります。3.税額を計算する
特例を適用しても譲渡所得が発生すると、譲渡所得税がかかります。国税庁によると譲渡所得にかかる税率はそれぞれ以下の通りです。
※表内の復興特別所得税は所得税に対して2.1%をかけたものです。区分 所得税 住民税 復興特別所得税 合計 長期譲渡所得 15% 5% 0.315% 20.315% 短期譲渡所得 30% 9% 0.63% 39.63%
税率は不動産の所有期間によって異なり、譲渡した年の1月1日から数えて所有期間が5年を超えると長期譲渡所得、5年以下は短期譲渡所得となります。例えば、2025年中に譲渡した場合、不動産取得日が2019年12月31日以前であれば長期譲渡所得、2020年1月1日以降であれば短期譲渡所得です。
短期譲渡所得は長期譲渡所得に比べて税率が19.315%高いため、長期保有の方が税率面で有利になる傾向があります。
例えば、譲渡所得が1,000万円だった場合の所有期間別の譲渡所得税を計算してみましょう。長期譲渡所得は約203万円なのに対し、短期譲渡所得は約396万円と200万円近く税額が高くなっています。
長期譲渡所得:1,000万円×20.315%=203万1,500円
短期譲渡所得:1,000万円×39.63%=396万3,000円譲渡所得税を納税するには確定申告が必要
確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に発生した所得と、それに対する所得税を計算して確定させる手続きです。申告期間は毎年2月16日〜3月15日までとなっていますが、土日・祝日の都合で期限が繰り下がる場合もあります。
通常、会社員であれば給与所得の確定申告は会社側が行ってくれますが、譲渡所得が発生すると不動産を売却した翌年に確定申告を行わなければなりません。一方、譲渡所得が発生しなかった時は申告が不要となるケースもあります。ただし、損失が発生しても優遇措置や特例を利用する場合は確定申告が必要です。
譲渡所得税を納税するための確定申告は、譲渡所得を算出して必要書類を準備し、申告書を作成する流れが基本となります。申告書は管轄の税務署に持参・郵送する、またはe-Taxで送信して提出する方法も広く用いられています。また、特別控除の特例を利用するのであれば控除を受けるために必要な書類を確定申告書に添付して申請します。
確定申告の際に必要な書類
確定申告書第一表・第二表
確定申告書第三表(分離課税用)
不動産売買契約書
登記事項証明書
譲渡所得内訳書
領収書-

では、不動産を売却した際どのようなケースだと税金がかからないのでしょうか。ここでは、3パターンを解説します。
売却しても利益が出ない
不動産を売却しても、利益が出ずに損失が残る場合もあります。譲渡所得は不動産の譲渡によって得た利益であり、譲渡所得がマイナスになると課税対象が存在しないため、譲渡所得税は発生しません。なお、譲渡所得がマイナスの状態を「譲渡損失」と呼びます。
控除や特例を利用する
要件を満たすことで、不動産の売却時に控除や特例を適用できます。「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」や「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」などが代表的です。
例えば、居住用財産の3,000万円の特別控除を適用できれば、所有期間に関係なく譲渡所得から最高3,000万円を控除できます。そのため、譲渡所得が3,000万円以下であれば譲渡所得税がかからないかもしれません。
税金を抑えられる可能性がある特例・控除に関しては、別の項目で詳しく解説します。電子契約であれば印紙税はかからない
一般的に不動産売却では印紙税がかかりますが、電子契約であれば印紙税は発生しません。これは印紙税の課税対象が紙の書面による課税文書のみであり、電磁的記録は課税文書に該当しないためです。これにより、収入印紙の購入も不要になります。
なお、不動産売買ではこれまで紙の契約書によって契約が進められていましたが、2022年5月の宅地建物取引業法改正により、電子契約が可能になりました。-

ここでは、節税につながる可能性がある、5つの特例や控除を紹介します。特例や控除を活用することで節税につながりますが、それぞれ要件は異なるため、売却の前に調べておくと安心です。
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」
マイホームを売却する際、要件を満たせば「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例(マイホームを売ったときの特例)」を適用できます。
この特例は売却する不動産(土地)にマイホームがあれば、最高3,000万円の特別控除を受けられるというものです。売却によって得た利益が3,000万円以下の時に利用すれば、譲渡所得が0円となります。共有名義であれば、名義人全員でそれぞれ3,000万円の特別控除を適用可能です。
国税庁によると、以下の要件に全て該当すれば特例の適用を受けられます。
1.売った資産が以下のいずれかに該当する
a.現在自分が住んでいる家屋
b.現在住んでいない家屋で、住まなくなった日から3年目の12月31日までに売却した
c.上記a・bの家屋とともに売却した土地や借地権
d.上記aの家屋が災害により滅失した土地で、災害があった日から3年目の12月31日までに売却した
e.上記bの家屋が災害により滅失した土地で、住まなくなった日から3年目の12月31日までに売却した
f.上記a・bの家屋を取り壊して売却された土地で、取り壊した日から1年以内に譲渡契約を締結し、かつ住まなくなった日から3年目の12月31日までに売却した。また、その日まで土地をその他の目的で利用していない
2.配偶者や親子など、特別な関係にある相手に譲渡していない
3.売却してから2年以内にこの特例を受けていない、かつ「マイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例」を適用していない
4.「特定居住用財産の買換えの特例」や「収用等により土地建物を売ったときの特例」など、他の特例を適用していない
また、売却した年の1月1日から数えて所有期間が10年を超えているマイホームを売却すると、「マイホームを売ったときの軽減税率の特例」との併用も可能です。この特例では、6,000万円以下の部分に通常より低い14.21%の税率が適用されます。「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」
売却する土地にマイホームがあり、土地と家屋を相続で取得した場合、要件を満たすと「被相続人の居住用財産(空き家)を売った時の特例」を受けられます。これは、令和9年12月31日までに空き家を売却すると、最高3,000万円の特別控除を適用できる特例です。
売却によって得た利益が3,000万円以下の時に利用すれば、譲渡所得が0円となります。共有名義であれば、名義人それぞれで3,000万円の特別控除を適用可能です。なお、令和6年1月1日以降の相続において、家屋や土地を取得した相続人が3人以上いる場合、控除額は最大2,000万円となります。
国税庁によると、特例を適用するための要件は以下の通りです。
1.昭和56年5月31日以前に建築された家屋である
2.相続が始まる直前まで被相続人(故人)しか居住していなかった
3.相続した日から3年目の12月31日までに売却する
4.売却金額が1億円以下
5.配偶者や親子、内縁関係にある人、特殊な関係にある法人などに譲渡していない
6.相続から売却まで、家屋や敷地を居住・事業・賃貸として利用していない
7.同一の被相続人から相続・遺贈した別の家屋や敷地に対し、この特例を適用していない
8.売却時に家屋を取り壊すこと、取り壊さない場合は一定の耐震基準を満たしていること
9.家屋が区分所有建物登記されていない
10.他の譲渡所得の特例を受けていない「特定居住用財産の買換え特例」
新たにマイホームを購入した際は「特定の居住用財産の買換え特例」を利用できます。これは売却益にかかる税金を繰り延べられる特例です。
例えば、3,000万円で購入した家屋を5,000万円で売却すると、2,000万円の譲渡所得を得られます。その後、新しく購入した住宅が2,000万円以上なら、売却した分の譲渡所得は全額繰り延べることができ、売却したタイミングでは課税されなくなります。
ただし、新しく購入した住宅を売却した時には、その売却益に繰り延べた2,000万円も加えて譲渡所得税がかかってくるため、非課税になるわけではありません。そこで、買換え特例を適用できれば購入した住宅を売却する時まで売却益にかかる税金を繰り延べられるため、売却代金をそのまま購入資金として使用できます。
国税庁によると、特例を適用するための要件は以下の通りです。
1.令和7年12月31日までにマイホームを売却した
2.売却した家屋と買い換えた家屋は日本国内にある
3.売却金額が1億円以下
4.売却する家屋は以下のいずれかに当てはまる資産で居住期間が10年以上かつ、売却した年の1月1日において家屋と敷地の所有期間10年以上である
a.現在自分が住んでいる家屋
b.現在住んでいない家屋で、住まなくなった日から3年目の12月31日までに売却した
c.上記a・bの土地や借地権
d.上記a・bの家屋を取り壊した場合の家屋・土地で、取り壊してから1年以内に譲渡契約を締結し、かつ住まなくなった日から3年目の12月31日までに売却した。また、取り壊してから譲渡契約を締結するまでその土地をその他の目的で利用していない。
e.上記aの家屋が災害により滅失した土地で、災害があった日から3年目の12月31日までに売却した
f.上記bの家屋が災害により滅失した土地で、住まなくなった日から3年目の12月31日までに売却した
5.家屋を売却した年の前年から翌年までの3年の間にマイホームを買い換える。また、売った年・その前年に取得した場合は売った年の翌年12月31日、売った年の翌年に取得した場合はその年の翌年12月31日までに住む。
6.配偶者や親子、内縁関係など特別な関係にある人に売却していない
7.買い換えた家屋が一定の省エネ基準を満たしている(令和5年12月31日以前に建築確認を受けた、または令和6年6月30日以前に建築された家屋は例外)「収用等により土地建物を売ったときの特例」
土地収用法や法律で収用権が認められている公共事業のために家屋や土地を売却すると、課税の特例を受けられるケースがあります。
国税庁によると「収用等により土地建物を売ったときの特例」として適用できるものは以下の2つです。
「対価補償金等で他の土地建物に買い換えたときは譲渡がなかったものとする特例」
「収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例」とも呼びます。売却した金額よりも買い換えた金額のほうが多い場合、所得税の課税が繰り延べられ、売却した年には譲渡所得がなかったものとする特例です。売却した金額よりも買い換えた金額のほうが少ない時は、その差額を収入として譲渡所得を計算します。
適用要件は以下の通りです。
1.売却した家屋や土地が固定資産である
2.売却した資産と同じ種類の資産を買い換える(土地と土地、建物と建物など)
3.原則として土地建物の収用等があった年の翌年1月1日から2年以内に代わりの資産を取得する
「譲渡所得から最高5,000万円までの特別控除を差し引く特例」
公共事業のために土地・建物を売却した時に、譲渡所得から最高5,000万円を控除できる特例です。
適用要件として、以下の条件が挙げられます。
1.売却した家屋や土地が固定資産である
2.その年に公共事業のために売却した資産の全てについて、「収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例」の適用を受けていない
3.最初に買取の申出があった日から、6か月目までに家屋や土地を売却した
4.事業施行者から最初に買取の申し出を受けた者が譲渡している、または申し出を受けた者が亡くなっている場合はその土地を相続した人が譲渡している「平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除」
平成21〜22年の間に土地を取得している場合、要件を満たせば利用できる特例です。平成21年に取得した土地は平成27年以降に、平成22年に取得した土地は平成28年以降に売却することで、1,000万円の特別控除を受けられます。
国税庁によると、特例を適用するための要件は以下の通りです。
1.配偶者や親子、内縁関係にある人、特殊な関係にある法人などから取得した土地ではない
2.他の譲渡所得の特例を受けていない
3.相続・遺贈・贈与・交換などによって取得した土地ではない-

不動産の売却では取引価格が高額になるため、節税できるポイントを押さえておくことが大切です。特例の要件を満たせば、数百万円の節税につながるかもしれません。
譲渡費用は漏れがないように計上する
不動産の譲渡時に発生した費用は、必要経費として差し引けます。高額になる可能性もあるため、漏れがないように経費として計上しましょう。
主な譲渡費用
売却時に必要な仲介手数料や印紙税
建物を取り壊した場合の費用
測量費
借家人に支払った立退料
名義書換料(譲渡承諾料)
売却に要した交通費
また、譲渡費用と併せて取得費用も計上しましょう。不動産売買契約書や売買代金の領収書など、証明書類があれば取得価額がわかります。売却の予定がないと書類を残していなかったり相続で取得したりしていて正確な取得費用がわからない場合、売却価格の5%を概算取得費として計上可能です。ただし、この場合の取得費用は実際よりも下回るケースがほとんどのため、証明書類の保管は徹底することをおすすめします。利用可能な特例・控除は全て活用する
不動産の売却時に利用できる特例や控除を最大限に活用することで、税金の負担を大きく軽減できます。適用できる特例は売却した不動産の種類や用途などで異なるため、それぞれの制度を確認することが重要です。
中には、併用できない特例や控除もあります。複数の制度で適用要件を満たしている場合は、より節税効果の高い制度を選ぶとよいでしょう。売却のタイミングを見極める
譲渡所得税の税率は、売却する不動産の所有年数によって変わります。税率は、所有期間5年未満の短期譲渡所得が39.63%、所有期間5年超の長期譲渡所得が20.315%です。
両者を比較すると、短期譲渡所得の税率は長期譲渡所得より2倍近く高くなっています。例えば、譲渡所得が1,000万円の場合、長期譲渡所得では約200万円となりますが、短期譲渡所得では約390万円となります。
そのため、所有期間が5年に近い不動産を持っている場合は、税額も含めて売却タイミングを見極めることが重要です。所有期間は売却した年の1月1日を基準に数えられるため、数え間違えないようにしましょう。
また、所有期間が10年を超えているマイホームを売却する場合はさらに税率が軽減されます。課税譲渡所得にかかる所得税率が5%、住民税率が1%軽減されますが、6,000万円を超える部分には軽減税率が適用されません。
ただし、建物は基本的に築年数が経過するにつれて価値が下がっていきます。そのため、税金面だけでなく不動産の価値も考慮して売却を検討することが重要です。不動産会社に相談する
不動産売却で節税につながる特例や控除は、自動で適用されず、自身で申告しなければなりません。しかし、状況によって適用できる特例や控除は異なることから、税金対策を調べるのが難しいと感じる方もいるでしょう。
その場合は専門家である不動産会社や税理士に相談すると、状況に適した税金対策を提案してもらえる可能性があります。-

不動産売却で税金がかからないと判断しても、条件を見落としてしまっているかもしれません。ここでは、不動産売却で税金がかからないケースで注意しておくべきポイントを解説します。
本当に税金がかからないか確認が必要
損益通算の有無も調べて、本当に税金がかからないかどうか確認しましょう。損益通算とは、事業や投資などで発生した損失を、別の利益と相殺して税金の支払いを減らす仕組みです。
マンション・アパートの家賃収入や敷金・礼金などは不動産所得に該当し、不動産所得は給与所得や事業所得など他の所得と損益通算できます。
一方、不動産の譲渡所得は分離課税であり、原則として他の所得と損益通算はできません。損益通算できない費用を計算に含めると税金がかからないと勘違いする恐れがあるため、不安な点がある場合は税理士や税務署などに相談しましょう。控除によって税金がかからない時でも申告する
税金がかかるかどうかにかかわらず、控除や特例の適用を受けるには確定申告が必要です。確定申告を通して特例や控除の適用を受け、適用要件を満たしていることを証明しなければ特例や控除は適用されません。
期限内に確定申告をしないと控除・特例の適用を受ける権利を失い、本来の税金を納めなければならなくなります。場合によっては、無申告加算税や延滞税がかかるかもしれません。
確定申告を正確に行うためにも、不明な点がある場合は税務の専門家に相談しましょう。特例が適用できる条件や期限を確認してから申請する
不動産売却に関する特例や控除には、それぞれ適用要件や売却の期限、所有年数や併用の可否などが詳細に決められています。例えば、マイホームの売却時に利用できる制度には「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」や「特定居住用財産の買換え特例」などがあります。適用要件を誤ったり期限を過ぎたりすると、特例や控除が適用できなくなってしまうため、しっかりと条件や期限を確認してから申請しましょう。
-

不動産の売却時には税金だけでなく、仲介手数料や登記・抵当権抹消費用などの費用も発生します。ここでは、不動産の売却時に発生する税金以外の費用を解説します。
仲介手数料
仲介手数料とは、不動産売買の契約が成立した後に仲介した不動産会社に対して支払う報酬を指します。不動産売却でかかる費用の中では、高額になりやすいのが特徴です。
宅地建物取引業法により、売却金額に応じて上限額が定められています。
200万円以下:(売却金額×5%)+消費税10%
200万円超400万円以下:(売却金額×4%+2万円)+消費税10%
400万円超:(売却金額×3%+6万円)+消費税10%登記・抵当権抹消費用
登記・抵当権抹消費用とは、不動産についている抵当権を法的に抹消するための登記にかかる費用です。抵当権は住宅ローンを借りる際に金融機関が借りた人の不動産を担保として設定する権利で、抵当権が残っていると不動産の売却や金融機関からの借入が難しくなります。
ローンを完済すれば抵当権は実質的になくなりますが、登記簿上の抵当権は自動的に消えないため、売却する際は抹消手続きが必要です。
登記方法によって費用は異なりますが、不動産1件につき1,000円となっています。家屋と土地に抵当権が設定されている場合、2件合わせて2,000円です。住宅ローンの返済手数料
不動産を売却する際は、抵当権を抹消するためにローンを完済する必要があります。住宅ローンが残っている場合、売却代金で残っているローンを一括で返済するのが一般的です。一括で返済する際は、繰り上げ返済手数料や一括返済手数料と呼ばれる費用がかかります。
金融機関によって異なりますが、手数料は3万~5万円程度が相場です。引っ越し代
マイホームを売却する場合、物件の引き渡し日までに新居へ引っ越す必要があります。引っ越し代は荷物の量や移動距離、引っ越し時期によって変わるため、計画的に準備を進めることが重要です。
ハウスクリーニング代
不動産を売却する際、物件の印象を良くするためにハウスクリーニングを利用する方もいるでしょう。物件の種類や間取りや汚れ具合によって、ハウスクリーニング代の相場は変わります。部屋が広いほどコストはかかりますが、空室だとスムーズに作業がしやすいため、コストが抑えられる場合があります。費用を抑えたい場合は物件全体を依頼するのではなく、自分では掃除が難しい水回りや換気扇など汚れが目立つ場所に絞って依頼すると費用を抑えられます。
測量費用
不動産売買において、売主は買主に対して土地の境界を明示する義務があります。登記簿に記載されている土地の面積は、実際の面積と異なる場合も少なくありません。そのため、土地または家屋と土地を売却する場合、事前に土地の面積と境界線の測量が必要です。
売却時に行われる主な測量として土地の形状・面積・高低差を現況のまま図面化する現況測量と、関係者の立ち会いのもと土地の境界を確定する確定測量があります。100平方メートルあたりの相場は現況測量が10万~20万円、確定測量が35万~90万円です。土地の面積が広い場合や形状が複雑な場合、隣接する土地が多い場合や公有地と隣接している場合は費用が高くなります。解体費用
家屋を解体して土地を売却する場合、解体費用がかかります。1坪あたりの解体費用の相場は木造が2万~4万円、軽量鉄骨造が4万~6万円、鉄筋コンクリート造が5万~7万円といわれます。解体する物件に面した道路が狭かったり隣家との距離が近かったりすると、費用が高くなる傾向です。
各種書類の発行費用
不動産を売却するには、必要書類を用意する必要があります。具体的には、住民票や登記簿謄本、固定資産税評価証明書や測量図などです。一般的に、これらの書類を発行する際は数百円程度の費用が発生します。なお、住民票や固定資産税評価証明書は市区町村役場、登記簿謄本や測量図は法務局から入手可能です。
司法書士への報酬
所有権移転登記や抵当権の抹消登記などの手続きは専門性が高く複雑なため、基本的に司法書士に依頼します。司法書士への報酬は手続内容により数万円程度となることがあります。また、司法書士への報酬には消費税も課税されます。
-

不動産売却で発生する手数料や費用などをうまく抑えられれば、費用を安くできます。ここでは、不動産売却でかかる費用を抑えるコツを紹介しましょう。
仲介では良質な不動産会社に依頼する
不動産売却では大きな金額がかかる分、仲介手数料も高額になるため、良質な不動産会社に依頼する必要があります。良質な不動産会社に依頼すれば、売却価格が高くなり手元に残る金額が多くなるでしょう。不動産会社を見極めるポイントとして、相場に適した査定価格を提示してくれる、不動産売却において実績や得意分野がある、丁寧に対応してくれるなどが挙げられます。
複数社に査定を依頼する
複数の不動産会社に査定を依頼することで、各社が提示する費用や手数料を比較でき、より安価な不動産会社に依頼が可能です。また、相場価格から大幅に外れている金額を提示する不動産会社も避けられます。一括査定サービスを利用すれば物件情報を一度入力するだけでまとめて査定を依頼できるため、手間を省きたい方におすすめです。
ハウスクリーニングは複数業者に見積もりを依頼する
売却物件をハウスクリーニングする場合は、複数業者に見積もりを依頼することで、安価な依頼先を見つけられます。サービス内容や品質も比較できる、適正な費用相場がわかる点もメリットです。
なお、ハウスクリーニングは掃除箇所によって費用は細かく分かれます。正確に比較するためには、全ての業者に清掃範囲を同じように伝え、見積もりの具体的な内訳を確認することが重要です。費用は売却価格の5%を目安にする
発生する費用は、売却価格の5%程度を目安にしましょう。これは仲介手数料の上限が売買価格の3~5%と定められており、印紙税や登記費用などを加えると売却価格の約5%に収まるケースが多いためです。この基準を持つことで、適切な売却判断や資金計画の策定ができます。ただし、多額の売却益が出た場合や測量・解体が必要な場合は5%を大きく超えるケースも少なくありません。そのため、不動産会社に発生すると思われる費用とその概算を教えてもらうことが重要です。
資金は余裕を持って準備しておく
不動産売却にかかる諸費用の多くは、売却代金を受け取るより前に支払う必要があります。手元に資金がないと売却が滞ってしまう恐れがあるため、売却のための資金は余裕を持って準備しておきましょう。また、自治体が行っている補助金制度がある場合は利用するのもおすすめです。
-

ここでは、不動産売却の流れを解説します。不動産会社に査定してもらい、募集価格を決定して媒介契約を結んだ後、売却活動が始まります。
1.不動産会社に相談し査定を依頼する
売却したい不動産について、不動産会社に相談・査定を依頼します。査定は不動産会社に問い合わせたり不動産査定サイトから一括査定を申し込んだりして依頼するのが一般的です。
査定を依頼する際は、少なくとも2〜4社から見積もりを取るとよいでしょう。比較するだけでなく、見積もりの相場把握にもなります。2.募集価格を決定する
売却する不動産の募集価格も決めましょう。いつまでに売りたいか、最終的にいくら手元に残したいかなど希望条件を整理することで、具体的な募集価格を決められます。不動産の中でも、土地は取引時期や相場の動きによって価格が変動しやすい傾向です。
なお、募集価格はあくまで売主の希望額であり、必ずしも成約価格と同じになるとは限りません。特に、中古不動産の売買では価格交渉が行われやすく、募集価格の5~10%程度値引きされる傾向があります。そのため、買主からの価格交渉を想定して査定価格に少し上乗せした価格で売り出すのも一つの戦略です。3.不動産会社と媒介契約を結ぶ
不動産会社を決めたら、不動産会社と媒介契約を結びます。媒介契約とは、不動産会社に物件の売却に向けて活動するように依頼する契約です。媒介契約には、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があります。
また、売却に必要な書類も用意しておきましょう。主な必要書類は身分証明書や登記事項証明書や敷地測量図、購入時の売買契約書やローン残高証明書などです。4.売却活動を始める
媒介契約後は、不動産会社が仲介・主導して売却活動を開始します。希望者からの問い合わせがあれば、物件の説明や案内を行いますが、仲介する不動産会社に任せても問題はありません。通例では、仲介会社が主導し、売主が同席する場合もあります。
なお、専任媒介契約・専属専任媒介契約を結んでいる場合、不動産会社から定期的にオーナー様へ売却活動の報告が来ます。そのため、売却活動がどの程度進んでいるのか把握できるでしょう。5.買主と売買契約を結ぶ
買主が決定したら、不動産売買契約を結びます。当事者である売主と買主が顔合わせした後、宅地建物取引士による重要事項説明が行われるのが基本的な流れです。不動産会社が作成した売買契約書の内容に双方が合意したら署名・捺印を行います。その際、契約締結の証として売買価格の5~10%程度の手付金が払われるのが一般的です。また、不動産会社に仲介手数料の半金もこの時に支払います。
6.不動産の引き渡し・決済を行う
契約を結んだ後は、契約時に決定した日程で引き渡しが行われます。所有権移転登記に必要な書類が全てそろっているか、内容に不備がないか確認し、完了したら売却金額を受け取りましょう。住宅ローンが残っている場合は、融資先の金融機関での一括返済が必要です。完済したら、決済の前に抵当権の抹消準備も行います。
7.不動産売却後に確定申告を行う
売却によって得た利益にかかる税金を納付するため、税務署で確定申告を行わなければなりません。利益が出なかった・損失が出た場合でも、特例を利用する場合は確定申告が必要です。
確定申告は、不動産を売却した翌年の2月16日から3月15日までに行わなければなりません。確定申告書や譲渡所得の内訳書など、必要書類も用意しましょう。確定申告を終えたら、不動産売却は完了です。-

不動産売却では、仲介手数料や諸費用の他に印紙税・登録免許税・消費税・譲渡所得税といった税金が発生します。しかし、売却しても利益が出ない場合や電子契約の場合、一部の税金は発生しません。
また、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」や「特定居住用財産の買換え特例」などを利用すれば税負担の軽減につながる可能性があります。節税を検討される場合は、どういった特例・控除が適用できるのか、適用要件を確認しておくと安心です。関連記事
-
 マンションの相続税がかからないケースは?特例や控除の考え方も解説詳しく見る
マンションの相続税がかからないケースは?特例や控除の考え方も解説詳しく見るマンションなどの不動産の相続が発生した際に、悩まれる方も多いでしょう。なかには「多額な相続税の支払いが必要なのでは」と不安になる方もいるかもしれません。ただし、マンションのなかには、相続の際に相続税がかからないケースがあります。高額なマンションの相続なのに、相続税がかからないのはなぜなのでしょうか。 そこで、この記事ではマンションの相続税がかからない場合の考え方について詳しく解説します。実際に例を挙げて相続税を計算しながら、マンションの相続について整理しましょう。 しかし、所有している土地でアパート経営を始めるには、いくつかのリスクがあることも覚えておきましょう。それぞれのリスク回避のために適切な対策を行って、効率的な土地活用を行いましょう。 この記事では、土地有りでアパート経営を行うメリット・デメリットについて、そして経営を進める時の流れや必要な資金などについて解説します。
-
 オーナーチェンジ物件をなぜ売るのか?購入時は売却理由に注意しよう詳しく見る
オーナーチェンジ物件をなぜ売るのか?購入時は売却理由に注意しよう詳しく見る収益が出ているにもかかわらず、売りに出されている物件を見ると「何か物件に問題があるのでは」と疑ってしまうこともあるでしょう。しかし、オーナーチェンジ物件の売却理由はさまざまで、理由によって購入しても問題がない物件と、注意が必要な物件に分類されるのです。 この記事では、オーナーチェンジ物件について解説し、問題のない売却理由と注意が必要な売却理由を紹介します。さらに、オーナーチェンジ物件を購入するメリットとデメリット、起こりうるトラブル、購入する際に確認したいポイントについても詳しく解説します。
-
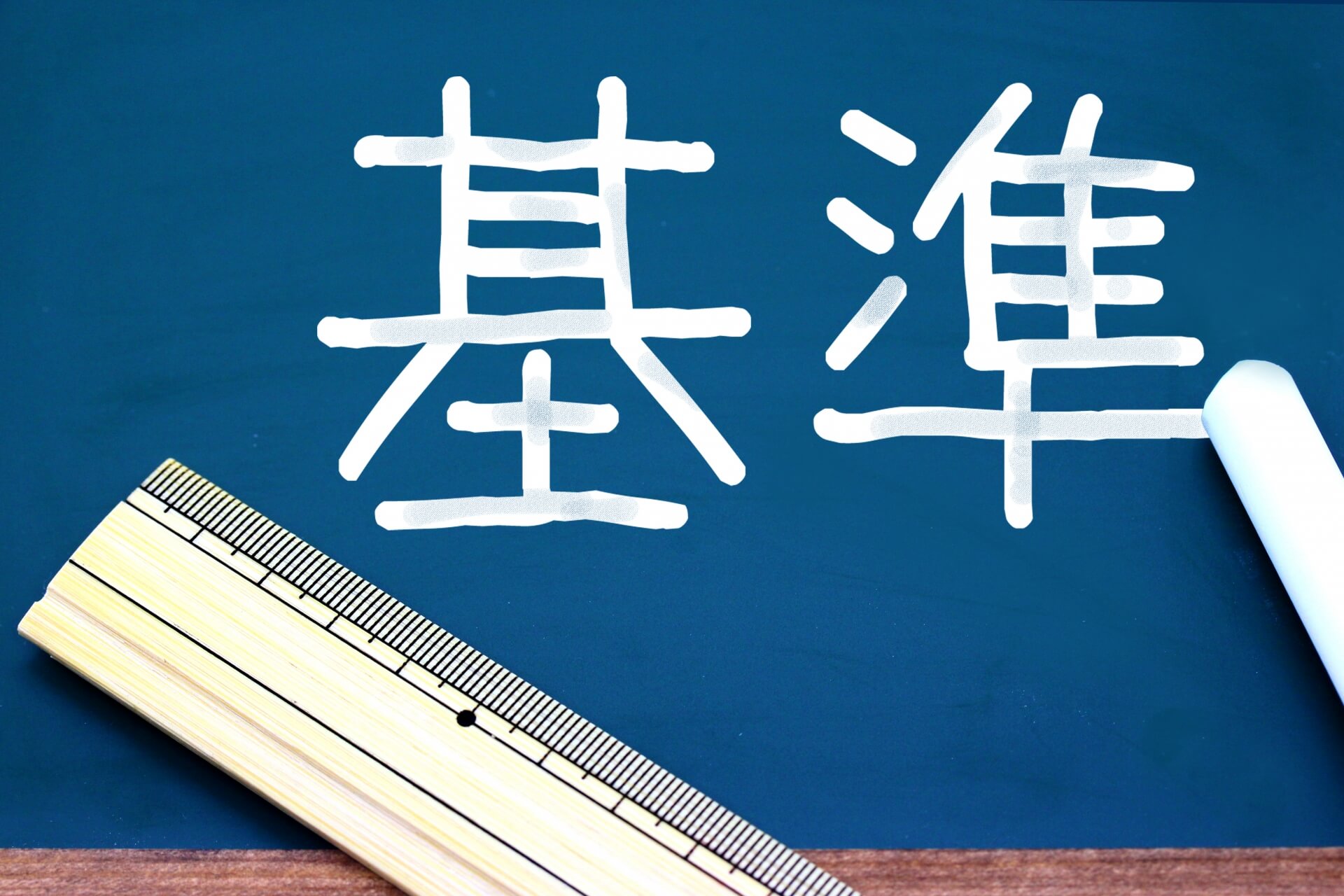 マンション経営が儲からないとされる理由とは?効果的な対策方法も紹介詳しく見る
マンション経営が儲からないとされる理由とは?効果的な対策方法も紹介詳しく見るマンション経営は安定した収入を得られるというメリットがあり、利益獲得に優れた投資手段です。しかし、経営に成功するオーナー様がいる一方で失敗してしまうケースも多いため、「マンション経営は儲からない」ともいわれているのです。 この記事では、なぜマンション経営が儲からないとされているのか、その理由を解説しています。併せて、マンション経営を成功させるためのポイントも紹介します。
タウングループ不動産仲介・周辺事業- 賃貸不動産仲介(東京・神奈川・埼玉・千葉) タウンハウジング
- 賃貸不動産仲介(東海) タウンハウジング東海
- 賃貸不動産仲介(九州) タウンハウジング福岡
- 土地・建物の不動産販売及び仲介 タウン住宅販売
- 首都圏を中心に引越サービスを展開 タウン引越サービス
- 賃貸不動産仲介(東北) タウンハウジング東北
- 賃貸不動産仲介(北関東) タウンハウジング北関東
建築事業- 賃貸住宅の企画・設計・施工 アヴェントハウス
多角化事業- 都内を中心に飲食店を運営 タウンダイニング
- インドアテニススクール タウンインドアテニスアカデミー


 一覧へ戻る
一覧へ戻る