不動産利回りの相場は?10パーセントや20パーセントは高い?
広告や物件資料などで「利回り10%」「利回り20%」などの物件を目にして、「なぜこんなに高いのか」「裏があるのではないか」と思った方も多いでしょう。利回り10%・20%は相場よりも高いですが、実際の利回りは掲載されている利回りより下がることがほとんどです。
本記事では、不動産投資の利回りの概要や相場、高利回りの不動産のリスクや探し方を解説します。
-

利回りとは、投資元本に対する収益の割合を表す指標です。ここでは、不動産投資における利回りの概要や計算式を解説します。
表面利回り
表面利回りとは、物件の価格に対して1年間で家賃収入をどれくらい得られているかを表す指標です。グロス利回りとも呼ばれ、おおよその収益性を判断できます。広告に掲載されている利回りは表面利回りが一般的ですが、固定資産税や管理費などの諸費用は考慮されていないため、実際に運用する利回りよりも高い数値になります。計算式は以下の通りです。
●年間家賃収入÷物件価格×100=表面利回り(%)実質利回り
実質利回りとは、家賃収入から諸経費を差し引いた収益率を表す指標です。ネット利回りやNOI利回りとも呼ばれ、表面利回りよりも正確な数値を求められます。主な諸経費として、物件購入費や管理費や固定資産税、修繕積立金や火災保険料などが挙げられます。計算式は以下の通りです。
●(年間家賃収入-年間諸経費)÷(物件価格+購入時諸経費)×100=実質利回り(%)想定利回り・現行利回り
表面利回りや実質利回りだけでなく、想定利回りや現行利回りという利回りもあります。 想定利回りとは、物件が満室時の場合の収益性を表す指標です。物件を大まかに比較検討する場合や期待できる最大の利益を概算する場合に用いられます。満室時の1年間の家賃収入を合計し、販売価格で割ることで算出できます。
現行利回りとは、現在の家賃収入に基づいて算出した年間の家賃収入を物件価格で割った値です。表面利回りと計算方法が同じで、空室の発生も考慮されますが、実質利回りのように諸経費を含めないため、精度には欠けます。キャッシュ・オン・キャッシュ・リターン
キャッシュ・オン・キャッシュ・リターン(CCR)とは、投資効率を表す指標の一つです。
この指標は、投じた自己資金に対する利益の割合で、CCRが高いほど投資効率が高いと判断できます。計算式は以下の通りです。
●(年間家賃収入-年間諸経費)÷物件取得に使った自己資金額×100=CCR(%)
例えば、1,000万円投資して毎年100万円の現金が残る場合、CCRは「100万円÷1,000万円×100」で10%です。この場合、10年で自己資金を回収できる計算となりますが、家賃の下落や修繕費の発生なども考慮する必要があります。そのため、投資回収期間を正確に把握するためには、年ごとにCCRを算出することが重要です。-

ここでは、不動産投資の表面利回りの相場を解説します。利回りの相場は建物の構造によって異なる点に注意しましょう。
一戸建て
一戸建ての場合、新築では5〜6%、中古では6〜8%が相場です。中古物件は初期費用を抑えられるため、利回りが高くなりやすい傾向があります。
また、地方では利回りが約10%であるのに対し、都市部では4〜7%が相場となっています。
地方の物件は物件価格が安いため、利回りが高くなるでしょう。ただし、地域によっては空室リスクがあるため、慎重に検討することが重要です。
なお、一戸建ては土地も含まれており、土地の価格上昇が期待されるため、利回りの相場が高くなっています。区分マンション・一棟マンション
区分マンションは都心部の場合、築浅物件では3.5〜4.5%、築古物件では5〜6%が相場です。地方の場合は築浅物件で5〜6%、築古物件で7〜8%が相場となります。区分マンションは一部屋当たりの購入価格が高く、固定費も発生するため、利回りが低くなる傾向です。
一棟マンションの場合、新築では3〜4.5%、中古では7〜12%が相場となっています。一棟全体を購入することで一部屋当たりの購入価格を抑えられ、効率的な運営もできるため、利回りは区分マンションよりも高くなる傾向です。
また、ワンルームとファミリータイプによっても利回りは異なります。地域によってまちまちですが、ファミリータイプの方がわずかに利回りが高い傾向です。一棟アパート
一棟アパートの利回りの相場は8〜8.5%です。比較的物件価格が安く運営の自由度も高いため、利回りが高くなりやすい傾向があります。一棟マンションと同様に、一棟全体を購入することで一部屋当たりの購入価格を抑えられる点も理由の一つです。
また、築年数が経過するほど利回りが高くなる傾向があり、利回りが10%を超える場合もあります。ただし、築年数が古い物件はランニングコストや空室リスクも高くなるため、実質利回りとの差は大きくなる傾向です。-

ここでは、利回りが10%・20%と表示される理由や実質利回りが10%・20%を超えるには表面利回りがどの程度必要かを解説します。実質利回りが10〜20%の物件はかなり珍しく、一般的にはあまり見かけないと考えられます。
利回りが10パーセントや20パーセントと表示される理由
広告や物件資料で利回りが10%・20%と掲載される理由は、表面利回りで計算されているためです。
例えば、1億円の物件で毎年1,000万円の家賃収入が得られる場合、利回りは10%と表現されるでしょう。しかし、実際にはさまざまな諸経費がかかるため、実質利回りは10%を下回ります。
また、高利回りをアピールするために、想定利回りで計算していることもあり、この場合も利回りは高く見えることがあります。したがって、掲載されている利回りが高くても、実際の収益性は悪いケースもあります。実質利回りが10パーセントや20パーセントを超えるには
具体的な数値は物件の条件や規模によって異なりますが、表面利回りが実質利回りよりも5〜10%高い必要があるといわれています。したがって、実質利回りが10〜20%を超えるには最低でも表面利回りが15〜25%必要です。しかし、表面利回りが15%以上の物件は珍しく、高利回りの物件にはさまざまなリスクが伴うため、実質利回りとの差が大きくなる場合もあります。
新築物件よりも中古物件の方が利回りは高くなりやすい
中古物件は新築物件よりも利回りが高くなる傾向です。利回りが高くなる理由として、以下が挙げられます。
物件価格の安さ
一般的に、中古物件の方が新築物件よりも物件価格が安いため、家賃収入が同じ場合は投資額が低い中古物件の方が利回りは高くなります。
下落リスクの低さ
新築物件は、住み始めた瞬間から中古物件として扱われるため、購入直後から資産価値が下落するケースも多いです。一方、中古物件はこうした下落リスクが相対的に低いため、利回りが高くなる傾向があるとされています。
入居者を見つけやすい
新築物件は人気が高いものの、競合物件が多く家賃も高くなりやすいため、入居者が決まらないケースもあります。一方、中古物件は一定の居住歴があるため、入居者を見つけやすい傾向です。そのため、空室リスクを抑えやすく利回りが高くなります。不動産投資の理想的な利回りと最低ライン
物件の種類別の理想的な利回りと最低ラインは以下の通りです。
ただし、これらは物件の築年数やエリアや運用方法、投資の目的によっても異なります。中古物件や地方の物件であれば、理想的な利回りと最低ラインはやや高くなるでしょう。そのため、同じエリア・築年数の物件の利回りを確認することをおすすめします。物件の種類 理想の利回り 最低ライン 一戸建て 7~8% 5% 区分マンション 4~6% 3% 一棟マンション 6~8% 3% 一棟アパート 8~10% 5%
また、副業として不動産投資を行う場合は利回りの最低ラインは低くなりますが、本業の場合は不動産投資のみで生計を立てられるほどの収益が必要です。-

高利回りの物件だからといって深く考えずに購入するのは危険です。ここでは、高利回りの不動産で注意したいリスクを解説します。
空室リスクが高くなりやすい
価格が安い物件は利回りが高くなりますが、築年数が経過していたり立地条件が悪かったりする恐れがあります。そういった物件は新築物件よりも人気が低いため、空室リスクが高くなりやすい傾向です。また、地方は交通利便性が低いことや人口が減少していることから、空室が埋まらないケースも多く見られます。
売却時の流動性が低い
投資の流動性とは、売買や換金のしやすさのことです。不動産投資は他の投資に比べて流動性が低いといわれますが、特に高利回りの物件は売却時にリスクがあります。高利回りの物件は、中古物件が多く、中古物件は新築物件に比べて人気がありません。そのため、安価で購入しやすい反面、買い手が付きづらいのです。このような状況では、売却したくても迅速に現金化できず、予期しない損失を被る恐れがあります。不本意な価格で取引せざるを得なくなるリスクもあり、出口戦略に失敗してしまうかもしれません。
利回り通りの収益を上げづらい
高利回りだからといって収益性が高いとは限りません。空室リスクが高い場合、家賃収入を得られない恐れがあります。修繕リスクが高い場合は修繕費で利益が帳消しになってしまうかもしれません。
さらに、表面利回りや想定利回りを基に計算されているため、高利回りに見えることもありますが、実際の利回りが低いケースも多く存在します。修繕・維持管理の費用がかかる
高利回りの物件は中古物件が多いため、新築物件に比べて修繕費や維持管理費が高くなる恐れがあります。壁や床などが劣化している場合は大規模修繕を行う必要があり、共用部やエレベーターなどが老朽化している場合は修繕積立金が高くなるでしょう。
運用するうえでの出費がかさむと実質利回りは低くなります。また、新しい入居者を獲得するために物件を修繕する場合、原状回復に時間がかかり、空室期間が長引いてしまうでしょう。-
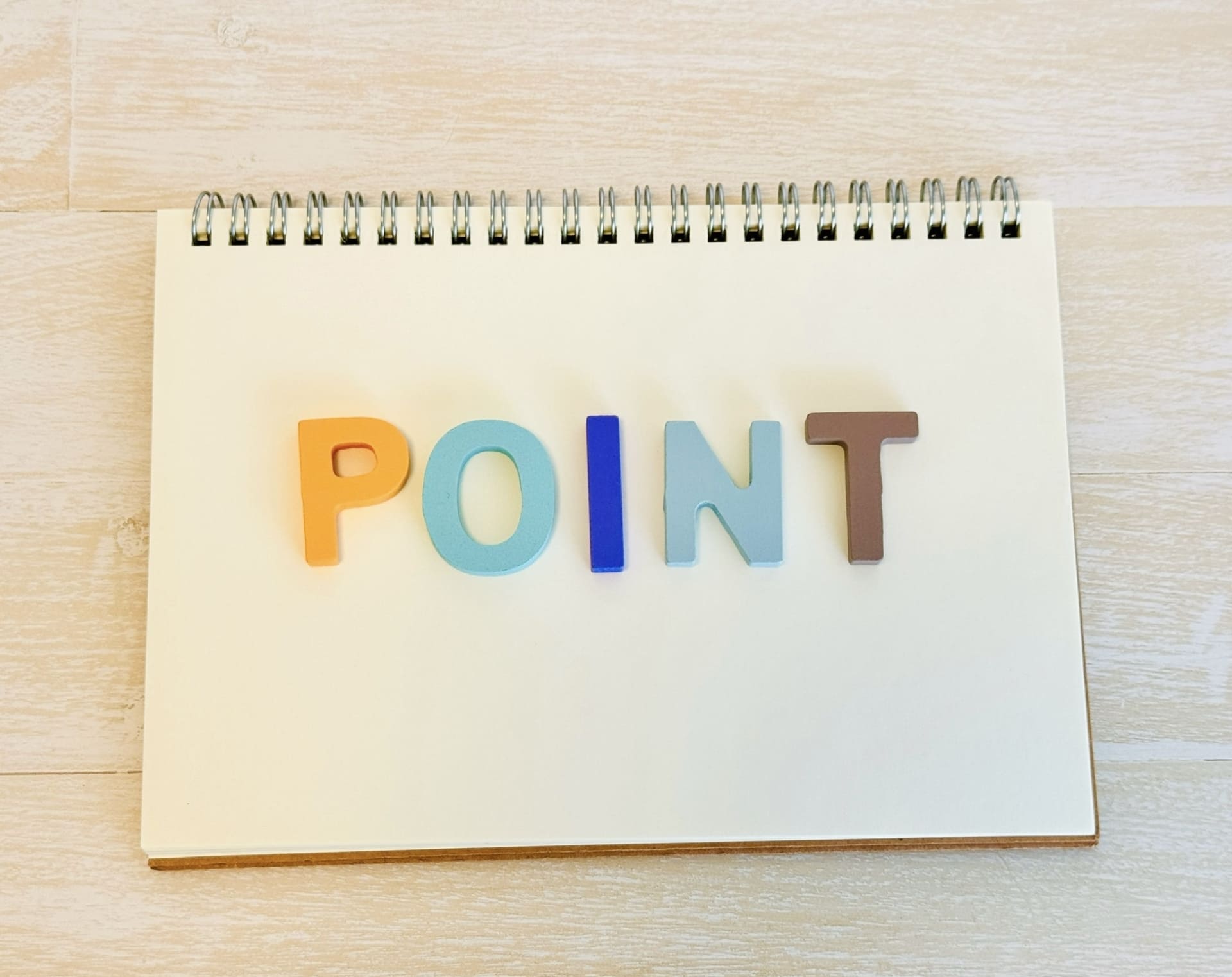
ここでは、利回りを見る際に注意したいポイントを解説します。算出条件の確認や近隣の物件との家賃の比較を行うことで、高利回りの物件を購入するリスクを抑えられます。
極端に高い利回りの場合は条件を確認する
極端に利回りが高い場合は実際の状況と異なる恐れがあるため、算出条件を確認することをおすすめします。広告や物件資料の利回りは表面利回りであり、購入時・賃貸経営の諸経費や空室リスクは考慮されていません。
また、立地の悪さや築年数の古さなどを理由に物件価格が安くなり、利回りが高くなるケースもあります。特に、1981年以前の建物は旧耐震基準で建築されているため、金融機関からの融資も受けづらく、将来的に大規模な修繕も必要になるでしょう。そのため、諸経費を含めた実質利回りや現行利回りを計算することが重要です。区分マンションの場合は管理費や修繕積立金など、できる限り諸経費を算出しましょう。一棟アパート・マンションであれば、空室状況の確認もおすすめします。近隣の物件と家賃を比較する
不動産会社は物件を購入してもらうことで、仲介手数料や売却益などを得ています。中には、高利回りの物件として見せるために家賃を高く設定している場合もあります。
このような不動産会社に惑わされないためには、不動産ポータルサイトでの検索や地域の不動産会社への問い合わせなど、自身で近隣の物件と家賃を比較することが重要です。近隣の物件よりも家賃が極端に高い場合は、慎重に検討した方がよいでしょう。利回りの高さだけを見て判断しない
利回りの高さは、必ずしも投資対象として優れた物件であることを示すものではありません。資産価値が高い物件は物件価格も高いため、利回りが低くなるケースも多く見られます。しかし、立地条件が良い場合や設備が充実している場合は空室リスクが低いため、安定的に収益を得られるでしょう。
そのため、利回りを見る際は空室期間や諸経費を盛り込んでシミュレーションすることが重要です。また、現地に足を運んで交通利便性や周辺施設を確認すればその物件の価値を正確に判断できます。利回りは経年で下落していくことに注意する
建物の築年数が経過すると外観や内装、水回りや設備が古くなっていきます。家賃は賃貸需要が高ければ下がらない場合もありますが、徐々に下がっていくのが一般的です。また、建物が劣化・老朽化すれば修繕やメンテナンスによる出費も避けられなくなります。
そのため、購入時の利回りを前提に資金計画を立てると、築年数が経過した際に損失が生じてしまうかもしれません。-

ここでは、高利回りの不動産の探し方を解説します。主な探し方はインターネットでの検索、メルマガへの登録、不動産業者への資料請求の3つです。
インターネットで探す
不動産ポータルサイトや大手不動産会社のサイトで物件を探します。物件の取り扱い数の多さや不動産投資家たちの情報量の多さがメリットです。定期的にチェックすることで、良い物件を見つけられる可能性が上がります。
しかし、誰でも手軽に利用できることから競争が激しく、物件の雰囲気が伝わりにくくなることや、古い情報や誤った情報が掲載されるデメリットがあります。不動産業者のメルマガに登録する
インターネット上で探し続けるのは骨が折れるという方にはメルマガがおすすめです。不動産業者の多くはメルマガで物件情報を発信しているため、登録することで効率的に物件を探せます。
なお、不動産業者によって一棟アパート・マンションや一戸建て、土地など発信されている情報はさまざまです。闇雲に登録するとかえって効率が悪くなるため、目的に合った不動産投資情報を扱うメルマガに絞って登録することが重要になります。不動産業者に資料請求する
良い物件が見つかった場合は、不動産業者に資料を請求しましょう。資料請求の方法は電話・メール・インターネットの3つです。電話で請求する場合は、物件担当を指名して資料を送付してもらいます。
資料請求する際は、仲介業者ではなく売主から直接物件の売却を依頼されている業者である元付に連絡するのが重要です。顧客と直接やり取りしているため、情報を入手しやすく、価格交渉においても有利に進めることができます。-

利回りには表面利回り・実質利回り・想定利回り・現行利回りなどの種類があります。
広告や物件資料に記載されている利回りは表面利回りや想定利回りがほとんどです。これらは諸経費を計算にいれていないため、掲載されている利回りが高くても収益性が悪いケースもあります。
極端に利回りが高い場合は、算出条件の確認や近隣の物件との家賃の比較が重要です。
利回りの高さだけにとらわれず総合的に判断して、投資物件の購入は、慎重に判断することが大切です。-
キャッシュ・オン・キャッシュ・リターン(CCR)とは、なんですか。
キャッシュ・オン・キャッシュ・リターン(CCR)とは、投資効率を表す指標の一つです。
この指標は、投じた自己資金に対する利益の割合で、CCRが高いほど投資効率が高いと判断できます。計算式は以下の通りです。
(年間家賃収入 - 年間諸経費)÷ 物件取得に使った自己資金額 × 100 = CCR(%) -
想定利回り・現行利回りについて教えてください。
想定利回りとは、物件が満室時の場合の収益性を表す指標です。物件を大まかに比較検討する場合や期待できる最大の利益を概算する場合に用いられます。満室時の1年間の家賃収入を合計し、販売価格で割ることで算出できます。
現行利回りとは、現在の家賃収入に基づいて算出した年間の家賃収入を物件価格で割った値です。表面利回りと計算方法が同じで、空室の発生も考慮されますが、実質利回りのように諸経費を含めないため、精度には欠けます。
関連記事
-
 【アパート建設に必要な土地の広さ】目安をまとめてみた詳しく見る
【アパート建設に必要な土地の広さ】目安をまとめてみた詳しく見る相続税対策などでアパート経営を検討している方のなかには、「そもそもどれくらいの土地が必要なのかわからない」という方もいるのではないでしょうか。また、土地を所有しているのであれば、活用して利益を得たいと考えるはずです。アパート建設では、土地は広ければ広いほど良いという訳ではありません。土地の大きさや形によって、適切な方法が異なります。 しかし、所有している土地でアパート経営を始めるには、いくつかのリスクがあることも覚えておきましょう。それぞれのリスク回避のために適切な対策を行って、効率的な土地活用を行いましょう。 この記事では、土地有りでアパート経営を行うメリット・デメリットについて、そして経営を進める時の流れや必要な資金などについて解説します。
-
 公務員でアパート経営をするには?知っておくべき条件と注意点を解説詳しく見る
公務員でアパート経営をするには?知っておくべき条件と注意点を解説詳しく見るこの記事では、公務員がアパート経営可能な理由、副業禁止の理由、一定規模を超える際の申請手順、申請が許可されやすいケース、公務員がアパート経営をするメリット、注意点についてご紹介します。 しかし、所有している土地でアパート経営を始めるには、いくつかのリスクがあることも覚えておきましょう。それぞれのリスク回避のために適切な対策を行って、効率的な土地活用を行いましょう。 この記事では、土地有りでアパート経営を行うメリット・デメリットについて、そして経営を進める時の流れや必要な資金などについて解説します。
-
 100万円以下でマンションは購入できる?その方法や必要な費用、デメリットや注意点も解説詳しく見る
100万円以下でマンションは購入できる?その方法や必要な費用、デメリットや注意点も解説詳しく見るマンション投資に興味がある方の中には、投資資金が少なくて始められないと考えている方も多いでしょう。マンション投資には、まとまった初期費用が必要になりますが、少額からでもマンション投資を始めることは十分に可能です。 本記事では、マンション投資を100万円以下で始める方法や必要な費用、デメリットや注意点などを解説します。
タウングループ不動産仲介・周辺事業- 賃貸不動産仲介(東京・神奈川・埼玉・千葉) タウンハウジング
- 賃貸不動産仲介(東海) タウンハウジング東海
- 賃貸不動産仲介(九州) タウンハウジング福岡
- 土地・建物の不動産販売及び仲介 タウン住宅販売
- 首都圏を中心に引越サービスを展開 タウン引越サービス
- 賃貸不動産仲介(東北) タウンハウジング東北
- 賃貸不動産仲介(北関東) タウンハウジング北関東
建築事業- 賃貸住宅の企画・設計・施工 アヴェントハウス
多角化事業- 都内を中心に飲食店を運営 タウンダイニング
- インドアテニススクール タウンインドアテニスアカデミー


 一覧へ戻る
一覧へ戻る