不動産取得税の軽減措置を受けたい!手続き方法や必要書類をわかりやすく解説
家屋や土地などの不動産を購入したり建物を建てたりすると「不動産取得税」が一度だけ課されます。不動産取得税には、税率が定められており、固定資産税評価額を用いて計算します。税の負担を抑えられる軽減措置が設けられているのが特徴です。適用要件を満たすことで軽減措置を利用でき、申請すれば節税につながるでしょう。
また、納めすぎた場合には還付申請も可能です。
この記事では、不動産取得税の軽減措置について、手続きの方法や必要書類、還付申請の流れなどを解説します。
-

まずは、不動産取得税がどういった税金なのか概要を確認しておきましょう。支払い時期や納付先、納付方法の他に、納付する上で不動産に該当する土地や家屋の種類についても押さえておくことが大切です。同じ不動産に関する税金でも、固定資産税とは異なる特徴がいくつかあるため、両者の違いも把握しておくと良いでしょう。
不動産取得税の歴史
不動産取得税の歴史は古く、大正時代に府県税として創設されたのが始まりです。その後、1950年(昭和25年)のシャウプ勧告の際、不動産の税負担を考慮して一旦は廃止されています。1954年(昭和29年)の税制改正で、固定資産税の税率の引き下げとともに再び不動産取得税を徴収するようになりました。シャウプ勧告とは、経済の安定、長期的・安定的な税制、均衡のとれた公平な税制、地方自治確立のための地方財政の強化、強力な執行体制の整備など、国税・地方税を通した税制や税務行政全般にわたる勧告書です。 戦後税制の基本となりました。
出典:国税庁/19-2 昭和24(1949)年 シャウプ勧告書不動産取得税は不動産を取得した人が納める
不動産取得税は、購入や贈与、家屋の建築などで不動産を取得した際に、取得した方に課税される税金です。不動産を取得した方が、納税義務者となります。土地と家屋それぞれに課税される点が特徴で、土地付きの一戸建て住宅を購入した場合は、土地と家屋両方の分を納付しなければなりません。
不動産取得税は、不動産を取得した時のみに課されるため、あくまでも一度きりの納付で済みます。税収の動向としては、1996年(平成8年)をピークに減少した後、2012年(平成24年)以降は堅実に上昇傾向にあるといえます。
不動産の取得とは、取得時の有償か無償かを問わず、不動産所有権を得ることを指します。不動産は土地と家屋を総称したもので、土地であれば畑や田んぼ、山林、牧場、温泉といった鉱泉地などさまざまです。家屋であれば住宅や店舗、倉庫、工場といった建物が該当します。不動産取得税の納付先・納付方法
不動産取得税の納付先は、不動産の所在地がある都道府県です。住所地とは別の、他の都道府県で不動産を取得した場合でも、納付先は不動産の所在地がある都道府県になるため注意しましょう。
納付は、不動産取得税の納税通知書に記載されている期限までに行います。納付方法は自治体ごとに決まっているため、納税通知書や各都道府県税事務所のホームページで確認しましょう。
主な納付方法
現金
クレジットカード
金融機関・郵便局の窓口
コンビニエンスストア
PayPayなどのスマートフォン決済アプリ
ペイジー(Pay-easy)
e-TAX
近年では現金や窓口での支払い以外に、アプリ決済など納付方法の種類が増えてきているため、支払いの手間も省けるようになってきています。固定資産税とは異なる税金
不動産を所有すると、さまざまな税金がかかります。ここでは、不動産取得税と混同されやすい固定資産税との違いについて確認しましょう。
固定資産税とは、固定資産に課税される税金です。固定資産は、家屋や土地の他、パソコンや棚といった会社の備品や工場の機械などを指します。固定資産税の納付先は、不動産の所在地がある市町村です。例外として、東京都23区内の場合は都税として納付します。
不動産取得税と固定資産税は、両者とも不動産に課税され、固定資産税評価額を用いて税額を計算する点が共通しています。大きな違いは納付先と課税の回数です。不動産取得税は取得の際に1回の納付だけで済む税金ですが、固定資産税は不動産を所有する限り、毎年課税されます。また、税率も不動産取得税は4%、固定資産税は1.4%と異なります。不動産取得税を計算するには
不動産取得税は、実際の不動産の購入価格や建築費ではなく、固定資産税課税台帳に登録されている固定資産税評価額を用いて、以下のように計算します。
固定資産税評価額 × 4%(税率)= 不動産取得税
税率は基本的に4%ですが、土地と家屋に関しては、軽減税率の適用により3%として計算されるケースがあります。軽減税率の詳細については、本記事にある不動産取得税の軽減措置の項目で解説します。-
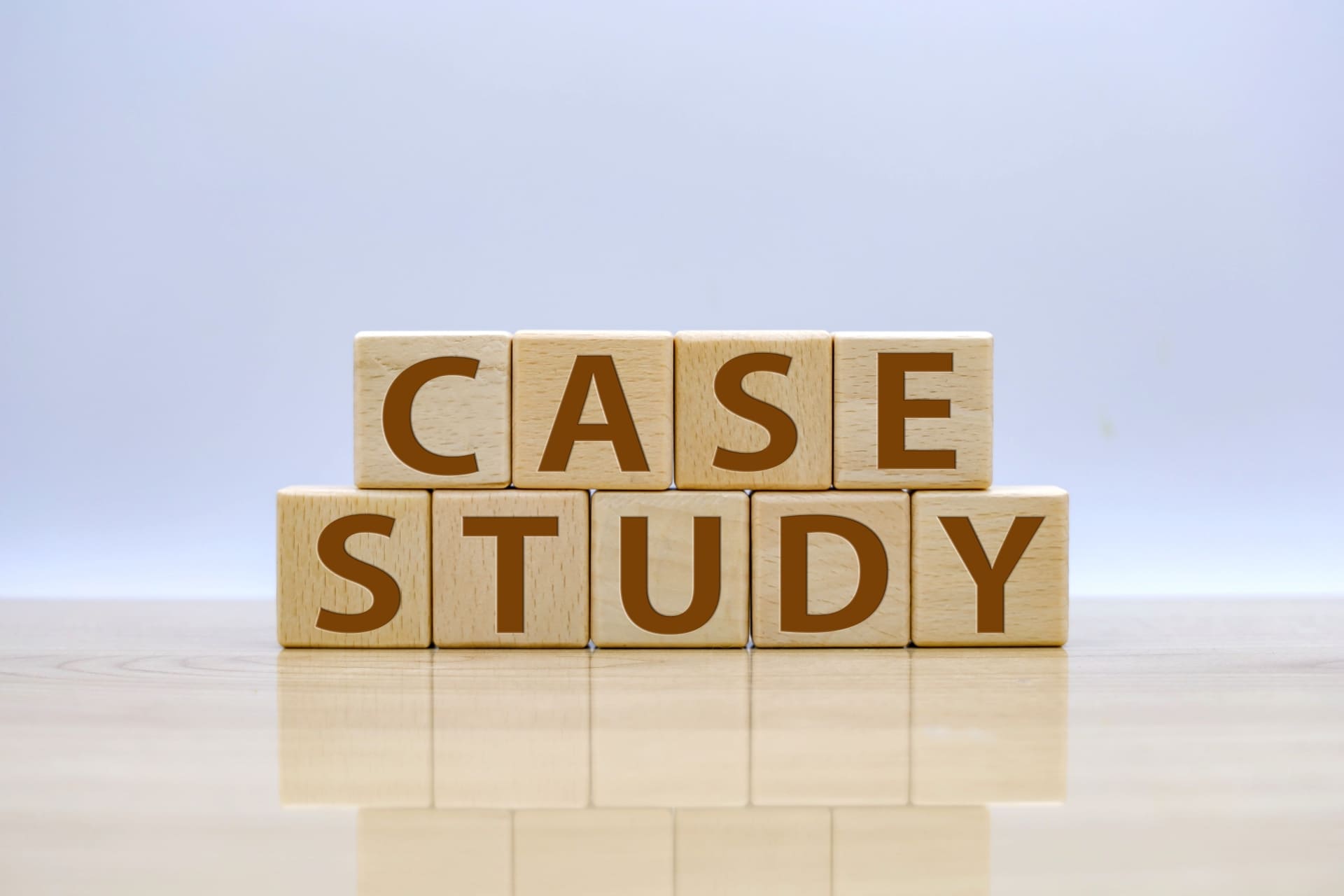
地方税法第73条の4の条件に該当する場合など、不動産を取得した方法や価格によっては、不動産取得税が課税されないケースもあります。軽減措置の手続きを行う前に、不動産取得税自体が非課税になるかどうかをしっかり確認しましょう。
不動産取得税が非課税になる条件は、主に以下の5つです。取得した不動産の価格が免税対象になる金額よりも低い場合
取得した不動産の価格が免税点に満たないとき、不動産取得税は課税されません。
なお、免税点は、不動産取得税の課税標準になる金額を指します。土地や家屋における、不動産取得税の免税点は以下の通りです。
土地
10万円未満で取得した場合
新築や増築などで取得した家屋
1戸につき、23万円に満たない場合
売買や贈与などで取得した家屋
1戸につき、12万円に満たない場合
上記の条件を満たした上で「免税対象の土地に隣接する土地を1年以内に取得」または「免税された家屋と隣接する家屋を1年以内に取得」した場合は、それぞれ1つの土地・家屋とみなされて価格が評価されます。取得時に免税点を超えたときは、不動産取得税が課税されるため注意しましょう。相続で不動産を取得した場合
相続によって不動産を取得すると、不動産取得税は非課税になります。これは、相続が本人の意思とは無関係に、財産以外の負債も相続するため、税務上の配慮で認められているためです。なお、非課税になるのは法定相続人に限定されます。相続税対策で行われる生前贈与に関しては、相続ではないため不動産取得税が課税されます。
不動産を相続する場合「特定遺贈」と「包括遺贈」に注意が必要です。特定遺贈とは、遺言書により遺産の内容と遺贈者を指定するもので、特定遺贈で法定相続人以外が受贈するケースでは、不動産取得税の課税対象になります。法定相続人が相続するのであれば、特定遺贈であっても課税されません。
特定遺贈とは異なり、遺贈する際に遺産の内容を指定しない包括遺贈では、法定相続人以外が受け継いでも非課税となります。法人の組織再編で合併や分割が行われて不動産を取得した場合
法人が組織再編で合併や分割を行い不動産を取得したときは、不動産取得税は課税されません。法人の合併や分割では、不動産の所有権が変更されるだけであって、新しく不動産を取得したわけではないためです。
法人の分割における非課税の場合「金銭等不交付要件」を満たさなければならないケースもあります。金銭等不交付要件とは、法人税法にある適格組織再編の要件の1つです。組織再編の対価で、株主に対し承継法人株式以外の金銭が交付されないように求める要件を指します。土地区画整理で取得した換地や一般に広く開放されている私道の場合
土地区画整理などで換地を取得すると、不動産取得税は非課税となります。換地とは、区画整理された土地が新しく割り当てられたものです。
また、一般に広く開放されている私道も、公共の用に供する道路と見なされるため課税されません。具体的には、周辺住民によく利用されている公道の間にある私道などが該当します。特定法人が事業用の不動産を取得した場合
特定の法人が事業用の不動産を取得した場合は、不動産取得税が非課税になります。例を挙げると、学校法人が保育や教育の場に使用する不動産、社会福祉法人が老人ホームのような社会福祉事業を行うために取得した不動産などが該当します。この他、宗教法人が境内地として不動産を取得した際も非課税です。
注意点として、非課税になるのは本来の事業用に使用する不動産のみです。本来の事業とは異なる使用用途で取得した不動産に関しては、従来通り課税されます。上記に該当する場合は不動産取得税非課税申告書を提出する
取得した不動産の価格が免税点よりも低い、相続で不動産を得たなど、上述した条件に該当する場合は、不動産の取得後に「不動産取得税非課税申告書」の提出を求められることもあるため注意しましょう。
不動産取得税非課税申告書の提出先は、不動産の所在地がある都道府県税事務所になります。受付期間は、原則として不動産を取得してから60日以内と定めている自治体が多いようです。申告書の提出時は、必要書類の添付が必要になるケースもありますが、不動産の内容によって用意する書類は異なるため、管轄の都道府県税事務所へ確認します。-

ここでは、不動産取得税を抑えるために設けられている軽減措置について、基本の概要や対象となる不動産を確認しましょう。
不動産取得税には軽減措置が適用される
住居用の土地を購入したり家屋を建てたりと、不動産を取得することでただでさえ高額な費用がかかります。取得のための費用以外にも不動産取得税が課税されますが、税負担を軽減してくれる制度として軽減措置が設けられているのです。
不動産取得税の納付額は、固定資産税課税台帳に登録されている固定資産税評価額に税率を掛けて算出します。税率は4%に定められていますが、現在では土地と家屋の税率は軽減税率として3%が適用されているため、納付額を算出する際は注意しましょう。軽減措置の対象となる不動産とは
不動産取得税で軽減措置を受けるとき、条件の1つとして対象となる不動産かどうかを確認しなければなりません。対象となる不動産は、「新築住宅」「新築住宅用の土地」「中古住宅」「中古住宅用の土地」の4つに分類されます。
建物や土地のそれぞれで適用要件が異なるため、順番に確認すると良いでしょう。軽減措置の詳細や適用要件に関しては、この後の項目で解説します。-

不動産取得税の軽減措置は、行政が自動で適用してくれるわけではないため、不動産の取得者が申請手続きを行わなければなりません。軽減措置の手続きは、都道府県税事務所で行うのが基本です。ここでは、申請手続きの基本的な流れを順番に解説します。
なお、手続きに電子申請が可能な自治体もあります。電子申請は、電子申請受付システムにアクセスして必要項目を入力し、内容に問題がなければ受理され、軽減措置が適用された税額の納付書が送付される仕組みです。管轄の都道府県税事務所に申請する
不動産取得税は、都道府県に納付する地方税であるため、申請は税務署ではなく不動産の所在地がある都道府県税事務所で行います。不動産取得後に、軽減措置を受けるための申請書を提出しましょう。申請場所は、都道府県税事務所の不動産取得税担当課です。提出期限は都道府県によって異なりますが、不動産の登記が完了してから、10日〜60日以内と定められているケースが多いようです。申請前に、都道府県税事務所に確認すると良いでしょう。
申請書は、都道府県税事務所の窓口やホームページから入手可能です。申請書の他にも、後述する必要書類を用意する必要があります。納税通知書を確認して不動産取得税を納める
申請後、都道府県税事務所から不動産取得税の納税通知書が送付されます。納税通知書の内容を確認し、記載されている期日までに納付しましょう。不動産取得税は、原則として一括で納付します。納付方法は、現金払いやクレジットカード払いの他にもさまざまで、キャッシュレス決済に対応しているところもあります。
納税通知書が送付される時期の目安は、不動産を取得した日の半年〜1年後くらいです。自治体によって時期は異なるため、納付の時期を把握したい場合は都道府県税事務所に確認しましょう。不動産を取得した段階から税金の納付まで期間が空いてしまうため、事前に準備をしておくことも大切です。なお、軽減措置が適用されることで納付額が0円になったときは、納税通知書は送付されません。-
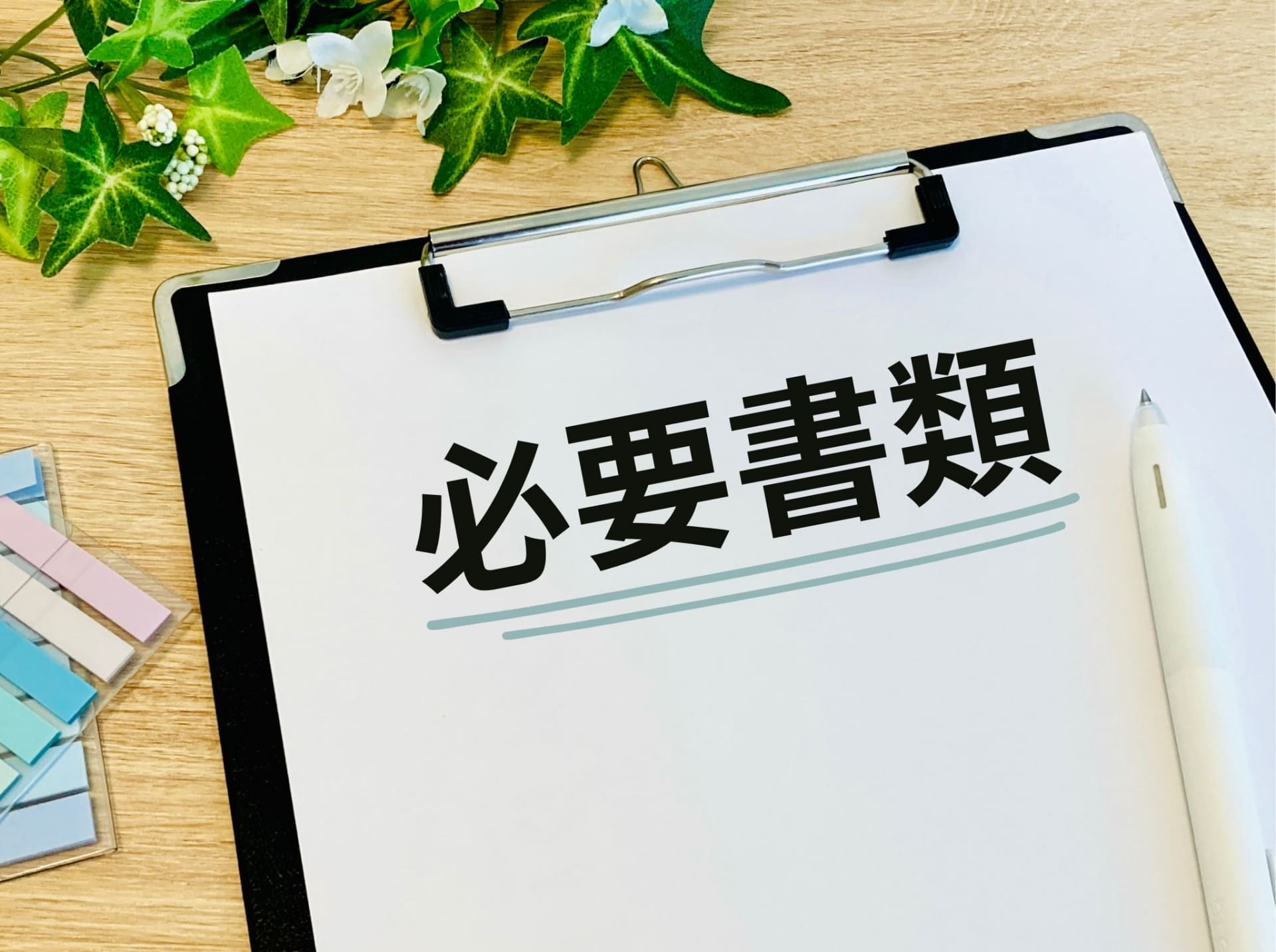
不動産取得税の軽減措置を受けるには、都道府県税事務所への申請が必要になりますが、申請の際はいくつかの書類を用意しなければなりません。
軽減措置を申請するための申請書には「住宅に係る不動産取得税の課税標準の特例の適用があるべき旨の申告書」などがあります。これらの申請書の名称は、自治体によって変わるため注意が必要です。申請書は、建物と土地でそれぞれ1部ずつ用意して、必要書類と一緒に提出します。一部の自治体では、申請書類を郵送で提出することも可能です。
取得した不動産が新築か中古かで、必要書類に違いがあるため、どの書類を用意するかは申請前に確認するようにしましょう。不動産取得税申告書
不動産取得税を納付する際は、必要事項を記入した「不動産取得税申告書」が必要です。申告書は窓口でなくても、都道府県税事務所のホームページからダウンロードできます。取得した不動産の所在地を管轄している都道府県税事務所から、ダウンロードするようにしましょう。
不動産取得税申告書の記入欄には土地と家屋に関する項目があり、それぞれを記入します。不動産の図面や登記事項証明書などを確認しながら記入すると良いでしょう。都道府県のホームページには、不動産取得税について申告書などの記入例を掲載していることもあるため、そちらを参考にするのもおすすめです。不動産取得税の納税通知書
管轄の都道府県税事務所から送付される、不動産取得税の納税通知書が必要になるケースもあります。不動産を取得する場合は所有権の移転登記を行いますが、登記を行う法務局と自治体が連携しているため、登記を行えば自動的に納税通知書が送付される仕組みです。都道府県税事務所から送付された納税通知書が届いたら、不動産取得税を納付します。
納税通知書が送付される時期は、所有権の移転登記からおおよそ4〜6か月後と見て良いでしょう。都道府県税事務所の調査状況や、不動産の取得方法などによっても送付の時期は変わります。法務局で所有権の移転登記を行った、市や町が家屋評価を行ったなど、状況別に細かく条件を分けている都道府県も少なくありません。
都道府県によっては、ホームページに不動産取得税に関する情報を掲載しているケースもあるため、納税通知書が送付される時期について記載がないか確認しておきましょう。建築工事請負契約書
「建築工事請負契約書」とは、注文者が請負人に対して工事を発注した際に、その内容を記載する契約書で、建設業法の規制が適用されます。建築工事請負契約書が締結される工事の種類は、建物の新築工事や増改築工事などです。
軽減措置の申請に建築工事請負契約書が必要なケースとしては、土地を取得した後、取得者が3年以内にその土地に住宅を新築した場合が挙げられます。ただし、管轄の都道府県によっては、他の条件でも建築工事請負契約書の用意を求められる可能性があります。不動産売買契約書
「不動産売買契約書」とは、売買取引の対象である不動産について、記載されている内容で取引を行う旨を規定する契約書です。不動産の売買代金や支払日、支払い方法の他に、建物の住所や面積、所有権の移転と引渡しといった情報が記載されています。
不動産売買契約書は、不動産の販売会社や仲介会社が作成してくれます。受け取った後は手元で管理しておくものですが、もし紛失してしまった場合は再発行が可能です。ただし、再発行には収入印紙の貼付が必要になります。登記事項証明書
不動産の所有者や場所、所有者の氏名などは法務局の登記簿に記載されており、電子データとして管理されています。不動産の「登記事項証明書」は、登記簿の電子データを証明書として発行したものです。
登記事項証明書は、法務局であれば他の都道府県・市区町村でも取得できます。なお、法務局以外の役所や役場では取得できません。取得する際は、1通600円の手数料を収入印紙で納めます。登記事項証明書は、オンラインによる申請も可能です。
軽減措置で登記事項証明書を用意するケースは、新築未使用の住宅とその土地を取得した場合、土地を取得した後に住宅を3年以内に新築した場合などが挙げられます。なお、登記事項証明書には全部事項証明書や現在事項証明書などの種類がありますが、不動産取得税の申告では基本的に全部事項証明書が求められます。また、都道府県税事務所の指示がない限り、証明書はコピーでも構いません。耐震基準適合証明書・住宅性能評価書
軽減措置を受ける際は、「住宅の耐震基準適合証明書」あるいは「住宅性能評価書」を用意しなければならないケースもあります。
耐震基準適合証明書とは、建物の耐震性が建築基準法における耐震基準を満たしているかを証明する書類で、自動で発行されないため、取得には指定の検査機関などに申請が必要です。住宅性能評価書は、住宅品質確保法に基づいた客観的な基準で評価された住宅性能が記載されている書類で、住宅性能評価機関から検査を受けて取得できます。
基本的に、1981年12月31日以前に建築された住宅は旧耐震基準で建築されています。そのため、軽減措置を受ける際は新耐震基準を満たしていることを証明するための耐震基準適合証明書や住宅性能評価書が必要です。すでに新耐震基準を満たしていることが証明されている住宅の場合は、不動産会社や売主から原本を受け取るかコピーを依頼しましょう。
ただし、一般的に軽減措置の要件は不動産取得日の前2年以内に耐震診断が終えていることが条件となっているため、書類の発行日には注意が必要です。また、耐震診断を行っていない住宅の場合は、建築士や国土交通省が指定した指定性能評価機関に依頼することで、耐震基準適合証明書を取得できます。
住宅性能評価書は、住宅性能評価機関に住宅性能評価を申請し、検査を受けることで取得が可能です。ただし、前述した通り耐震診断は不動産取得日より前2年以内に終えている必要があるため、取得後に耐震診断を行っても適用外となります。
また、指定性能評価機関や住宅性能評価機関の依頼には数万〜数十万程度の費用がかかるため、複数の機関に見積もりを依頼して費用を比較検討することをおすすめします。なお、都道府県税事務所の指示がない限り、証明書や評価書はコピーでも構いません。平面図
建物の内部を確認するのに用いる「平面図」は、建物を水平方向に輪切りにし、それを上から見た図面のことです。間取り図とも呼ばれます。
平面図は、新築かつ未使用の住宅とその土地を新築から1年以内に取得した場合や、土地を取得した後3年以内に、土地の取得者が住宅を新築した場合に用意するケースがあります。また、土地の取得後に、取得者が1年以内に土地の上にある中古住宅を取得したときも平面図が必要になることもあります。
上記の他にも、以下の書類が必要になる場合もあります。
住民票
軽減措置では、不動産の取得者自身が居住していることが要件となっているケースも多いため、住民票も重要な証明書類となります。住民票は現住所のある市区町村の役所の窓口で申請することで取得できるほか、郵送での請求やコンビニでの取得も可能です。取得する際は、マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類と手数料を用意する必要があります。手数料は自治体によって異なりますが、1通あたり200〜400円程度が一般的です。
建築確認済証
建築計画が建築基準法や関連法規などに適合していることを証明する書類で、建築年月日や建築主、確認番号などが記載されています。不動産取得税の申告では、建物の種類や用途、床面積などを確認する際に必要です。特に、中古住宅の軽減措置には新耐震基準の要件があるため、建築確認済証は重要な書類となります。
不動産会社や元の所有者などから入手できますが、紛失した場合は建築計画概要書や台帳記載事項証明書などの発行が必要です。なお、都道府県税事務所の指示がない限り、確認済証はコピーでも構いません。-

軽減措置を受けるための手続きを進める前に、措置の内容や適用要件の確認が必要です。取得した建物や土地が、新築か中古かで要件や内容は変わります。
ここでは、不動産取得税の軽減措置を受ける際の適用要件と、措置が適用された場合の内容を確認しましょう。新築住宅の場合
憧れのマイホームとして、新築住宅を取得するケースは多いでしょう。新築住宅の適用要件は以下の2点です。
1.マイホームやセカンドハウスなど、個人の居住を目的とした住宅であること
2.延べ床面積が、50㎡(一戸建て以外の賃貸住宅では40㎡)以上240㎡以下であること
新築住宅の場合は、上記の条件を満たすと新築住宅の固定資産税評価額より1,200万円の控除が受けることが可能です。この固定資産税評価額が1,200万円以下のとき、不動産取得税は課税されません。軽減措置を受ける際の計算式は以下の通りです。
(固定資産税評価額 - 1,200万円)× 3%(税率)= 軽減措置後の不動産取得税
例として、新築住宅の固定資産税評価額が1,600万円とすると、軽減措置を受けない場合は1,200万円が控除されないため、不動産取得税の計算式は以下のようになります。
1,600万円 × 3% = 48万円
上記と同じ固定資産税評価額で軽減措置を受ける場合、1,200万円の控除が適用されます。
(1,600万円 - 1,200万円)× 3% = 12万円
固定資産税評価額が1,600万円であるとき、軽減措置を受けると課税される不動産取得税は12万円となります。新築住宅用の土地の場合
軽減措置が適用される新築住宅の土地で、軽減措置が適用される要件は、以下の通りです。
土地を先に取得した場合
土地の取得日から3年以内にその土地に軽減措置の対象となる新築住宅が建てられた場合は、軽減措置が適用されます。
ただし、土地の取得者が新築住宅の建築まで土地を所有し続けているか、土地の取得者からその土地を取得した人が新築住宅を建てていることが条件です。
新築住宅を同時・先に取得した場合
新築住宅を建てた人が新築後1年以内にその土地を取得している場合は、軽減措置が適用されます。
また、新築未使用の住宅・土地を新築後1年以内に同じ人が取得している場合も対象です。
軽減措置が適用された新築住宅用の土地は、以下のいずれかのうち高い額が不動産取得税額から控除されます。
1.150万円×税率(4万5,000円)
2.(土地1平方メートル当たりの固定資産税評価額 ÷ 2)×(住宅の床面積 ×2(1戸あたり200平方メートルまで))×3%
前述した通り、住宅用土地の場合は固定資産税評価額が1/2になります。
例えば、土地の面積が200平方メートルで住宅の床面積が150平方メートルで土地部分の固定資産税の評価額が1,500万円の場合、土地1平方メートル当たりの価格は3万7,500円です。この場合、上記2で計算すると控除額は22万5,000円となるため、1よりも高い2の控除額が適用されます。
軽減措置を受けない場合、固定資産税評価額の1,500万円 ÷ 2× 3%で税額は22万5,000円です。一方、軽減措置を受ける場合は税額の22万5,000円から控除額の22万5,000円が差し引かれるため、全額控除となります。中古住宅の場合
中古住宅で軽減措置が適用される要件は、以下の3点です。
1.個人が自分で住むために取得した住宅
2.床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下
3.1982年1月1日以降に新築された住宅
床面積は登記床面積ではなく、現況の床面積で判定されます。
また、1981年12月31日より前に建てられた住宅でも、耐震診断で新耐震基準を満たしていると証明された住宅は軽減措置の対象です。
ただし、証明に必要な調査が住宅の取得日の前2年以内に終了している必要があります。
東京都の場合の控除額は以下の通りです。建築日 控除額 1954年7月1日~1967年12月31日 100万円 1968年1月1日~1972年12月31日 150万円 1973年1月1日~1975年12月31日 230万円 1976年1月1日~1981年6月30日 350万円
例えば、2000年に建てられた中古住宅で固定資産税評価額が2,000万円の場合、軽減措置を受けない場合は2,000万円×3%で60万円です。建築日 控除額 1954年7月1日~1967年12月31日 100万円 1981年7月1日~1985年6月30日 420万円 1985年7月1日~1989年3月31日 450万円 1989年4月1日~1997年3月31日 1,000万円 1997年4月1日~ 1,200万円
一方、軽減措置を受ける場合は800万円×3%で24万円となり、課税額が36万円減ります。
出典:不動産取得税/不動産と税金/東京都主税局中古住宅用の土地の場合
中古住宅の土地で、軽減措置が適用される要件は以下の通りです。
土地を同時・先に取得した場合
土地の取得者が土地の取得日から1年以内にその土地の中古住宅を取得している場合は、軽減措置が適用されます。
ただし、1981年12月31日以降に建てられた中古住宅を取得した場合は以下の3つが条件です。
1.取得後半年以内に耐震改修を行い、耐震診断で新耐震基準を満たしていると証明を受けた
2.取得者自らが居住している
3.2018年4月1日以降に土地を取得している
中古住宅を先に取得した場合
中古住宅の取得者がその住宅を取得してから1年以内にその土地を取得している場合は、軽減措置が適用されます。
軽減措置が適用された中古住宅用の土地は、新築住宅用の土地と同様に以下のいずれかのうち高い額が税額から控除されます。
1.150万円 × 税率(4万5,000円)
2.(土地1平方メートル当たりの固定資産税評価額 ÷ 2)×(住宅の床面積 × 2(1戸あたり200平方メートルまで))× 3%
前述した通り、住宅用土地の場合は固定資産税評価額が1/2になります。
例えば、土地の面積が150平方メートルで住宅の床面積が100平方メートルで土地部分の固定資産税評価額が1,000万円のケースを考えましょう。
この場合、土地1平方メートル当たりの価格は3万3,000円(百円以下切り捨て)となり、2で計算すると控除額は19万8,000円となるため、1よりも高い2の控除額が適用されます。
軽減措置を受けない場合、固定資産税評価額の1,000万円 ÷ 2 × 3%で税額は15万円です。
一方、軽減措置を受ける場合は税額の15万円から控除額の19万8,000円が差し引かれるため、全額控除となります。マンションでも軽減措置を受けられる
ここまで住宅や土地の軽減措置について、適用要件や内容を確認しましたが、マンションでも軽減措置を受ける際は、新築・中古住宅・土地の軽減措置と同じ適用要件と内容になります。つまり、新築マンションでは新築住宅・新築住宅用の土地の軽減措置、中古マンションでは中古住宅・中古住宅用の土地の軽減措置が受けられる仕組みです。
なお、賃貸マンションに住むだけの場合は課税されません。これは、不動産取得税があくまでも不動産を取得したときに課税されるためです。マンションの所有権を取得した際は、課税対象になります。認定長期優良住宅には特例措置がある
認定長期優良住宅とは、耐震性や省エネルギー性などに優れていることがわかる基準を満たし、行政から認められている住宅のことです。行政は認定長期優良住宅の普及のため、新築あるいは建築後未使用の認定長期優良住宅の取得を行ったとき、不動産取得税や固定資産税、登録免許税などの納付額が軽減される特例措置を設けています。
不動産取得税の場合、認定長期優良住宅では建物に関して、1,300万円の控除が受けられます。これは通常の軽減措置である、新築住宅の1,200万円に代わって適用されます。ただし、認定長期優良住宅の特例措置は2026年(令和8年)3月31日までです。-

不動産取得税を納付する際、軽減措置の申請を忘れたために払い過ぎてしまったというケースもあるでしょう。払い過ぎた場合は、還付請求の手続きを行うことで不動産取得税の還付を受けられます。
ここでは、不動産取得税の還付を受ける流れと、手続きに必要な書類を解説します。還付請求権によって認められている還付請求は、法的に時効が5年と設定されているため、還付請求が可能な日から5年以内に申請手続きを進めるようにしましょう。不動産取得税申告書を提出する
不動産取得税の納付後に軽減措置を適用する場合は、一旦は納税通知書に記載されている税額を納付してから、後日「不動産取得税の還付(減額)申請書」と必要書類を提出することで、還付請求ができます。
まずは、「不動産取得税申告書」または「不動産取得申告書」の必要事項を記入し、管轄の都道府県税事務所に提出しましょう。提出する期限は、東京都であれば不動産を取得してから30日以内、大阪府であれば不動産を取得してから20日以内と、都道府県によって異なるため注意が必要です。事前に都道府県税事務所のホームページなどで、申告書の書式と提出期限を確認しましょう。
申告書を提出する際は、不動産の登記事項証明書や住民票、売買契約書といった必要書類を同時に添付します。添付する書類に関しては、不動産の内容により用意するものが異なるため確認が必要です。不動産取得税を納付する
不動産取得税の納税通知書が各都道府県から送付されてくるため、必ず通知書に記載されている指定の期限内に納付しましょう。納税通知書は、不動産の所有権移転の登記を行った後、おおよそ4〜6か月後に送付されます。
ただし、不動産の内容によっては価格決定の手続きが必要になるケースがあるため、通知書が届くまでさらに時間がかかることに注意しましょう。
ここまでの還付手続きの流れでは、不動産取得税を支払うまでの通常の流れとあまり違いはありません。不動産取得税の還付(減額)申請書を提出する
不動産取得税の軽減措置が受けられると判断された場合、不動産取得税の還付申請書あるいは減額申請書を各都道府県税事務所に提出します。提出先は、不動産取得税申告書を提出した場所と同じです。還付(減額)申請書は、都道府県の窓口で直接入手するか、ホームページからダウンロードして記入しましょう。
還付(減額)申請書の提出には、取得した不動産の登記事項証明書や売買契約書、建築確認済証といった書類が必要です。提出先のホームページや窓口で、用意する書類を確認しましょう。その後、提出書類の記載内容に問題がなければ、還付請求の手続きは完了となります。
不動産取得税の還付請求手続きに必要な書類について、詳細は以下で解説します。還付を受ける際は指定された書類を用意する
不動産取得税の還付申請では、通常の申告と同様に以下の書類が必要になります。求められる書類は都道府県によって異なる上、書類の中にはコピーでも問題ないものと原本を提出すべきものがあるため、事前に確認しておきましょう。不動産取得税の申告時に添付する書類と重複するものもあります。
不動産取得税の還付(減額)申請書
不動産取得税還付(減額)申請書とは、納め過ぎた税金の還付を申請するために提出する書類です。申請書には、申請者の情報や不動産の所在や取得年月日、納付した年月日や税額などを記入します。記入方法がわからない方は、各都道府県のホームページで紹介されている不動産取得税還付(減額)申請書の記入例を参考にしましょう。
なお、申請用紙は管轄の都道府県税事務所の窓口やホームページから入手可能です。また、申請書の名称は自治体によって異なる場合があります。
不動産の登記事項証明書
登記事項証明書とは、登記簿に登録されている事項を証明する書類です。不動産の住所や面積や種類、所有権や抵当権に関する事項が記載されています。不動産取得税の申告や還付申請では、不動産の所有者や種類や取得日を確認するために必要です。
不動産取得税の納税通知書
都道府県税事務所が税額や納付状況を確認するための納税通知書も必要です。納税通知書には、不動産取得税の税額や納付期限などが記載されています。原則として、納税通知書は再発行できないため、紛失しないように注意しましょう。なお、都道府県税事務所の指示がない限り、納税通知書はコピーでも構いません。
また、納税通知書は不動産取得税申告書に記入する際や還付申請に使用する以外に、不動産を売却する際の手続きにも必要になるため、引き続き保管しておくことをおすすめします。
不動産売買契約書
不動産売買契約書は、売主と買主と間で不動産売買を行う際に交わされる契約書で、売主や買主の氏名や住所、物件の住所や面積や売買代金などが記載されています。不動産取得税の申告では、不動産の取得原因や取得日や、取得価格を確認する際に必要です。
建築確認済証
建築確認済証とは、建築計画が建築基準法や関連法規などに適合していることを証明する書類で、建築年月日や建築主や確認番号などが記載されています。不動産取得税の申告のほかに還付申請でも、建物の種類や用途や床面積などを確認する際に必要です。特に、中古住宅の軽減措置には新耐震基準の要件があるため、重要な書類となります。
不動産会社や元の所有者などから入手できますが、紛失した場合は建築計画概要書や台帳記載事項証明書などの発行が必要です。なお、都道府県税事務所の指示がない限り、確認済証はコピーでも構いません。
平面図
不動産取得税の申告では、平面図も用意しなければならないケースもあります。平面図を基に住宅の床面積や構造などを確認して、軽減措置の要件を満たしているかどうか判断するためです。
平面図は、建築会社や不動産会社から入手できるほか、中古住宅の場合は前の所有者が持っているケースも少なくありません。なお、建築会社や不動産会社に平面図の再発行を依頼する場合は一般的に手数料がかかります
印鑑
還付申請の際には、書類に押印が必要となる場合があります。認印でも問題ない場合が多いですが、念のため実印を持参しておくと安心です。
本人の口座番号がわかるもの
不動産取得税の還付金は、原則として申請者本人の名義の銀行口座に振り込まれます。そのため、申請の際は口座名義や金融機関名や口座番号が確認できるものが必要です。具体例として、預金通帳やキャッシュカードなどが挙げられます。
ただし、一部のネット銀行は還付金の振り込みに対応していない恐れがあるため、事前に確認しておくことをおすすめします。-

不動産取得税の軽減措置を受けるには、手続きを進めたり書類を用意したりと、さまざまな準備が必要です。納付額を軽減し税負担を抑えるためにも、軽減措置を受ける際の注意点を押さえておきましょう。押さえておくべき注意点は以下の3点です。
軽減措置の適用の有無で不動産取得税は変動する
不動産取得税は、軽減措置の適用の有無で税額が大きく変わります。少しでも税負担を抑えるには、軽減措置の申請をきちんと行わなければなりません。軽減措置は不動産取得税がかかる前提のため、当記事の前半でも述べたように不動産取得税がかからないケースもあるため、注意しましょう。
送付された納税通知書の税額が、必ず軽減措置として適用されているとは限りません。納税通知書が届いたら、算出されている税額が正しいか確認するようにしましょう。軽減措置の申請を忘れてしまった場合
不動産取得税を納付するときに軽減措置の申請を忘れてしまった場合、軽減されていない額を納付しなければなりません。しかし、すでに解説した通り、不動産取得税は還付が受けられます。そのため、軽減前の税金を納付しても払い過ぎた分は申請を行うことで還付されます。
なお、還付申請の後に受理されても、還付金が振り込まれるまでは1か月〜2か月ほどかかるケースもあるようです。還付申請の手間も増えるため、軽減措置の申請は不動産取得税の申告時に忘れず行うようにしましょう。
不動産を取得したとき、通常では取得した日から60日以内に、不動産の所在地がある都道府県税事務所に不動産を得たという事実を申告しなければなりません。ただし、不動産登記法の規定における表示に関する登記、あるいは所有権の登記の申請を指定の期日までに行った場合は、申告が不要になる場合もあります。不動産取得税の納付が遅れるとペナルティが発生するケースもある
不動産取得税の納付が遅延してしまうと、追徴税や延滞税などのペナルティが課される可能性があります。
納付期限までに不動産取得税を納めなかった場合、課されるのが延滞税です。延滞税は、納付期限の翌日から納付日までの期間、年7.3%または14.6%の割合で加算されてしまいます。延滞税を支払わないと督促措置が取られ、最終的に差し押さえといった強制執行が行われるケースもあるため、納付期限は必ず守りましょう。
また、過料の対象になる行為に該当する場合、法律に定められた義務を守らなかったとして罰金を課されることもあります。具体的には、不動産取得税の申告を行わなかったり、虚偽の申告を行なったりといった行為です。なお、不動産取得税の過料の金額は10万円以下となります。過料を防ぐには不動産取得税の納付期限を守り、正しく申告しなければなりません。
不動産取得税は原則、一括で納付します。一括での納付が難しい状況のときは、分割払いが認められる可能性もあるため、都道府県税事務所に相談してみると良いでしょう。
納付猶予の措置が取られた事例としては、経済情勢や大規模災害といった特殊な社会状況が挙げられます。2008年に起きたリーマンショック後の景気悪化や、2011年に発生した東日本大震災では被災者支援のため、納付猶予の措置が取られました。-

不動産を取得した人に課せられる不動産取得税には、軽減税率が適用されており、一定の要件を満たす不動産の場合は軽減措置が受けられます。軽減措置を受けられる不動産の種類は大きく4つに分けられ、新築または中古住宅、新築住宅用と中古住宅用の土地です。
また、軽減措置を受ける際や還付申請を行う際は申告書のほか、各都道府県が定めている書類を用意する必要があります。主な必要書類は、不動産取得税申告書や不動産取得税還付(減額)申請書、納税通知書や登記事項証明書や不動産売買契約書などです。
不動産取得税は、軽減税率を適用しない状態だと費用が高額になり、大きな負担になってしまいます。そのため、軽減措置や還付申請を活用して、支払う納付額を抑えられるようにすることが大切です。-
不動産取得税とはなんですか。
不動産取得税は、購入や贈与、家屋の建築などで不動産を取得した際に、取得した方に課税される税金です。
-
不動産取得税の納付先について教えてください。
不動産取得税の納付先は、不動産の所在地がある都道府県です。住所地とは別の、他の都道府県で不動産を取得した場合でも、納付先は不動産の所在地がある都道府県になるため注意しましょう。
関連記事
-
 相続した不動産の名義変更のやり方は?費用や必要書類についても解説詳しく見る
相続した不動産の名義変更のやり方は?費用や必要書類についても解説詳しく見る土地や建物といった不動産を相続した場合、被相続人から名義を変更しなければなりません。名義変更は自分で行えますが、司法書士に依頼することも可能です。しかし、自分で進めるとなるとどういった手続きを行えばいいのか、どの書類を用意すればいいのか分からない方は多いでしょう。この記事では、不動産を相続した際に自分で名義変更を行う手続きや、発生する費用、準備が必要な書類について解説します。
-
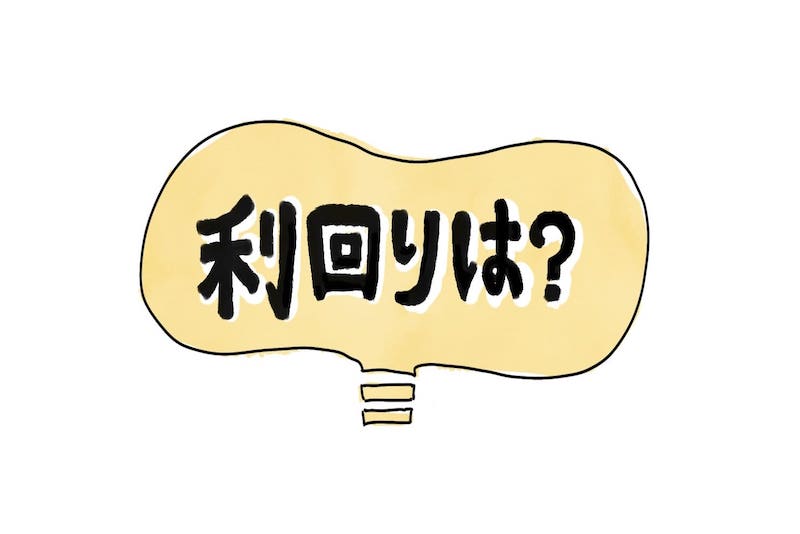 アパート経営の回収期間は?パターン別に目安を調査詳しく見る
アパート経営の回収期間は?パターン別に目安を調査詳しく見る不動産投資の一つとしてアパート経営を検討されている方のなかには、「投資資金の回収期間をあらかじめ知っておきたい」という方もいるのではないでしょうか。不動産投資は、家賃収入を継続的に得るだけではなく、投資資金以上の金額を回収できることも大切になります。不動産商品は高額のため、投資する前に資金回収のシミュレーションを行いましょう。 しかし、所有している土地でアパート経営を始めるには、いくつかのリスクがあることも覚えておきましょう。それぞれのリスク回避のために適切な対策を行って、効率的な土地活用を行いましょう。 この記事では、土地有りでアパート経営を行うメリット・デメリットについて、そして経営を進める時の流れや必要な資金などについて解説します。
-
 【アパート経営がうまくいかない方へ】よくある13の失敗ポイント詳しく見る
【アパート経営がうまくいかない方へ】よくある13の失敗ポイント詳しく見る自己資産を運用して増やしたいと思っている方のなかには、アパート経営を検討しているケースがあるかもしれません。アパート経営は、株式取引などとは異なり現物がイメージしやすいため、比較的安全で簡単な投資先に思えます。しかし、魅力的な反面、うまくいかなかったときのリスクについて注意する必要があるのも事実です。この記事では、よくある13個の失敗ポイントと、その対策についてご紹介します。
タウングループ不動産仲介・周辺事業- 賃貸不動産仲介(東京・神奈川・埼玉・千葉) タウンハウジング
- 賃貸不動産仲介(東海) タウンハウジング東海
- 賃貸不動産仲介(九州) タウンハウジング福岡
- 土地・建物の不動産販売及び仲介 タウン住宅販売
- 首都圏を中心に引越サービスを展開 タウン引越サービス
- 賃貸不動産仲介(東北) タウンハウジング東北
- 賃貸不動産仲介(北関東) タウンハウジング北関東
建築事業- 賃貸住宅の企画・設計・施工 アヴェントハウス
多角化事業- 都内を中心に飲食店を運営 タウンダイニング
- インドアテニススクール タウンインドアテニスアカデミー


 一覧へ戻る
一覧へ戻る