家賃収入にかかる税金の種類は?不動産所得の算出方法や確定申告についても解説
家賃収入で収益を得ると、税金を支払う義務が生じます。賃貸経営の収支計画を立てるうえでは、その税金を正しく理解し、計上しなければなりません。
そこで本記事では、家賃収入と不動産所得についての概要と、家賃収入にかかる税金を紹介します。加えて、家賃収入の経費になるものとならないものと確定申告の必要性についても解説します。
-

家賃収入とは、マンションやアパート、貸事務所などを所有し、部屋を貸し出すことで得られる収入の総称を指します。ここでは、家賃収入の詳細を項目別に紹介しましょう。
家賃
家賃とは、賃貸物件の使用者(入居者)から貸主に支払われる賃貸料金を指します。概して、賃貸マンションやアパートなどの住居物件の賃料を家賃と呼びます。物件の立地や築年数、間取りや設備などによって金額はさまざまで、毎月支払うケースが多いとされています。住居物件の家賃に対しては、消費税は非課税ですが、事務所や店舗、工場や倉庫など住居物件以外の賃料は課税対象となります。
礼金
礼金は、借主が貸主に対してお礼の意味で支払うお金になります。目安となる金額は、家賃1か月分です。敷金とは違い借主の退去時に返金する必要がないため、家賃収入となります。なお近年では、礼金なしの物件も増加傾向にあります。
敷金
敷金は、新たな入居者から賃貸借契約を締結する際に預かるお金になります。家賃の滞納や退去時の入居者負担の修繕費に充てます。一般的には家賃の1~2か月分に設定するケースが多いようです。退去時にかかった費用を差し引いて返金します。返金しない分が、家賃収入となります。
更新料
更新料とは、賃貸物件の契約更新の際に契約書の記載内容に基づいて借主が支払うお金を指します。更新料は、2年ごとに家賃1か月分を支払うのが一般的です。ただし、空室対策として更新料を設定しない物件も増えています。なぜなら、更新料のせいで退去となると、原状回復工事が必要だったり次の入居者が決まるまで家賃が入らなかったりするため、利益が少なくなる場合もあるからです。
管理費と共益費
管理費と共益費は、家賃と併せて借主が毎月支払うお金です。家賃収入の一部ですが、共用部分の維持管理費用として、共用設備の電気代や水道料、共用廊下やエントランスの電球交換費用などに充てることがあります。加えて、物件の清掃費やエレベーターなどの保守点検費用にも充てられます。
駐車場代・その他
住居や事務所など以外に駐車場を賃貸している場合は、毎月の駐車場代も家賃収入に含まれます。また、自販機や看板などを設置したことで得られる収入も家賃収入の一部です。
-

家賃収入にかかる税金を知るには、まず不動産所得を算出しなければなりません。その際に注意が必要となるのは、家賃収入と不動産所得の違いです。ここでは、両者の違いと不動産所得の計算式について解説します。
家賃収入と不動産所得との違い
家賃収入と不動産所得は、一見同じようですが異なります。まず家賃収入とは、借主が毎月支払う家賃だけでなく、前述した礼金・敷金・更新料・管理費と共益費・駐車場代などを含めた賃貸経営で得られる売り上げです。それに対して、不動産所得は、家賃収入から必要経費を差し引いたものを指します。
不動産所得の計算式
不動産所得は、以下の計算式で算出できます。
●不動産所得=家賃収入ー必要経費
また、所得税などの税金を計算するには、以下の計算式で課税所得を計算する必要があります。
●課税所得=不動産所得+他の所得ー所得控除
なお、計算式からも分かるように、不動産所得は会社員として得ている給与所得など、他の所得と合算して損益通算が可能です。副業で賃貸経営している方は、他の所得も漏れなく合算して計算しましょう。-
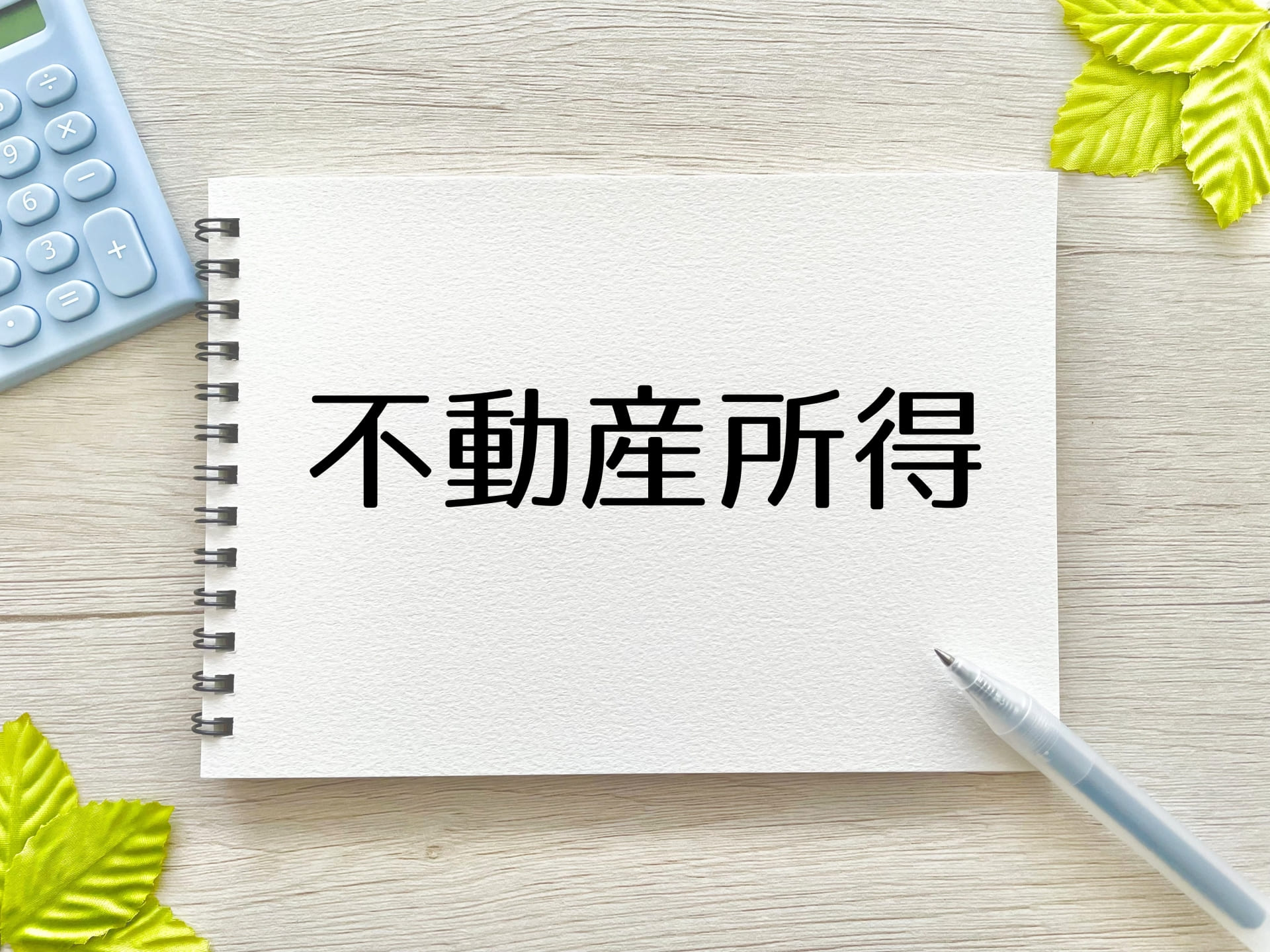
不動産所得における「事業的規模」とは、不動産によって所得を得る行為が、社会通念上事業といえる程度の規模であることを指します。事業的規模で賃貸経営しているのであれば、税務上有利な特例が適用されることがあります。ここでは、事業的規模と認められる要件とメリットについて解説します。
事業的規模と認められる要件
事業的規模かどうかは、原則として社会通念上事業といえる程度の規模で行われているかどうかによって判断されます。ただし、建物の貸付けについては、以下のいずれかに該当すれば、原則事業として行われていると認められます。
●貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上あること。
●独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。
出典:国税庁|No.1373 事業としての不動産貸付けとそれ以外の不動産貸付けとの区分事業的規模と認められるメリット
事業的規模と認められるメリットは、以下の通りとなります。
●青色申告特別控除が受けられる
65万円の青色申告特別控除が受けられます。青色申告の届出をし、複式簿記による記帳などを行う必要はありますが、必要経費を差し引いた不動産所得からさらに65万円差し引くことが可能です。事業規模と認められない場合は、青色申告でも10万円の特別控除しか利用できません。
●家族への給与が経費扱いできる
青色申告では配偶者や子どもなどの家族への給与を「青色専従者給与」として経費として扱えます。なお、給与の上限は定められていませんが、勤務実態や仕事内容などから妥当性のある金額までとなっています。
●回収不能の賃料を必要経費扱いできる
回収不能となった賃料を回収不能になったその年に必要経費として扱えます。
●取り壊しや除却などによる損失を全額経費にできる
取り壊しや除却などによる損失を全額経費として計上できます。また、当該年度の所得から引ききれない場合は、3年間の繰り越しが可能です。-
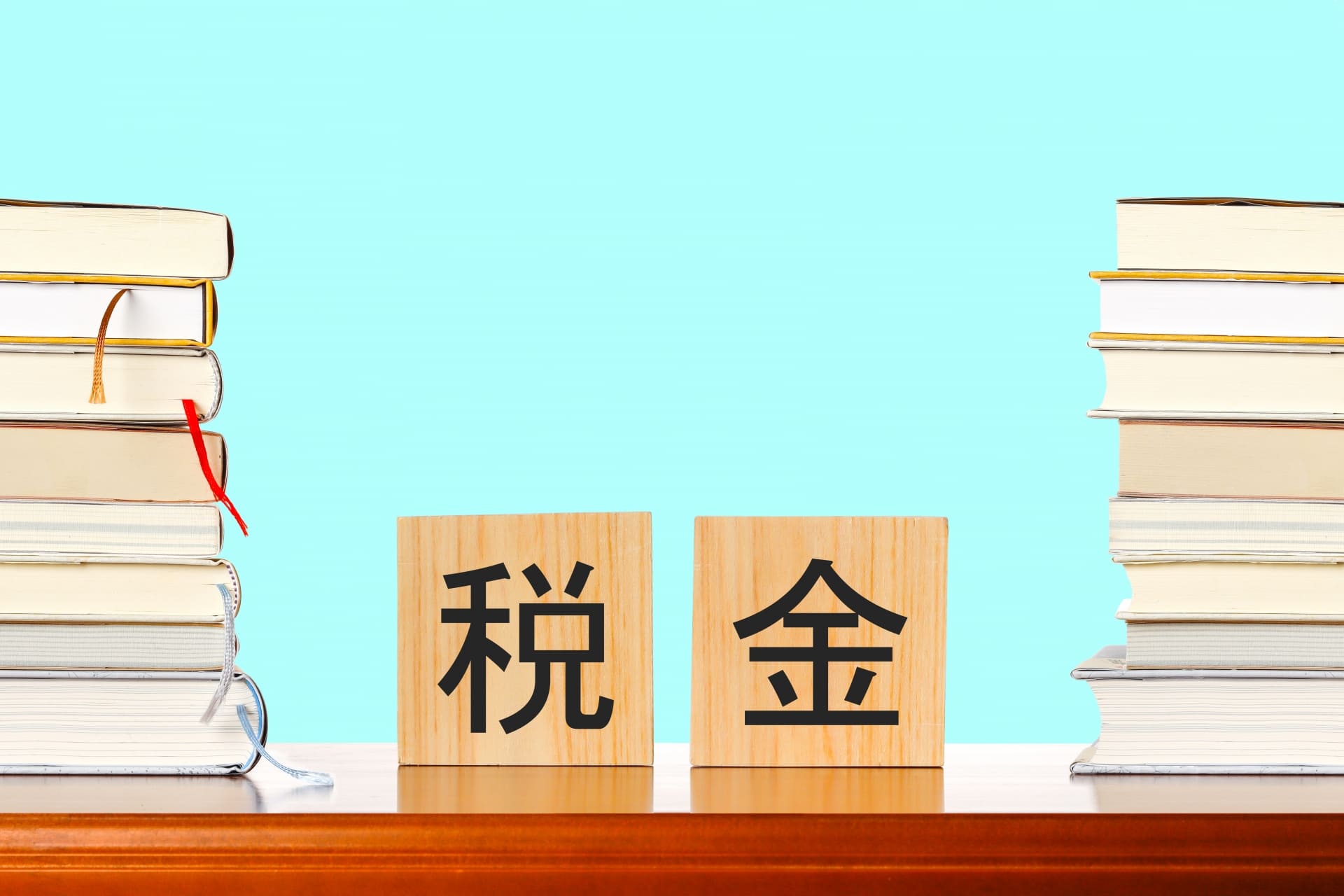
適切に納税するためには、家賃収入にかかる税金を正しく理解する必要があります。ここでは、家賃収入にかかるさまざまな税金について解説します。
所得税
所得税は、個人の所得に対してかかる税金です。1年間のすべての所得から所得控除を差し引いた課税所得に税率をかけて税額を計算します。なお、所得税の税率は、以下の表の通り5%から45%の7段階に区分されます(分離課税に対するものなどは除く)。
出典:国税庁|No.2260 所得税の税率課税される所得金額 税率 控除額 1,000円~1,949,000円 5% 0円 1,950,000円~3,299,000円 10% 97,500円 3,300,000円~6,949,000円 20% 427,500円 6,950,000円~8,999,000円 23% 636,000円 9,000,000円~17,999,000円 33% 1,536,000円 18,000,000円~39,999,000円 40% 2,796,000円 40,000,000円以上 45% 4,796,000円
所得税の計算式は以下の通りです。
●所得税の計算式:所得税=課税所得×所得税率住民税
住民税は、1月1日時点で住民登録していた都道府県や市区町村に納める地方税です。都道府県民税と市区町村民税に分かれており、納税する際は一括して各市区町村に納め、都道府県民税は各市区町村を通じて支払われます。住民税には、所得に応じて納める「所得割」と所得にかかわらず定額を納める「均等割」があります。所得割の税率は、都道府県民税が4%で市区町村民税が6%の計10%(政令指定都市については道府県民税が2%で市民税が8%)です。均等割は4,000円(都道府県民税1,000円、市区町村民税3,000円)ですが、2024年度からは均等割と併せて森林環境税(国税)が1,000円徴収されています。
消費税
消費税は、商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して課税される税で、事業者が納付する仕組みです。ただし、家賃収入で所得があっても、賃貸物件が住宅用の場合は非課税となります。一方、店舗やオフィスなどの事業用の場合は、1,000万円以上で消費税が課せられます。なお、賃貸物件が住宅用だと判断してもらうためには、以下のふたつの要件を満たさなければなりません。
●契約書に明示されていること
住宅用かどうかは、契約で住宅用と明示されているかで判断します。
●賃貸期間が1か月以上
住宅用として運用している物件でも、賃貸期間が1か月未満の場合は、住宅用と判断されず課税の対象となります。ただし、課税所得が1,000万円以下の場合は、非課税となります。固定資産税
固定資産税は、土地や家屋、償却資産といった固定資産にかかる税金です。固定資産の所有者が、資産価値に応じて算定した税額を市町村に納めます。なお償却資産とは、土地や家屋以外の事業の用に供することができる資産です。税額は、土地や家屋などの固定資産税評価額(適正時価)に基づく課税標準額で定められています。また、償却資産の評価は、取得年月や取得価格および耐用年数に基づき、申告のあった資産について一品ごとに賦課期日(1月1日)現在の評価額を算出することで行います。固定資産税は、固定資産を所有している間は毎年徴収される点がポイントです。
都市計画税
都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業の費用に充てるために課される市町村税(東京23区は都税)です。原則として市街化区域内に所在する土地や建物を1月1日時点で所有している人に対して課される地方税になります。固定資産を所有している間は、基本的に毎年発生するのが特徴です。この都市計画税の課税については、都市計画事業などに応じた市町村の自主的な判断に委ねられています。詳しい内容については、住んでいる自治体に問い合わせてみるとよいでしょう。
不動産取得税
不動産取得税は、土地や家屋の購入・贈与、家屋の建築などで不動産を取得したときに、取得者に対して課される税金です。取得者は、取引された不動産が所在する都道府県に納税します。前述した固定資産税とは異なり、不動産を取得したときだけに発生する一時的な税金です。不動産取得税の税額は、以下の通り不動産の評価額(固定資産税の税額算定に使用される課税標準額)に税率を掛けて算定します。税率は4%ですが、現在は軽減税率として土地と住宅については3%が適用されています。
●不動産取得税の税額 = 不動産の評価額(固定資産税の税額算定用の課税標準額)× 税率
なお、不動産取得税は、以下の通り税負担を軽減する特例措置が適用されるケースもあります。
「新築住宅・住宅用地特例」
●新築住宅を取得するケース
新築住宅を取得するケースでは、評価額から1,200万円控除されます。ただし、住宅の床面積が50㎡(一戸建て以外の住宅で貸家の用に供する場合は40㎡)以上で240㎡以下である必要があります。
●住宅用地を取得するケース
住宅用の土地を取得したケースでは、以下の①②のいずれか高い方の額を土地の税額から軽減する。
①150万円 × 税率
➁土地1㎡当たりの価格×住宅の床面積の2倍(1戸当たり200㎡を上限)× 税率
ただし、土地の取得日から一定期間内に、取得した土地に住宅が新築されているなど、一定の要件を満たす必要があります。登録免許税
登録免許税の主なものは、不動産の登記で、土地と建物の両方が課税対象です。不動産の取引では、売買で所有権が移転した際や住宅ローンを借りて抵当権を設定した際などの登記申請時に納付します。税額は、固定資産税評価額に税率をかけて算出しますが、新築で固定資産税評価額がつけられていない場合は、法務局で認定した課税標準価格に税率をかけて算出します。税率は登記の種類によって異なり、中古建物や土地などの所有権移転登記の場合は2.0%、建物を新築した際の所有権保存登記の場合は0.4%です。なお、条件によっては、軽減措置が適用され、税率が引き下げられることもあります。
印紙税
印紙税とは「不動産売買契約書」や「金銭消費貸借契約書」などを含むさまざまな課税文書に対して発生する税金を指します。「収入印紙」を書類に貼り、課税文書の作成者が消印をすることで納税が完了する形式です。税額は、契約書に記載されている金額によって異なります。なお、収入印紙とは、税金や手数料を支払う目的で書類に貼り付ける証票を指します。
-

不動産所得を計算するためには、家賃収入を得るのにかかった必要経費を正しく把握し計上する必要があります。ここでは、家賃収入がある場合に経費となるものを、ご紹介しましょう。
租税公課
租税公課とは、国や地方自治体に納める税金と公共団体に納める会費や罰金などの公課に対する科目です。租税公課で経費扱いできる代表的なものは、以下の通りとなります。
●固定資産税
●不動産取得税
●登録免許税
●都市計画税
●個人事業税損害保険料(火災保険料、地震保険料など)
火災保険や地震保険、施設賠償保険など、自身で負担した保険料は必要経費として計上できます。ただし、数年分の保険料を一括で支払った場合に必要経費として計上できるのは、申告する年にかかる分のみなので注意しましょう。
減価償却費
土地以外の建物・車・備品・駐車場の舗装など、月日の経過によって価値が減少する固定資産を「減価償却資産」といいます。減価償却資産の取得費用は、取得した年に全額経費となるわけではなく、減価償却資産の耐用年数で分割して減価償却費として経費を計上するのです。資産によって耐用年数と償却率が定められており、例えば、建物の場合は鉄筋コンクリートや木造など、構造に応じて変動します。
維持管理費
建物の定期点検や修繕などにかかる維持管理費用は、経費になります。具体的には、エレベーターや階段、エントランスなどの共用部分の修繕費が該当します。また、管理会社への業務委託費や賃貸管理代行手数料も維持管理費にあたります。さらには、退去後の原状回復費も維持管理費として経費扱いとなるのです。
修繕積立金
分譲マンションの区分所有者が支払う修繕積立金は、経費として計上可能です。原則として、大規模修繕工事が行われた年に計上するものですが、以下に示す一定の要件を満たせば、支払った年の経費にできます。
「一定の要件」
●区分所有者となった者は、管理組合に対して修繕積立金の支払義務を負うことになること
●管理組合は、支払を受けた修繕積立金について、区分所有者への返還義務を有しないこと
●修繕積立金は、将来の修繕等のためにのみ使用され、他へ流用されるものでないこと
●修繕積立金の額は、長期修繕計画に基づき各区分所有者の共有持分に応じて、合理的な方法により算出されていること
出典:国税庁|賃貸の用に供するマンションの修繕積立金の取扱いローン金利
ローンを組んで賃貸物件を購入した場合、ローン返済金の利息分は経費として計上できます。ただし、元本返済部分は経費として計上できないため、注意が必要です。
青色専従者給与
納税者と生計を一にしている配偶者やその他の親族が、納税者が経営する事業に従事している場合、支払われる給与は原則として必要経費とはなりません。しかし、青色申告者の場合、一定の要件を満たしていれば、支払った給与を必要経費とする「青色事業専従者給与」の特例が認められています。
税理士・司法書士への報酬
賃貸物件経営では、さまざまな業務を専門家に依頼するケースがあります。例えば、税理士に確定申告の手続きを依頼したり、司法書士に不動産登記の手続きを依頼したりすることです。仕業への依頼報酬は、高額になるケースもありますが、その際の報酬も経費として扱える場合があります。
その他経費
入居者募集のチラシやパンフレット制作時に発生する印刷費、消耗品費や通信費などの事務費用、物件を管理するための移動で発生する交通費も経費として扱えます。
-
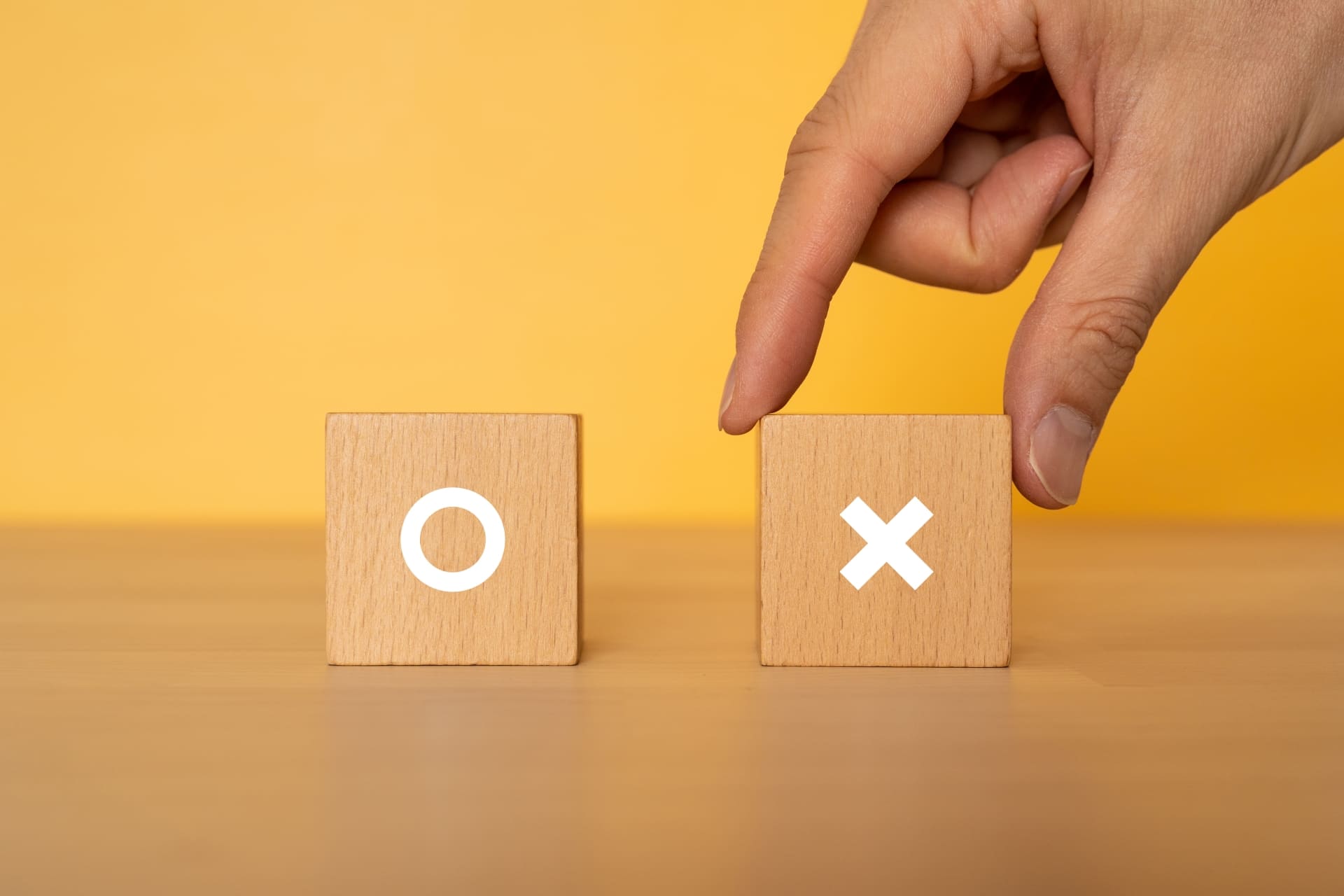
プライベートでの支出や個人に課される税金など、経費扱いできない費用があります。経費として不適切な費用を計上すると、税務調査の際に修正を求められてしまうため注意が必要です。ここでは以下の通り、経費扱いできない費用を解説します。
借入金のうち「元本分」
前述した通り、借入金のうち利息分は経費として計上できますが、元本分は経費として計上できないため、注意が必要です。
所得税と住民税
所得税と住民税は、賃貸経営とは関係なく発生する税金のため、家賃収入の経費として計上できません。基本的に経費として計上できるのは、賃貸経営と関連するものだけになります。
プライベートとの判別が難しいもの
賃貸経営に関係のない支出は、経費として計上できません。例えば、カバンやスーツなどプライベートとの判別が難しいものは、不動産会社や管理会社などとの打ち合わせで使用するとしても経費とは認められないため、注意が必要です。
賃貸経営に関わらない私生活で発生した交通費や通信費、自宅の修繕費など
賃貸経営とは無関係の私生活で発生した交通費・通信費・自宅の修繕費などは、経費として計上できません。
-

確定申告とは、1年間(1月1日~12月31日)の所得に対して納税額を計算・申告・納税する手続きを指します。主に個人事業主や自営業者、フリーランスなど一定額以上の事業所得のある人が対象ですが、会社員でも確定申告の対象となるケースもあります。ここでは、家賃収入がある場合は確定申告が必要なのか解説します。
家賃収入が年間20万円を超える場合は確定申告が必要
不動産所得が年間20万円以上ある場合は、確定申告が必要です。なお、家賃収入には、前述した通り毎月の家賃だけでなく入居時の礼金や契約更新時にかかる更新料なども含まれます。
不動産所得が赤字でも確定申告をしたほうがよい理由
家賃収入を含む各種収入から、必要経費を差し引いた金額が年間で20万円以下の場合は、一般的に確定申告の必要はありません。しかし、不動産所得が赤字の場合でも、確定申告をおすすめします。なぜなら、不動産所得と本業で得た給与所得とは損益通算できるからです。損益通算とは、本業などの給与所得と合算した額で所得税の金額を算出する制度になります。この損益通算によって課税所得が減ることで、必要以上に納めていた税金が還付される可能性があるのです。この損益通算制度をうまく利用することで、節税も可能となります。
損益通算には例外あり!
不動産所得における損益通算には例外があります。例えば、融資を受けて物件を購入する場合、毎月のローン利息は必要経費となります。ただし、赤字になった場合に損益通算できるローン利息は、建物の購入資金にかかる利息のみです。土地の購入資金にかかる利息は、損益通算できません。
所得20万円以下でも、住民税の申告は必要
不動産所得が20万円以下の場合には、確定申告が不要という特例措置があります。しかし、これはあくまでも所得税の話です。住民税は、特例措置がないため申告する必要があります。なお、所得税の確定申告を行う場合は、確定申告の内容が税務署から自治体に通知されるため住民税の申告は必要ありません。しかし、確定申告しない場合は、別途申告が必要となるため注意が必要です。
-

家賃収入で得た収益には、税金がかかります。毎月の家賃だけでなく、礼金・返却しない敷金・更新料・管理費と共益費・駐車場代などを含む収入の総称が家賃収入です。そして、家賃収入から必要経費を差し引いたものを不動産所得といい、この不動産所得を基に税金が算出されるのです。賃貸経営するうえで避けては通れない税金ですが、適切に経費を計上したり控除制度を適用したりすることで節税が可能となります。なお、賃貸管理・サブリース・賃貸仲介など、不動産を中心に生活関連事業を展開している株式会社アレップスでは、家賃収入の税金に関して専門士業に無料相談できます。賃貸経営に興味がある、または実際に賃貸経営していて、税金に関してわからない点がある方は、一度専門士業に相談してみてはいかがでしょうか。
-
家賃収入と不動産所得との違いを教えてください。
家賃収入とは、借主が毎月支払う家賃だけでなく、礼金・敷金・更新料・管理費と共益費・駐車場代などを含めた賃貸経営で得られる売り上げです。それに対して、不動産所得は、家賃収入から必要経費を差し引いたものを指します。
-
不動産所得の計算式を教えてください。
不動産所得は、以下の計算式で算出できます。
不動産所得=家賃収入ー必要経費
また、所得税などの税金を計算するには、以下の計算式で課税所得を計算する必要があります。
課税所得=不動産所得+他の所得ー所得控除
なお、計算式からも分かるように、不動産所得は会社員として得ている給与所得など、他の所得と合算して損益通算が可能です。副業で賃貸経営している方は、他の所得も漏れなく合算して計算しましょう。
関連記事
-
 大阪でアパート経営をするならココ!メリット・デメリットもご紹介詳しく見る
大阪でアパート経営をするならココ!メリット・デメリットもご紹介詳しく見る全国の政令指定都市の中で2番目に人口が多い大阪市は、西日本の中心都市とも言えるエリアです。2025年に開催予定の大阪万博や大阪駅北側の再開発計画「うめきたプロジェクト」など、都市の発展に向けた事業計画が多くあり、話題性もあります。 加えて、大阪は、東京と比較して地価が安く、より高い利回りを実現できると言われています。ただし、大阪の総人口は減少傾向にあり、経営するアパートによっては空室リスクが課題となることもあります。 そこで、この記事ではアパート経営を始めたい方が知っておくべき大阪の実情や、おすすめのエリアなどについて解説します。
-
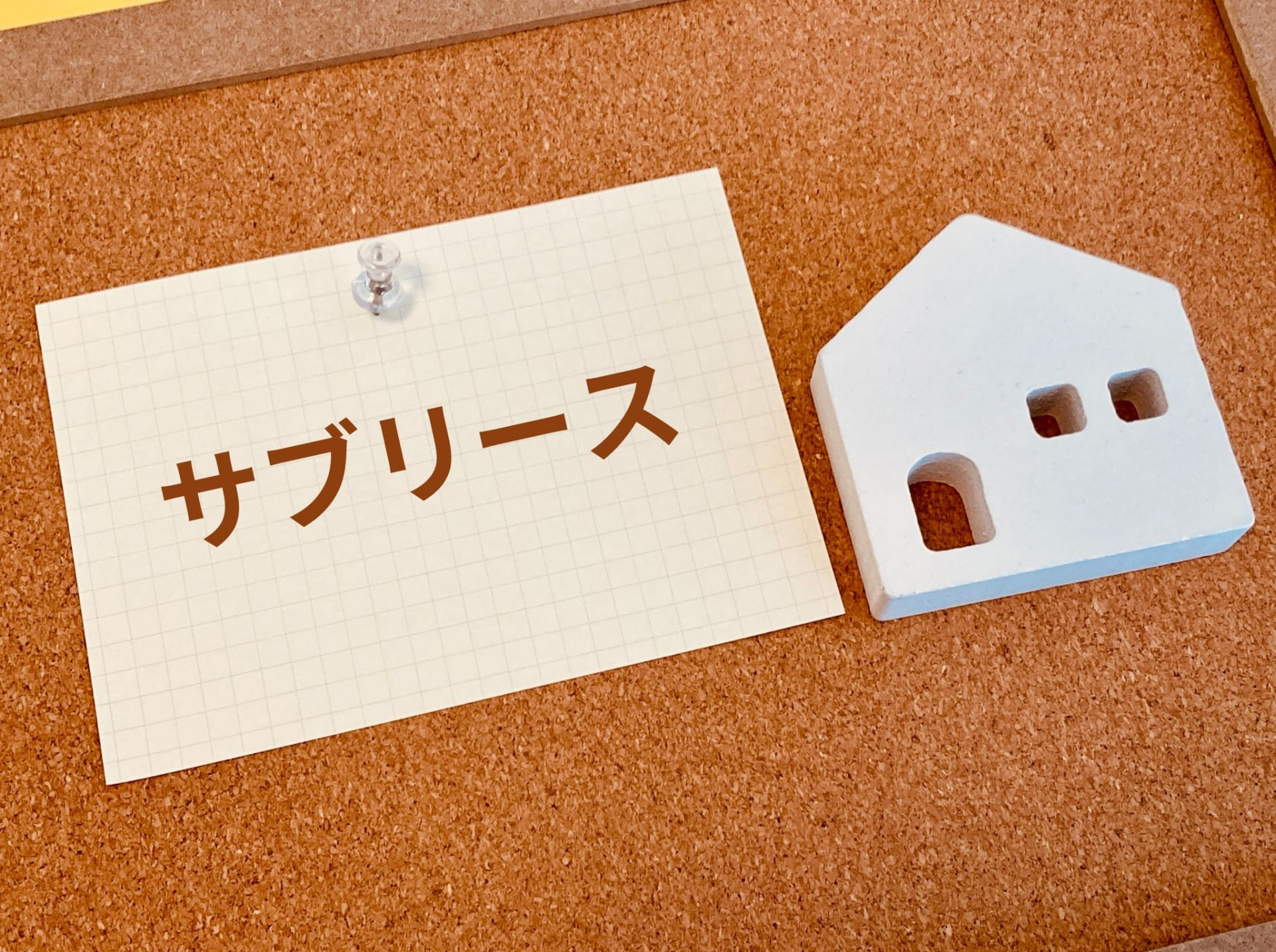 サブリースと家賃保証の違いは何?仕組みや特徴を解説詳しく見る
サブリースと家賃保証の違いは何?仕組みや特徴を解説詳しく見るサブリースと家賃保証は、どちらも家賃を保証してもらえるサービスですが、特徴が異なります。オーナー様は、どちらのサービスが所有する賃貸物件に適しているか、よく検討する必要があるでしょう。 この記事では、サブリースと家賃保証の違いや、各サービスのメリット・デメリット、業者を選ぶポイントなどを解説します。
-
 【アパート経営の利回り最低ラインは?】計算方法や目安を解説!詳しく見る
【アパート経営の利回り最低ラインは?】計算方法や目安を解説!詳しく見るアパート経営を始める際、まず考えることは「より収益を得られる物件はどれか」ということでしょう。不動産投資では、投資した金額をどれだけの期間で回収できるかが収益性を判断する材料となります。そこで参考とされる数値が「利回り」です。この記事では、アパート経営の利回りについて、種類と計算方法、注意点とリスク、パターン別の利回り最低ラインなどを解説します。
タウングループ不動産仲介・周辺事業- 賃貸不動産仲介(東京・神奈川・埼玉・千葉) タウンハウジング
- 賃貸不動産仲介(東海) タウンハウジング東海
- 賃貸不動産仲介(九州) タウンハウジング福岡
- 土地・建物の不動産販売及び仲介 タウン住宅販売
- 首都圏を中心に引越サービスを展開 タウン引越サービス
建築事業- 賃貸住宅の企画・設計・施工 アヴェントハウス
多角化事業- 都内を中心に飲食店を運営 タウンダイニング
- インドアテニススクール タウンインドアテニスアカデミー


 一覧へ戻る
一覧へ戻る